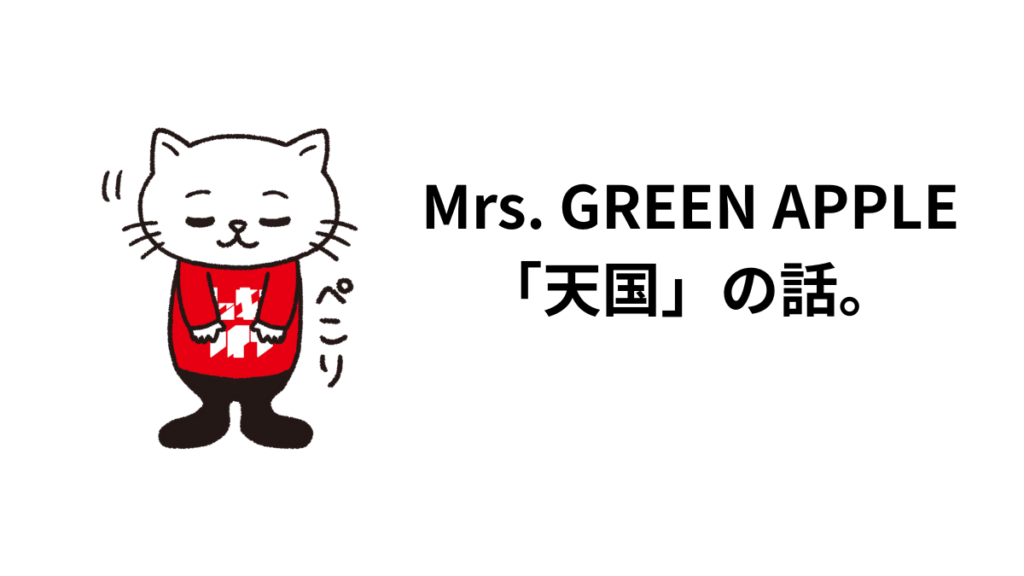
Mrs. GREEN APPLE「天国」のサウンドと歌詞の考察
Mrs. GREEN APPLEって、良くも悪くもバンドとして個性的で、目立つ存在だから、わりと楽曲とは関係のないところで話題になりがちである。
でも、それってそれだけバンドが魅力的だからだとは思う。
ファン以外の人でも、思わず「気にさせちゃう」求心力を持っているということの現れで、こういう境地になれるバンドって、考えたら凄い話だなーと思う。
でも、思いもよらぬ形で話題になるたびに思うことがある。
それよりMrs. GREEN APPLEの作る楽曲、年々その進化、凄まじいぞ、と。
Mrs. GREEN APPLEはバンドとして大きく変化したバンドであり、バンドを物語として語るとちょっと複雑で、込み入った部分もある。
けれど、大森元貴が作る音楽のやばさは年々増しているよなーと思う。
そのヤバさっていうのが、大森元貴にしか作れない音楽の具合が増している感。
アイデア、発想、構成力。
ボーカルのハイトーンさや歌詞の言葉選びまで、大森元貴の音楽でしか味わえない魅力がたっぷり詰まっている。
「天国」を聴いて、改めてそんあことを思ったのだった。
あえて名前を出すけれど、「天国」を聴いた襲撃は、Official髭男dismの「アポトーシス」と通ずるものがある。
楽曲のテイストが似ているとかそういう話じゃなくて、その楽曲との出会ったことで何か自分の価値観がごわっと変わる凄まじさ、そこが似ていたのだ。
感動という言葉ともちょっと違う、何とも言えないぐっとくる感じ。
なぜそう感じたのか、この記事で簡単に言葉にしてみたい。
Mrs. GREEN APPLEの「天国」の音楽的な魅力
まず、冒頭。
シンプルに鍵盤な音で楽曲が始まる。
でも、ボーカルにはいくつもの歌声を重ねており、独特の響きを与える。
しかも、メロディーの変遷が強烈で、そこでそういう低音を魅せるのか・・・!というゾクゾク感がある。
「高い」で変化をつけることが多いJ-POPにおいて、「天国」のメロパートの「低いで変化をつけている構成は見事なものである。
そこから鳴っている音の全てが、文字通り楽曲の世界観を構築するために響いていく。
歌を盛り上げるためじゃない。
楽器が紡ぐすべての音がまるでキャンバスのように、歌の世界を描いて魅せるのだ。
まるでジブリ映画に出会ったような趣き。
幻想的で、でも景色はクリアになっていて。
最初は静かな装いで楽曲が始まるからこそ、後半にかけてどんどん音が増えてきて、物語が躍動していく変化も心地よくて、ゾクゾクさせられる。
楽曲中盤では、エッジの効いた音が合流して、ボーカルの感情も豊かになってくることで、怒涛の何かが動くような印象を与える。
楽曲終盤では感情の変化を示すかのように、強烈な転調を何度も繰り返し、5分ちょっとの楽曲とは思えないような壮大感を浴びることになる。
そして、ラスト。
こんな幕切れになるの・・???
という強烈かつ唐突なエンド。
このゾクゾク感は、マジで聴いたものにしかたどり着けないものがある。
映画よりも物語的な何か。
どこまでも音楽でありながら、音楽を超えた表現の一端をそこに見た気がした。
サブスク時代、ショート動画時代だからこそ「全部を聴かないと味わえない興奮」を、「天国」という楽曲で見事に描いてみせた印象を受けた。
Mrs. GREEN APPLEの「天国」の歌詞の魅力
「天国」が意味するもの
天国ってパンチの効いたタイトルである。
この「天国」って何なのか?と想像しながら楽曲を聴くのも一興である。
フレーズをみていると、人との関係を色んな視点、感情で描いてみせている印象。
ネガティブなワードも平然と織り込ませながら、安易なハッピーソングや、暗い内向的な歌になることなく、哲学的に味わい深く楽しむことができえう。
もしも 僕だけの世界ならば そう
誰かを恨むことなんて
知らないで済んだのに
というフレーズからは、失われたものへの深い絶望や、過去に対する執着が読み取れます。
死の雰囲気
楽曲の終盤に登場するこのフレーズが、特に印象部会。
あぁ またお花を摘んで
手と手を合わせて
もうすぐ其方に往くからね
心に蛆が湧いても
このフレーズは死を踏まえた言い回しであり、贖罪にも似た何かを語るフレーズになっている。
このフレーズの意味合いについては、聞き手それぞれが考えるにしても、この歌がどこまでも物語的に響くのは、ラストにこういう展開を用意しているからこそだと思うし、このフレーズとリンクするようにサウンドが展開するからだ。
この辺りにも、楽曲の魅力が強く反映されている。
まとめに替えて
ということで、2000字程度では魅力を語ることがまったくできない「天国」という神曲。
マジで、この歌はきちんと歌詞をみながら、フルできちんと聴くべき。
この記事では、とりあえずそれだけを強弁して、この記事を終えておきたい。

