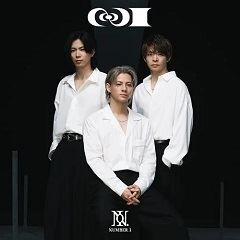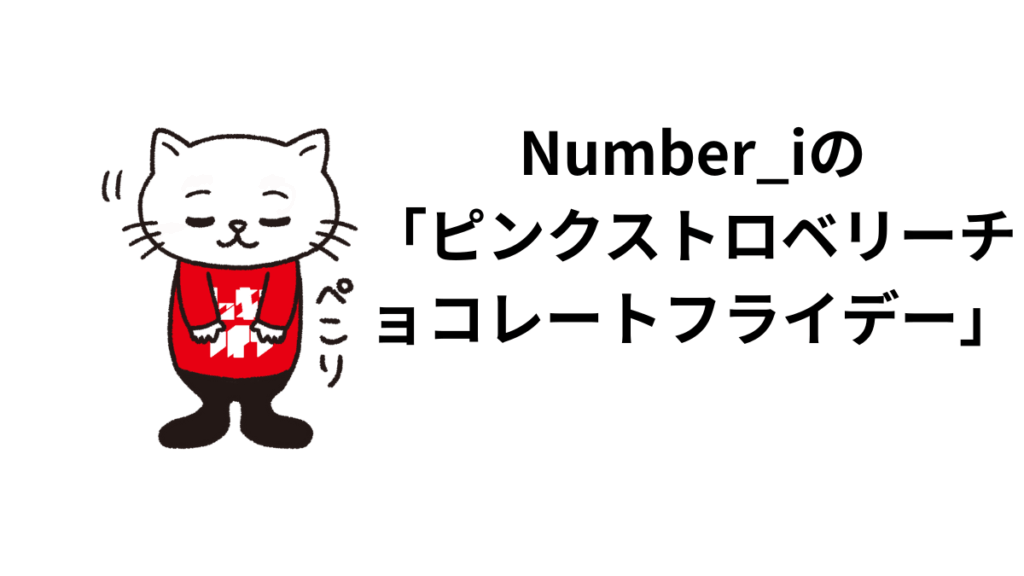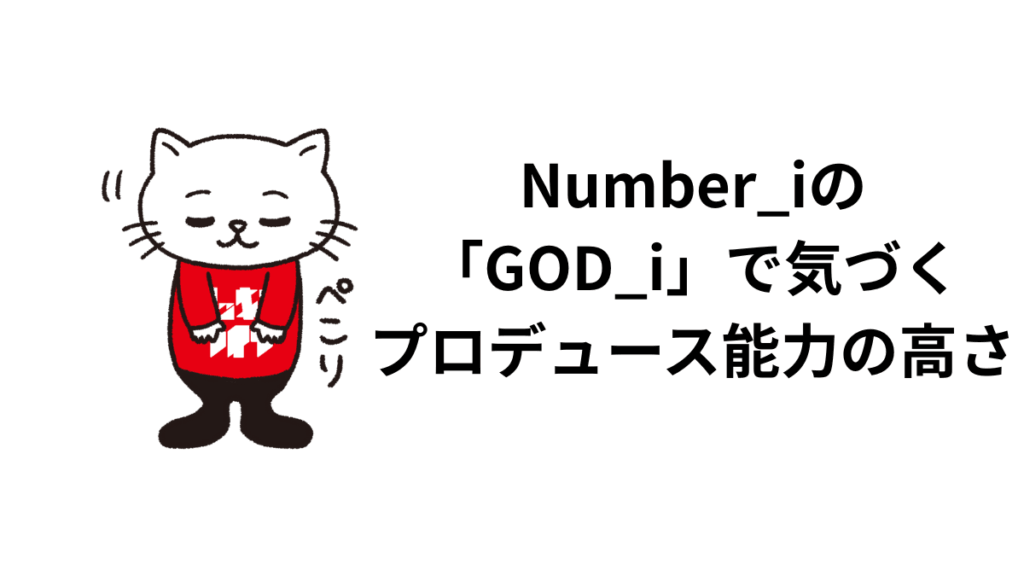
Number_iの「GOD_i」で気づくプロデュース能力の高さ
Number_iの新曲「GOD_i」を聴いてみたら、そのあまりの面白さに驚かされた。
いったい何がそんなに面白いのかというと、一つひとつの展開が予測不能なのだ。
一般的に音楽というのは、ある程度はお約束の構成が存在する。
最初は起伏の少ないメロがあって、次に高低差のあるメロがきて、最後はインパクトのあるサビで展開するとか。
J-POPやK-POP、あるいはメタルやクラシックにしても、ジャンルごとの“型”があって、それに沿った展開を踏んでいくのが通例だ。
そういう様式美こそが、そもそも重要という話もある。
その型を組み合わせたり、あえて壊してみたりする“意外性”が面白さにつながるという話もある。
それだけ音楽は枠や定型があるという話。
・・・なんだけど。
マジで、「GOD_i」は、展開の予測がつかない。
こういうジャンルの音楽って、こういう展開になるよね、って予測した2秒後には、その予測とは異なる展開になるのだ。
面白すぎる。
しかも、それはジャンル性とかサウンドの話に留まらない。
鳴っている音楽もビートの刻み型もボーカルの展開も、全てが刺激的なのだ。
四方に向けて「予想外のトキメキ」を与えてくる。だから、最強なのだ。
今回のプロデュースを手掛けたのは岸優太だが、その才能に脱帽する。
だって、「GOD_i」って、本当に面白い楽曲だ。
「GOD_i」の面白さ
順を追って、面白いと感じた部分を言葉にしたい。
まず、この歌は浮遊感のあるサウンドと、語り口調っぽいテイストで始まる。
・・・かと思えば、25秒を超えたあたりから、どんどん展開が変わる。
規則的になっていたリズムはどんどん均衡を崩していくし、呼応するようにサウンドの表情も変わる。
気がつくと、それまでとは異なる音楽的快楽に誘うわけだ。
ボーカルのテイストも変わっていく。
クールで切れ味鋭いだったボーカルは、いつの間にか、艶やかな情感の中で、スタイリッシュにメロディーを歌い上げていく。
以降も、歌の展開が数秒単位でどんどん変わる。
和のテイストを見せる展開があるかと思えば、アメリカのヒップホップシーンと接続するような空気感を作る瞬間もある。
結果、単純なジャンル名では言い表せられない展開を作り出し、安易に言葉にできないドキドキを与えてくれる。
1分40秒あたりの打楽器の鳴らし方も面白い!
このテイストの楽曲でありながら、こういうビートの刻み方をして、かつボーカルはこの感じなんだ!という絶妙なバランス。
このパートもまた、面白さが炸裂した瞬間だ。
以降、しばらくはラップが続いていて、全体としてみたらクールな楽曲だなあ・・と思ったら、2分30秒あたりではロングトーンでインパクトのあるボーカルを披露する。
その展開から、次はこういうドラマチックを作り出すなんて!
マジで、どこまでいっても耳が離せない。
Number_iって、これまでの楽曲もそうなんだけど、歌全体の尺に対して情報量が多い。
結果、濃厚な音楽体験をすることができる。
四コマ漫画と思ってページを開いてみたら、実は漫画「ワンピース」くらいの超大作だったみたいな感触。
かといって、聴いていて疲れることはない。
それだけ没入して音楽を浴びることができるから。
思えば、濃厚なのに、体感は一瞬という感覚も独特だ。
まとめに代えて
あと、この楽曲、Number_i以外の布陣も良いんだよね。
ODD Foot WorksのPecoriが作詞、DATSのMONJOEとFIVE NEW OLDのSHUNが作編曲でしょ?
「GOAT」からの継続的な布陣ではあるが、然るべき人がプロフェッショナルを手がけるからこそ、バンドが好きな自分もしっかり刺さる興奮があるんだなーと思う。
どこを切っても革新的で、芸術的で、妥協がない。
かつ、メンバーのプロデュース能力の素晴らしさも痛感している近年。
だって、平野紫耀は「BON」を、神宮寺勇太は「INZM」を、岸優太は「GOD_i」はプロデュースを手掛けたわけでしょ?
各々の個性を発揮しながら、圧倒的なクオリティの楽曲を世に放ったわけでしょ?
ここまで名曲をリリースしてきたら、そりゃあぐっとくる濃度も大きくなるというもの。
つくづく、Number_iが切り開く音楽の世界は面白い。
「GOD_i」を聴いて、その思いがより強くなったという、そういう話。