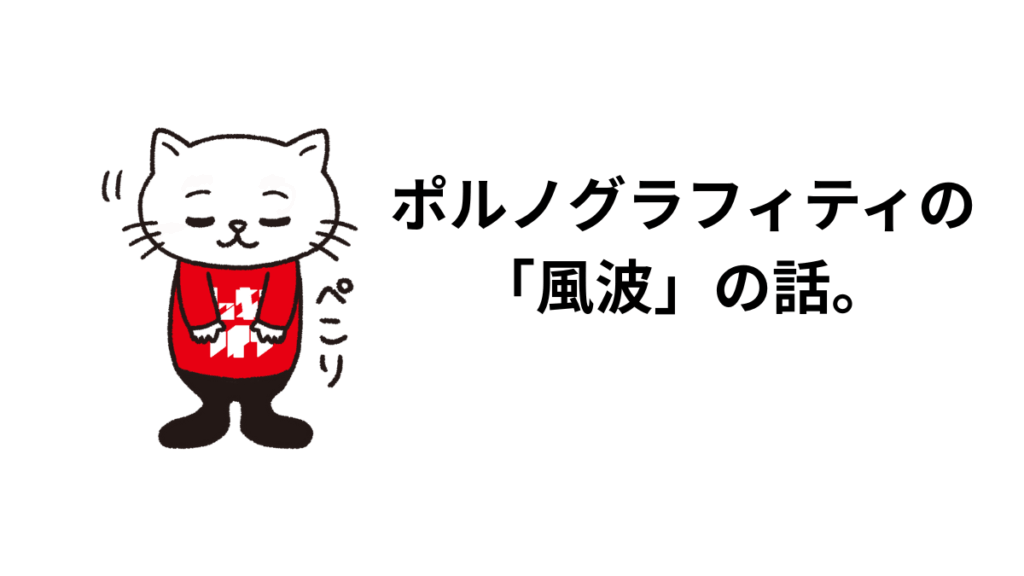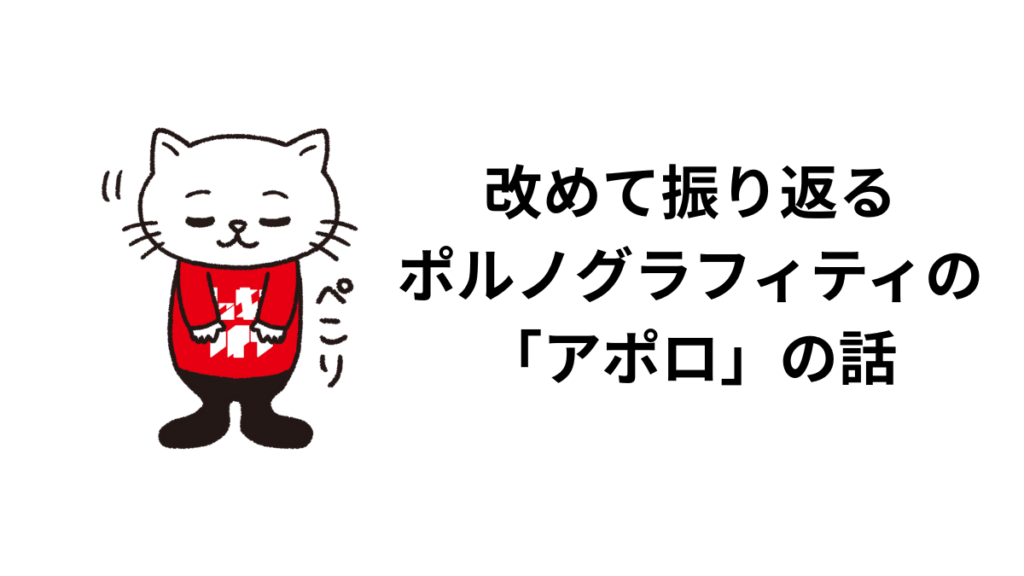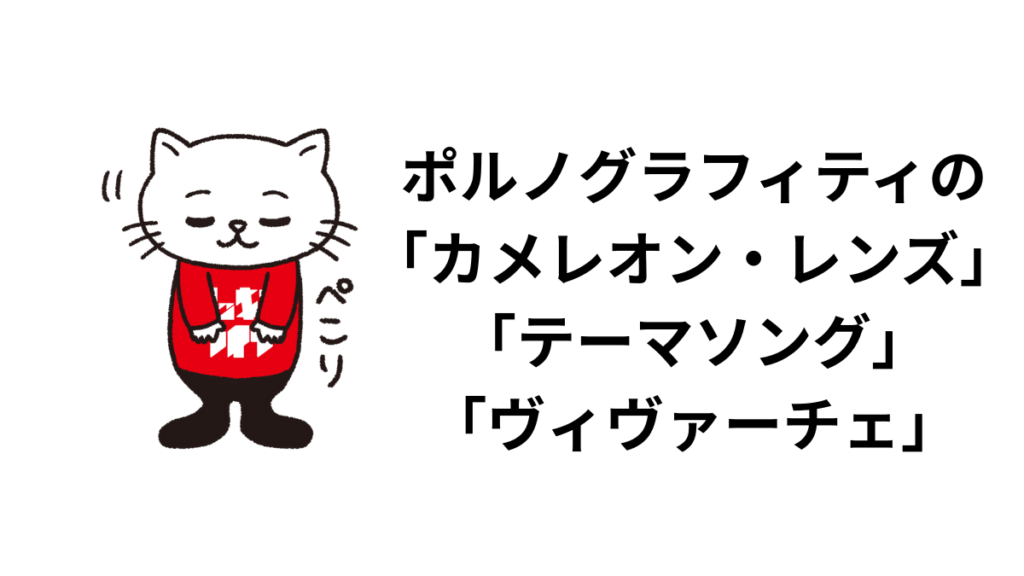
ポルノグラフィティの「テーマソング」-「ヴィヴァーチェ」から弾ける岡野と新藤の魅力
※この記事は2021年に執筆した記事に加筆する形で、更新しています。
ブログを開設した10年前から定期的にポルノグラフィティのことは触れてきたけど、長い音楽リスナー人生の中で、自分が「お金を払って音源をフルで聴きたい」と最初に思ったアーティストは、ポルノグラフィティである。
それだけ、自分の感性に革命をもたらしたアーティストなのである。当時、ポルノグラフィティが音楽番組に出演する、となると自分はかじりついてテレビを観ていたものである。
とはいえ、歳を重ねたら、誰だって良くも悪くも感性は変わる。
自分のポルノグラフィティの音楽に対する温度感も、時代ごとに変化していった。
ライフステージが変わる中で、あまり、ポルノグラフィティの音楽を聴かなくなった時期もあった。
しかし、音楽ブログを始めたあたりで、ポルノグラフィティを改めて聴き直して、再びポルノグラフィティの音楽に惚れ込むことになる。
特に、きっかけとして大きかったのは、「カメレオン・レンズ」。
「カメレオン・レンズ」の話
いやね、「カメレオン・レンズ」。すごくハマったんですよ。
言葉にすると、けっこう難しいんだけど、繊細と躍動の混じり方がこれまでに聴いていた他のどんな音楽とも違って、興奮したのだった。
岡野昭仁のボーカルって、はきはきとした滑舌と伸びのあるパワフルな歌声で持ち味で、その長所を活かす楽曲が多い。
でも、この歌って、冒頭は囁くような繊細なボーカルで始まり、Bメロではボーカルに加工を加えた変化球をつける。
だからこそ、味わいがちょっと異なる。
でも、楽曲を聴いていく中で、岡野昭仁のコアの魅了も注ぎ込まれていき、ゆっくりとアルコールがまわる酔いやすいお酒のように、どんどんその歌の世界に引き摺り込まれるようになる。
新藤晴一の作詞作曲ということで、詩的な表現やイメージを喚起させる絶妙な言葉のチョイス、そして弱火でコトコトと煮込むような丁寧な構成で、穏やかな熱狂に包まれる感じも良い。
今もそうだし、この楽曲がリリースした時期もそうだけど、とにかくフックが多くて刺激が強い楽曲が多かった。
そんな中でも、独特の渋みと、歌・メロ・言葉・構成・音づかい。様々な要素で魅了する「カメレオン・レンズ」にぐっと引き込まれたのだ。
タイトルのカメレオン・レンズも歌詞を全部追うことで、そういう役割の単語なのね!とわかる構成なのも良いしが、楽曲のテーマ性そのものも何回も聴いていくことで、その輪郭が見えてくる感じなのも良い。
そう。
一発で意味がわかるし、一発で聴いて楽しい。でも飽きるのが早い。みたいな音楽もある中で、岡野昭仁の洗練された”力強くて表現力豊かな”ボーカルと、新藤晴一の研ぎ澄まされたセンスが組み合わさった「世界」を感じたのだった。
ああ、ポルノグラフィティってどんどん進化している。
「アポロ」でデビューしたあの頃のポルノグラフィティも確かに良かったけれど、岡野昭仁と新藤晴一の個性が混じり合う今のポルノグラフィティも最高で感動的。
そのことに、改めて気づいた楽曲の出会いだったのだ。
テーマソングの話
あれから月日が流れて、発表されたのが、「テーマソング」。
2021年8月2日に発表された『ポルノグラフィティ 2021 “新始動”[3]』のファンファーレとなるニューシングル。
前作『VS』から過去最長となる784日(2年2か月)のインターバルを経てのリリースとなった楽曲だ。
この楽曲の作詞は、新藤晴一。
この楽曲の作曲は、岡野昭仁。
ポルノグラフィティが凄いのは、どちらも作詞作曲を手掛けられること。
なんなら楽曲によって、作詞と作曲の役割すら交代できることだ。
「テーマソング」の楽曲構造の話
振り返ってみると、意外と「ポルノグラフィティらしさ」って、何かを考えるのは難しい。
魅力はたくさんあるし、挙げようと思ったらいくらでも挙げられる。
岡野昭仁の個性も挙げられるし、新藤晴一の個性も挙げられる。
でも、これこそがポルノグラフィティの核だ、ワンフレーズで言語化するのは難しい。
Xで業務連絡をするし、個性的なグッズ販売もするけれど、そもまたポルノグラフィティの核かと言われたら違うし。
ただ、その上で「テーマソング」という楽曲は、これまでのポルノグラフィティの楽曲とは違う魅力を覚えることになった。
というよりも、今のポルノグラフィティだからこその光が満ちていた、とでも言えばいいだろうか。
というのも、「テーマソング」って、楽曲展開がけっこう独特なのだ・。
特にそれを感じるのが、2番のBメロ以降の流れ。
予想のつかないメロディーの流れにゾクゾクさせられる。
特に、「振り向けば夕日があって〜」のフレーズ。
ここで、強烈な存在感を示す。
一定のリズムを刻むことで、高揚感を生み出すビートメイク。
その中を多重なコーラスがメロディーを紡ぎ、楽曲の空気を大きく変える。
爽やかな印象の強いアレンジなんだけど、ふいに今までの違う流れを生み出す。
結果、良い意味で違和感が生まれて、ぐっと楽曲の世界に引き寄せられる。
このパートに至るまでに使用したワードも相まって、「テーマソング」というタイトルの意味性も浮かび上がる。
タイトルも歌詞のチョイスも楽曲の構成にも繋がりがあることが感じられるのが良い。
ポルノグラフィティのキャリアであれば、楽曲構成なんて己の手癖を使った構成にするアプローチもあるが、「テーマソング」は明確に歌のタイトルがこうだから、こういう歌詞があって、だからこそ楽曲構成にした、みたいな意志を感じる。
それが、楽曲構成の独特みに繋がっているのだと思う。
なお、楽曲全体でいえば、1番・2番のBメロも独特の雰囲気を作り出している。
サビは爽やくて王道ポップスな雰囲気を作り出しているのに対して、Bメロの音選びや空気感はどこまでも独特。
ここが良い。
そういうアレンジにすることで、一旦曲の流れを変えるんだ・・・!?みたいな驚きがある。
ボーカルが作曲を手掛けているからこそ、歌のテンションとメロディーの流れがシンクロしている心地も覚える。
<ポジティブなメッセージ・ソング>という装いではあるんだけど、ふいにこういう<独特さ>を楽曲の中に忍ばせる巧み。
ベタなテーマながら、ベタでは一切ない魅せ方を体感できるのである。
「テーマソング」の言葉の話
<フレー>という言葉が印象的な応援歌なのに、Aメロでは<歴史学者のペン先>という独特のフレーズをさらっと忍ばせる。
こういうワードチョイスは、新藤晴一らしさを感じる。
一般的なポップソングでは絶対に使わないワードチョイスを忍ばせつつ、ちゃんとその言葉を使う意味を楽曲内で昇華させる。
こういう技が、新藤晴一は上手い。
また、<私>と<君>ではなく、<私>と<私みたいな人>の対立軸の楽曲にしている辺りも、新藤晴一らしい眼差しが炸裂している。
歌詞を立体的に絵に起こして考える余白が歌詞全体であるというか。
一回聴いて「はいはいこの歌ってそういう歌ね」と感じるようなサプリみたいな歌ではなく、何度も聴くことで世界を体感できる薬味のような世界・・・みたいな感じ。
狙ってやろうとしても、きっと普通のアーティストでは「こうはならない」。
新藤晴一のセンスが炸裂している楽曲であると言えるだろう。
ボーカルの話
「テーマソング」は、こういう時代だからこそのポジティブなメッセージ・ソングだと受け取っている。
にしても、岡野昭仁の<言葉に魂を込める表現力>は相変わらず凄まじい。
ポジティブな歌の場合、言葉そのもの切れ味はどうしても薄くなりがちだ。
下手をすると、言葉がありきたりなものになる分、ボーカルの妙に軽くなってしまう可能性だってある。
でも、岡野昭仁が歌う場合において、そういうことが一切ない。
ありきたりな言葉であっても、その歌にしかない魂が込められる。
例えば、<フレー>というワード。
応援歌における<フレー>ってあまりにもベタな存在のものだ。
だから、ベタな言葉=軽く聞こえる可能性もある。
でも、岡野昭仁が<フレー>を歌うと、<フレー>という言葉以上の意味づけが<フレー>になされる=言葉に魂が込められる。
だからこそ、楽曲そのものの表情が豊かになる。
岡野昭仁のボーカルの表情の豊かさって、こういうところに詰まっているように思う。
もともと、新藤晴一がテクニカルな歌詞を書きがちだけど、それが時にポップに着地することもあれば、より何難解な世界に誘うことができているのは、それを岡野昭仁が歌うから。
作詞と歌い手が異なるからこその面白さでもあるし、それぞれがプロフェッショナルを発揮するからこその境地であるとも言える。
「テーマソング」って、定番なテーマでありながらも、定番の歌っぽくはない言葉の魅力がある。
それは、新藤晴一が歌詞を書いて、岡野昭仁からこそであると、改めて感じられる楽曲である。
ヴィヴァーチェの話
この記事を執筆した段階での最新曲が「ヴィヴァーチェ」。
びっくりするのは、「テーマソング」と役割が逆になっていて、
作詞が岡野昭仁、作曲が新藤晴一というところ。
前項目でも書いたが、作詞作曲をここまでフレキシブルにできるところが、ポルノグラフィティの圧倒的な魅力。
だからこそ、同じアーティストなのに、時期ごとにどんどん魅力が変わるという面白さもあるのだ。
さて、「ヴィヴァーチェ」の話だけど、疾走感がありつつも、どこか異国情緒あふれる雰囲気なのが良い。
ポルノグラフィティの楽曲って、初期からポップともロックともちょっと違う、他のジャンルの音楽のエッセンスを感じることが多い。
「サウダージ」然り、「アゲハ蝶」然り。「シスター」然り、「オー!リバル」然り。
毎回、+αのエッセンスが鮮やかかつ、他のアーティストにはない楽曲の色合いなので、ポルノグラフィティの強鉄な個性として響くことも多い。
「ヴィヴァーチェ」もまた、そういう装いだ。タイトルもイタリア語というだけあって、どこかイタリアっぽい空気感をアレンジから感じる気もする。
しかも、ひとつのパートの中で様々な音がなっており、鍵盤も弦楽器も盛りだくさん。
その上で、新藤晴一が弾く軽快なギターが楽曲の軸を組み立てていく。
ここもポイントで、ポルノグラフィティって二人組だからサウンドの縛りがなくて、楽曲ごとにフラットにアレンジを組み替えられる。
その一方で、どの楽曲も新藤晴一のギターが重要なポイントの音を紡ぐことで、ある種の一貫性を生み出す。
自由ではある。
でも、ブレはしない。
そういうポルノグラフィティの矜持を感じる一作でもあるような気がする。
あとは、シンプルにメロディーが良い。
中毒的という感じではないんだけど、何度も味わいたくなるような溌剌さがある。
これは、岡野昭仁のボーカルの抑揚の付け方が絶妙だからだと思う。
音を伸ばすところと、リズムを詰め込むところのコントラストが鮮やかなので、ぐいぐい歌の世界に引き摺り込まれるのだ。
まとめ
改めてこうやって連作で聴いていくと、この二人だからこその楽曲だらけであることを痛感する。
二人組のアーティストは世にたくさんいるが、そのどれとも違う関係性だからこそ生み出すことのできる楽曲の数々。
2025年も、そんな二人だからこその世界が展開されていくのだろう。
そんな予感しかない。