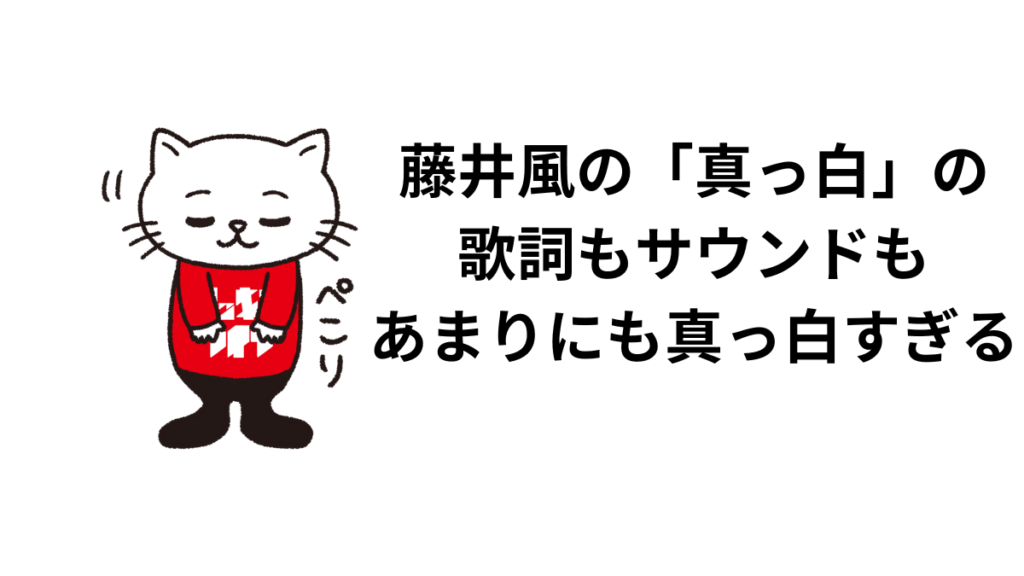藤井風の「きらり」に宿るささやかな中毒性の考察
大ブレイクを果たすと、マニアックだった作風で存在感を放っていたアーティストが大衆的な作品を生み出すことがある。
なんというか、楽曲の引っかかりポイントが変わっていくというか、持ち味だった個性がナリを潜めて、聴きやすくなっていくことってあると思うのだ。
良くも悪くも。
そして、もしかしたら藤井風の「きらり」もそういう類の楽曲になってしまっているのではないかと勝手ながらに思っていたのだ。
というのも、この歌はCMソングのための書き下ろし楽曲となる。
ということは、少なからず、たくさんの人に聴かれることを想定して生み出した楽曲であると言えるわけだ。
そのため、自ずと楽曲全体の装いも今までの藤井風の楽曲よりも大衆的になるのではないかと思ったわけだ。
個性的なアレンジや言葉遣いで勝負するような楽曲とは、違うテイストになると思っていたわけだ。
もちろん。
楽曲が大衆的になることは悪いことではない。
当然、それで藤井風の魅力が軽減されるわけでもない。
でも、それが楽曲の魅力の方向を変えてしまうとは思ったし、それがどの方向に転がるかは未知数だと思っていた。
フルでこの楽曲を聴くまでは。
藤井風の「きらり」の感想
磨かれていく才能
タイトルが「きらり」であるこの歌。
楽曲全体の装いも初夏にマッチしそうな、爽やかなテイストの一曲である。
この一年で、より洗練された藤井風のスマートかつ甘い歌声が存在感を解き放つ。
そうなのだ。
この<洗練された>がこの楽曲においては重要なポイントだと思っていて。
この歌は、わかりやすい個性でぶちかますというよりは、円熟味した表現力で音楽の心地よさを提示するような印象を持つ楽曲、と言えるのではないだろうか。
でも、考えたらここで<円熟味>というワードが出るのも変な話である。
だって、最近は30代後半でも<若手お笑い芸人>とラベリングされる時代である。
芸能分野における高齢化が進んでいるわけだ。
音楽シーンだってその例外ではなく、<若手>という位置づけのアーティストでも、それなりにキャリアを重ねている人だって多い。
藤井風は20代前半のアーティストである。
十分に<若手>と評されてもおかしくないアーティストだし、確かに若い感性を炸裂させているアーティストでもある。
だけど、ひとたびボーカルとしての魅力を語るうえでは、<フレッシュ>というワードよりも<円熟>という言葉が腑に落ちるように思うのだ。
少なくとも、個人的には。
それだけ藤井風のボーカルが洗練されているということである。
「きらり」では、その円熟性が炸裂している。(変な日本語ではあるが)
「きらり」って良い意味で、さらっと聴ける質感があると思う。
スルメ曲と評したくなるような聴きやすさがあるように思う。
それは、なぜか。
深く聴き込んでいくと、それは藤井風のボーカルがどこまでも研ぎ澄まされているからこその聴き心地のように思うわけだ。
まだまだ若いアーティストでありながら、すでにこの領域に到達しているように思うわけだ。
ダンサンブルなリズムメイクと藤井風の歌声
昨年5月に発表された『HELP EVER HURT NEVER』だと、シンプルなアレンジだったり、鍵盤をメインにした楽曲が多く収録されていたように思う。
そのため、ダンサンブルというよりはソウルフルな楽曲が多かったように思うのだ。
しかし、「きらり」はダンサンブルな部分が際立った楽曲のように思う。
テンポ良くリズムを刻む打楽器の音だったり、洒脱で軽妙なサウンドを鳴らすギターの音色が、そういう空気感を作っている。
規則的なビートの中を藤井風が鮮やかに歌い上げるからこそ、どこまでも楽曲がダンサンブルに輝くのである。
で。
「きらり」を感じて思ったのは、こういうテイストの楽曲でも、藤井風は藤井風らしい輝きを放っているんだなあ、ということ。
規則的なリズムが印象的になるということは、エッジの効いた個性は(ぱっと聴きには)見つかりにくい可能性が高くなる。
確かにその結果、それがこの歌のマイルドな印象を与えているように思うわけだ。
が、単純なシンプルな歌になっているかといえば、そんなことはない。
聞きやすい楽曲ではあるが、印象に残らない楽曲かといえば、そんなことはまったくない。
むしろ何度も聴きたくなるという意味で、中毒性を放っているともいえる。
素朴な曲なのに、中毒性があるのだ。
こんな芸当、選ばれた人間にしかできないと思うし、藤井風だからこそ成立している事例だと思う。
つくづくこの男、凄まじいと思わずにはいられない。
細かい部分での楽曲の魅力
イントロとアウトロはなしにしているのも、この歌のダンサンブルな一面を劇的なものにしている理由のひとつな気がする。
これにより、ダレることなく楽曲の魅力がぎゅっと詰まっている印象を受けるのだ。
でも、サウンドが<手抜き>かといえば、そんなこともまったくなくて。
この歌には、しっかりと間奏があるけれど、そこも印象的なものにになっている。
というのも、この歌って爽やかで聴き心地が良いんだけど、不思議と妙な切なさも宿しているように思うのだ。
で、そのことをはっきりと感じさせてくれるのが、間奏の流れだったりするのだ。
音の流れとか、その音が紡ぐグルーヴの中に、きらりとした輝きを発見する。
そこから再び藤井風のボーカルが合流したとき、そこにある表情にもはっと気付かされたりして、どんどん楽曲の深みにハマっていったりするのだ。
なんにせよ、シンプルな楽曲に見えて細かい部分にもこだわっているからこそ、この楽曲にはっきりとした中毒性が宿っている、という話である。
まとめ
まとめると、ただ一言になる。
今年も、藤井風は圧倒的な存在感を放つはず。
「きらり」を聴いて、それが確信に変わったということだ。
まだ聴いていない人は、ぜひ彼の音楽世界に浸ってみてほしいと、ただただそう思うのである。