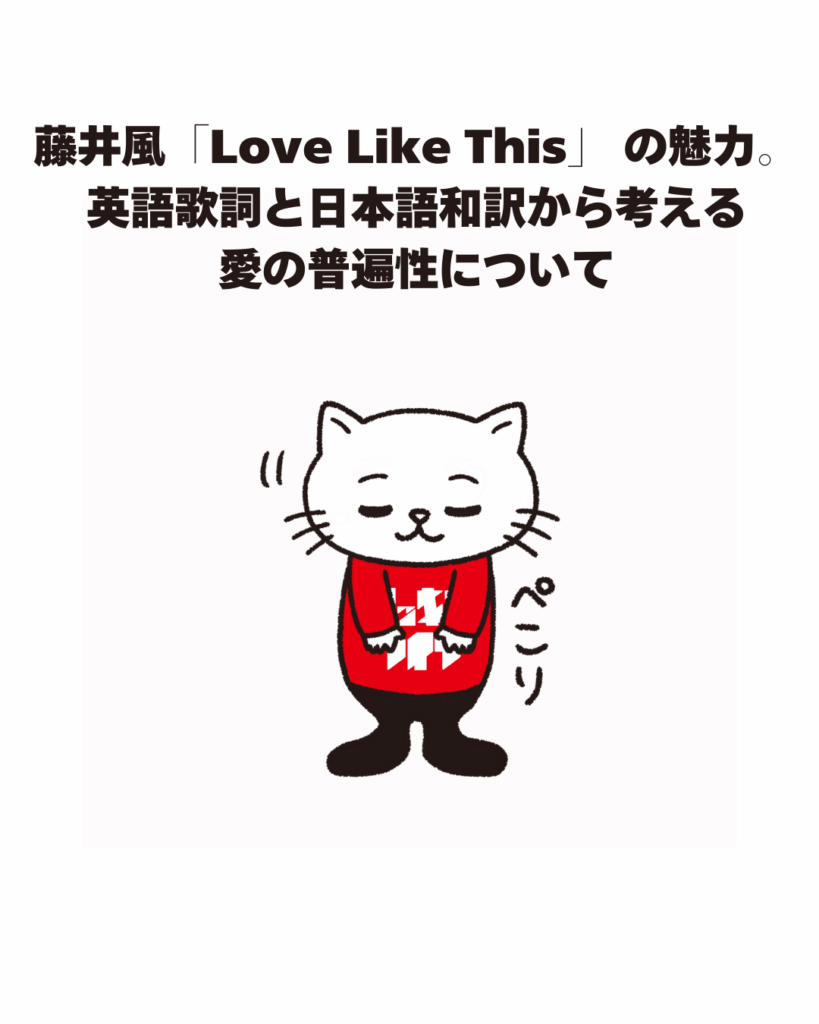藤井風の「まつり」、やば。
あるタイミングで、「このひと、すげー」と様々な人から大きな称賛をもってシーンで躍進したとする。
そういう人って、大方、以降の作品も「すげー」の作品を連発することになる。
でも、悲しいかな、人間は良くも悪くも慣れの生き物である。
あんなに「すげー」といってきたあのアーティストの作品も、いつしかその「すげー」が標準装備になってしまうことってある。
卓越したボーカルも、リズミカルな歌いこなしも、個性的なメロディーラインも、気がついたら「すげー」が「また、これか」に変わってしまうことって、よくある。
しかも難儀なのが、この「すげー」を裏切って、まったく違った「すげー」を提示しようとしても、必ずしも暖かい称賛で迎えられるわけではないということ。
というのも、過剰な方針転換をすると、「この変化はこの人の魅力が消えてしまった」みたいなことを言われてしまうからだ。
バンドの中の場合だと、ゴリゴリに荒削りな日本語ロックを展開していたバンドが、洋楽顔負けのかっこいい音でぶちかますと、「上手くはなっているんだけど、えぇ・・・・・・初期の頃の方が良かった」なんてことを言われる。
かといって、ハンコのような毎回同じ作品を作ると、「どの楽曲も全部同じじゃん」みたいな評価のされ方をするので、難儀も鰻登りになってしまうのである。
前置きが長くなってしまった。
要は、革新性を持ちながら「初期の頃のすげー」を維持するのは、なかなかに至難の業なのだという話。
しかし、だ。
そういう難儀をへでもねーよと言わんばかりに更新させてしまうアーティストがいるのである。
彼の名を、藤井風、という。
この記事では、セカンドフルアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』に収録されている「まつり」の楽曲から、藤井風の魅力について書いてみたい。
本編
ソウルフルな歌声
「まつり」を聴いて、感じた人も多いと思う。
やば。
と。
いや、これ「何なんw」と思った人も多いかもしれない。
では、あえてここで問うてみるが、藤井風の圧倒的な魅力とは何だろうか。
色んな要素があるとは思うけど、なんといっても、そのボーカルにあると思う。
というのも、藤井風ってピアノの弾き語り、みたいなシンプルな構成でもゴリゴリに個性を発揮するタイプである。
なぜこういうシンプルな構成でもゴリゴリに個性を発揮するかといえば、それは藤井風のボーカルそのものが圧倒的な個性を放っているからだ。
シンプルに文章にしてしまうと、
・歌声がどこまでもソウルフル
・でも、ソウルフルな中にセクシーさ(?)も宿っている
・声の質も良いし、メロディーの乗りこなし方もとてもナチュラルかつダイナミック
こういうところにあるのかなーなんて思う。
「まつり」って、単純にメロディーだけ切り取って他のアーティストが歌うとしたら、まったく違うテイストになる気がするのだ。
藤井風のボーカルが命を吹き込むことで、圧倒的な輝きを増す・・・というか。
例えば、人気な楽曲の中では「誰が歌っても良さが変わらない普遍的な良い曲」と、「この人が歌うからこそ輝きを放つ歌」があると思っていて。
藤井風の歌の場合、両方の要素を持っていると思うが、藤井風のボーカルがあるからこその輝きが強い分、後者のイメージが大きく付与されていることになると思うのだ。
カラオケで歌うのが難しいメロディー展開をしているわけではない。
圧倒的なハイトーン・・・みたな選ばれた人しかなぞることができないメロディーになっているわけではない。
でも、絶対に他の人にたどり着くことができない境地の中で、メロディーが紡がれている。
サビのコーラスのさしこみ方ふくめて、どこまでもボーカルが秀逸だからこそであるように思う。
<ねーから>からとか、<肩落とすこた>みたいな部分の口語的なフレーズの歌いこなし方も絶妙だしね。
少し予想を裏切る楽曲展開
個人的には、この<少し>がポイントだと思っている。
これが<大きく>になってしまうと、前置きで述べたような藤井風らしさがきらりとしなくなる気がするのだ。
いやいや、そんなアクセント、もうええわってなってしまうと思うのだ。
こんな新曲ならもうさよならべいべだし、裏切りの繰り返しなんてキリがないから、そんなひねくれなんて燃えよ、ってなると思うのだ。
でも、「まつり」って、その辺りの塩梅が絶妙なように思うのだ。
Aメロのラインは、藤井風らしさをもたせた流れだし、A→Bメロの流れ自体も予想の範囲内のような流れも気もする。
でも、Bメロを聴いている中で少しずつ「ん?」という感触を覚えだし、まつりだからこそのリズムの世界の中にどんどん誘われることになるのだ。
不意に出てくる、えいっ、の掛け声とかはそのアプローチのひとつ。
そして、サビを終わってからエレキギターを存在感を示すアクセントや、和太鼓のビートメイクなど、少しずつ良い意味で秩序を崩していくアプローチに魅了されていき、「良い歌だなあ」となっていた感想が「やば。」に変わっていくのだと思う。
この辺りの変化が絶妙だからこそ、中毒的な魅了をされてしまうのだと思う。
っしゃ っしゃ っしゃ、って歌う頃には歌の世界のど真ん中に自分の意識がもっていかれている。
まあ、あえて言うならば、音楽に対する絶大なるセンスだけは変わりはないといえるのだろうけれど。
ボーカルだけでも個性的かつ魅力的にも関わらず、楽曲展開や言葉選び、サウンドメイクなどでも少しずつ予想を裏切る構成を生み出していくからこそ、「まつり」の名曲感がどこまでもスキのないものになっていくのだと思う。
まとめ
特にない