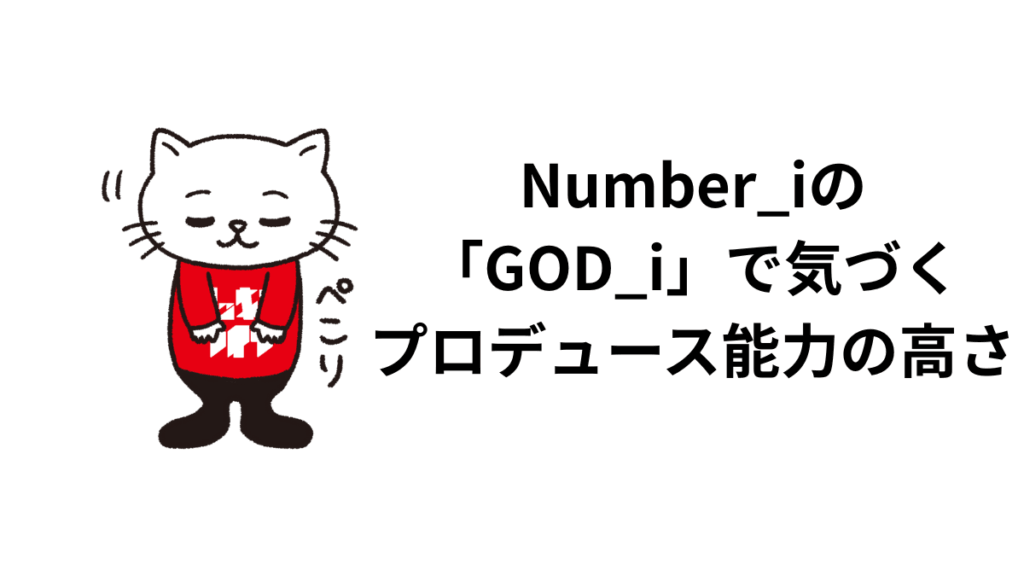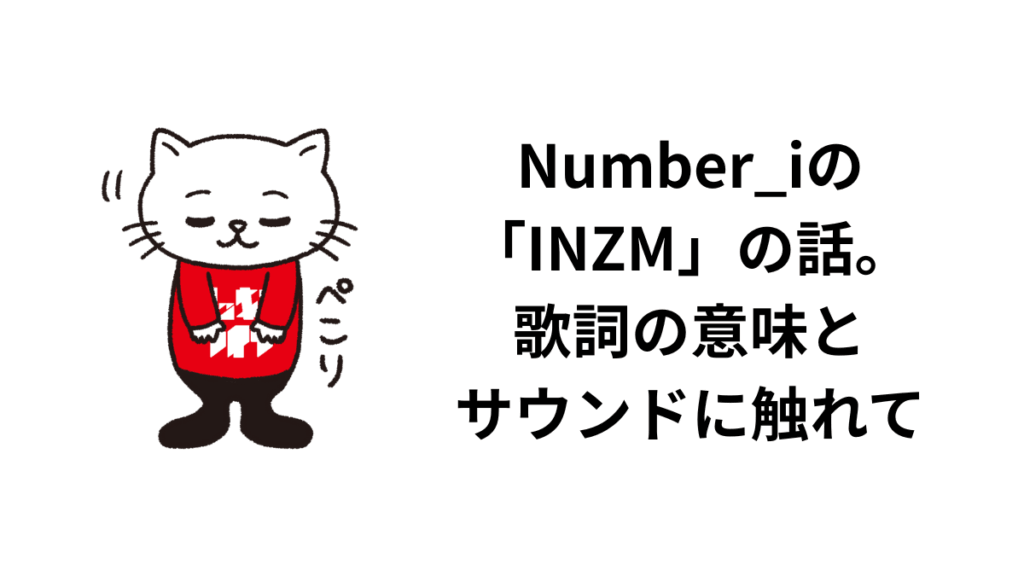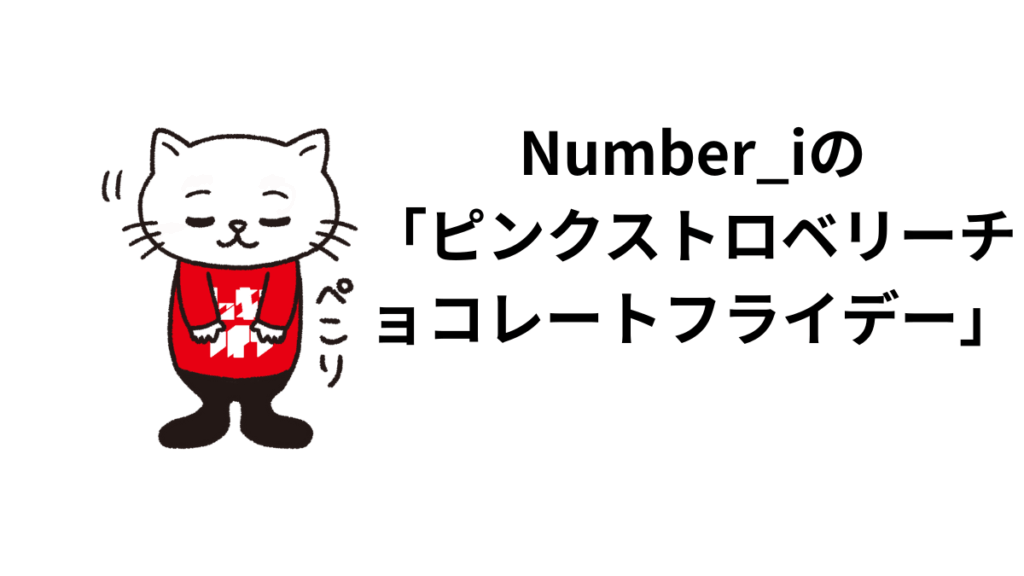
Number_iの「ピンクストロベリーチョコレートフライデー」の話。平野紫耀の歌詞、作曲に触れて
Number_iの「ピンクストロベリーチョコレートフライデー」。
この歌は平野紫耀プロデュースで、平野紫耀ソロ楽曲ということらしい。
あんまりソロ曲にまでスポットを当てて感想を書くことはないんだけど、「ピンクストロベリーチョコレートフライデー」を聴いていると、やっぱりこのグループは底なしだなーと思ったという話だ。
一言で言うと、多面的。
Number_iの「ピンクストロベリーチョコレートフライデー」の音楽的な魅力
というのも、自分は別記事でNumber_iの音楽にはどことなく、オラオラ感があるという言葉を書いた。
で、Number_iってそういう洗練されたオラオラ感をひとつの武器にしているグループであるという前提でこの楽曲を聴いてみると、なんて優しくて、なんてノスタルジックなんだと思うわけだ。
Number_iといえば、力強いビートとシャープなラップで攻めてくるイメージが強い。だからこそ、この楽曲で聴かせるメロウな雰囲気は、意表を突かれるというか、新鮮な驚きがある。
同じアーティストが、こうも違う表情を見せられるというのは、それだけ引き出しが多いということだ。強さを知っているからこそ、優しさがより際立つ。そういうコントラストの妙が、この曲の最初の魅力だと思う。
もちろん、「ピンクストロベリーチョコレートフライデー」にも、ゆったりとしたテンポの中で、切れ味鋭いラップを披露するんだけど、この歌においては鋭さそのものよりも、鋭さの中に隠された繊細の部分にぐっと胸を打つことになる。
ちょっとダウナー的というか、柔らかさのある展開の中で、切ない思い出をていねいに描いてみせる。
Number_iの歌全体でみても、ある種のポップさやエモさが際立った歌と言えるのではないだろうか。
ストロベリーチョコレート甘いまま
手についたからデニムで拭くばか
なんてフレーズも然るべきタイミングで、然るべきトーンでフロウされて、歌の中に組み込まれていく。
フレーズから想像させる景色が巧みだし、それをメロディーに落とし込む音のチョイスが絶妙で。
言葉が想像する景色と、音楽になるときのあり方があまりにも素晴らしくて、マジで見て聴いてほしい一節だ。
まじで「ばか」の響きが良すぎるのだ。
サビのフレーズもストレートでわかりやすいからこそ、歌としての破壊力も際立っていて、柔らかい空気感とあいまって、これまでのNumber_iの楽曲とは異なる感涙を与えてくることになる。
派手な表現や難解な比喩ではなくて。
シンプルで耳馴染むような言葉ながらも、ここにぴったりハマる言葉のチョイス。
そして、歌としては最終的に切なく響くのも絶妙だ。
切ないR&Bが好きな人に刺さるだろうし、ユーモアのあるトラックメイクがツボという音楽リスナーも刺さるような包容力がある。
現代の音楽的なスタイリッシュ感=ある種のデジタル性を歌の中に巧みに組み込み、オートチューンをかけたボーカルときれいに融合させながら、歌を展開する。
機械的でもあり、エモーショナルでもあるという不思議な響きを与えることになる。
特にオートチューンの使い方が秀逸だ。過剰に加工するのではなく、生声の温もりを残しながら、ほんの少し機械的な質感を加えることで、懐かしさと新しさが同居する独特の空気感を作り出している。
この絶妙な塩梅が、R&Bというジャンルに現代的な解釈を加えた結果なんだと思う。トラックもシンプルながら洗練されていて、ボーカルを引き立てつつ、心地よいグルーヴを生み出している。
さらに言えば、この歌が2分30秒ちょっとということに驚く。
実際に楽曲を聴けばわかるが、歌のドラマがどこまでも深くて、心地良いからだ。
もっと中尺の言葉としてのドラマ性がたっぷりある楽曲を味わったような快感。
短いからこそ何度もリピートしたくなる。その中毒性も、この曲の大きな武器だと思う。
そういう魅力が、「ピンクストロベリーチョコレートフライデー」にはある。
まとめに替えて
結論。
平野紫耀の音楽的センスが炸裂している。
なにより、Number_iの音楽的な幅広さに脱帽する。
アルバム全体を聴くことで、なぜNumber_iは凄いと言われているのかを改めて実感することになるのだ。
そんな魅力がたっぷり詰まった、そんな作品。