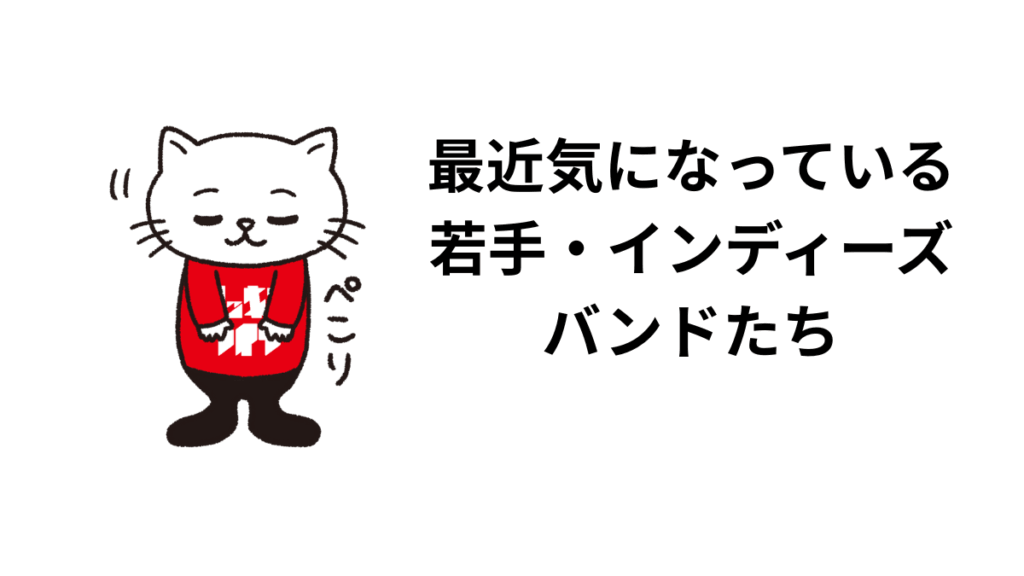赤い公園というバンドの素晴らしさについて
赤い公園は、他のバンドにはない稀有な歴史を持ったバンドである。
その中でも、もっともトピックとして大きいのはボーカルの脱退と、新たなボーカルの招聘であろう。
赤い公園は、活動中の中でボーカルが変わるという転換を迎えたバンドである。
佐藤千明と、石野理子。
ふたりとも、魅力あるボーカルであったことは間違いない。
どちらの赤い公園も良かったし、両者とも己にしかない技を持っているボーカルだった。
ただ。
自分がどう思うのか、という話をさせてもらえるならば、自分はとくだん石野理子がボーカルを取るようになってからの赤い公園が好きだった。
彼らの音楽がより自分のツボにジャストミートするようになったのだ。
それはボーカルが変わったから、というだけの話ではない。
なんというか、これを契機にサウンドのカラーやバンドが持つ武器の類も変わったように感じたのだ。
少なくとも、津野米咲が生み出す楽曲世界と、石野理子の混ざり方が絶妙だった。
「消えない」は冒頭のギターのカッティングが印象的な歌である。
ただ、美しく音を響かせるギターに対して、ドラマのアプローチがわりと挑戦的で、「わかりやすさ」ではなく「己の美学」で勝負することを予感するような構成になっている。
サウンドアプローチが細かくて丁寧で、そこからは圧倒的な繊細も感じさせる。
トータルでみると、繊細なんだけど、ロックバンドだからこその攻撃性も音に内包しているサウンドで。
ソリッドなギターサウンドを響かせるのに、「美しい」という言葉が似合う音の広がりを見せるようなサウンドで。
グイグイと音の世界を自分の色に染め上げる「消えない」という歌は、他のバンドにはない美しさとワクワクを持った一曲だった。
相反するふたつの要素を持ったサウンドだけでも十分に魅力的なのに、そこに凛とした透明感を持っている石野理子のボーカルが組み合わせられる。
冗談抜きで、無敵なように感じられた。
一時期ロックとポップの境目を揺れ動いていた赤い公園が、ついに然るべき形に進化した。
そんな気分にさせられたのだった。
ここから自分たちのやり方でロックシーンをひっくり返すような、とんでもないことをしでかすような、そんな予感を感じたのだった。
「Highway Cabriolet」でも、赤い公園ならではの魅了を随所に感じさせてくれる。
一連の歌を聴いていると、赤い公園の持つオルタナティブに磨きがかけられたように感じるのだ。
バンドサウンドが中心にある。
でも、その音は先の先までこだわりと美学を感じさせてくれていて、ちゃんと空間の中で音が響いている感じがするのだ。
音が表面的なのではなく、立体的な響きを持っている、とでもいいだろうか。
だからこそ、音の余韻が楽曲世界を幻想的に彩るような心地を覚えるのである。
バンドサウンドの響かせ方にこだわっていることを実感させられるサウンドディレクションだったのだ。
そして。
繊細かつ大胆な赤い公園のサウンドに、石野理子のボーカルがどこまでも似合っていた。
そういう話なのである。
リズムやメロディーそのものにスポットが当たりがちな音楽シーンにおいて、バンドってこういう魅力もあるんだぜ、ということを突きつけるような、そういう感触だった。
豊富なアイデアから生み出されるアレンジ力と、そのアイデアをちゃんと形にする演奏力があるからこそ成立する魅せ方だった。
THE PARKというアルバムについて
そういう赤い公園ならではの魅力が炸裂したのが、2020年4月にリリースされた「THE PARK」というアルバムだった。
ギターロックとしてのゴリゴリさがある。
まがいなく、赤い公園のオルタナティブ・ロックが炸裂している。
攻撃的なサウンドが印象的な「絶対零度」は、まさにそういうテイストの代名詞な一曲だ。
ただ、この曲でも、きちんと繊細さとゴリゴリのアンサンブルを見て取ることができる。
Aメロは「絶対零度」のタイトルにふさわしく、クールになるパートとバンドの音がアグレッシブになる対比が見事になっている。
このバンドサウンドの変化のさせ方にふれるだけでも、一気に息を呑ませられる。
そんなテイストであるんだけど、サビはわりとキャッチーでダンサンブルになるのも、赤い公園の面白いところ。
ドラマのビートがちょうどいい軽妙さを持っていて、オルタナティブなサウンドに良いアクセンスを生み出していく。
ロックそのものに一方通行というわけではなく、オルタナティブの土台がありつつも、そこに揺さぶりをかけるようなアプローチも絶妙なのである。
だからこそ、よりゴリゴリしているのに、繊細さを感じるのかもしれない。
ダークなのにキャッチーさも感じさせる、と言い換えることもできるかもしれない。
いずれにせよ、そういう独特のレンジの広さを持っている作品だったわけだ。
「公園」というバンド名と同じ単語が入っているこの曲でも、そういうものをたくさん見て取ることができる。
冒頭のギターのカッティングは超絶なるオルタナだし、そこからのバンドアプローチもゴリゴリなロックのそれ。
でも、ボーカルが入るとさっきとはまたちょっと違う景色を見せる感じ。
赤い公園ならではの視界の開け方をしていくのである。
石野理子の透明感のあるボーカルがあって。
藤本ひかりの技が光るベースがあって。
歌川菜穂の引き出しの多いドラムがあって。
そして、なにより。
津野米咲という”音楽オタク”が様々な要素を楽曲に放り込むからこその、絶妙かつ超絶なるアンサンブルがそこから生まれていく。
つまり、この四人だからこそ、生み出すことができた、そういう快作だったように思うわけだ。
「THE PARK」というアルバムは。
ロックバンドって、こういう音も鳴らせるんだぜ。
こういう魅せ方もできるんだぜ。
そういう可憐なかっこよさに包まれた作品だった。
赤い公園というバンドの素晴らしさが詰まっている、そういう作品だった。
このタイミングになって、改めて聴き直して、そのことを強く、強く、いまさらかもしれないけれど、改めてそのことを感じるのである・・・