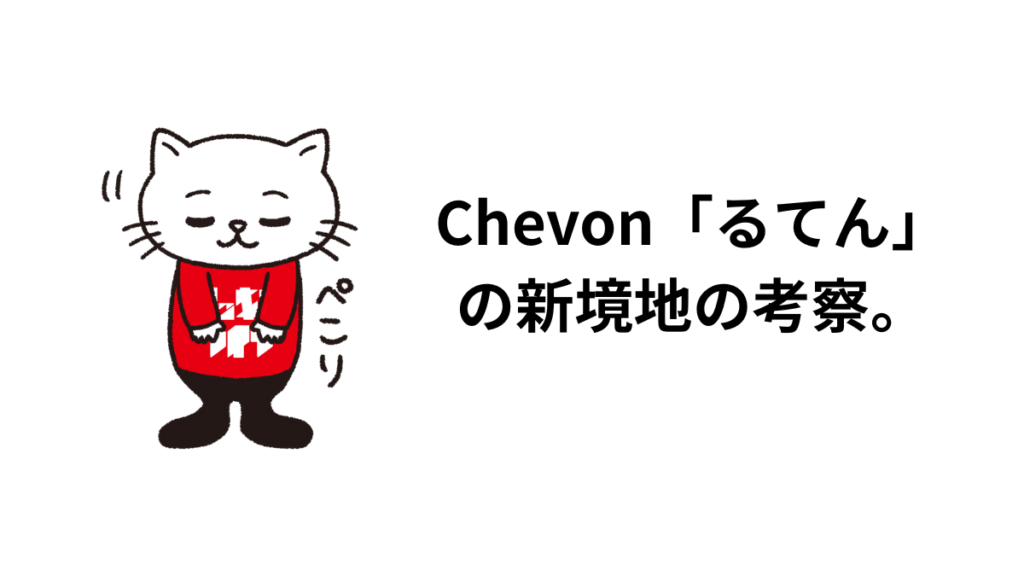Chevonの『Chevon』、あまりにも”ベスト”アルバムな件
昨年は、Chevonの音楽は比較的コンスタントに聴いてきたと思っているので、多少なりともその良さは知っているつもりでいた。
が。
改めて、ファーストフルアルバムとなる『Chevon』を聴いて、思った。
このバンドの凄っ!、と。
というのも、作品全編を通じて、とにかく自分のツボへの刺し方がえげつないのである。
話は逸れるが、誰もが音楽に対して、好みという名のツボを持っていると思う。
で、自分のツボを的確に刺激する音楽には沼のようにハマっていくだろうし、若い時に刺激されたツボがその人の音楽の好みのベースになることも多い。
このツボって人によって浅かったり、広かったりと、様々ではあるんだけど、どれだけツボが敏感な人でも、中毒性を喚起するほどのツボのツボを刺激されるケースって、そこまで多くないとは思うのだ。
逆説的に言えば、そこまでのレベルでツボを刺激されるケースって多くないからこそ、本当にそこを刺激されてしまったときに、ハマってしまう感じはやばいものになるんだろうなあと思っていて。
何が言いたいかというと、Chevonの『Chevon』はそういうレベルのツボ押しをされる心地があったという話だ。
アルバムの流れがあまりにも惜しみなくて、『Chevon』というアルバムを聴いて、改めてそのことを実感したという話だ。
というわけで、この記事では『Chevon』という作品を通しながら、自分が思うChevonの魅力を言葉にしてみたいと思う。
Chevonの『Chevon』の感想
今回のアルバム、まず、曲の並びがえぐい。
キラーチューン祭りすぎる。
まず、最初は「No.4」だ。
Chevonの楽曲の中では、比較的テンポが落ち着いた楽曲ではあるけれど、リズムに余白がある歌だからこそ、ノリノリになって楽曲を聴くことができる。
かつ、サビはキャッチーで、一度耳に入れると、何度も頭の中でリフレインする。
いきなりドストレートに”ツボ”に刺激する楽曲が登場することを実感する。
すると、ここから「ダンス・デカダンス」「ですとらくしょん!!」「ボクらの夏休み戦争」と、ライブでも盛り上がりそうなアッパーチューンを容赦なく連発させる。
ライブだったら、もう踊りすぎて疲れちゃったぜ・・・って思ってしまってもおかしくないほどの容赦なさ。
Chevonのこういう疾走感のある楽曲のビートメイクって、とにかくエネルギーが宿りまくっていて、密度が濃い。
だからこそ、動き出さずにはいられない衝動が生まれることになる。
2010年前半のボカロシーンで存在を魅せていたような、切れ味鋭いビートメイクのイズムも感じさせるような、でも、別にボカロをバンドでやりました、みたいな安易さは一切なくて、バンドとしての切れ味がダイレクトにビートにのっかているからこその熱量。
しかも、このビートは速いから良いとかそんなんじゃなくて、テンポに依存しない切れ味がある。
だからこそ、「ノックブーツ」「サクラループ」「薄明光線」のような、疾走感よりも、ポップさが際立つようなナンバーでも、ノリノリのビートで魅了されることになる。
Ktjmのギターサウンドと、オオノタツヤのベースラインが土台となって構築されるスリリングなバンドアンサンブル。
この楽曲のこのパートでは、こういう手できたかと思うと、次はこんなアプローチできたぞ!うおーっ!ぐおーっ!となるのである。
しかも、Chevonてビートとかアンサンブルだけで聴かせているわけではない。
バンドサウンドの存在感も良いんだけど、それ以上に際立つボーカルの存在感。
楽曲ごとに表情が変わる谷絹茉優の表現力ある歌声があるからこそ、Chevonの歌はどこまでも生き生きとして響く。
アルバム中盤にやってくる「セメテモノダンス」なんかでも、改めてそういうボーカルの魅力の強さを実感することになる。
以降の楽曲でも、Chevonのライブのキラーチューンが惜しみなく収録されており、あまりにもスキがない。
結果、どこを切り取っても沼になるし、常に刺激に満ちることになる。
なぜ、Chevonの楽曲は良いのか?
『Chevon』というアルバムは、これまでのChevonの魅力をベストアルバムっぽい体裁でぎゅっとした作品だと思っているんだけど、こうやって楽曲を聴いていくと、”飛ばしてしまいたくなる歌”がマジでないことに気づく。
どんな人にも好みはあるだろうから、アルバムの単位のパッケージだと、飛ばしたくなる曲って、わりとあったりすると思うのだ。
でも、『Chevon』という作品においては、本当にそれがない。
これだけは飛ばせない、これだけはフルで聴きたい、の楽曲が連続してしまっていて、アルバムの頭から聴いていった場合、意図せずしてアルバムの曲順通りに聴いてしまうような魅力がある。
ベストアルバムっぽい作りとはいえども、そういう楽曲だけを発表し続けてきたChevonの感度の凄さを実感することになる。
ライブのセットリストにおいて、このアルバムの収録曲だけで構成されていたものが続いたとしても、きっと「ぜんぶ神曲」と答えてしまいそうな感がある。
しかも、ここでいう「神曲」は、玄人好み的な話ではなくて、もっと素直かつダイレクトに、どの楽曲もツボを刺激してくるからこその話なのだ。
なぜ、Chevonの歌にここまで惹かれるのだろう?
これは、先ほどの項目で言葉にしたが、バンドアンサンブルにどこまでも切れ味が宿っているからであり、谷絹茉優のボーカルの表現力が素晴らしいから、に尽きると思う。(もちろん、生み出している根本の楽曲が素晴らしいことも前提にあるが)
特に、谷絹茉優のボーカルには特筆したい要素が多い。
低音だったり、がなりっぽい歌声のときもかっこいいし、ファルセットを使いこなしたり、ハイトーンで聴かせるときは聴かせるときで、また違うかっこよさを引き出していく。
だからこそ、どのメロディーラインを歌いこなす場合でも、ボーカルの輝きが半端ないことになる。
『Chevon』を振り返ってみると、どのアルバムもツボを刺激しまくることを通底しているんだけど、じゃあアルバムとして似たような曲ばかりが収録されているのかというと、そんなことはないことに気づく。
「Banquet」は骨太などっしりロックサウンドって感じだし、「antlion」はノリノリなビートメイクで中毒的に踊りたくなるようなパワーがあるし、「スピンアウト」は洒脱なギターのカッティングが印象的でクールな空気感があるし、幅広いアプローチを堪能することになる。
また、ひとつの楽曲内でも、1番と2番とラストのサビで、表情ががらりと変わり、アトラクションに乗っているような爽快感の中で、色んな景色を楽しむことができる。
だから、Chevonの楽曲って、どの曲も惹かれてしまうのだ。
特定のフォーマットにハマっているから、沼るのではない。
どういうフォーマットの楽曲であっても、類稀なる演奏力と、鮮やかなボーカルの表現力で、Chevon色に塗り替えながら世界観を構築するから、沼る。
『Chevon』というアルバムを聴いて、改めてそんなことを感じたのだった。
まとめに代えて
ただ、『Chevon』という音源を聴いて思ったことがもうひとつあって。
確かに『Chevon』というアルバムは名盤だと思うし、個人的に2024年を代表する作品のひとつになっていると思っている。
・・・んだけど、Chevonの魅力の全部が出ているかというと、必ずしもそうとは言えないな・・・と思ってしまっていて。
というのも、ライブは、音源で上がった期待値をさらに超えていく爆発力があるように思うからだ。
もし、音源を聴いて100点だなと感じるとしたら、ライブを観ると、その100点にプラス20点の加点をせざるを得ない凄さがあるというか。
何回かChevonのライブを観ているからそう感じるし、故に、2024年の今、Chevonはきっとさらなる飛躍を遂げるんだろうなーと感じている、そんな今の自分。