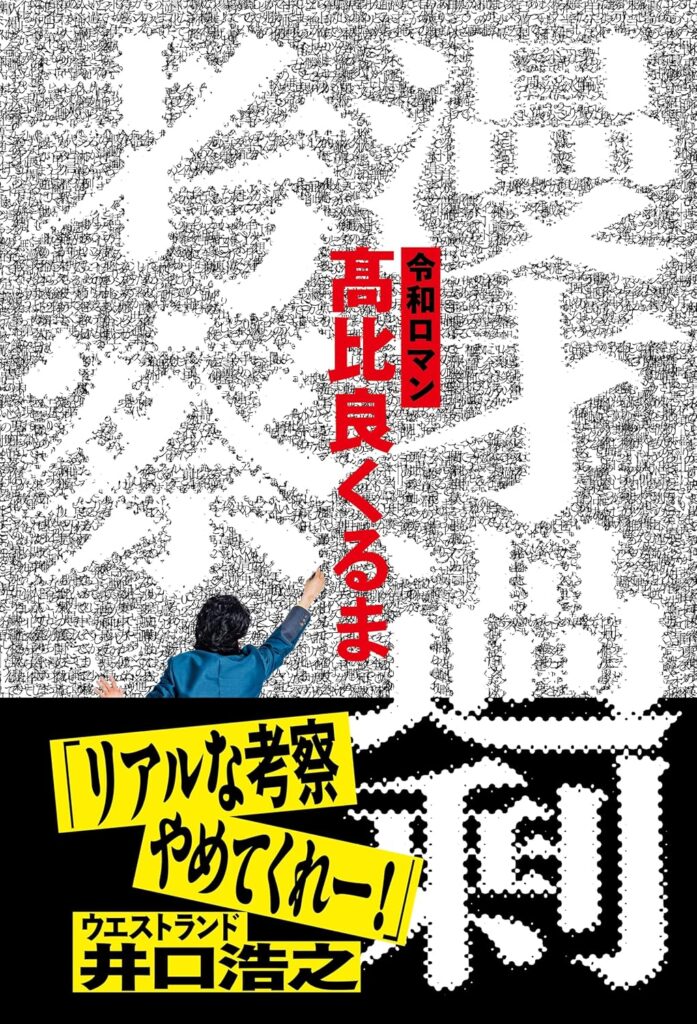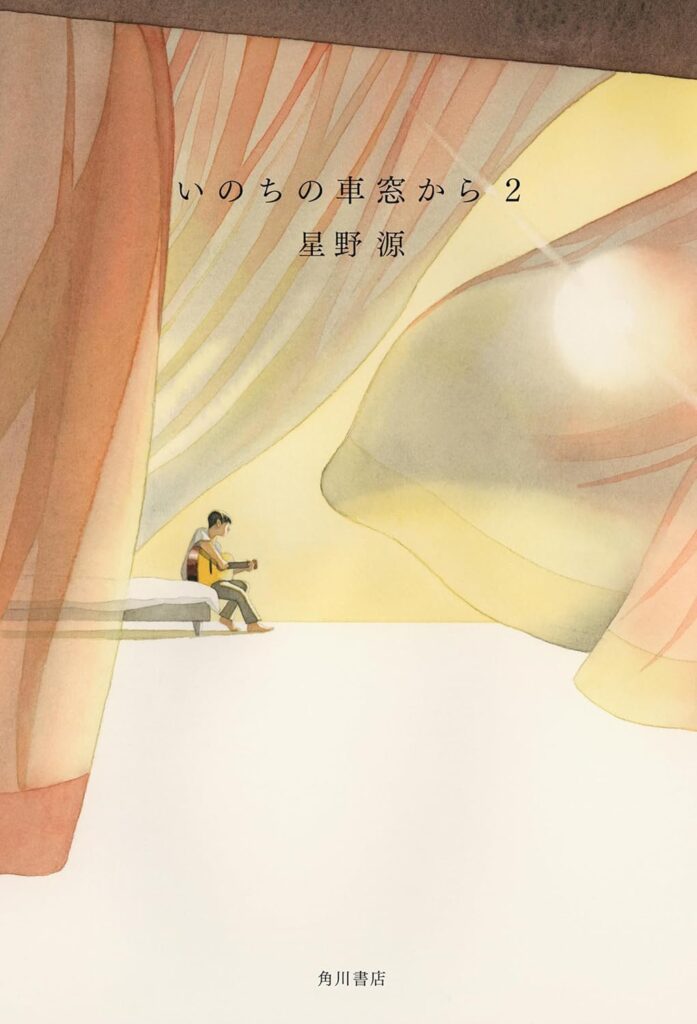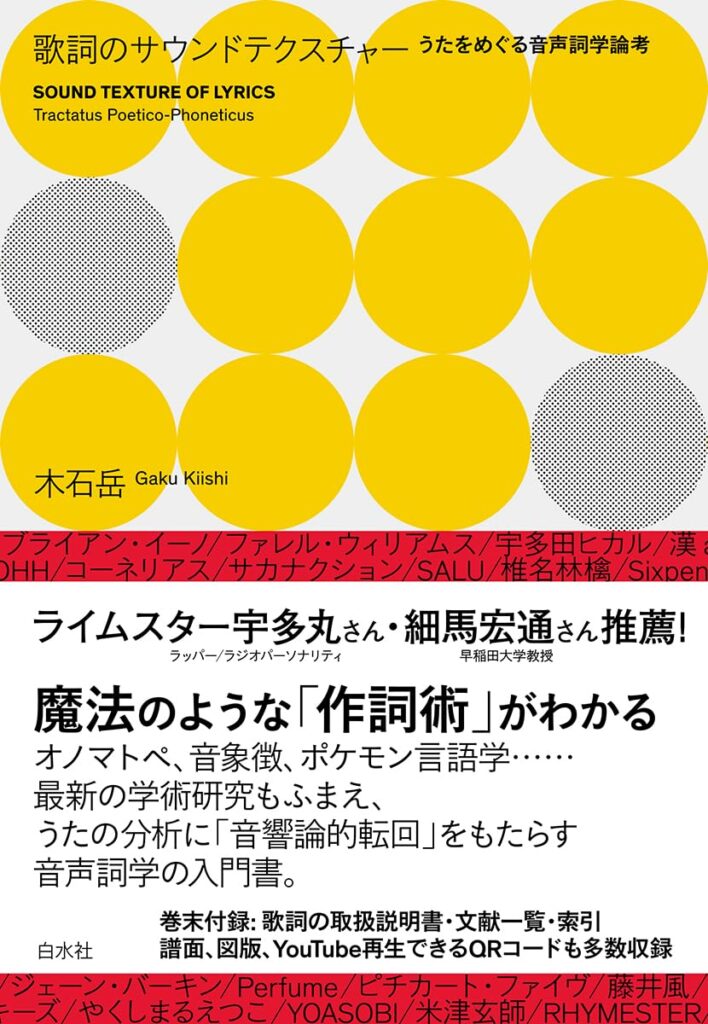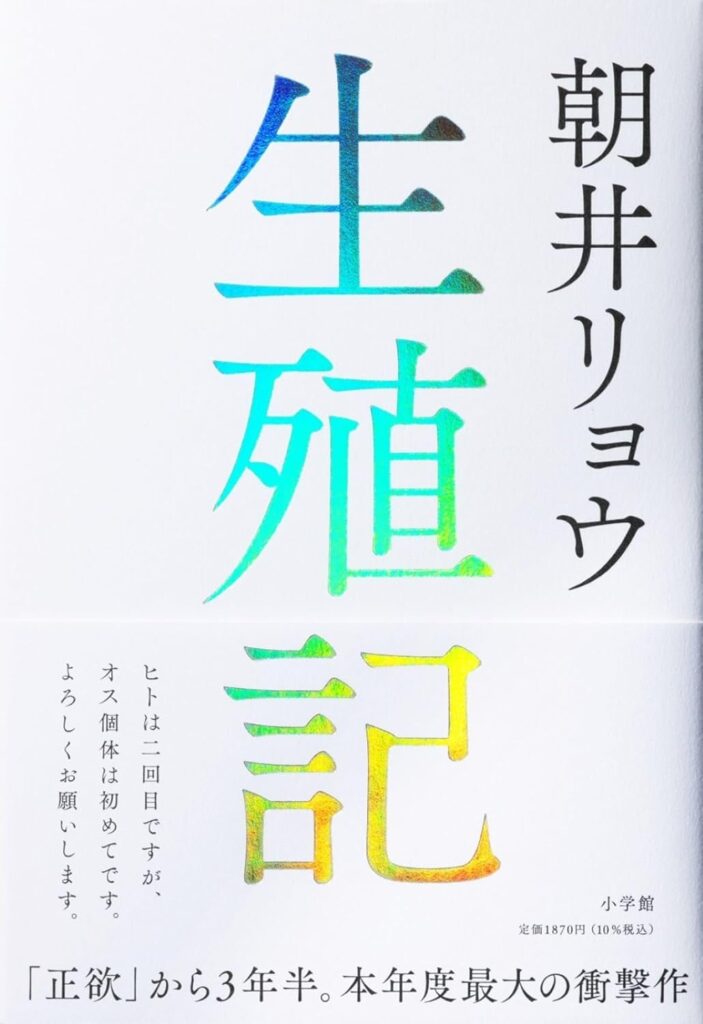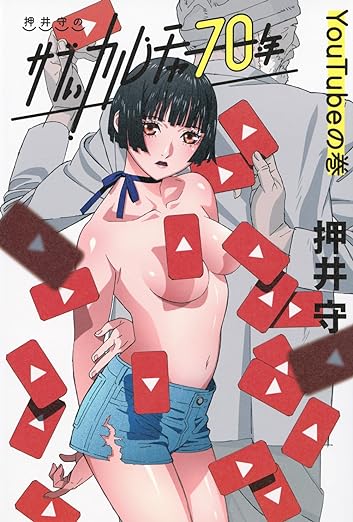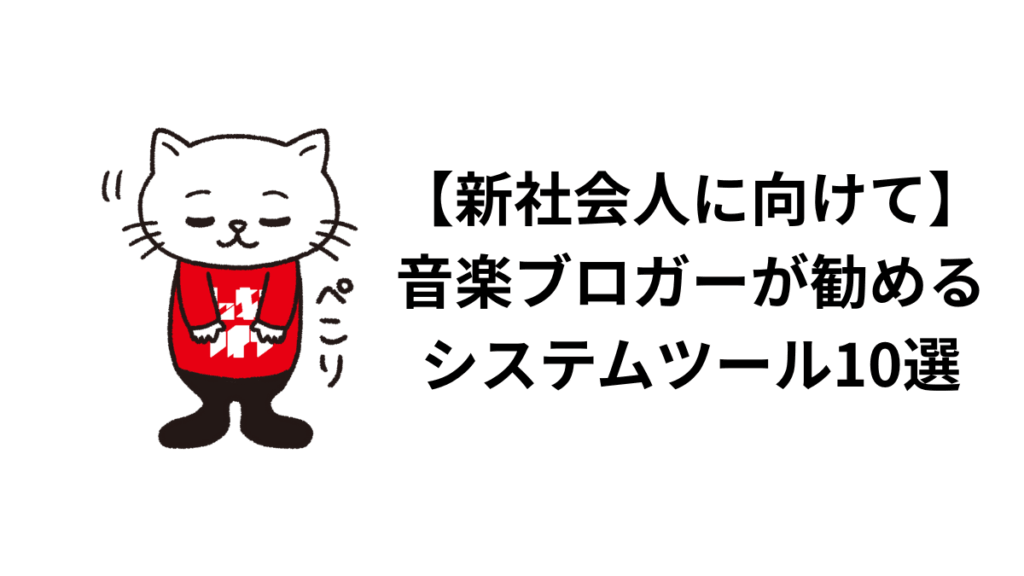個人的2024年オススメ本5選
年末年始は家でゆっくり過ごすという方も多いかもしれない。時間があるので、年末年始くらいは本を読もうと思っている方もいるかもしれない。そこで、個人的に2023年冬から2024年にかけて刊行された本の中で、個人的に好きだった本、おすすめしたい本を紹介したいと思う。
では、どうぞ。
本編
「漫才過剰考察」 令和ロマン・髙比良くるま (著)
M-1グランプリで2年連続チャンピオンに輝いた令和ロマンの髙比良くるまが、漫才やM-1グランプリについて、独自の視点で深く考察した書籍。書いている内容は、どれも論理的に推論されたもので、お笑い専門家でもない自分でも「なるほど!」と思うものもあれば、考察が深すぎて「なんじゃこりゃあ!」となる視点でも、良い意味で過剰に考察しているのが良い。
ただ、ここまで漫才やM-1と向き合い、深く考察していて、かつその考察を体現的に表現してきたからこそ、令和ロマンはM-1で2年連続でチャンピオンになったのだろうし、何かを本気で語ることのワクワクが詰まった一冊であるとも言える。
自分はインターネットの片隅で音楽の話をしてきた人間として、特定のカテゴリーを己の経験と洞察でもって、ひとつひとつ言語化していくサマにドキドキした。そのため、お笑い好きの方はもちろん、物事を分析的・言語化して捉えるにはどうしたらいいか?みたいなことを考えている人にもオススメしたい一冊である。
あと、M-1の考察においてはネタだけではなく、”流れ”とか”空気”という話も出てきており、自分が本来コントロールできない要素においても、可能な限りコントロールしようとしていたところに、髙比良くるまの凄さを感じる。
思えば、音楽ライブやフェスにおいても、凄いバンドって、単にライブがいいだけじゃなくて、流れを的確に読んでそこにうまくの買ったり、そもそもその場の空気を掌握して一気に塗り替えるみたいなところもあって、それは「運が悪かった」で済ます人が多いけれど、可能な限り「運」の要素を減らして本番に挑む、みたいなプロフェッショナルの極意を体感できる一冊でもあった。
余談だが、今年のM-1において、バッテリィズが大ウケしたタイミングで、真空ジェシカの川北が暫定ボックスから抜き出して、トムブラウンのところにやってきて、「自分たちは落ちることになってもいいので、剛力のネタをやった方がいい。ちんぽ」と言葉を交わしたことがトムブラウンのラジオで明かされているが、この話もその場にいた流れや空気を受けた話なんだろうなーとふと振り返るそんな胸中。
「いのちの車窓から 2」星野 源 (著)
星野源のエッセイ集。2017年から2023年までの連載原稿に加え、4篇の書き下ろしを含む全27篇を収録。前作『いのちの車窓から』から約7年半ぶりの刊行とのこと。
この期間だけでも、星野源として色んなフェーズを経験したはずで、特に結婚生活にも触れた「喜劇」のコラムは、色んな意味でニヤリとする内容になっているし、連載していたコラムでありながらも、当時と考えが変わったものもあるということが、本書の中でも言葉にされている。
昔のライブのMCではこういってしまったが、今ならきっとこうは言わない、みたいな話もあって、イエローミュージックというコンセプトもまた「今なら言わない言葉のひとつ」であることが本書でも語られている。なぜ、そういう考えになったのか?というところは本書の中で読んでもらうのがいいと思うけど、星野源の良さって、ひとつひとつの思考が明快で、かつその思考が常にアップデートされるところにあるなーと思っている。
ヒットソングをリリースしたポップアーティストって、「あの頃」を継続させて思い出の中でついつい語ってしまいがちだけど、星野源ってそういう感じじゃないというか。
「SUN」や「恋」という楽曲も痛烈だったけど、楽曲をリリースするたびに、楽曲をリリースする中で言葉を発するたびに、今はこう考えているのか凄い・・・っ!という気分になるのだ。
自分もブログをやっていると考えとか感覚とか変わるなーと思うし、「昔はこれが面白い」と思っていたが、今の感覚で触れるとちょっとひどいな、と感じる瞬間が多い。まったく何も背負っていなかった時期から、多少なりとも社会や界隈と関係を持つようになったから、の変化の部分もあるけど、素直に考えや感覚が変わったからこその結果であることも多くて。
なんにせよ、短いコラムの連作で、スキマの時間でも読みやすい一冊で、学びも多い一冊なので、星野源のことを深く知らない人にもぜひおすすめしたい一冊になっている。
「歌詞のサウンドテクスチャー:うたをめぐる音声詞学論考」 木石 岳 (著)
音楽家・木石岳氏による、歌詞の音響的側面を多角的に分析した一冊。言語学、音声学、認知心理学、脳科学などの最新の学術研究を取り入れ、宇多田ヒカル、椎名林檎、King Gnu、米津玄師、藤井風など、現代の人気アーティストたちの「作詞術」を深く掘り下げた一冊。
音楽ブログなので、音楽のことを取り上げた書籍もということで、入れてみた。
いやね、いわゆる作詞本とは違って分析の角度が面白いのだ。
自分的にも、こういう視点から歌詞をみたことがなかったので、学びが多かったのだった。某雑誌の音楽コラムの場合、歌詞ってアーティストの物語性を補完するための視点で言葉を紡ぐことが多いが、今作は学問的アプローチがびっしりで、俗語的に言えば、文系的というより理系的な視点で深く考察しているのが良い。
作詞について、違った視点で考察してみたい、「歌詞が素晴らしい」って結局どういうことなのだろうか?みたいなことを考えている人がもしいるのだとしたらぜひ読んでもらいたい一冊だし、音楽ライターになりたい、みたいな人もアプローチする引き出しのひとつとして、読んでも損はない一冊だと思う(そのまま利用できるかは別だけども)
「生殖記」 朝井 リョウ (著)
朝井リョウの小説が好きで、概要もよく知らずに購入したんだけど、今作はマジでそいつを視点で物語を紡ぐとは・・・の面白さが凄い。
しかも、単に「視点が面白い」みたいなコミック的な要素で終わるのではなくて、けっこう哲学的な内容に首を突っ込んだり、ある種の不条理を噛み砕いて再考察するような要素もあって、普通のエンタメはもう飽きた、という人にもぜひおすすめできる一冊になっている。
面白いと不気味が織り混ざった絶妙な仕上がり。
とはいえ、読んでスッキリする、みたいなタイプの小説でもないので、炭酸水を飲むようなスッキリ感が欲しいという方は「読まない」という選択もありだと思う。が、朝井リョウの著作が好きな人なら絶対におすすめだし、視点的な意味でも、物語の膨らまし方的にも「小説だからできること」がたくさん詰まっていて、文字で何かを語ることの魅力が詰まった一冊でもある。
映像メディアがどんどん存在感を示してる時代だからこそ、それでも文章を愛する人にはオススメしたく、このラインナップの中に組み込ませてもらった。
「押井守のサブぃカルチャー70年 YouTubeの巻」 押井 守 (著)
映画監督・押井守氏が自身のエンターテインメント体験を綴ったエッセイ集で、特にYouTubeに焦点を当てられた一冊。TV Bros.WEBでの連載に加筆修正を加えて、2023年12月28日に講談社から出版。
『うる星やつら オンリー・ユー』(83)、『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』(84)、『機動警察パトレイバー the Movie』(89)、『機動警察パトレイバー2 the Movie』(93)、『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』(95)』、。『イノセンス』など錚々たる作品を生み出し、アニメーションのシーンでは絶対的な評価を集めている氏。
そんな1951年生まれの押井守が、YouTubeというメディアを語っているのが面白いなーと思って購入した本なんだけど、これが面白かった。やっぱり、鬼才と言われるような人は年を重ねても吸収力が半端ないなーと思ったし、その咀嚼の仕方も面白いなーと感じた次第。
いくつかのYouTubeのコンテンツが取り上げられるんだけど、普通の人じゃ取り上げない変わったチャンネルが出てくるのもいい。
TOPに出てくるのが『Fラン大学就職チャンネル』というもので、他にも『あおぎり高校 / Vtuber High School』とか『六丸の工房』とか『アイザックZ – IsaacZ』とか、自分的にあんまりよく知らないチャンネルをどんどん出してきて、それを独自の視点で解説しているのがいいのだ。
Netflixくらいのコンテンツだと、きちんと評論する土壌もあると思うが、YouTubeもそんなに規模感の大きくないチャンネルも普通に話題に出してきて、色んなスポットを当てるのがいいのだ。
語っている内容もそうだし、語っている視座でも学びが多かったので、紹介しておきたいと思う。
まとめに替えて
ということで、5冊の本を紹介した。
音楽ブログなので、なるべく音楽寄りの本にしようかなーと思ったんだけど、もう少し間口を広げてた上で、5冊に絞って紹介させてもらった。
もし年末年始時間があって本を読みたいなーと考えている方がいればぜひ参考にしてください。