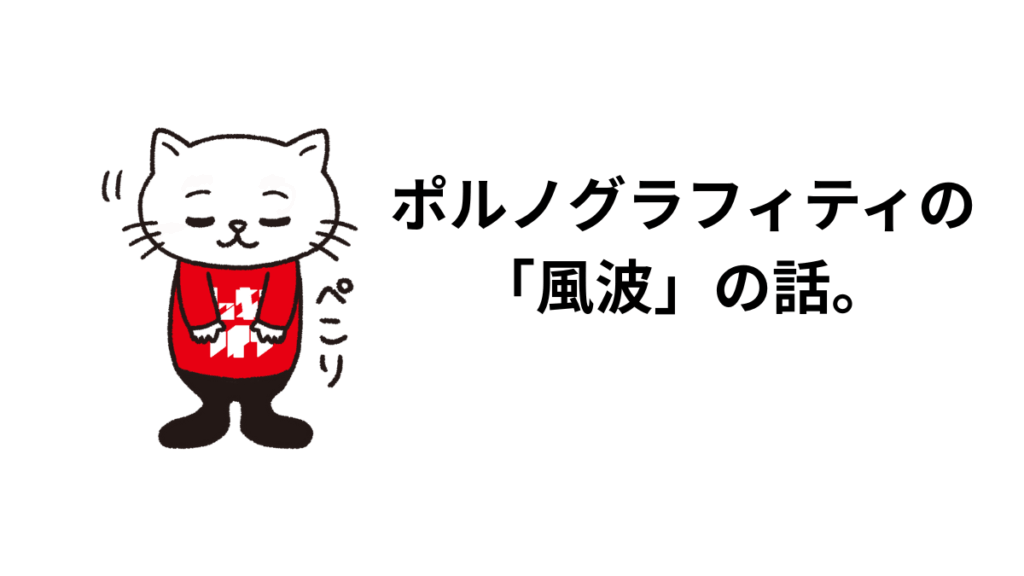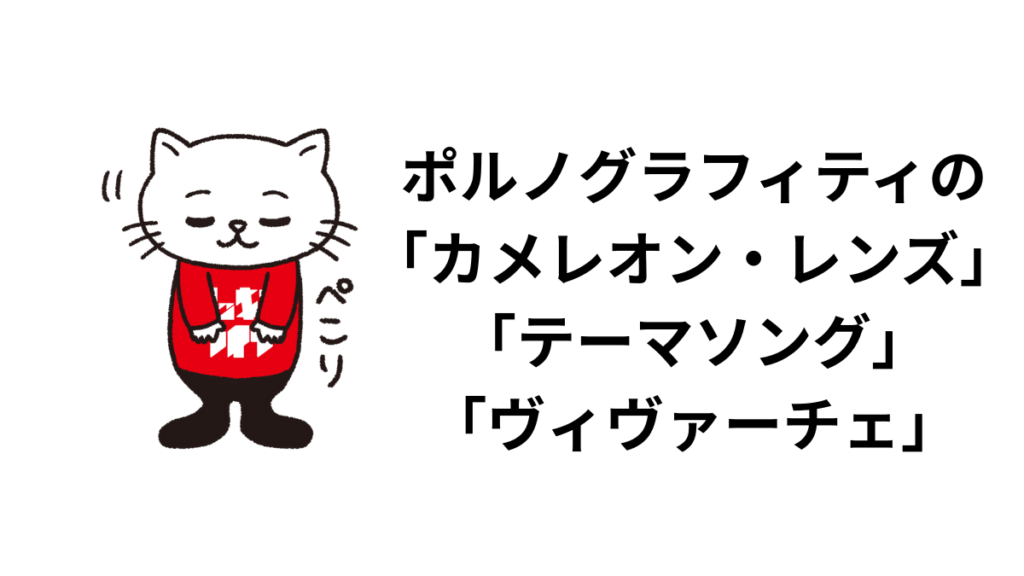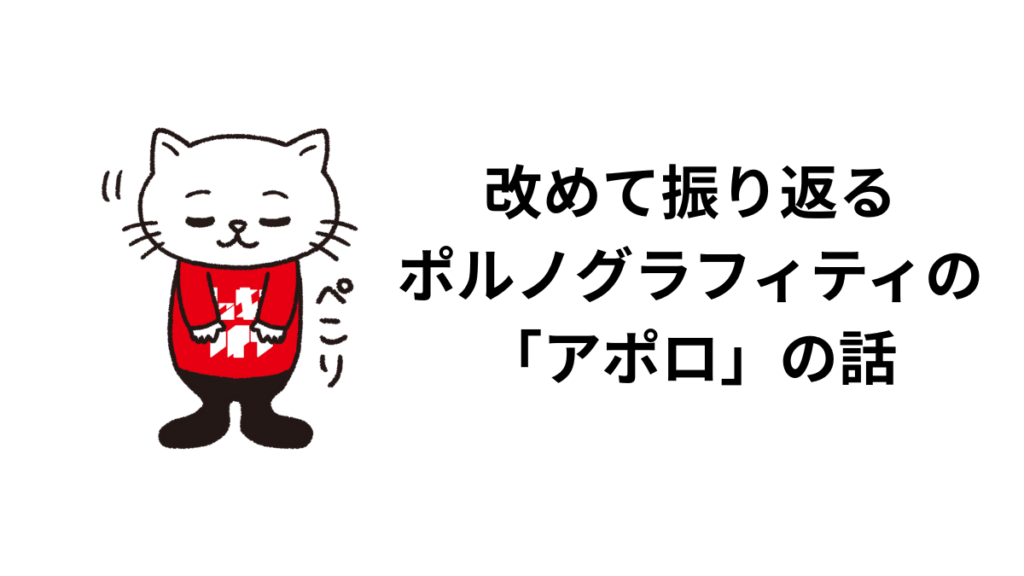
改めて振り返るポルノグラフィティの「アポロ」の話
最近、色々と素になって、ポルノグラフィティの「アポロ」を聴きなおしていたんですよ。
で、思いましたね。
この曲、1999年のリリースってマジか?と。
だってさ、1999年って26年前なわけよ。
26年前だぜ、26。
26歳の人は0歳、52歳の人は26歳だった頃なわけ話よ。
26年前って、当然まだスマホなんてないし、それどころかまだWindows XPすら登場していない。
動画文化なんてまだまだ先の話だし、掲示板すらまだまだ整備されている時代だったはず。ブログとかがキリ番とかで盛り上がるよりも、ちょい前くらいの時代のはんず。
当時のパソコンの画面をのぞいてみたら、やれ一太郎とかやれrWordに潜むイルカのキャラクターがブイブイ言わせていたような、あの頃。インターネットに暴力も喜びもなかった無味乾燥なあの時代。Chat GPTでAIとコミュニケーションしたり、SNSで誰でもカジュアルに繋がれたりする今の時代からは到底想像もできない、インターネット的化石の礎。
そうなのだ。
別の切り口からみると、1999年って、とっても昔に見える年代なわけだ。
なのに、そんな1999年にリリースされた「アポロ」は、今聴いてもどこまでも新鮮で、どこまでも革新的。そんなことってあるかい???なわけで。歌詞だって、今聴いても、ある種の近未来感が漂っていって、いまだにナウい。
これって考えたら凄い話だ。
そりゃあ、テクノロジーと音楽に違いがあるんだからそりゃあそうでしょ、という人もいるかもだけど、音楽だってモロにテクノロジーの恩恵を受けるジャンルだ。
鳴る音だって、流行りのメロディーだって、歌詞のトーンだって、時代によって大きく変わる。
しかもアーティスト自身がどんどん進化するものだから、昔の歌を聴くと、なんだか「懐っ!」ってなることが多い。でも、ポルノグラフィティは違う。「アポロ」って、キャリア25年以上のアーティストのデビュー曲なんだよ、って言われても「えっ?」って感じになると思う。
それくらいに今聴いても瑞々しいし、完成度が高い。
完成度が高いエビデンスは山ほどある。
- スタイリッシュで、スマートなアレンジ
- 岡野昭仁のハキハキとしたクリアなボーカル
- しかも、どこまでも安定感があって、変なよれが一切ない
- だから、パワフルさがあるのに、聴きやすい
- 新藤晴一と岡野昭仁の歌声のアンサンブルも見事
- 間奏でも独自の展開を作る、新藤晴一の華麗なギターアンサンブル
- 一聴するだけでは安易に「意味」に辿り着かない、独自のメタファーやワードチョイスを組み合わせた新藤晴一の歌の世界
etc・・・。
書けば書くほどに無限に出てくる。
だってさ、Apple Watchが出てきた今の世で聴いても「君の腕時計はデジタル仕様」ってワードとして、きちんと浮かずに時代に落とし込んでいるのが凄い。
結果的にこういうフレーズが「古さ」を感じさせない要素のひとつにもなっている。
「ビジンが意味ありげなビショウ」とか「赤い赤い口紅でさぁ」というワードチョイスも見事だ。
「アポロ」という特異な切り口から歌が進むのに、歌に集約されるフレーズが<変わらない愛の形を探している>という普遍的なテーマに着地させるバランス感とかも良いよなーという話。
マジで、こういうワードをこういう角度で歌詞にしてみせるセンスが1999年の当時で考えても、2025年の今からみても、素晴らしすぎるのだ。
あと、音色ね。
ポルノグラフィティって、バンドでありながらもバンドの枠に留まらないサウンドメイクが印象的で、それは独自のバンドの道を切り拓いたから辿り着いた境地である。
ラテンっぽい楽曲とか、フォルクローレ的な民族音楽なんかも歌いこなすポルノグラフィティだからこそのバランス感があって、1から0までセルフでやるんじゃなくて、プロデューサーとがっつり組み合って生み出した楽曲だからこそのニュートラルな感じもまた、今聴くとたまらない革新感を覚えるのである。
まとめに替えて
あと、いまはメンバー全体、落ち着きのあるかっこよさ、って感じだけど、当時のポルノ、シンプルのかっこよさ炸裂ボンバーで、映像でみると違う意味で卒倒しそう。
マジで、子どもの頃のあこがれすぎて、色んな意味でドキドキがえらいことになる、そんなことを思い出す、そんな夜。