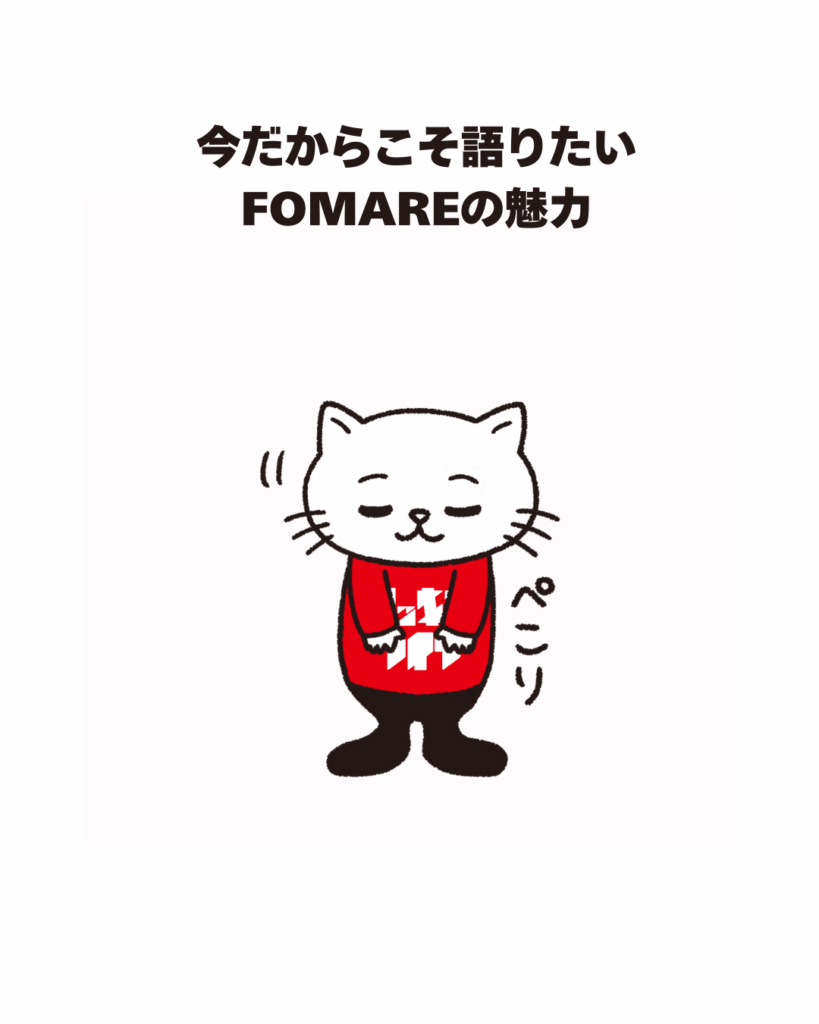
今だからこそ語りたいFOMAREの魅力
いつか記事を書こうと思って、ずっと心の下書きに入れてしまっていたFOMAREの紹介記事。
記事としてはあまりFOMAREのことを扱ってはこなかったけど、FOMAREって他のバンドにはない魅力があるよなーと常々感じていた。
この記事では、そんなFOMAREの魅力を掘り下げていきたい。
他のバンドにはない”接続”できるジャンル性
自分的にFOMAREの一番の魅力と感じるのは、そのジャンル性である。
というのも、FOMAREのライブを一度でも見たことがある人ならわかると思うが、FOMAREのライブって激しい。
エモーショナルで衝動的。
パンチ力があって、爆発力がある。
オーディエンスもそれに呼応するかのように、オーディエンスはモッシュなどでエネルギッシュに弾けていることが多い。
「Lani」のように、楽曲はストレートで激しくて、静と動のコントラストが鮮やか。
歌詞もまっすぐに感情を突き刺すような強烈アッパーで、核の部分をしっかり揺さぶる。
だからこそ、それを全力でライブで披露したときの刺さり方はえげつないことになる。
そういう意味で、FOMAREはメロディック・パンク的な文脈で語ることができる魅力を持っているバンドといえる。
スリーピースバンドとして、シンプルながらも隙のないバンドメイクだからこそ、よりライブとしての破壊力は痛快で、鮮烈なのだ。
でも、メロディックパンクにありがちな、ただシンプルで暴れるだけで楽しい、って感じの音楽ではないところが、FOMAREの真骨頂。
「長い髪」だったり、「愛する人」だったり、彼らの代表曲のどの楽曲でも言えるところだけど、FOMAREの音楽って、アッパーであろうがバラード調であろうが関係なく、どの歌も「刺さる」のだ。
繊細な感情もしっかり汲み取りながらフレーズにした歌詞と、洗練された美しいメロディーがベースにあるから。
ここぞの場面で差し込まれるクリーンな音色のアルペジオだったり、カマタリョウガとオグラユウタがタッグを組んだ、絶妙な強弱の中でリズムを作り出すベースとドラムの組み合いだったりが、それぞれの楽曲を歌詞の中身以上にドラマチックに楽曲を展開する。
だから、歌が刺さるのだ。
そういう意味では、FOMAREは切ないギターロックとしての文脈で語ることができる魅力もある。
あと、どの歌もイントロが良いのも、FOMAREの特徴。
例えば、「君と夜明け」
冒頭のギターのカッティングの音色は妙な切なさを喚起させるテイストだ。
そして、アマダシンスケのボーカルが入ってきて、しっかりボーカルにスポットをあてた後に、バンドサウンドがパワフルかつエッジを効かせてがっと入り込んだタイミングで、がらっと楽曲のモードが変わる。
切なくて泣ける。
でも、アグレッシブでエグい高揚感を生み出す。
この行き来が美しい流れの中で展開されるからこそ、FOMAREの歌は心に深く響く。
2025年にリリースされた「サウンドトラック」は、そういうFOMAREの魅力も踏まえたうえで、歌ものとしての芳醇な広がりを感じさせてくれる楽曲になっている。
よりぐっと歌に入り込めるからこそ、アマダシンスケの甘さと激しさを両立したボーカルがダイレクトに入り込んでくるし、物語性のある赤裸々な歌詞もイメージしながら耳の中に入り込んでくる。
バンドが持つベースやルーツは大きく変化をさせない中で、バンドとして様々な一面を楽曲ごとに披露してみせる。
この色んな文脈に接続できる無敵感が、自分がまず最初に思うFOMAREの大きな魅力なのである。
誰かの人生に重ねる歌詞だからこそ
バンドによって歌詞のアプローチって大きく異なる。
メロディーに綺麗にのってさえいれば意味はいらないと考えるバンドもいるし、文学性を重視したり観念的なフレーズを散りばめるようなバンドもいる。
そんな中で、FOMAREの楽曲はどの歌も物語性が強く、この歌で歌うべき想いはきちんと言葉にするぞという潔さを感じる。
どの歌も等身大であり、時にはダサい面も臆面もなく言葉にするからこそ、聴いている人の人生に重なるような言葉になるのだと思う。
景気良い言葉や美辞麗句を並べて、バンドの体裁を”かっこよく”することだってできるけれど、FOMAREの音楽はそういう方向にベクトルが向かっていない感じ。
しかもそれをエネルギッシュなバンドサウンドで展開するからこそ、よりフレーズひとつひとつの尖り方が半端ないものになって、誰かの人生に重ねる歌詞になっていくのだと思う。
なお、「SONG」や「Needy」のように、女性目線に近い視点で歌詞を紡いでも、歌がリアルに響き、リスナーの誰かの生活とリンクしていくのは、FOMAREというバンドの凄さのひとつだと感じる。
ちなみに自分は「夕暮れ」が好きで、歌の中で描く空模様の変化と、感情の変化のシンクロのさせ方が良いなあと思っていて。
感情の描き方そのものはストレートで赤裸々なんだけど、単に赤裸々なだけじゃなくて、仮に「切ない」の感情が軸にあるとして、その「切ない」をこの表現と合わせて歌うのか?みたいな組み合わせもFOMAREの楽曲の面白さだと思っていて。
そう考えたときに「夕暮れ」は、ちょこちょこ空模様に視点を向けて風景描写をしながら、その風景の変化の中で、言葉以上に繊細な感情の表現をしている感があって、自分的に好きなのである。
ライブがかっこいい
という感じで一旦は楽曲軸でFOMAREの魅力を書いたんだけど、やっぱりFOMAREの魅力はライブに凝縮されているよなーと思う。
もし仮にサブスクとかの音源で、すぐにはぴんとこなかったとしても、ライブでは音源で聴いたイメージを一気にひっくり返す感動がある。
激しくて、でも胸にぐっときて、劇的な瞬間が連続するFOMAREのライブだからこその感動。
激しいライブはなんだか苦手・・・という人でも、FOMAREのライブだけは”素”になって全力でライブに揉まれる・・・みたいな人もいるんだけど、それは熱狂的ながらも隙のないバンドとしてのパフォーマンスの巧みさ(ここぞでばっちりと決めるMCの温度感も含め)や、楽曲それぞれが持つ魅力の織りなしが成せるものなのだと感じる。
確かにライブがかっこいいバンドはたくさんいる。
でも、FOMAREのライブのかっこよさは、他のバンドにはないドラマが横たわっている。
何度かライブを観たうえで、そのことを強く実感している。
まとめに替えて
FOMAREというバンドは、2025年大きな変化を迎えることになる。
その変化についてはバンド側の発信をみてもらえたらというのと、この記事ではそこについて語るのはちょっと蛇足かなと思ったので、あえてそれは「関係ないもの」として一切割愛しておく。
あくまでも、この記事はこれまで感じていたFOMAREの魅力だけスポットを当てて、自分なりの言葉で書いたつもりだ。
そして、きっとこの先もFOMAREのこの魅力を己の形で尖らせながら、このバンドでしか到達できないものを積み上げるのだとは思う。
改めて、FOMAREの楽曲をがーっと聴いている今、そんなことを強く思った次第。
