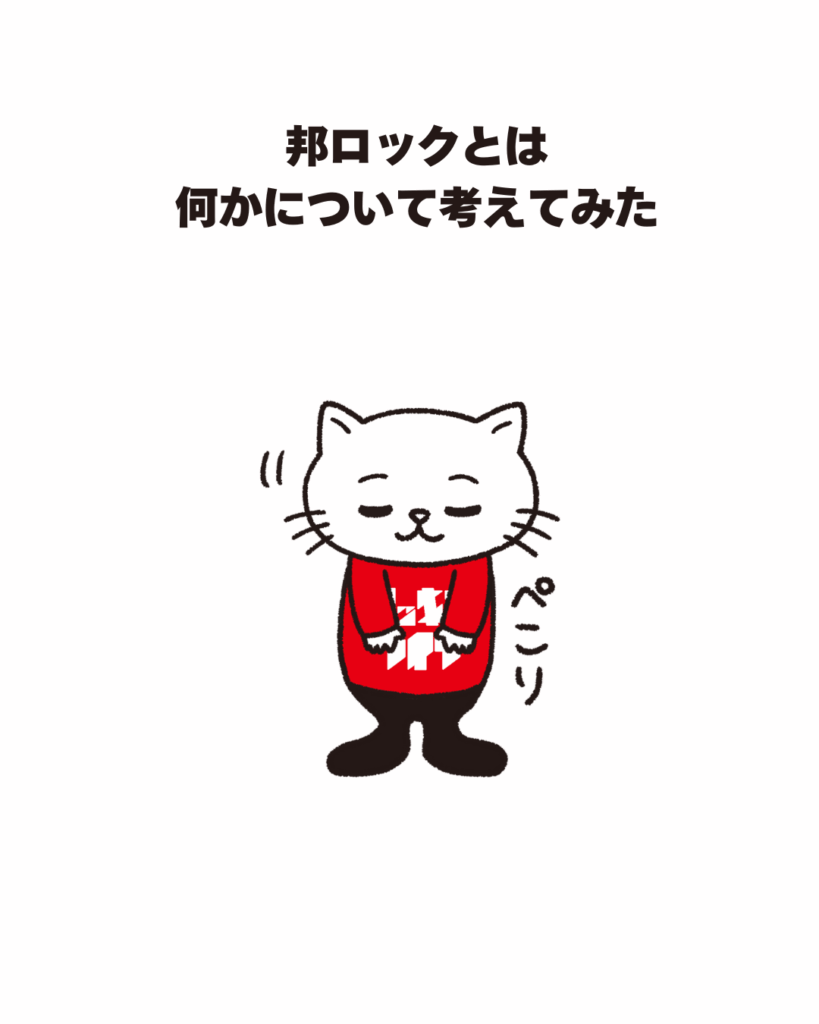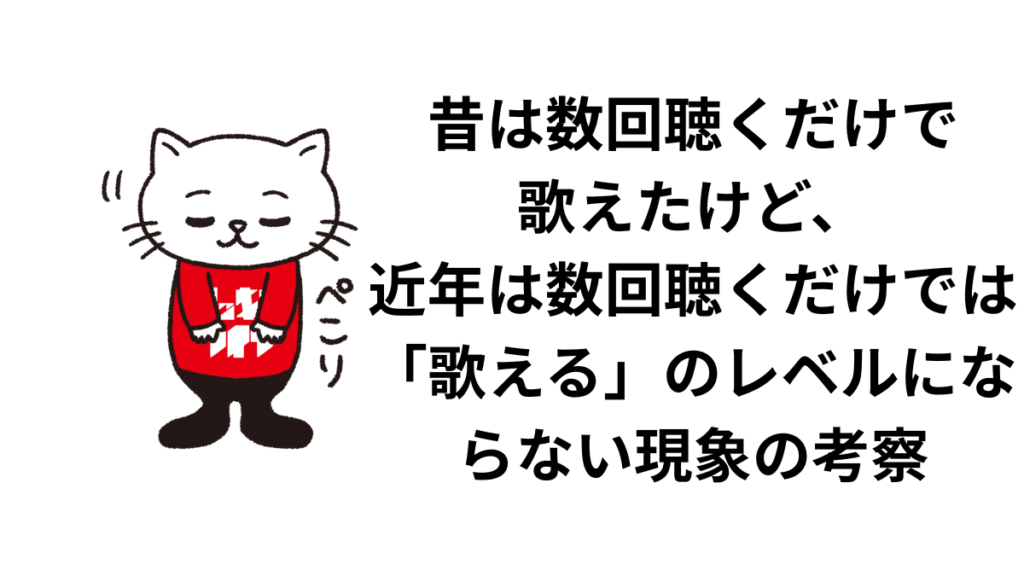
昔は数回聴くだけで歌えたけど、近年は数回聴くだけでは「歌える」のレベルにならない現象の考察
本日、こんなX(旧Twitter)にこんなポストを行った。
昔は数回聴くことだけで歌えたけど、近年は聴くだけでは「歌える」のレベルにならない現象
— ロッキン・ライフの中の人 (@rockkinlife) February 1, 2025
自分ごとで恐縮だが、最近下記のようなことになっていた。
・中学生とか高校生のときは、数回楽曲を聴くと、カラオケで歌えるレベルで「歌えた」
・でも、社会人になって10年ほど経った今では、数回聴くくらいでは、カラオケで歌えるレベルにならない
なぜなのか・・・。
みんなもそういうことある????というノリでポストをしたのだった。
すると、わりと共感をもらうことが多かったのだが、なぜそうなるのか?の見解については各々でけっこう分かれていた。
そこでいただいた意見を踏まえつつ、自分側でも意見を整理して、この事象の考察を進めてみたいと思う。
昔の楽曲に比べて、今の楽曲が難解になったから
この意見はわりとあった。
確かに小室プロデュースの楽曲であれ、つんく♂プロデュースの楽曲であれば、小林武史アレンジの楽曲であれ、ヒットチャートを賑わした他の楽曲であれ、昔はわりと大衆がカラオケで歌いやすいようなビートメイクの楽曲が多かった。
00年代くらいまでは、ポルノグラフィティの「サウダージ」のように、並の滑舌では歌い切ることが難しい楽曲もあったが、それでも、ボカロ的なエッセンスが大衆音楽に入り込むまでは、ビートメイク的には落ち着きがあったのは確かである。
たしかにラップミュージックだと素早いテンポで繰り出すものも多かったが、ヒットチャートに目を向けると、当時のJ-POP的なイズムを継承しているものも多かった。
ハチがボカロシーンでぶいぶい言わせる頃には、ボカロの音楽は人類では歌えないレベルになっていたし、人類では歌えない技巧性になっていたはずの当時のボカロを、いつしか人力で歌うケースが増えてきたのは、10年代のころの変化であろう。
どこかのバンドが、最近のバンドの楽曲はキーが高すぎると、あるあるネタにしてしまうくらいに楽曲のキーは高くなり、楽曲のテンポもどんどん速くなり、カラオケで歌うという意味では難易度が高くなった。
じゃあ自分が中学高校くらいのときは、数回聴くと「歌えた」ことを考えると、今の若い人は、まったく「歌えなくなった」のだろうか?
人によるだろうが、みなさんの声を聴くと、若い人はわりとすんなりと歌えていることが多いようだ。
わりとBling-Bang-Bang-Bornしている人も多そうだし、それが「標準」に感じる若い人は、きっちりその大衆音楽に適用して進化している節がある。
なので、楽曲の平均的な難易度が高くなったから、数回聴いても「歌えなくなった」は理由のひとつではあるだろうが、核心をつく事象かと言われると、ちょっと怪しい、というのが回答になりそうだ。
昔の楽曲はCDなどで聴き込んでいたが、今の楽曲はサブスクで「流し聴き」することが増えたから
実は、これはあると思う。
自分軸の話で言うと、昔に比べると、一曲単位の「聴く」にしか時間が減ったし、その密度は年々薄まっているように感じるからだ。
青春時代に何度も聴いた、好きなバンドの楽曲は今でも歌詞を見ずに余裕で歌える。
でも、今のヒットチューンも同じノリで歌えるかといえば、それは怪しい。
それは、やはり歌に達する接し方が変わったから。
そのようにも考えられる。
昔は歌詞カードを見ながら、没入するように音楽作品に触れていたが、今は正直そういう聴き方はしない。
あえていえば、広く浅くになってしまってはいる。
とはいえ、サブスク時代の今でも、ゴリゴリに「歌える」リスナーはきっといるし、中学高校の自分が同じ試聴態度だったとしても、「歌えた」気はする。
なので、これも核心をつく回答なのかというと、怪しい。
大人になって、実験的に「歌う」をしなくなったから
これもあるとは思う。
社会人になると忙しくて、子どもの頃に比べて、「歌う」に向き合う時間は減ったはずだ。
家庭をもっている人だと、なおのこと、その時間は少なくなったことだろう。
いや、子どもの頃もゴリゴリに「歌う」に向き合っていたかは個々によるが、好きな歌ができるとめっちゃ聴いたし、めっちゃ歌っていた気はする。
でも、今は聴いても、「歌う」というアウトプットはあまりしない。
少なくとも、その試行回数は減ってしまったころだろう。
確かにこれなら、子どもと大人に差ができる理由の説明にもなるため、きっと理由として核心をつく適切な理由になるはず・・・
老い
老いることで、音楽まわりの色んな能力が落ちる。
その結果、リスニングしたあとのアウトプットの感度も下がった。
ただ、それだけの話という指摘。
・楽曲が難しくなったから
・試聴環境が変わったから
・時間の使い方が変わったから
そういう他責な部分に理由があるのかもしれない。
でも、それよりも絶対的な自責の部分の現実。
老い。
この言葉に対して「いや、それは違う」と明確に返せる論拠を持っていない。
そう。
この言葉を受け止めるしかないのだ・・・。
まとめに替えて
若い子が数回聴くと、めっちゃむずい人を歌えるのは、若くてそういう感度がビンビンだからだし、少なくとも、吸収力とアウトプットの力は、年をとるごとに変動する。
そういうものとして、受け止めるのが、態度としては正しいことなのだろう。
とはいえ、それは必ずしも悲しいことではない。
なぜなら、たくさんの音楽を聴いてきたからこそ、若いときには気づかなかった視点での楽しみ方に気づくことができるからだ。
・子どもの頃は意味がわからなかったと思った歌詞の意味がわかったり
・テクニックや技巧的な要素の視点がクリアになったり、
・あのときは「聞こえなかった音」がちゃんと聞き分けることができたり
年を重ねるからこそ、手にいれることができる「楽しさ」も多々ある。
だからこそ、今の自分のフェーズに合う楽しみ方で、音楽と向き合うのが一番素敵なんだろうなーと感じる、そんな夜。