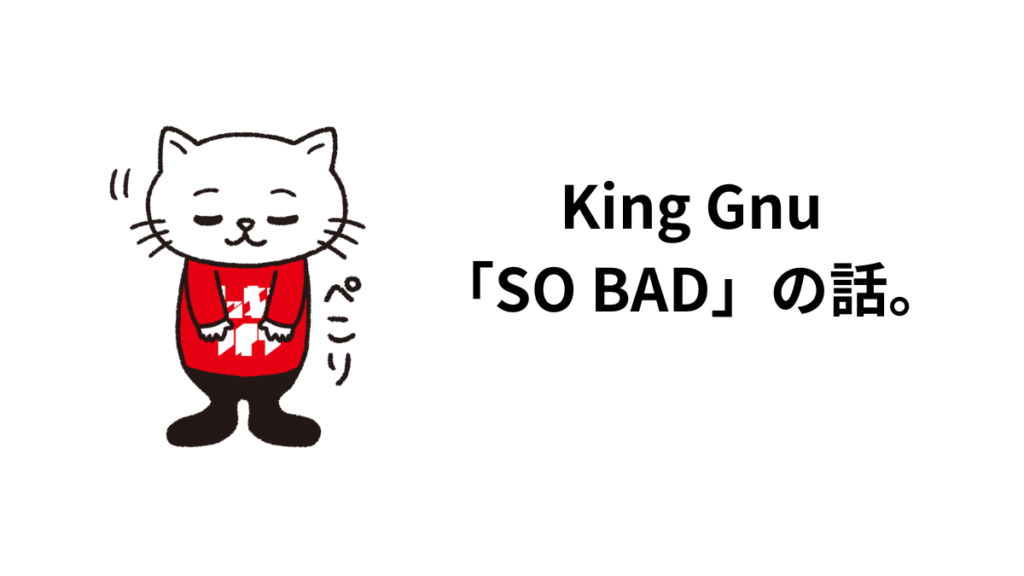King Gnuの「雨燦々」に感じるしとしと感と荒ぶりの融合
自論でしかないんだけど、音楽ってふたつの要素が良い感じに混じり合っているときの中毒性が半端ないと思っている。
アッパーな曲なのに、切なさが同居しているとか。
ハイトーンが鮮やかなのに、低音もキレキレに響くとか。
サビは轟音なのに、メロはめっちゃ静かだとか。
要素は何でもいいんだけど、本来なら同居しないはずの要素が隣り合っていて、かつその2つが水と油になるんじゃなくて、コーヒー牛乳のように美しく溶け合っているときに、中毒性が爆発する印象を覚えるのだ。
そう考えたとき、King Gnuは色んな意味で異なる2つの要素が美しく混じり合うバンドだなーと思う。
「雨燦々」を聴いて、改めてそんなことを感じるのである。
King Gnuの「雨燦々」の話
ボーカルの話
King Gnuの二人のボーカルが同居するバンドだ。
ハイトーンが美しい井口と、エッジの効いた歌声で魅了する常田の二人の歌声が鮮やかに混じり合う。
なので、前述した内容に寄せて話を進める場合、このボーカルのコントラストを軸にして語ることが多い。
確かに、それはKing Gnuの大きな魅力だとは思う。
ただし、「雨燦々」は常田がメインボーカルを務めるパートはない。
終始、井口のボーカルで楽曲を展開していく。
一見すると、少年のようなイノセント感を放つ井口の歌声が、「雨燦々」の世界観を美しく立体的に構築していく。
それがこの楽曲における大きな魅力になっている。
ただ。
ボーカルと軸にして考えてみると、前述したような<異なる要素が共存しない>ということになる。
ということは、「雨燦々」という楽曲自体が、冒頭で述べた<ふたつの要素が混じり合う歌>ではないのだろうか。
実は、そんなことはまったくない。
サウンドを聴くと、そのことを強く思うのだ。
サウンドの話
「雨燦々」はオーケストラ的なバンド構成のサウンドが響く楽曲で、弦楽器の存在感が際立つアレンジになっている。
バンドだけではなく、こういった音楽にも造形がある常田らしいアレンジだなあと思う。
しかし、単にオーケストラが際立つポップな楽曲なのかといえば、そんなこともなくて。
というのも、華やかで洗練されたサウンドの核の中にいるのは、King Gnuのバンドサウンドなのだ。
そして、そのバンドサウンドが妙に荒ぶっている心地を覚えるのだ。
まあ、聴き方によっては荒ぶっているサウンドに<丸さ>を覚えるのかもしれない。
が、サウンドのテイストを踏まえると、King Gnuのサウンドはミクスチャーロックを標榜するときと変わりのないアグレッシブさを感じるのだ。
常田はゴリゴリにギターを弾くし、新井は存在感強めなベースラインを描いてみせるし、勢喜はグルーヴの際立つリズムメイクを繰り広げていく。
そう。
華やかで穏やかな一面を魅せつつも、真髄の部分ではKing Gnuの攻撃的なサウンドが見え隠れするのである。
このアンサンブルの融合が「雨燦々」の中毒性を生み出す要素のひとつになっているように感じるのだ。
幅広いサウンドアプローチにより、スリリングなバンドサウンドで魅了してきたKing Gnuだからこそのコントラストが「雨燦々」の世界に投影されているのである。
まとめに替えて
<雨>が楽曲に出てくるので、しとしと感が際立つ楽曲になっている。
・・・かと思って、耳をすませていると、しとしとの中に台風が巻き起こっていて、暴風にも似た荒ぶりを巻き起こしている。
そんな不思議な心地を覚えるのだ。
今年の<雨>ソング史上、屈指の暴風を巻き起こしている、そんな歌のように感じるのだ。
この本来なら混じり合うはずのない2つの要素が水と油になることなく、したたかに混ざり合い、溶け合っていく。
その感じに、圧倒的な中毒性を覚えるし、この中毒性はKing Gnuだからこそのものだなあと、曲を繰り返す聴くたびに感じていくのである。