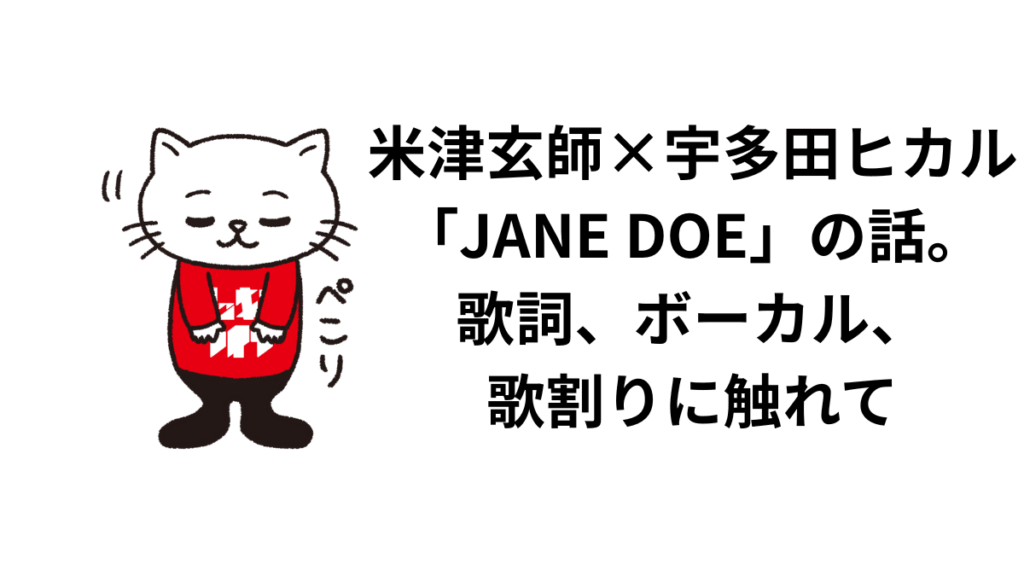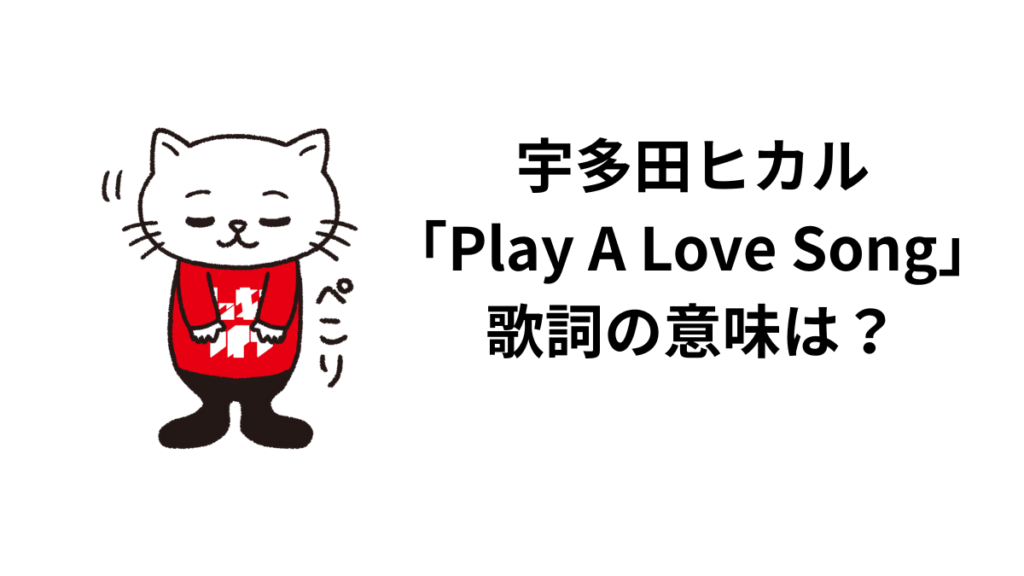
宇多田ヒカル「Play A Love Song」歌詞の意味は?解釈と考察!離婚の果てのラブソングについて!
宇多田ヒカルの「Play A Love Song」について書いてみたい。
作詞:Utada Hikaru
作曲:Utada Hikaru
離婚をしてからのモード
前作のアルバムの「私信感」が強かった分、どうにも宇多田ヒカルのプライベートと作品を紐づけながら歌詞を読んでしまう人は多いのではないかと思う。
今年報じられた宇多田ヒカルのプライベートニュースとして大きいのは、離婚報道。
報じられた数か月前から離婚はされていたそうで、となると、この楽曲を作っていたタイミングと離婚はリンクしている可能性だって十分にありえる。
「長い冬が終わる瞬間」というフレーズの、「長い冬」に対する邪推がどうしても生まれてしまう。
この歌が指す「長い冬」に離婚という要素も少しは絡んでいるのではないか、と。
もちろん、宇多田ヒカルほどの作詞家の場合、ひとつの要素に引きずられながら歌詞を書くことはなくて、色んな要素をミックスさせながら、歌の世界観を作ることが多いし、この歌も、色んなモードが混ぜながら作っているとは思うけれど。
親という単語があるように、母親の死を意識した文脈も見えてくるし、生い立ちのトラウムというフレーズも、宇多田の半生とシンクロするような感じがする。
宇多田ヒカルのインタビューを読むと、ようやく「自分は愛されるに値する人間なんだ」「自分で自分を赦せるようになった」と述べているので、「過去の自分との折り合い」というのが裏テーマになっているのかもしれない、なーんて思ったりして。
僕と君はふたりとも宇多田説
僕が歌詞を読む場合、この人称って誰を指しているのかを考えてしまう。
この歌に出てくるのは、僕と君。
僕は言葉の裏に他意を宿さない人間で、君は深読みをしてしまう人。
二人とも同じように生い立ちのトラウマを抱えており、親の話もさらりと歌詞に出てくる。
僕が成長すれば、同じように君も成長して〜なんてフレーズも出てくる。
宇多田ヒカルは自身のことを、すごく客観的な人間であり、主観的になろうとすればするほど客観的になってしまう、というようなことを語っている。
であるとするならば、自分という人格を語るうえでも、君と僕というふたつの人格を使って「自分の気持ち」を語るというトリッキーな方法論を使ったのではないか?と勝手に思ってしまうわけだ。
僕という宇多田ヒカルが、君という宇多田ヒカルを見る、という構造を通して自身を語るという手法。
行き着くのは、「長い冬もあったけれど、ここからは雪解けだし悲しい話はもうたくさんだから、笑顔で迎えましょうよ」みたいなメッセージである、なーんて思ったりして。
僕は宇多田ヒカルの子ども説
例えば、僕という部分に宇多田ヒカルの子どもを代入するとしたら、どんなふうに歌詞が読めるだろうか?
生い立ちのトラウマは離婚の話で、僕の親は宇多田ヒカル自身を指すことになる。
「僕の親がいつからああなのか知らないけど」というフレーズだって、僕が子どもと過程すれば納得がいくし、君と僕はこれからも成長するというフレーズだって説得性が出てくる。(親は子を成長させる過程で成長していくわけだし)
だから、僕はピュアな存在として描くし、君に甘えるように寄り添うのだ。
ほら。意外と僕=宇多田ヒカルの子どもって説、筋が通る。
「落ち着いてみようよ一旦どうだってよくはないけど、考え過ぎているかも悲しい話はもうたくさん飯食って笑って寝よう」だって子どもが言うかもしれない無邪気な言葉として捉えることも可能だし。
やたらとこの歌のラストがゴスペルモードになるのも、そういうことなのかなーと勝手に思ったりして。
そして、結局のところ、子どもが親に望むのは、自分を愛してくれるというその気持ちだけで。
だから、僕は最後のフレーズで、君にこれだけを求めるのである。
「好きだって聞かせてくれよ」と。