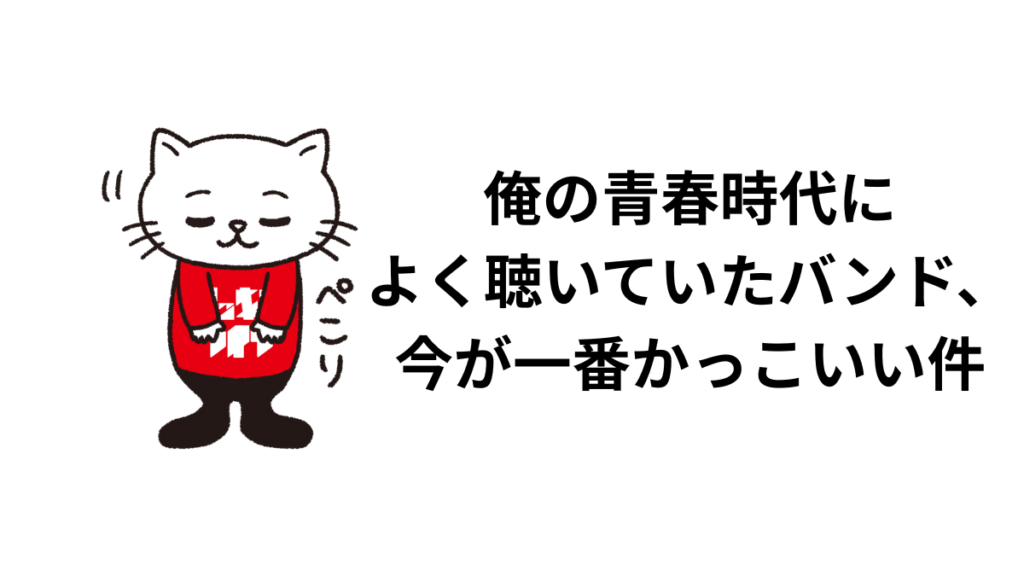
俺の青春時代によく聴いていたバンド、今が実は一番かっこいい件
気がついたら自分が音楽を聴き始めて20年くらい経った。
その20年、いくつも音楽については新しい発見や出会いがあった。10代の頃の音楽は今でも自分にとって大切な宝物だし、30代に出会った音楽も「今だからこそ」の愛着がたくさんある。
なので、いつが本当の意味での”青春”やねんという話はある。
が、20年の中でも特にインパクトが大きかった時期はもう少し絞り込めたりする。そういう記憶の中で今も強い印象が残っているひとつの時代が、2010年代前半だったりする。
というのも、2010年代で新しく出会ったバンドは強いインパクトが残っているものが多いのだ。フェスの空気感ががらっと変わっていた時期、サブスクがまだ一般的ではなかった時期だからこその音楽との接触性。
自分にとっては、強烈なインパクトを残すうえで絶対的な時代だったのだ。
そうやって振り返っていく中で、気づくことがひとつある。
それは、2010年代前半あたりによく聴いていたバンド、どんどんまだまだ進化しているぞ、という感覚だ。
2010年代のあの頃、あのバンド、確かに最高だった!けれど、直近でリリースされた新婦を聴いていると、マジで今の方がより最高じゃねえか!かっこよさ、青天井じゃねぇか!
そういう気持ちにさせてくてるのだ。
確かにどんなバンドだって、10年経てば技術とか知識のアップデートがされている。とめどなくインプットをしてきたバンドの破壊力はとんでもないことになっていることが多い。ただ、音楽メディアはこういう熟達のバンドの扱いはわりと小さくて、大ブレイクしたバンドか新世代のバンドにスポットを当てがちなので、その辺りが歯がゆかったりはするんだけども。
まあ、そんな話はさておき、俺的に「第二青春時代によく聴いていたバンド、今が実は一番かっこいいぞ」と感じるバンドをいくつか取り上げて紹介してみようという次第。
では、どうぞ
パスピエ
2010年代でも、パスピエって独特の立ち位置のバンドだった記憶がある。
今でこそ、顔を直接的には出さないアーティストは多々いるが、パスピエはそういう魅せ方がメジャーになる前から、意図的にそういうミステリアスな演出をするバンドだった。
また、音楽性においても、当時のフェスシーンのベタとベタではないこだわりを絶妙なバランスで落とし込んでいたのもパスピエの特徴だった。
パスピエ的にはがっつり当時のフェスのムードと合わせた「S.S」だって、パスピエだからこその美学を感じるサウンドや楽曲構成を体感できる楽曲だった。
元々、芸術なものとポップなものだったり、革新的なものとベタなものを融合させるバランス感覚が自分的にツボだった。クラシック的なものとロックなものを融合させるようなアプローチを行うこともあった。
そんなパスピエはサブスク時代となり、当時よりも色んな音楽にアクセスしやすくなった今なお、独自的な美学を作品の中で鮮やかに描いてみせる。
「トゥパリタ」のメロディーラインは不思議な浮遊感に満ち溢れていて心地良いし、シンセサイザーの際立ちが絶妙で、近未来ともちょっと違う、でも現代ポップスの先にいった高揚感がある。
「sui-sou」も複合的な音楽ジャンルの組み合わせと自由自在なビートメイクで興奮を誘う屈指の楽曲である。
あと、初期からパスピエが好きな自分にとっては、「電影夢想少女」のあの頃のバンド的な疾走感と、ベースにあるニューウェーブ感がたまらなくぐっとくる。
Czecho No Republic
Czecho No Republicも自分にとって印象的なバンドだった。
最初、バンドとして知ったときは冴えない感じのする男性二人のバンドだったのに、次にバンドを観たときは男女混合で、キャラクターに強さのあるメンバーも増えたので、ぐっと明るさが際立つバンドだった。
エレクトロポップな世界観のものが多い印象だが、楽曲によってはインディーロックも趣きを強めたり、ポップな色合いを強めたりと、多様ながらもこだわりを感じる音楽性で惹かれていったのだった。
やってることはわりとオタク敵だけど、キャッチーでもある不思議な手触り。
だから、作品に触れるたびに**Czecho No Republicの音楽には独特の興奮を覚えるのだった。
武井優心やタカハシマイを軸に、バンド全体で美しいコーラスワークを育み、ボーカルが組み合わさりながら、カラフルな音楽世界を作り上げているのも印象的だ。
で。
最新アルバム『Mirage Album』がこれまた良いのだ。
「Wonderland」のイントロからの壮大なサウンドメイクは見事だし、ロックバンドとしての独特なザラザラ感を響かせ渡っているのが良い。後半にかけてぐっとテンポを上げて、終わりに向けてピークをコントロールする構成なのも良い。
「Hope」のシンセサイザーが場作りしている音色と、跳ねたようなリズムメイクも面白くて、惹かれる。
他のバンドではあまり出会わないタイプの興奮が散りばめられており、アルバムを聴き進めるなかで、グイグイに惹き込まれるのがたまらない。
Halo at 四畳半
おいおいおい復活するなら言ってくれよ!?待ってたんだよ!?という気持ちにさせてくれたのは、Halo at 四畳半。
突如の復活のニュース。
パワーアップしたハロを体感できるのは、ここからの話だと思うが、個々でもしっかり活動しており、プレイヤーとして進化している予感がするし、このタイミングなので、紹介したい。
Halo at 四畳半の魅力は物語性のある文学的な歌詞と、それを彩るバンドサウンドであろう。
フレーズが良いバンドはたくさんあるが、小説のようなもっと大きな単位の言葉に惹かれるのは、Halo at 四畳半だからこその魅力だと感じる。
「イノセント・プレイ」だったり、「リバース・デイ」だったり、様々な名曲が生み出されていることを実感する。
ヒトリエ
今回の記事で最後に紹介したいのは、このバンド。自分にとっては伝説的なバンドのひとつであり、ボカロとフェスとバンドシーンが直接的に接続する上で、このバンドの存在を避けて語ることはできないと思う。
10年代のフェスシーンを語る上で、「高速4つ打ちビート」というワードがよく使われていた。それだけこのビートメイクが一般的に根付いた証なのだが、紐解くと、様々なジャンルで音楽の高速化が進んでいたことが確認できる。
特にボカロでは、一足先に作品の高速化が進んでいたわけだが、そういうシーンの代表的な作り手の一人がヒトリエというバンドを生んだwowakaだった。
そして、ヒトリエの初期はwowakaがボカロで生み出していた躍動感や興奮をバンドとして人力で生み出す試みから話が始まる。
ヒトリエが偉大なのは、ただボカロを人力で焼け直すで留まることはなく、バンドとしてどんどん進化を果たし、新たな音楽敵アプローチを生み出していたところにある。
2019年にヒトリエはバンド体制を帰ることになり、三人組のバンドとして活動を再開させることになる。
再会した当初は、あの頃のヒトリエをなぞるのように動いているようにみえた。しかし、そこから数年が経って、2025年の今、ヒトリエはあの頃のコアな部分は内に秘めつつも、常に進化を遂げる、今が最高にかっこいいバンドとして君臨している。
アルバム『Friend Chord』を聴いて改めてそのことを感じた。
メンバー全員が作詞作曲を手がけており、それぞれの個性が発揮している。
しかも、今作はwowakaが作詞作曲を手がけた「NOTOK」をシノダが歌唱して収録されているのも、今のヒトリエだからこそ感があって、ぐっとくる。
ダウナー楽曲もあれば、カラッと演奏する楽曲もあって。
ちなみに自分は、「月をみるたび想い人」が好きである。
まとめに代えて
好きなバンドの好きなところを書いただけなので、たいそうなまとめはないんだけど。
間違いなく今がかっこいい!というバンドは、こんな感じで定期的に「最高だぜ!」を叫びたいなーと改めて感じた、そんな夜。


