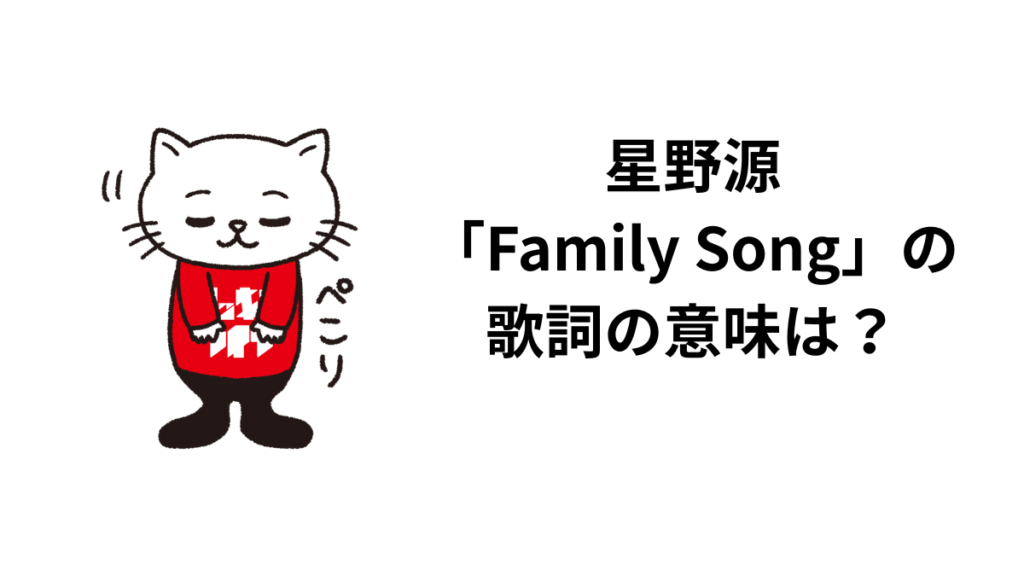星野源と若林正恭が紡ぐ『LIGHTHOUSE』、そして「Orange」に一発くらわされた話
星野源とオードリーの若林が対バンするNetflixのトークバラエティ「LIGHTHOUSE」を観た。
全6話の番組なんだけど、この作品で語られる言葉にいちいち刺さる自分がいたのだった。
この番組を観たあとだと安易に「わかる」の言葉を使うことも憚れるんだけど、それでも自分はこの番組内で交わされる言葉のひとつひとつに、いちいち「分かる」を感じてしまうのだった。
いや、まあ自分なんて本業においても、副業(というほど大げさなものではないが)として行なっているロッキン・ライフの活動もまだまだちっぽけなものでしかないし、たいした苦労話を持つこともなく、のらりくらりと生きて今に至るので、自分の人生の比較すると、二人のキャリアやこれまで感じたものはきっと異なりすぎるものがあるとは思う。
それぞれの分野の第一線で活躍する星野源と若林正恭と、自分とでは見えているものや感じていることに、当然ながら違いだっていくつもあるはずだと思うのだ。
でも、やっぱり節々に「解る」ではなく「分かる」を覚えてしまう自分がいるのである。
ひとつの対象がそこにあったとして、そこに投げかける眼差しとか、その眼差しを通じて生まれた考えの部分に、確かに「分かる」と思ってしまう自分がいたのである。
というのと、なんとなく重ねる部分の話もあったなーなんてこと思う。
世の中には、自分と同じように音楽(などを扱う)ブログを運営している人間がいるが、自分はそんな中でも「ずっと同じことができない」タイプだなあーと思った。
好みの音楽だって今でも(比較的)コロコロ変わってしまうタイプだし、ブログを更新することに飽きてしまった結果うっかりライブイベントをやってみたり、色んなことに手を出してウダウダと音楽業界の片隅に生きてしまっているからだ。
対して、自分のまわりで芽をだしたり、成果を出している人の多くが<実直に繰り返す>を続けている人だなあということも考えたりしてしまうのだった。
番組中、星野源と若林正恭が自分たちは同じことを繰り返すことができない側であり、春日はそれができる側である、というような話をする場面があるんだけど、そのときに星野源が<自分たちは同じ場所にずっといることができない側だから、居場所を作ってきた>というような話をする場面がある。
「喜劇」という楽曲でも、そういうニュアンスを込めていることを述べる場面がある。
<私の居場所は作るものだった>というフレーズは、まさしくそのことを歌った部分であることを話す場面がある。
そういう『LIGHTHOUSE』での二人の言葉の応酬を聴いたあとに、「喜劇」を聴くと、また違った見え方がする。
ひいては、オードリーの漫才だったり、星野源のほかの楽曲を聴いてもまた、別の見え方がしたり、刺さり方が変わっていくのだった。
そういう点も『LIGHTHOUSE』の面白さのひとつだなーと感じる自分がいた。
『LIGHTHOUSE』という番組が持つ面白さ
『LIGHTHOUSE』は単純に面白いなあ、と思った。
この面白さの中身はいくつかある。
例えば、星野源とかオードリーの作品を今後楽しむうえでの視点としての面白さもある。
どんなエンタメでも作品に触れるにあたって、知識というものは時に初期衝動のときに感じた面白さを阻害するケースもあるけれど、知識があるからこそ、楽しむことができる視点ってあるように思う。
この歌ってこんな意味だったんだとか、こういう考えでこういうアウトプットをしているんだあ・・・!という面白さは、そんな類の代表であろう。
それはお笑いでも音楽でも等しくあるものだと思っているし、お互いの作品に奥深さを与える言葉が綴られていた印象を受けたわけである。
また、そういう知識ベースの話だけではなく、『LIGHTHOUSE』は単純に<真面目に何かをきちんと語る>という構図だからこそ宿る面白さもあるよなーと感じたのである。
しかも、これって必ずしもお笑いから乖離した面白さではなく、普段通常のお笑いを観るときと繋がるお笑い的な面白さもあるよなーなんてことを、『LIGHTHOUSE』を通して改めて感じたのである。
自分は『あちこちオードリー』という番組が好きで、配信回もきちんと購入して観てきたんだけど、個人的にあれは「ビジネス的な気づきを得るための仕事論」という観点で観るというよりも、茶化すこともなく、普段自分が仕事に対して考えていることを真面目に開示する、という構図そのものに面白さがあり、それはお笑いに漫才やコントという種類と同列にある面白さなんだということを、『LIGHTHOUSE』を観て改めて感じたのである。
で。
語ることの内容と、語ることそのものの面白さ。
『LIGHTHOUSE』には、その二つが強く宿っているように感じる。
星野源のepとしての『LIGHTHOUSE』の話
というのと、『LIGHTHOUSE』の第一回目で、星野源がひょんな流れから、毎回分のEDの楽曲を作ると口にすることになり、結果、星野源は有言実行で楽曲を6つ作り、『LIGHTHOUSE』というepをリリースすることになるのだった。
どの回も濃い言葉の応酬が行われるからこそ、それぞれの楽曲の歌詞も「このフレーズはあの時に話したあの時のとこを踏まえたフレーズだな」と回想しながら、楽しむことができる。
特に「灯台」は、二人がブレイクする前、下積み時代を過ごした阿佐ヶ谷のエピソードが軸になった楽曲となっているので、色んな意味で尖ったフレーズが並んでいるのが印象的である。
そんな中で、自分が好きな楽曲が若林正恭のラップにトラックをつけて、そこに星野源のメロディーもそえて、ひとつの楽曲になっている「Orange」という歌だ。
若林のドープで切れ味鋭いフロウが、淡々としながらも溌剌としたリズムの中で繰り出されていく。
番組を観ていたら分かるエピソードで紡がれた、色んな感情で交錯したラップの中、「あんたもそうだろ?ファンクの源さん!」と星野源に投げかけるように紡ぐ流れはなんだかぐっとくる。
自分はどちらかというと、歌詞は音楽を楽しむうえで1番最後にする要素である。
なんなら、歌詞の面白さを味わうことなく、素通りする楽曲も多い(メロディーやサウンドなどに先に意識が向いてしまうからだ)。
でも、『LIGHTHOUSE』に収録されている6曲は、LIGHTHOUSEという番組を観たからということもあるが、とにかく言葉が1番脳内に入ってくるのだ。
実際、番組を観た上でも、それぞれの回の濃い感情が歌詞になって、歌になっている印象を受けるのだ。
だから、ぐっと言葉が入ってくるのである。
そういう意味で、2023年の音楽体験として考えても、『LIGHTHOUSE』って刺激的なものであったなーと感じる自分がいるのである。
まとめに替えて
もしかしたら、音楽は聴いたけれど、LIGHTHOUSEという番組は見ていない人もいるかもしれないし、逆のケースの人もいるかもしれない。
でも、LIGHTHOUSEという作品においては、Netflixの番組も、星野源が作った音楽も両方並行して味わった方が絶対に面白いと思うのである。
それぞれの生み出すアウトプットが好きな人であれば、『LIGHTHOUSE』で刺さるものはいくつもあると思うので、そういう意味でもオススメできると強く思うのである。