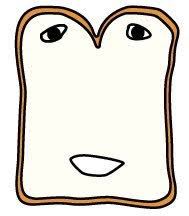某音楽雑誌をぺらっと見ていたら、田淵がこんなことを語っていた。
[ad]
「前のアルバムが僕的にものすごく達成感があったのでそれをちゃんと宝物として語り継いでもらうために3年くらいあけようと思った」
けれど、フタを開けてみたら、タイアップ案件はドカドカとやってくるし、シングルが溜まればアルバムリリースのタイミングだって決まってしまうのが、大人の世界。
というわけで、結局、前作から1年半のスパンでリリースすることになった7枚目のアルバム。
そういや、その雑誌に載っていた同じレコード会社に所属している先輩バンドであるBUMP OF CHICKENも、BRAHMANも、オリジナルアルバムはまだ6枚しかリリースしていない。
ユニゾンの方が「若手」のはずなのに…。
なんだかんだでトイズの「大人」たちに上手いこと転がされ働かされて、ユニゾンは大変だなーと思ったりして。なんかよくわからんカフェまでオープンさせられてるし。
まあ、トイズ界隈はなんだかんだで大変で、ミスチルは大御所すぎるし、でんぱ組は色々あってテンヤワンヤだし、ベビメタはいつしか世界を股にかけているし、トイズが抱えているアーティストで、安心安定でタイアップ案件任せられるのはユニゾンしかいないわけで。
だから、ユニゾンばかりリリーススペースが早くなっちゃうわけなんだけども。
そうなると、タイトになるのが制作スケジュール。
そんなタイトなスケジュールでリリースされたのが7枚目のアルバムである「MODE MOOD MODE」。
前置きが長くなってしまったので、そろそろ徹頭徹尾にアルバムの話をしていきたい。
「ロックバンドのポリシーと憧憬」
田淵は「自分たちがロックバンドであること」を強調するし、他のバンド以上に「ロック」というものに対する憧憬が強い。
今作の冒頭も、それが色濃く出ている。
一曲目の副題になっている「nano-mile-met」は、恒例となりつつあるアルバム枚数コール<7枚目>とかけているわけだけれど、表の意味はnano-mile-met=とても近い距離で会う、になるわけで、「時間がかかってもファンの“地元”に足を運ぼう」とするユニゾンのライブに対する姿勢を的確に表明したフレーズとなっている。
だから「精度上がったら拡張化」はするけれど「無意味に目立ったら逆効果」なユニゾンのスタンスも表明するし「ちょい戸惑ってる親米も 勝手を知ってる備蓄米も 顔は知らないままお櫃にブレンド」というフレーズからもわかるとおり、新参も古参も関係ないから、ふらっとライブハウスに遊びに来てくださいな、と言うユニゾンのスタンスも表明するわけである。
ユニゾンはロックバンドであるから「ここらでぐらつかせてやろう」という意識で良い曲を作るし、良い曲ができたら、君の地元にあるライブハウスで「僕と君とで遊んでやろう」って算段を常に持っており、田淵が持つロックバンドの哲学がそこに全て詰め込まれているわけである。
結局、歌詞で伝えるのは「僕たちユニゾンってこんなバンドです」的な自己紹介なわけだけれど、2曲目では「じゃあなんで僕たちがここまでロックバンドであること」に拘り、意識するのかの自己紹介を始めるのである。
歌詞を読めばわかるとおり、この歌は「Dizzy Trickster」というバンドに「まだ火照って」おり「僕は追いかけずにいられなくなって」しまい「この高揚感は誰にも奪えない」くらいに熱に浮かされてて、いつしか「端から端まであなたの血が僕に流れてる」という、ロックバンドに憧れた男のサマを歌う構成となっている。
「Dizzy」というワードはthe pillowsの「RUNNERS HIGH」からの借用であり、「Dizzy Tricker」にthe pillowsを重ねるようにして言葉を紡いでいる。
と言うのも、田淵の敬愛するバンドと言えば、the pillowsである。
the pillowsがいたからロックバンドに憧れた田淵がいるわけで、そんな根っこがあったから僕たちはロックバンドに拘るんです、って意志が見え隠れする。
そんな田淵。
あなた=the pillowsの世界で息をさせてくれ、と歌詞で表明するわけだけど、あなたの世界で息をした結果、「MIDNIGHT JUNGLE」では完全にthe pillowsのオマージュを捧げる。
冒頭のコールは、ピロウズの楽曲である「NAKED SHUFFLE」のコールをバリバリ借用している。さわおへの惜しみない愛が光る。
[ad]
「差し出されたものへの変化」
曲順通りに歌詞を見ていくと、ある変化を見てとることができる。
それは、差し出されたものに対する変化だ。
どういうことかというと、1曲目では「差し出された手は噛み切っていた」し、2曲目では「差し出された手は掴まなかった」ことがわかる。
ロックバンドのユニゾンは孤高の存在であり、誰にも媚びない姿勢をみせていた。
けれど、3曲目では「何気なく差し出され何気なく取った」モードへと変わっていくことがわかる。
3曲目で手に取ったのは「チューインガム」ではあるんだけど、それは「書いてある果物と違う甘い香りだけが横切った」と書かれており、ここからアルバムのモードも変わることが宣告される。
「オーケストラを観にいこう」というタイトルからもわかるとおり、この歌からロックバンドのサウンドだけではなく、オーケストラの音も入ってきて、ロックバンドの音に揺さぶりをかけていく。
ムードが変われば、モードも変わるわけで、(歌詞における)君へのスタンスも、差し出されたものに対する対応も、ユニゾンとして鳴らす音の類にも変化が生じるわけだ。
このようにして、次々と「揺さぶり」をかけてくる。
この「揺さぶり」のバトンを繋ぐのは、音にスキマがあることが特徴で、ユニゾンとしての真骨頂感のある曲調の「静謐甘美秋暮抒情」なわけだけど、その前に「甘いか苦いか」を決める「fake town baby」を挟むのは、ポイントだと思う。
街中で混乱しながら前に進もうとするのが「fake town baby」って歌なんだけど、最終的に「うるせえ」と啖呵をきりながら、何かの覚悟を決めて「勝算万全でお待たせ」と言い切っている。
だから「fake town baby」では不特定だった「街」というワードは、次の「静謐甘美秋暮抒情」では「東京」という具体的な街の歌に変わるわけだ。
この歌は手が差し伸べられることはないけれど、「両手にあった景色が零れてしまう」状態になるわけで、自分の側に変化が生じていることがわかる。
それをあえて言葉にするなら「モードなムード」になっていると言えるんだろうけど、その変化は言葉を尽くさずとも「音」の変化に現れる。
その音をあえて言葉にする静謐甘美である。
そんな空気のなか、アルバム全体をみていると、そろそろアルバム的には「派手にやるフェーズ」だよな……だって、俺たちロックバンドだし、って言いたくなってきたこのタイミングで、「Silent Libre Mirage」を入れてくるのは粋だと思う。
ノイズが邪魔になったから、ノイズを剥ぎ取って派手にやれる段取りするのが「Silent Libre Mirage」っていう歌なわけであり、ここから更に派手にやることを全面に押し出すかのように「MIDNIGHT JUNGLE」と「フィクションフリークライシス」で攻めてくる。
ユニゾンは良い意味であざとい。
で、こうして改めてアルバム全体を振り返ってみると、ここまで言ってるのは「僕たちユニゾンって、こんなバンドです」っていう自己紹介となる。
それは歌詞をみても、サウンドをみても然りで。
そんな流れのなかで、「夢が覚めたら」で一度エンディングを迎えるための準備をするために、テンション的にクールダウンをさせる。
ちなみに、「夢が覚めたら」の映画の元ネタって、たらればな僕と君を歌うテイストも、河もネオンの扱い方も、サビの末尾のラララからも、某大ヒットミュージカル映画しか僕は連想できないわけだけど、ユニゾンは冒頭は違う未来へ向かう。
「この答えが少し報われて欲しいと思い」ながら、このアルバムのエンドロールに向かうわけだ。
「拒んでいたその手をつかみ出す」
流れが変わるのはここから。
だって、「10%」では、いきなり「お手をどうぞ」って急に手を差し伸べるんですよ。
アルバム冒頭、一曲目では差し伸べていた手を拒んでいたバンドが、ここにきていきなり手を差し伸べて、照れながら手を握ったら追いつけないとこまで行きましょう、って言っちゃうんですよ。
なんというツンデレ具合。
そのツンデレ具合は「君の瞳に恋していない」で頂点に達し「ちょっと信じてみてはくれませんか? 保証がないのは本当だけど 僕の手握っていいから」で締めちゃうわけだ。
僕の手を握っていいから。
そこまで言っちゃいますか?田淵さん!長いのは髪の毛だけにしてくださいよ。なんかもうイケメンですよ、このヤローって感じで。
最初は、手を握ろうとしなかったバンドが、アルバムのエンドロールでは、「君」に手を差し伸べて「握っていいから」って言っちゃうわけだ。
小さじの一杯のカラクリがユニゾンの音楽であり、「君」がこの歌を聴いてるあなたなのだとしたら、もうこのツンデレ具合が最強の「揺さぶり」だよなーなんて思ったりして。
まあ、フタをあけてみたら、ある意味冒頭と同じことを言ってはいるんだけどさ
[ad]
「前のアルバムから変わったこと」
ユニゾンはたぶんシュガビタが大ヒットしてから、楽曲制作においても、ライブやメディア露出においても、わりと慎重になっていたと思う。
ユニゾンほどファンとの距離感に気を使ったり、目立つことを嫌がるバンドはいないと思うのだ。
このままメインストリームに駆け上がって売れまくればいいのに、それはしないで、自分たちがどういう立ち位置で活動していけばいいのか、すごく意識的になっていた感じ。
だから、前作「Dizzy」はあんな感じのアルバムになったのだろうし、「エアリアルエイリアン」は「あれ?これどのバンドのアルバムの曲よ?」と突っ込みたくなるような出だしにしたのだろうし、「Cheap Cheap Endroll」では
君がもっと嫌いになっていく もっと嫌いになっていく
空しいやら浅ましいやら もう呆然ですが継続パレード
もっと嫌いになっていく もっと嫌いになっていく
偉そうなやつ勘違いなやつ 全部記載から除外してエンドロール
って、余韻なんてクソ喰らえで、やたらと「君」を突き放した歌詞にして、アルバムのエンドロールに置いたのだと思うのだ。
だから「君」への距離感に気をつけていたけれど、そんな「目立ちすぎちゃう」危険なモードは過ぎ去った。
タイアップという名の労働は増えるし、なんかよくわからんカフェはオープンさせられるし、駅ばりの広告とかで死ぬほど目立つハメになってはいるけれど、「良い曲を作って」「ただただライブしてふらっと君に会いにいく」というロックバンドのスタンスは崩さず、自分たちは自分たちのままでいれる、良い意味でユニゾンはユニゾンのままでいれることがわかったからこそ、自ずと今回のアルバムのエンドロールのムードのモードは変わったのだと思う。
だから、音としても、ホーンも入れるし、鍵盤も入れちゃったわけだ。
確かに「君の瞳に恋していない」は、わりと「君」のことを突き放している。
でもそれだけじゃなくて、少しは「君」への歩み寄りも見せて、ツンデレしちゃうわけで、ユニゾンのモードの変化がここで見て取れちゃうわけだ。
「結局……」
もしあえてこのアルバムのメッセージを一言で表すなら「ユニゾンってこんなバンドだから、近くに寄ったときは、ふらっとライブに来てね」になると思う。
このアルバムによって、君に「見えない魔法」をかけたから、あとは君に任せた、と言わんばかりに。
物好きが好きな物好きなバンドは、物好きのために今日もロックバンドのライブをしてるからこっちおいでって感じですかね、田淵さん。
「大事なものに限って理由なんてない」
こうやってアルバム順に歌詞をみていて、このフレーズにはこういう意味があるんだって考えてみたところで、たぶん田淵は「いや、そんな計算はない」って言うと思うのだ。
けれど、大事なものというか、大きな物語の筋を決めちゃうものに限って、意識的な「理由」もなく、生まれちゃうものなのかなーって思ったりもして。
例えば、このアルバムはピロウズの「好き」で構成されている部分があるし、このアルバムによって見えない魔法をかけられた人は、細かいことは抜きにしてユニゾンが「好き」になっちゃうわけだけど、なんでそんなに彼らのことが「好き」になったのかを訊いてみても、具体的な答えなんて出ないよなーって思うのだ。
「好き」の感情を紐解いても、そこに残るのは「気がついたら、そういうふうになってしまったんです」って感覚だけだと思うのだ。
もちろん、ユニゾン側は「騙す算段で君の脳内に溶け込んだ」狙いはあるのかもしれないけれど、そんな算段によって脳内のねじを巻かれて罠に落ちてしまったのは「気がついたらそうなってしまったから」であり、言語化できる理由なんてそこにはなくて、それ以上も以下もない現状がそこにあって。
つまり、甘い一瞬に騙されて見えない魔法にかかっちゃったから、そう見えてきたんだし、そういうふうにアルバムを解釈したんだよ、っていう、そういうオチ。
[ad]