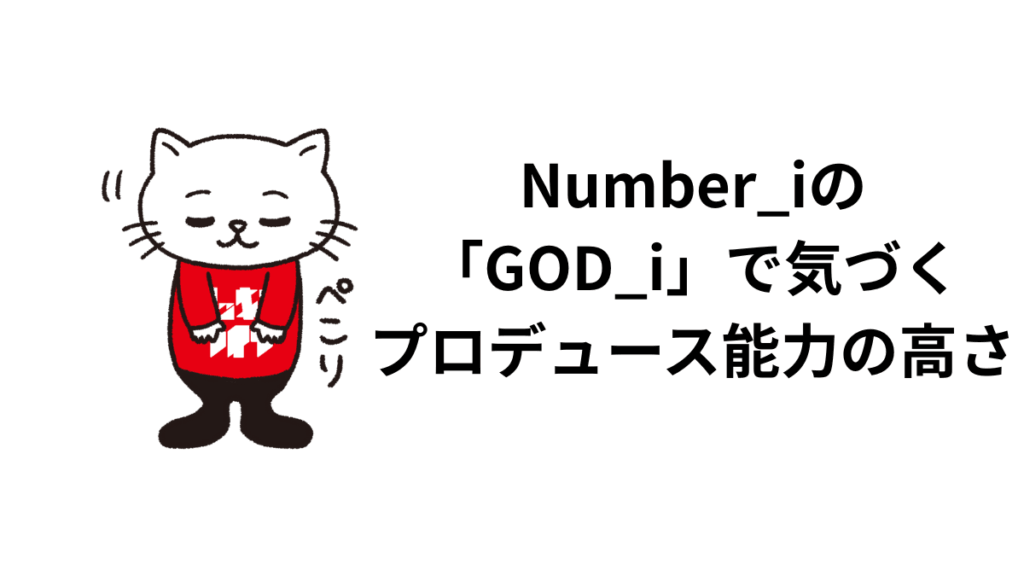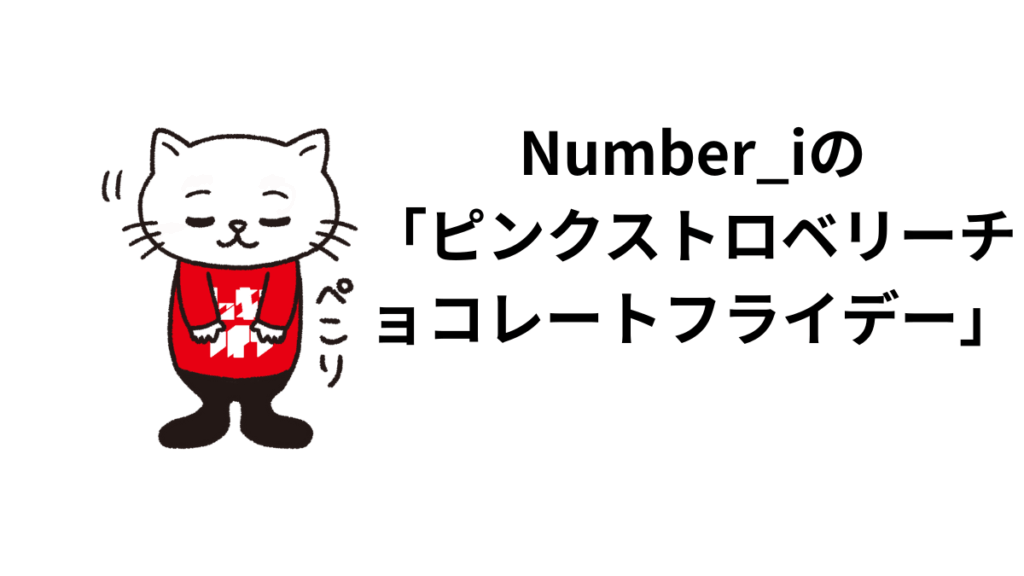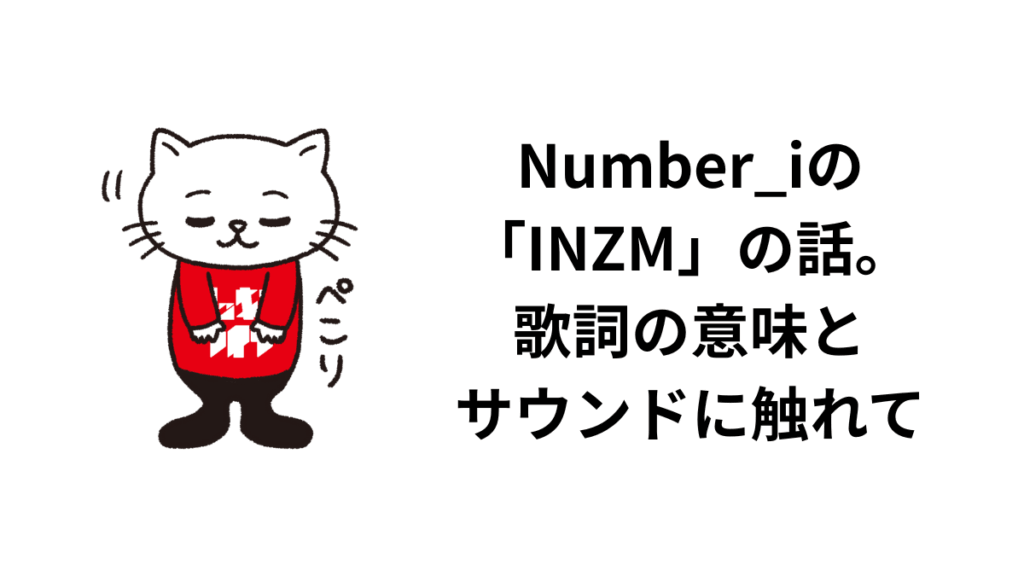
Number_iの「INZM」で感じる音楽の革新性
SONG出演のタイミングでもあったので、ふとNumber_iを聴きたくなってきた今。
そこで、SONGの話とは少し異なるが、この記事では「INZM」の話をしてみたいと思う。
改めて「INZM」を聴いてみたら、衝撃的な音楽だなあと感じる自分がいる。
というのも、Number_iの音楽って、ポップスの楽曲にある程度ある“型”やお約束を破壊する面白さがある。これは「INZM」以外の楽曲にも通ずる魅力だ。
イントロ、メロディー展開、ラップのエネルギー、サウンド構成、ジャンルの混ぜ方・・・。
どの切り口でみても、そのドキドキが突き抜けていく。
「INZM」のサウンドとしてのワクワク感
まず、「INZM」は強烈なギターリフと高速ビートで幕を開ける。鳴り響くギターリフはエッジが効いており、一聴するだけで、耳に残る。そこには、DJのスクラッチ音が加わり、重厚なミクスチャーバンドよろしくな、音の中に稲妻が見えてくるような突き抜けたワクワクを与えてくれる。
さらに、単にギターが軸を握るのではなく、シンセの音作りやぶりぶりのベースラインが絡み合うことで、激しさの中にも奥深さを生み出し、歌の世界観に深みを与えていく。
楽曲が進むにつれて、規則的に進んで行ったサウンドやビートメイクは然るべき変化を与えていき、良い意味で音楽的快楽の揺さぶりを与える。この感じも良い。
まるで一曲の中で、複数の楽曲と出会ったような面白さ。
このワクワクの展開はボーカルにも繋がる。
例えば、この歌、クールで切れ味鋭いラップが続いたかと思えば、一転して情感豊かなボーカルへと移行するタイミングがあるのだ。目まぐるしく表情の変わる声の展開にさらなるワクワクを覚え、脳内には圧倒的なアドレナリンがまれることになる。
面白いぞ!と。「いなづま」という音をこのような形でリズムとメロディーに落とし込み、高揚感のある歌に再構築していくセンスも素晴らしい。
日本語がキーポイントになっている歌詞も良い。
あと、歌詞を見ていくと、「GOAT」や「BON」といった過去作との関連性も感じられる部分があり、作品単体におさまらず、Number_iの総合的なクリエイティブとしての壮大さも感じられるのが良い。
プロデュース力の高さ
「INZM」のプロデュースを手掛けた神宮寺勇太だ。
この楽曲に触れるだけでも、そのプロデュース能力の高さを実感する。
特に、「INZM」は楽曲としてはコンパクトにまとまった楽曲ながら、音楽体験としては濃密。
こういう体験ができるのは、プロデュース能力が素晴らしいからこそであるように感じる。
ODD Foot WorksのPecori、DATSのMONJO、FIVE NEW OLDのSHUNといったプロフェッショナルが集ったからこその作品構成であり、並のバンドの音楽よりもロックでスリリングという隙のなさ。
俺たちはこういう音楽が好きなんだぜ!というこだわりもラップとサウンドに込められている印象もあって、質という観点からみたときに、本当に褒めるところしかない。
「INZM」においては、特に神宮寺勇太がプロデュースを手掛けたからこそのインパクトが輝いている。
まとめ:Number_iが切り開く未来
まあ、この歌、2024年の楽曲なので、ここからのNumber_iがさらにシーンにインパクトを与えていることは言わずもがなではあるんだけどね。
ただ、改めて、Number_iって凄いし、面白い楽曲、たくさんあるぞ、ってことが言いたくて、このように「INZM」をピックアップして、記事にしたためた次第。
どこまでも革新的で妥協のない姿勢、そして芸術性へのこだわり。それらすべてがNumber_iというグループを唯一無二の存在へと押し上げている。その点をこのブログでも、言葉にしていおきたい。