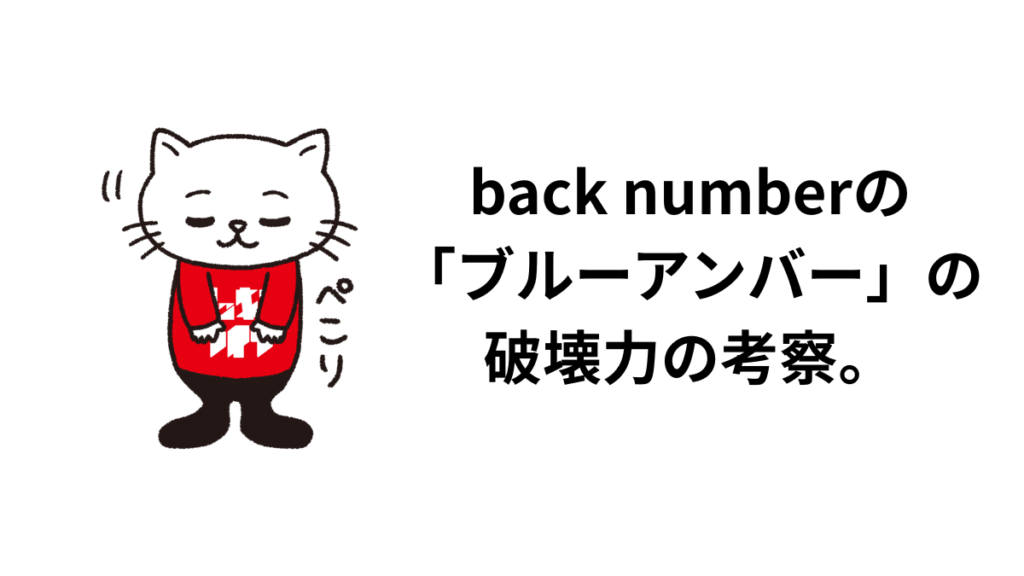
back numberの「ブルーアンバー」の破壊力の考察
青いよ。青すぎる。
きっと初めて地球を外側から観たときレベルで、青いと感じるはず。
それくらいに、back numberの「ブルーアンバー」から、何とも言えない青さを感じる。
イントロの話
冒頭のイントロ。
いきなり物悲しい音色。
しっとりアコギから生み出される、マイナー調の空気感。
歌詞を聞く前なのに、なんだか青い物語を予感させる音の運び。
back numberって過去曲も含め、歌詞の物語としての解像度が高いだけではなく、音そのものから物語と直列繋ぎになって、ストーリーに奥深さを生み出す凄まじさがあった。
「ブルーアンバー」でも、10秒ちょっとのイントロで、なんとなくそういう想像を生み出してくれる。
今作は、「高嶺の花子さん」「大不正解」などでもタッグを組んだ蔦谷好位置がプロデュースを手掛けているということで、よりダイレクトにそういう感涙を生み出している印象。
冒頭に登場する色は赤
この歌の最初のフレーズに出てくる、色に触れたフレーズが「赤い雫」というのが良い。
どこまでも感情を直接的かつストレートに表現するback numberではあるが、back numberってどの歌でも、きちんと表現する順番が整理されている。
だから、歌に感情移入できるし、その物語に没入することになる。
ブルーが主軸の歌だからこそ、最初の色の入りは、赤。
この辺りにも、清水依与吏の卓越した表現力を実感することになる。
あと、「身体の内側」でのフレーズのメロディーの入れ方も、フォークの語りっぽい温度感で良くて、メロディーの良さと、言葉の強さのバランス感を整えながら、歌が進行しているのも、「ブルーアンバー」の良さだなあと感じる。
全体的なアレンジの魅力
以降、「ブルーアンバー」は絶妙な温度感で楽曲が進む。
ピアノやストリングスが軸に入っているので、アルシュの王道バラード感もある。
でも、根っこにあるギターの差し込み方が秀逸出し、1番サビ終わりのギターのエフェクトの書け方も絶妙で、ただ壮大でドラマチックにするのではなく、独特の色を残しながら歌に進む感じなのが良い。
なんというか、絵の構図ははっきりと決まっているのだけど、印象派というか、独自のタッチでその絵を描くからこそ、知っている絵の題材と構図ではあるんだけど、「ブルーアンバー」にしかない味わいを堪能できるというか。
この歌は「青い」と書いたんだけど、その青って悲しみの青というよりは、純粋とかピュアという意味合いの青さもあるし、歌の中で風景がよく見えるからこその青さもあって、青は青はなんだけど、その青の中に芳醇さが宿っているのも特徴である。
歌詞とサウンドが結託しながら、然るべきタッチで歌の世界を作り上げる。
back numberがいて、蔦谷好位置がいるからこその音楽体験。
清水依与吏のソングライティングがあって、小島和也と栗原寿が的確かつ丁寧にリズムを作り上げるからこその音の集積。
壮大なんだけど、単なるベタにはならない心地。
バンドとしての音は控えながらも、それぞれの役どころで然るべきインパクトを与えながら、歌を展開させていくのも良いよなーと思う。
ボーカルの温度感
ところで、この歌、清水依与吏の歌の表情が良いなあと思う。
歌としての上手さと、感情の入れ込め方のバランスが良いというか。
上手さが際立ちすぎると、良くも悪くも歌の目線がぶれることもあるけど、今作の清水依与吏はそこの直値のさせ方が絶妙。
だから、歌は上手いのはもちろんのこと、するすると歌の世界に入れ込める。
切ないと感じるフレーズでは、優しい歌声が響くことで、切なさを際立たせるし、感情を抑えるような場面のフレーズでは、どことなくクールな響きのボーカルがそこに添えられる。
感情がはっきりしているけど、でも、コントラストが明確にある歌だからこそ、フレーズごとに必要なボーカルがそこにあって、それがより歌の輪郭をはっきりさせることになる。
アレンジが秀逸な上で、ボーカルもよりコントラストを鮮やかにするからこその歌の世界。
こういう魅せ方は、back numberだからこそだなあと感じる。
まとめに替えて
つくづく、back numberってこういうタイプのバラードを歌ったときの破壊力がえげつないなーと感じた次第。
でも、back numberって赤裸々に感情を歌うだけのバンドでしょ???って思っているリスナーほど、「ブルーアンバー」を聞くと、back number流の侘び寂びが炸裂しており、より表現のひとつひとつが洗練されており、過去曲とは異なる心の掴まれ方をするような気がしている。
もちろん、back numberだからこその感涙はある。
でも、そこで味わう感涙って三角のタイプでしょ??と思って構えていたら、台形のタイプが差し出されたような、面食らい方がある。
歌のタッチが絶妙で、感情の描き方が秀逸だからこその味わい。
「ブルーアンバー」には、そういう魅力を感じたので、気づいたら、このような形で記事を書いている自分がいたのだった。
多重の青。
それを強く感じたからこそ、この歌はどこまでも”青い”。そう感じた次第。

