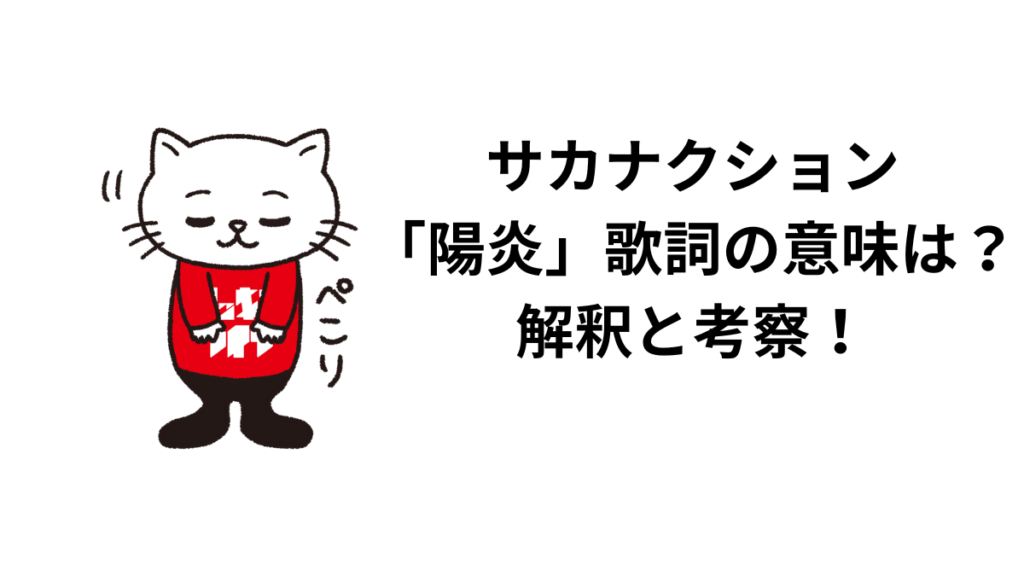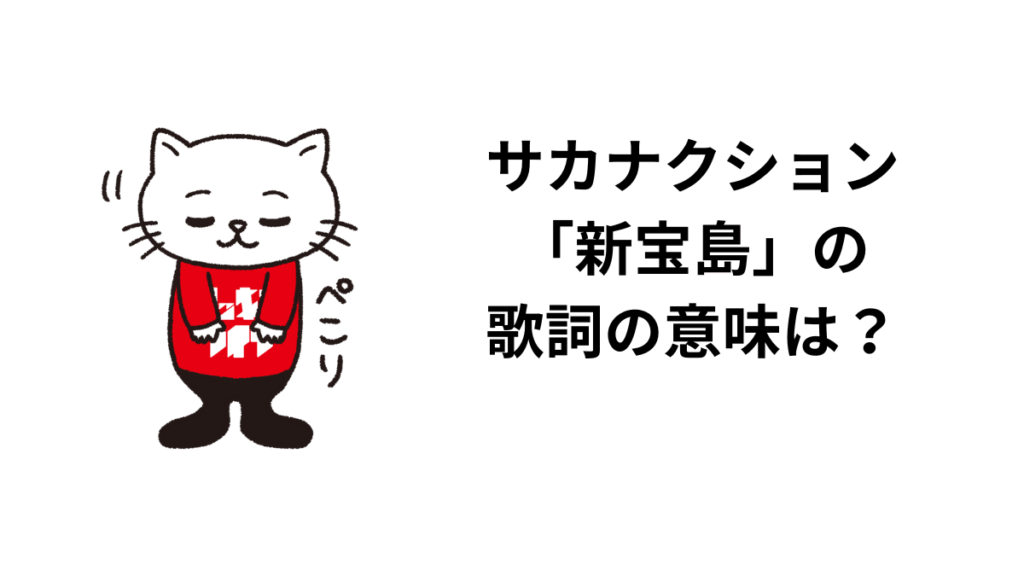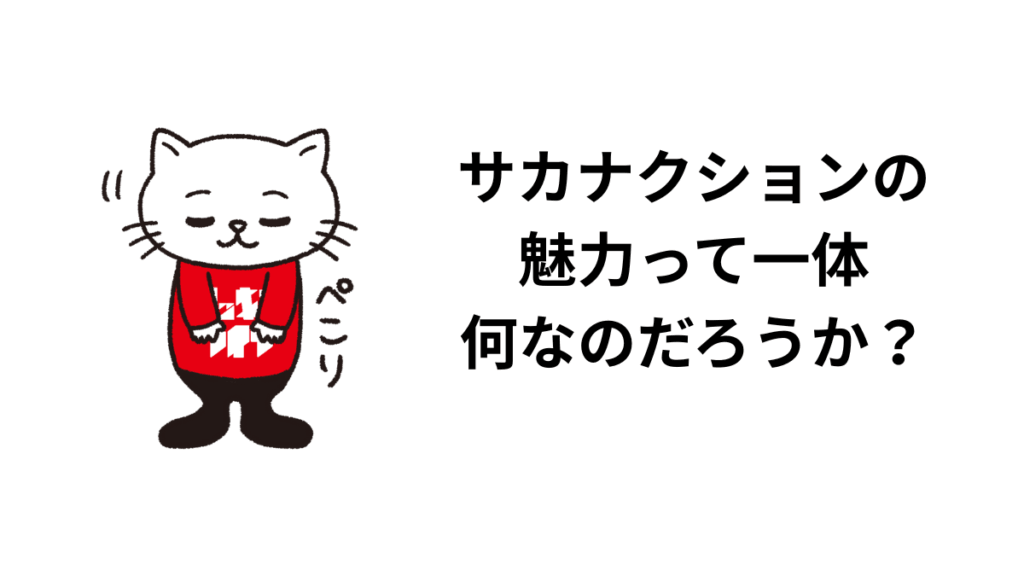
サカナクションの魅力って一体何なのだろうか?
過去の記事を遡ってみると、2021年以降、サカナクションの単独の記事を書いていないことに気づいた。でも、振り返ってみると、良い意味で2021年から自分にとってのサカナクションの魅力は変わっていない。
では、サカナクションの魅力って何なのか?
この記事では、そのことについて改めてスポットを当ててみたい。
変わったけど、変わらない魅力
例えば、「新宝島」。
この楽曲が発表されたのは2015年。まもなく10年が経とうとしている。
ところで、この歌、今聴いてもどう感じるだろうか?
もともとの楽曲としては、意図的にレトロな音色や様相を取り入れた楽曲ではあるけれど、9年経った今も楽曲が持つ鮮度は一切変化していない。
活動休止の時期を挟んだうえでの配信シングルというタイミングであり、どういう楽曲をリリースするかで、シーンにおけるバンドの存在感が大きく変わる時期の、強烈なインパクトを与えたの「新宝島」。
初めてライブで聴いたときの衝撃も含め、ここぞのタイミングで楽曲をリリースするときのサカナクションの求心力に、思わず感銘を受けるような一撃だった。
リズムの刻み方。
音色の触り心地。
サビのキャッチーさ。
メンバー全員の存在感。
どれもが絶妙であり、故に、何度も聴きたくなる楽曲。
でも、「中毒性がある」と一口に言っても、当時のバンドシーンでよく言われる中毒性とはまったく異なる中毒性で、だからこそ、色んな世代や層にも刺さることになり、さらにサカナクションが大きく飛躍していくことになる。
まあ時代的な話は置いといて、「新宝島」って、今聴いてもすごくワクワクする楽曲である。
既存の音楽のエッセンスを巧みに取り入れたり、ミックスしながら、他のバンドにはない音楽体験を生み出す。
サカナクションって、そういうアプローチがすごく上手いバンドだった。
そして、「新宝島」では、この「どういうエッセンスを参照するのか」という問いに対して、今まではこういうものはなかっただろうから、こういうものを形にしてみたぞ、という刺激が凄まじく、それは令和になった今でも色褪せていない、というのが自分の率直な感想。
サカナクションの魅力を端的に語るうえでも、「新宝島」は今なお圧倒的なインパクトを放つ楽曲だと感じる。
そして、サカナクションってバンドのフェーズとしては、時期によって細かく変化している。
バンドとしてのモードもそうだし、今ってバンドとしてはこういう音楽に関心を持っているのかな?という趣向の部分でも変化を感じる。
だからこそ、
GO TO THE FUTURE
NIGHT FISHING
シンシロ
kikUUiki
DocumentaLy
sakanaction
834.194
という感じで、アルバム単位で並べてみると、その味わいがまったく違うことに気づく。
幅広く、ダンスとロックの融合という切り口で捉えられるとしても、その作品が持つ体験はがらりと変わる。でも、逆に言うと、アルバム単位でみると、そのまとまりが素晴らしい。
それだけバンドのモードが変わってきたことの証であり、順を追って変化したことを示すエピソードだと考えられる。
そして、そういう変わり続ける歴史の中でも、でも、バンドのアイデンティティはキャリアを積む中で、むしろ強固になっている印象を受ける。
ファンの中でも、サカナクションってこういうバンドというイメージがどんどん洗練されていくというか。
この辺りに、サカナクションの「変わったけど、変わらない魅力」を感じることになる。
モードという切り口でみると、時代ごとに大きく変化している。
変化という意味では、サカナクションはわりとダイナミックに変化してきたバンドだとも思う。
でも、変化がダイナミックなバンドの中でも、すごく一貫しているバンドでもあるなーという、そういう印象だ。
例えるなら、今のバンドのモードで、ふいに初期曲を披露しても、一切浮かず、なんなら知らない人がその曲を聴いたら、「これって、もしかして新曲?」と思って受け止められるくらいの、変化はあるけど、一貫したアウトプットを生み出している印象なのだ。
『834.194』のアルバムのコンセプトには、まさしくそういうものもシンクロしていると思うんだけど、このあり方は、他バンドをみても、意外とあまりいない気がする。
変わりすぎるか、変わらなさすぎるか。
バンドとしてのジャンル性は、わりとどちらかに傾倒しがちだと思う。
でも、サカナクションはその中間に位置しているというか。
それだけコアな部分が確立させているという話だと思うし、だからこそ、サカナクションの音楽は時代を経ても、瑞々しい輝きを解き放つのだと思う。
歌が強い、サウンドも強い、そしてそれ以上にボーカルが強い
これは別の楽曲の感想でも書いた気がするのだけど、サカナクションって、わりとスタイリッシュなイメージが強いと思う。
フェスでのライブの演出に一度は度肝を抜かれた人も多いと思う。
常に斬新な演出やパフォーマンスを繰り広げ、フェスに出るバンドってこういう感じ、を常に変えていったサカナクションだからこその境地。
故に、サウンドとかリズムアプローチとか、演出とかパフォーマンスの部分で魅力を語られることが多いバンドである。
確かに、それも大きな魅力のひとつだ。
ただ、こうやって改めて楽曲を聴いてみると、サカナクションとサカナクションに憧れた「っぽいバンド」を比較したときの決定的な違いって、ボーカルの強さにある。
楽曲を聞き直していると、そんなことを思う。
サカナクションって、ダンスロックっぽい楽曲から歌謡曲っぽい楽曲まで歌いこなすバンドであり、リズムのフックが強い歌から、メロの要素が強い歌まで柔軟にアプローチする。
楽曲によっては、趣向性の強い歌だって多い。
でも、そういう楽曲でも多様な人が刺さる根源にあるのは、山口一郎のボーカルがあるからだ。
改めて、そんなことを思う。
耳に届きやすい音と、届きにくい音があると思う。
あるいは、歌詞や言葉が届きやすいボーカルと、そうじゃないボーカルがあると思う。
基本的にはサウンドとボーカルの相性がよければ何でもアリだとは思うんだけど、タイプとしてみたときに、サカナクションのボーカルって、何よりも先立ってボーカルが真っ直ぐに届く強さがある。
弾き語りでも十分に成立する。
そういうパワフルかつ言葉が届く歌声なのだ。
だからこそ、様相を際立たせて、サウンドも凝りに凝ったものに仕立てたときに繰り出される本気のボーカルのパンチ力がえげつないのだ。
ボーカル単品は普通だけど、サウンドとか曲がかっこいいからOKになっているバンドって、わりといたりする。
でも、サカナクションって、そもそもボーカルだけでOKになる魅力に溢れている。
そのうえで、サウンドも曲の良さも演出も磨きに磨くから、とんでもないことになるというそういう話。
だから、サカナクションにあこがれた感じのするバンドは、一時期シーンで散見されたが、サカナクションのイズムを引き継いでシーンを牽引する、みたいな状態はない気がする。
それは、色んな要素が組み合わさった結果ではあると思うが、サカナクションがテクニック的な部分とは異なる部分にも圧倒的な魅力からである、というのは大きい。
例えば、ボーカルとか。
っていう、そういう話。
まとめに替えて
何が言いたいかというと、やっぱりサカナクションの音楽っていいなあ、という話。
仮に2010年代の日本のバンド史みたいな本が刊行されるとしたら、間違いなくサカナクションは語られるべきバンドだと思う。
それだけ大きな魅力を解き放ってきたから。
そして、2020年代もまた、変わりつつも変わらない魅力を持ち続けながら、サカナクションの音楽は今なお響いている。
そのように感じる。