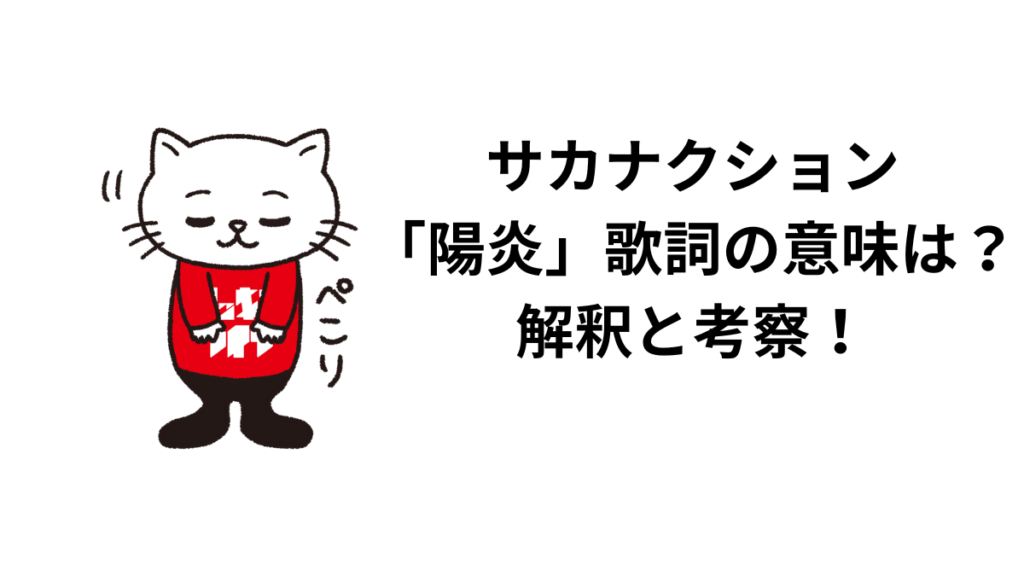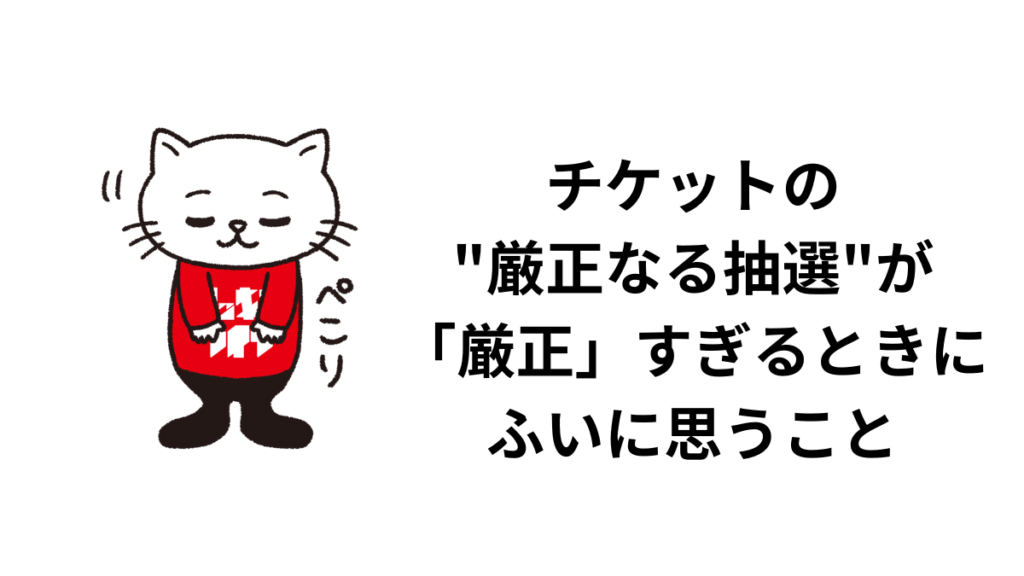サカナクションの人気が不動の理由とは?魚図鑑から考える山口一郎の制作スタイルについて!
2013年くらいからフェスに足繁く通っている人は感じると思うのだ。
ここ数年、ずっとサカナクションってフェスでトリやん、と。
もちろん、サカナクションはパフォーマンスの性質上、野外フェスだと夜しかブッキングできないというのはあるだろうが、それでも今年出演する春フェスは見事にトリばかりというのは異例というか凄いというか。
もちろん、出る順番なんて順番でしかなくて、そこに深い意味なんてないのだ!という指摘はあるのかもしれないが、それでも一番最後に出演するということは、他バンドが目的で残る人がゼロになるわけで、下手をすればガラガラになるリスクが出てくる。
そういう意味で、トリという立場は責任の重い立場である。
で、そういう責任ある出演場所を何年もかけてずっと任せられているサカナクションって、やっぱり凄いよなーという話になる。
特に近年のロックシーンは異常に興盛のサイクルが早くなっている。(特にフェスシーンにおいては)
そんななかで、ずっとフェスにおける扱いが変わらないサカナクションって、とても稀有で偉大な存在なわけで。
なぜサカナクションはここまでずっと人気であり続けることができたのだろうか?
この記事では、そのことを今一度考えてみたい。
サカナクションの凄さとは?
こういう問いを立てたうえでバンドの良さを語る際、ポイントとなるのは「楽曲の良さ」と「ライブパフォーマンス」のふたつだと思う。
楽曲の良さに関して言えば、メロディーとか歌詞とかサウンドとかノれるとかボーカルが好きとか、そういう切り口で語ることになる。
サカナクションの場合、ひとつの要素が飛び抜けて優れているというよりは色んな要素が噛み合っているからこそ、随一の楽曲になっているとは思う。
ベストアルバム「魚図鑑」のライナーノーツをみても分かる通り、サカナクションメンバーは全ての要素で納得するまで試行錯誤を続けるし、そこに妥協という文字は一切ないからこそ、圧倒的なクオリティーの楽曲を生み出すわけだ。(ただし、妥協をしなさ過ぎて締め切りを大きく破ることは多々あるが)
ライブパフォーマンスに関して言えば、楽曲の再現性はもちろんのこと、照明を駆使した独自の世界観の創出と、その完成度の高さがサカナクションの唯一無になものにしていると思われる。
これは、わざわざここで改めて述べるまでもないことだと思う。
結局のところ、サカナクションは楽曲の良さとライブパフォーマンスの両輪が圧倒的な水準に達しているからこそ、不動な人気を獲得している。これは間違いない。
まあ、ここで話を終えてしまっては「いや、そんなのわかってるし」ということになると思うので、この記事では「その両輪が圧倒的な水準に達している状態」をなぜ長い間維持できるのか?ということについてさらなる論考を進めてみたい。
①音楽への取り組み方がアート的であり、サイエンス的である
サカナクションは音楽に対するアプローチがアート的でありながら、サイエンス的である。
どういうことか?
ここでいうアート的とは、芸術的と言い換えることもできるし、「言語化・数値化出来ないもの」というふうにも言える。
音楽を聴いて感動したという場合、なぜその音楽に感動したのかを説明するのは難しく、一言で言ってしまえば、心が揺さぶられたからだ、という話になると思う。
音楽というのは、そういう言葉にはできない要素を持っている。
例えば、マイナーコードは物悲しい響きを与える、ということは言えたとしても、なぜマイナーコードが物悲しい響きを心に与えるのか、ということをちゃんと言語化することは難しい。
そういう言語化できないものの集積こそがアートであり音楽であるわけだ。
それでも、あえてそれを言語化するとしたら、それは見る者、感じる者が答えを導き出すしかない。
一方、サイエンス的とは言い換えれば科学的=理論的というふうにも言える。
これはアート的と対比して、言語化・数値化出来るものということになる。
音楽理論なんかはまさしくそれだ。
音楽理論というのは、過去の音楽のパターンを言語化したものである。
先人たちが苦労して研究してきた「こうしたら気持ちの良い音楽が作れる」というノウハウを言葉(あるいは記号)にして落とし込んだのが音楽理論であり、それはすごく科学的アプローチに近いものがある。
だから、音楽理論=サイエンスというふうに言えるわけだ。
一郎氏は、様々な要素を理論的というか理屈的に捉え、それを自身の音楽に落とし込むタイプのクリエイターである。
どういう音楽だったら人は踊れるのか?とか、こういうタイプの音を組み合わせるにはどうしたらいいのか?とか、そういう様々な理論をベースにしてサカナクションの楽曲は作り込まれていく。
各楽曲、どういう落とし込み方をしたのか、という話はベストアルバムの「魚図鑑」の付録のライナーノーツにチョコチョコ書かれていたりするわけだけど、ここで言いたいのは、一郎氏の音楽制作のアプローチはすごくサイエンス的な要素が強い、ということである。
そして、緻密な理論があるからこそ、一郎氏は毎回心に残る楽曲を「再現」できているわけである。
サイエンスがアートより優秀なのは、再現性を担保してくれることである。
一郎氏の制作スタイルがサイエンス的アプローチであるからこそ、サカナクションの楽曲のクオリティは安定的なものとなっている、と言えるわけだ。
②サイエンス的であることの見定め
ただし、理論化を推し進めていくと個性がなくなる。
一郎氏はそこに対しても相当自覚的である。
だからこそ、毎回別の要素から音楽のアイデアを持ってきてサカナクションの音を作ろうとする。
「グッドバイ」「さよならはエモーション」「多分、風。」「新宝島」「SORATO」「陽炎」を並べてみても、サカナクションのバンドサウンド+αにしている要素は毎回違うことがわかる。
色んな要素を理論的に拵えていくからこそ、サカナクションの楽曲はより安定的であり、長期的に高水準な楽曲を生み出し、飽きのこない楽曲を生み出すことができているわけである。
③最終的にはアート性が輝いている
ただし、サイエンスだけではアートを超えられない。
関ジャムなんかで蔦谷好位置が楽曲の良さを解説していたりするが、これはまさしく音楽をサイエンス化していると言える。
この音楽はここが凄いんだという説明=理論化=サイエンス化することで、音楽を模倣をすることは可能になる。
けれど、それをパターン化すると、初めてその音楽に触れたときの感動を超えるものは生み出せなくなる。
結局、どれだけ理論武装してもアート性というものは理論の中からは生まれないわけだ。
だって、アート性は言葉では説明できないようなものの中にあるから。感動そのものは言葉では説明できないものだから。
あくまでも、アートを再現させるためにツールとしてサイエンスがある。
ここがポイントなわけだ。
一郎氏がアート性を一番発揮するのは、できた楽曲にオッケーを出すタイミングだと思う。
サカナクションのどの楽曲でも言えることだが、毎回楽曲を作っては壊して作っては壊してを繰り返している。
それは端的に言えば、一郎氏が納得しないからである。
この「納得の基準」こそが一郎氏のアート性なわけである。
理論武装して作ったものに対して、自分のアート性を重ねる。
自分のアート性を照らし合わせて納得できたらその作品を世に出すし、ダメなら作り変える。
これがサカナクションの楽曲が高水準である最大な理由なわけだ。
言ってしまえば、一郎氏のアート性が未だに錆びついていなからこそ、最終オッケーを出すまでに楽曲は何度も化学変化を起こすし、自分のアート性に従って納得のいく作品ができたとき、初めてパッケージ化するからこそ、他の誰が聴いてもぐうの音の出ないクオリティの作品を生み出しているわけである。
この、自分のアート性を信じれるところがサカナクションの最大の強さなのがしれない。
まとめ
身もふたもないことを言うと、結局のところ、サカナクションはセンスが良いから間違いない楽曲を生み出せるという話。
けれど、そのセンスの再現性を高めるのはサイエンス=理論であり、一郎氏はその両方を使えるところまで使うからこそ、圧倒的なクオリティの楽曲を作れるというそういう話。