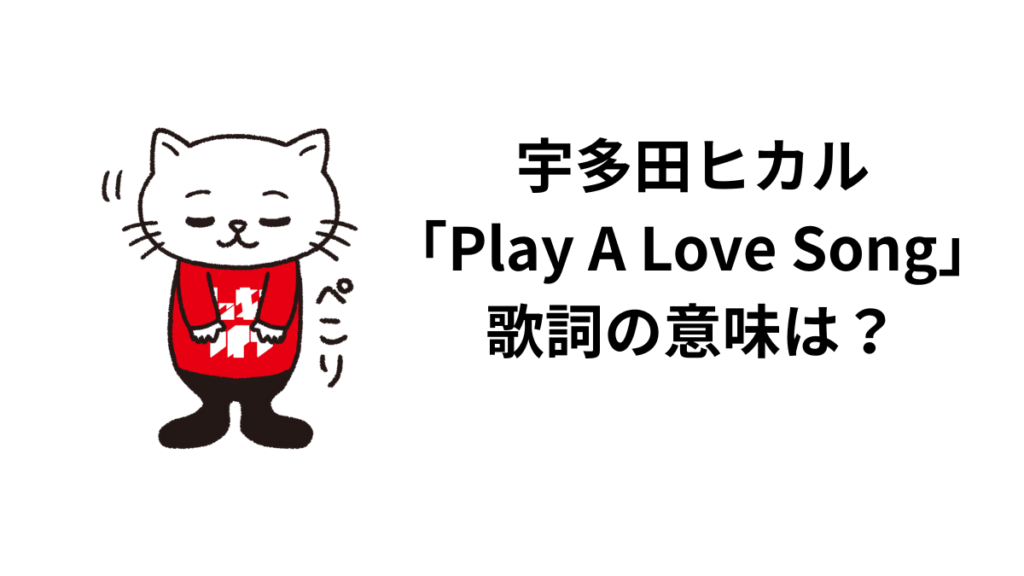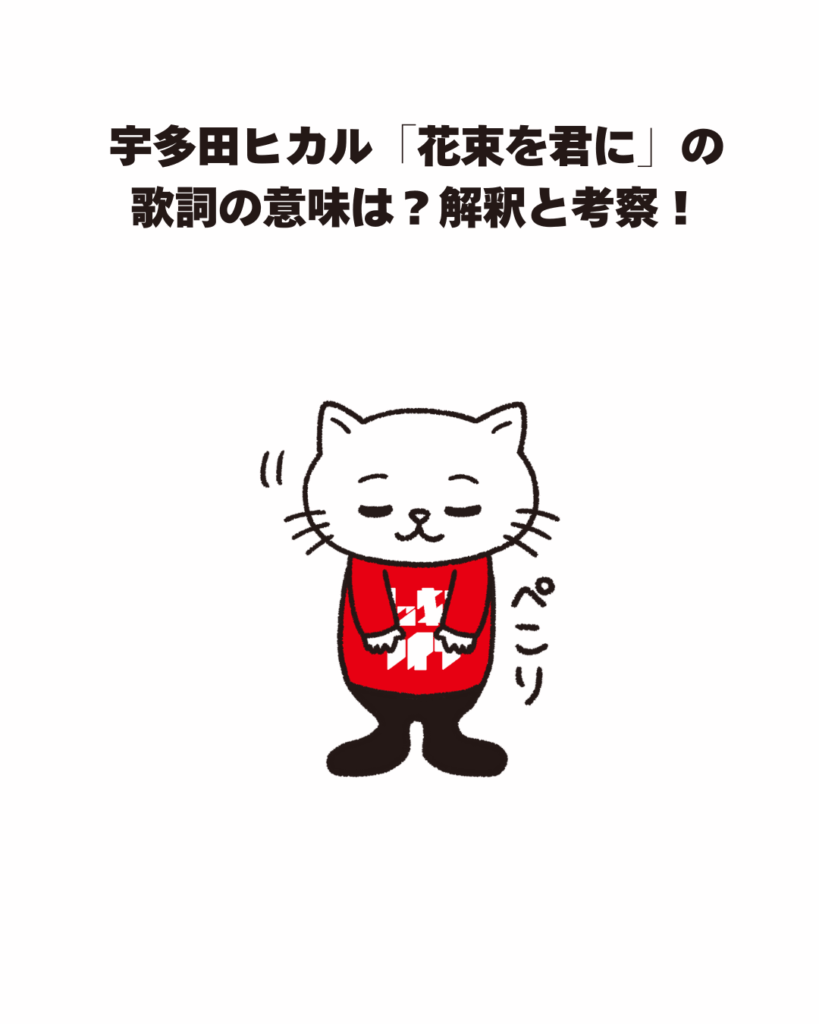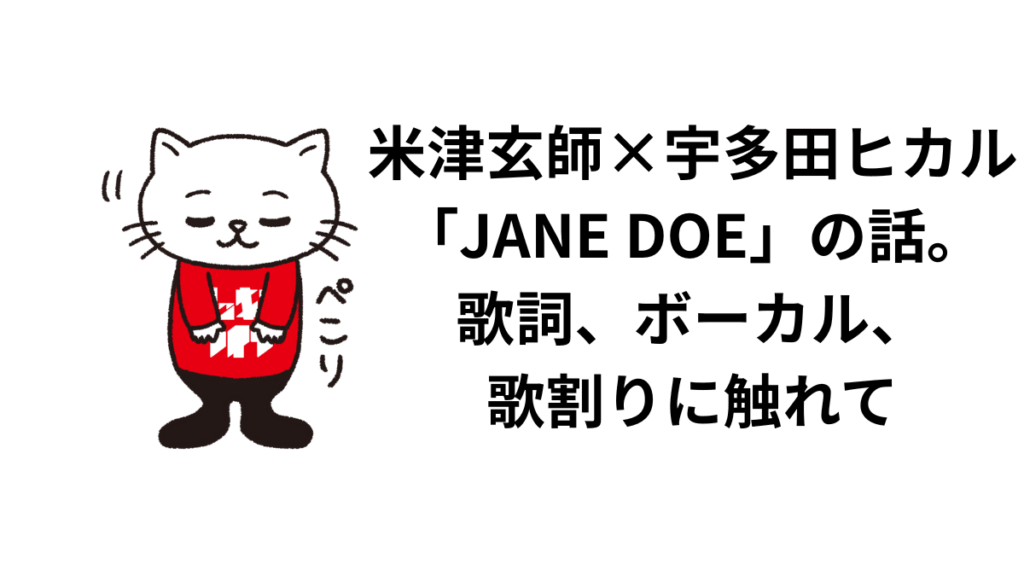宇多田ヒカルの「One Last Kiss」とエヴァンゲリオンのシンクロ率について
一部をのぞいて、基本的にはほとんどエンタメ映画には、主題歌というものがある。
楽曲が映画主題歌になるまでの道のりは、きっとそれぞれでまったく違う。
そのため、映画に対する寄り添い方やシンクロ率は映画主題歌ごとにまったく違う。
歌詞を読めば「あ、このフレーズはあのことを言っているのかな?」とニヤニヤする楽曲もあるし、何回聴いても主題歌としては、ぴんとこない歌もある。
そういうものだと思う。
さて、宇多田ヒカルの「One Last Kiss」もとある映画の主題歌である
この歌は『シン・エヴァンゲリオン劇場版』のために書き下ろされた歌である。
つまり、「One Last Kiss」は映画主題歌として生まれた曲といえる。
個人的には、この歌は『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の主題歌であることに、とても腑に落ちた歌であった。
今からこの記事では「One Last Kiss」の感想を書こうと思うのだが、この曲の感想を書く上では『シン・エヴァンゲリオン劇場版』に触れることなしに語ることはできないなー。
少なくとも、そう感じさせる歌ではあった。
というわけで、この記事は『シン・エヴァンゲリオン劇場版』に触れながら、宇多田ヒカルの「One Last Kiss」の感想を書いていきたい。
エヴァンゲリオンのネタバレに触れる可能性があるので、ネタバレが嫌な人は映画を鑑賞後に読んでもらえたら幸いである。
では、どうぞ。
本編
エヴァンゲリオンとのシンクロ
近年の宇多田ヒカルの楽曲は音の選び方が研ぎ澄まされて、楽曲世界への引き込み方がとんでもないことになっている。
細部への研ぎ澄ませ方が凄まじくて、作品世界に引きずり込み方がエゲツないという意味でも、エヴァンゲリオンとシンクロするなあなんて思う。
ただ。
「One Last Kiss」はそもそも楽曲の存在そのものがエヴァンゲリオンが物語ってきたこと(それは今回の劇場版のみならず、エヴァンゲリオンが25年で物語ってきたこと)ともシンクロしているように感じるのである。
どういうことか?
宇多田ヒカルがエヴァンゲリオンに楽曲を書き下ろすようになったのは、エヴァンゲリオンの新シリーズ(という言い方が正しいのかはわからないが)となる<新劇場版>からである。
エヴァンゲリオン史的に言えば、エヴァンゲリオンは一度『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に』で完結している中、新たに物語を再構築したような形で<新劇場版>が始まることとなった。
この辺りを掘り下げていくと、単なるエヴァの解説記事になってしまうので、細かい部分はカットしていくが、<新劇場版>から宇多田ヒカルはエヴァンゲリオンに関わった、ということがここでは重要となる。
<旧劇場版>までのエヴァといえば、「残酷な天使のテーゼ」や「魂のルフラン」など、エヴァの主題歌として人気の高い楽曲が多かったため、いわゆるJ-POP畑にある宇多田ヒカルの器用は良くも悪くもエヴァの世界にとっては、異端に映る部分もあった。
それこそ、人類の世界に使徒が襲来するかのような、インパクトを与えることになる。
もちろん聴き手ごとに感想は変わるだろうが、初めて宇多田ヒカルがエヴァンゲリオンのために描き下ろした「Beautiful World」は、必ずしもエヴァの世界観とのシンクロ率は高くなかったような気がする。
宇多田ヒカルそのものの作家性が強いゆえに、良くも悪くも<エヴァの歌>というよりも<宇多田の歌>になっていたような気がするのだ(少なくとも、自分はそんな風に感じた)。
ただ、今作の「One Last Kiss」(もっと言えば、その後に流れる「Beautiful World」のニューヴァージョンとなる「Beautiful World (Da Capo Version) は、どこまでもエヴァの世界とシンクロしていたように感じるのである。
今作の映画の一幕で、シンジがエヴァに乗った際、シンジはエヴァのシンクロ率がゼロだと思っていたが実は無限大だった、というくだりがあるんだけども、宇多田ヒカルの楽曲でも同じような印象を抱いたのである。
エヴァとの世界のシンクロ率が低いと思っていた宇多田ヒカルの楽曲は、実はとんでもなくシンクロ率が高かったのだという話。
前口上が長くなってしまっているが、なぜ宇多田ヒカルの今作に、そのようなイメージを覚えたのか。
この辺りをもう少し丁寧に説明したい。
歌詞が映画のことをきちんと物語っているから、そう感じたのだろうか?
もちろん、言葉の選び方も絶妙ではある。
んだけど、言葉の力はシンクロ率を高める上で、あくまでも副次的なもののように個人的には思っている。
どちらかというと、歌を構成する全ての要素が主題歌としてのシンクロ率を上げているように思うのだ。
「One Last Kiss」は冒頭からミニマムなサウンドと、華麗なリズムで心地よい楽曲世界を構築している。
宇多田ヒカルらしい音選びと、少しハスキーがかった歌声で、宇多田ヒカルらしい世界観を生み出していく。
そして、歌の中である種の秩序も生み出されていく。
この歌はこういう流れで進行していくんだな、というある種の調和のようなものを感じる。
・・・しかし。
2番のサビを終わった辺りから、歌の様相が変わっていく。
サウンドの構築のされた方が変化していき、「忘れられない人」という言葉がリフレインしていく。
しまいには、宇多田ヒカルの声が楽器のような響きを持つようになり、サウンドの中に溶けるかのように展開されていく。
やがて、そのサウンドが唐突に静まっていくと、宇多田ヒカルの歌声が余韻を残すように、最後の二小節を歌う。
その盛り上がり方と歌のケリに付け方に、今作の映画の後半の流れと通ずるものを覚えるのだ。
さらに言えば、<忘れられない人>がいた<美しい世界>は、新しく登場した<忘れられない人>によって、まったく別の<美しい世界>へと書き換えれていくという意味で、「Beautiful World」のニューアレンジで描かれる流れにもまた、映画の後半と繋がるものを覚えるのだ。
この辺りは映画を観てないからすれば、エヴァをまったく知らない人からすれば、?かもしれないが、この「(外部にいる人との出会いが世界を変える」というモチーフは、今作のエヴァンゲリオンの映画においてすごく重要な意味をもつ要素となっているのである。
そういうテーマを、物語が始まった段階ではエヴァという作品において外部の人間であった宇多田ヒカルが行っているところに、ドキドキさせられるのである。
『シン・エヴァンゲリオン劇場版』において、最終的にシンジが誰と一緒になったのかを考えれば、きっとこの意味がわかると思う。
こういう諸々を踏まえて、今作の宇多田ヒカルのシンクロ率は無限大といえるのではないか、と思ってしまうわけである。
宇多田ヒカルが自分のことを歌うようになったこと
宇多田ヒカルは2010年に人間活動なるものを発表し、翌年から(基本的には)活動休止に入る。
やがて2015年から活動を再開するわけだけど、エヴァンゲリオンとの関わりで言えば、活動休止の少し前にエヴァンゲリオンの主題歌を作り、活動休止中もエヴァの歌だけは作り、最終的に完全復活を遂げた今、今作を生み出すことになる。
宇多田ヒカルの文脈において印象的だったのは、活動休止開けにリリースされた「花束を君に」「真夏の通り雨」という二作品。
この歌は、これまでの宇多田ヒカルの楽曲では考えられなかったくらいに、自分のこと(自分の母親)を歌った歌となっている。
たくさんの人のために世に放つ歌の中で、あえて自分のことを語る選択をみせるようになるのだ。
エヴァンゲリオンという作品もまた、そういう私小説な色合いがものすごく強い作品である。
総監督である庵野秀明のコアな部分や価値観が色濃く投影された作品となっている。
旧劇場版までのエヴァにおいては、庵野秀明は明らかにシンジを自分の姿に重ねて物語を紡いでいる。
エヴァというのは、ある種の内面描写の作品であり、「逃げちゃダメだ」という台詞やATフィールドという要素もまた、庵野秀明の内面を描写するためのギミックになっている。
ただ、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』では、庵野秀明はシンジにではなく、その父親である碇ゲンドウに自分を投影している。
だからこそ、碇ゲンドウが自分と向き合い、ある種の価値を壊す場面が描写されるわけだけど(ここに庵野秀明の成長ドラマとしても享受できるわけだけど)、エヴァがこういう部分に向き合い、過去のエヴァシリーズで失敗し続けた<大円団>に向かうのは、物語の円環の外側からの女性の襲来がきっかけとなる。
庵野の物語的にいえば、配偶者である安野モヨコがその鍵を握る存在、ということになるんだけど、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』という作品もまた、そことリンクするように物語が展開されていくわけだ。
話がだいぶエヴァに寄せられてしまっていたが、宇多田ヒカルもまたエヴァと関わることで、自分を語るようになったのかなーなんて感じるのである。
思えば、活動休止を発表する際に言葉として出した「人間活動」というワードもまた、エヴァっぽいギミックの言葉のような気もする。
宇多田ヒカル自身が、どこまでエヴァに影響されているのかはわからないが、少なくとも、エヴァ以降の宇多田ヒカルには、明らかな変化がみれることは確かだということ。
歌への向き合い方みたいなものも変わってきたからこそ、「One Last Kiss」はどこまでもエヴァンゲリオンという作品のシンクロ率が上がったのかなーなんてそんなことを思うのである。
まとめに替えて
で、「「One Last Kiss」の作品についてはどう思っているんだ、という話になるわけだけど、日本のヒットチャートを接近するポップスと作り方の発想、音へのこだわりがまったく違いすぎて、やっぱり宇多田ヒカルってすげえ・・・・という感想に行き着く。
YOASOBIをはじめ、ネットをきっかけにしてシーンに存在感を魅せる新進気鋭なアーティストが増えてきた。
そういう世代の場合、あえて音はチープに表現することも多い(というよりも、こだわりのベクトルが音質とは違うところに向いている)。
そこについては良い悪いもないんだけど、そういう人たちが増えてくるからこそ、どこまでも音そのものを美しいまでにこだわっている宇多田ヒカルの凄まじさが際立つよなーとは思うのだ。
改めて、「「One Last Kiss」を聞くと、改めて宇多田ヒカルというアーティストがものすごいんだということを実感せずにはいられない。