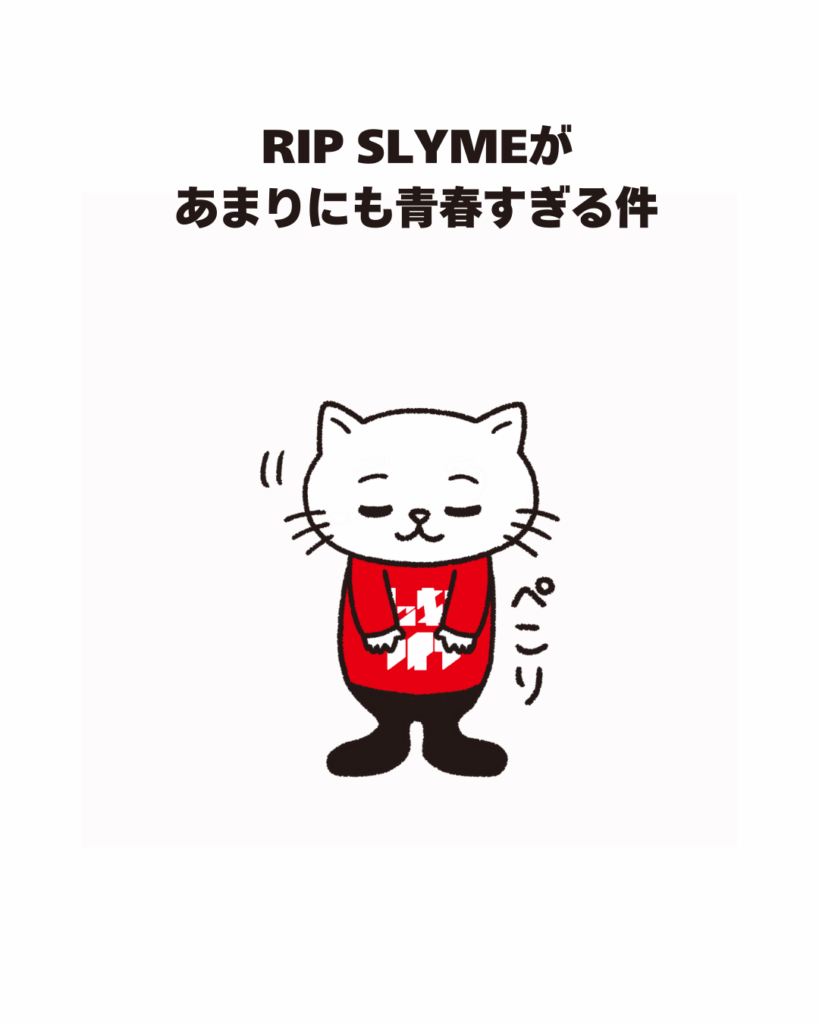
RIP SLYMEがあまりにも青春すぎる件
自分が「ラップ」という形式のパフォーマンスに触れるきっかけとして出会ったアーティストは、ざっくり3つくらいに分けられる。
KICK THE CAN CREW、ケツメイシ、そして今回記事のメインとして書こうと考えているRIP SLYMEだ。
まあ、ヒップホップ畑にどっぷりな人からすると、この辺りのアーティストはラップの文脈で語るには、あまりにも「ポップ」すぎると感じるケースもあるかもだ。
が、当時10代だった自分からすると、ラップというパフォーマンスとの出会いのきっかけは、間違いなくこの3組のアーティストだった。(そして、そこを軸にして、ラップの世界が縦にも横にも広がることになる)
歌ものしか知らなかった自分からすると、音楽ってこういうアプローチもあるのかと知ったきっかけになったのだった。
その上でも、自分的にはRIP SLYMEの存在がとんでもなく大きい。
なぜか。
そこで、この記事では、なぜ自分がRIP SLYMEにどっぷりハマったのか。
そして、今でもRIP SLYMEの音楽にグッとくるのか。
その辺りを軸にして言葉を紡いでみたいと思う。
4MCで作り出す、圧倒的な多彩感
RIP SLYMEの音楽がどこまでも輝いていたから。
それが端的にして、理由の全てではあるんだけど、その上で絶対的に言葉にしたいのは、これ。
個性的な4MCが揃っていたから、ということ。
思えば、音楽にハマるきっかけがバンドだった自分にとって、4MCの存在はあまりにも異色だった。
だってバンドの場合、メインを張るボーカルは普通は一人、例外的に二人くらい、みたいなパターンが多かったから。
少なくとも、当時の自分は、ボーカルってそういうもんという認識だったのだ。
でも、RIP SLYMEは違う。
1番と2番と3番も目まぐるしくマイクを握る人間が変わる。
しかも全員が個性を解き放つのだ。
「サブ」になるやつなんて、いない。全MCが圧倒的に主役。しかも、そのカラーが被ることはない。5レンジャーよろしく、それぞれがそれぞれのカラーを解き放つ。
そんなRIP SLYMEの音楽が、どこまでも印象的だったのだ。
例えば、グループの代表曲でもある「楽園ベイベー」。
冒頭は、しゃがれたILMARIのラップが軽快に駆け抜ける。
安定感のあるスリリングなラップを展開。常夏っぽいアレンジに対する、クールでホットなラップが印象的に響く。
そして、ILMARIのパートが終わると、すぐその後のバトンを受けるのは、低音ながらどこまでも心地よい、官能的なラップを披露するSU。
このトーンチェンジ。
昔の阪神のFJKの並びに興奮したのと同じくらいの、圧倒的なリレー。
そう。
このILMARIとSUのリレーだけで、途方もない高揚感を覚えることになる。
違った例えをするならば、ポケモン金銀で、ジョウト地方からカントー地方に踏み出したときのような、境界線で「!?」となる感じに近いかもしれない。
切り替わった瞬間そのものが稲妻のような衝動を与えることになるのだ。
そして、2番ではRYO-Zが気だるげながらも、切れ味鋭いラップを披露するのがまた良い。
あえて言えば、RIP SLYMEにおいて、もっともトーン的には真ん中なRYO-Zのラップ。
色んなところに向かうようなドタバタ感があるRIP SLYMEの歌に、ぐっと中心を据えていく。
結果、1番とは異なるスリリングを味わうことになる。
そして、もうこれ以上はないと思ったタイミングで、3番ではPESが登場するのだ。
それこそ、過去最高気温を更新するような猛烈感。
これまでのどのパートよりもアッパーで、スリリングで、容赦がない。ハイトーンで、良い意味で「軽い」のが刺さる。
オナる〜の締め方含め、この音楽体験はけっこう強烈なインパクトだったことを思い出す。
しかも、だ。
RIP SLYMEって、楽曲によって、4MCの順番はがらっと変わる。
誰が最大の盛り上がりを担っても良い。
どのフォーメーションで、進行するのもあり。
打順も守備位置も自由自在な野球チーム。オールスターの時くらいしかできない贅沢なあり方を、RIP SLYMEならどの楽曲でもやってのける凄さがあるのだ。
「どON」のような新譜でも、その根底は変わらない。
近年の楽曲の方がジャンルとしてのこだわりだったり、熟達した渋みは出ているが、4MCだからこその無敵感は一切変わらないのだ。
FUMIYAの音楽センス
そして、FUMIYAが紡ぐトラックが良い。
そこにその音を当てはめるのか!?の発見が凄い。
音楽の宝石箱や〜〜〜!なんて喩えが言いたくなるほど、4MCの裏で響くFUMIYAのトラックの中毒性が半端ない。
「GALAXY」のようなコミカルでひょうきんな音づかいをすることもあれば、「ラヴぃ」のようなスタイリッシュかつ近未来的なアレンジを手掛けることもあれば、「また逢う日まで」のようなバランス感で組むこともある。
多様な楽曲の中で、「そうそうそれそれ」なアレンジを組み立てる。
RIP SLYMEの楽曲に命を吹き込んでいるのは、紛れもなくFUMIYAの存在があるから。
なお、FUMIYAが作曲を手がけた楽曲は基本名曲だらけだが、ここぞのタイミングで放つPESの歌は良い。
PESって軽快なラップが持ち味だけど、ふいに放つエモさがたまらないのだ。「One」とか、今聴いても独特の感動にじんわりする。
まとめに替えて
色々あった果てに再び精力的に活動を開始したからこそ、RIP SLYMEのことがふいに話したくなったそんな夜。
つくづく自分の青春ど真ん中だなーと感じる。
