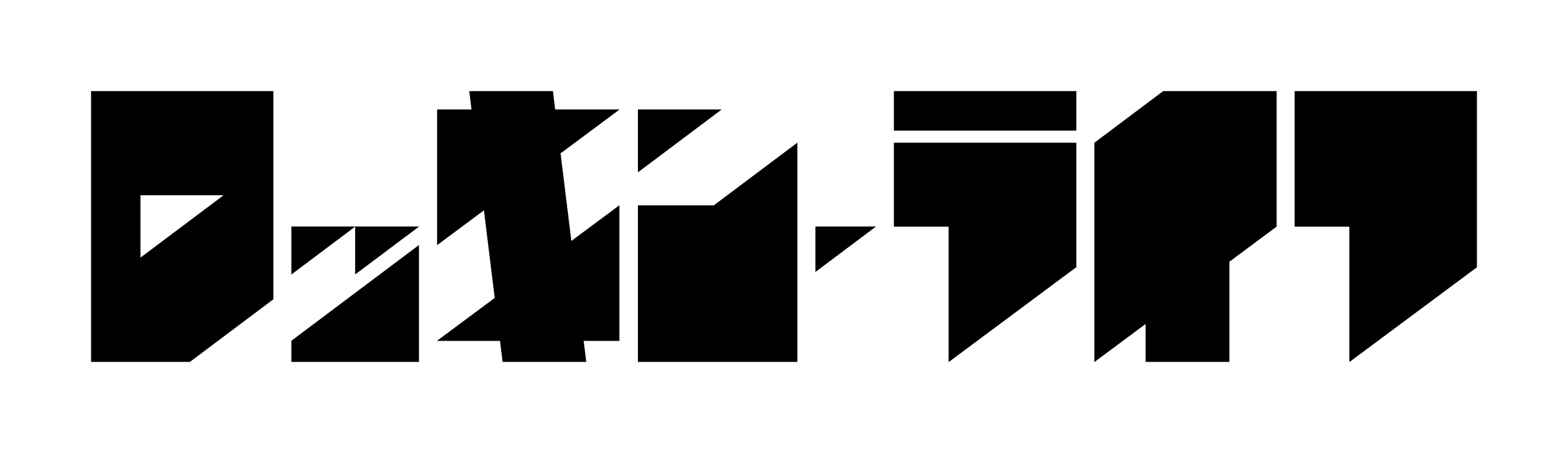SixTONESの「CREAK」、触ると火傷するタイプの氷な件
スポンサーリンク
毎回新曲のリリースを楽しみにしているアーティストは何組も存在しているが、SixTONESの場合、その「楽しみ」の温度感が他のアーティストとちょっと違う。
というのも、自分たちで作詞・作曲・アレンジを手がけるアーティストの場合、特にバンドなんかだったりすると、どれだけジャンルレスであろうとも、ある程度幅の中で収まってしまうことが多い。
言い換えれば、その幅がそのアーティストの作家性になっているとも言えるわけで、どちらかというと自分はそれを肯定的に捉えているわけだけど、新曲を聴く場合、その”幅”を意識しながら作品を聴く、というケースが多くなる。
なので、場合によっては「ああ、なるほど今回はこのパターンね」みたいな受け止め方をするケースもある。
一方、SixTONESの場合、それと逆のことを感じる。
これは、SixTONESが自分たちで作詞・作曲・アレンジを手掛けているわけではなく、毎回異なる人たちに楽曲を提供を受けているからこその部分もあるとは思うし、ジャンルに縛られない立ち位置にいるから、という部分もあるのだが、SixTONESはその”幅”を毎回拡張する面白さがあるのだ。
これまでリリースした作品ってこういう傾向のものだったから、SixTONESの幅ってそういうものなのだなあと捉え始めたそのタイミングで、その幅を軽やかに壊してしまう面白さが、SixTONESの作品には毎回あるのである。
特に近年は「人人人」や「こっから」といった意欲的作品が存在感を魅せているため、余計にその幅の拡張具合を実感するケースが多い。
とはいえ、である。
前作から前作までのスパンが長ければ、アーティストとしての表現力が高まっていくため、その幅が明確に大きくなる理屈もわかる。
が、リリースのスパンが短ければ、いきなりその幅が怒涛のものになることはちょっと考えづらいよなーとも思うわけだ。
まだ「こっから」の余韻が残りまくっている中で、SixTONESがそう簡単に新境地を魅せるのか、今回は・・・?と訝る自分もいたのだった。
並のアーティストであれば、きっと「今回は変わらない」に陥っていたと思う。
でも、しかし、SixTONESはリリーススパンが短い中でも、確実に新曲でそのドキドキを提示してくれていた。
「CREAK」を聴いて、そのことを実感したし、だからこそ、SixTONESの新曲の楽しみの温度感って、他のアーティストのそれとは異なっていることを改めて痛感したのだった。
SixTONESの「CREAK」の話
聴いて初っ端に思ったのが、コレ。
おいおいおいおい。ここに来てさらに新境地感を魅せるのかよ、「こっから」がマジで(凄さを提示していくうえでの)”こっから”でしかなかったのかよ、有言実行感ありまくりじゃねえかよ、マジで。
そう。
「こっから」では魅せていなかった、SixTONESの違った表情を至るところで表現に落とし込んでいる楽曲になっているのだ。
アレンジとしても、これまでのSixTONESのシングル曲にはなかったようなテイストである。
サビ前のドロップが印象的だし、かなり変調も大胆に行なっているし、アレンジの展開もボーカルの表情や楽曲構成も目まぐるしく変わるし・・・。
ふとYouTube上の説明欄をみてみると、「CREAK」のことをこのような台詞で紹介していた。
スリリングなビートに、力強いコーラスワークと壮大なストリングスが絡み合う、
ミステリアスダンスチューン!
確かに、ミステリダンスチューンという言葉が、言い得て妙だなーと感じる。
というのも、どんな楽曲にも色合いというものが確かに存在している。
自分の勝手なイメージであるが、「こっから」は楽曲の世界観としては赤色が見える楽曲のように感じていた。
「マスカラ」であれば、ピンクの色合いが見える楽曲のように感じるし、「Imitation Rain」であれば、雨の連想からブルーが見える楽曲のように感じていたのだった。
で。
「CREAK」という楽曲から見える色合いは、どこまでも真っ黒であるように感じたのだ。
なんというか、音やボーカルに触れただけでは、その曲がどんな色なのか予想をつかせない、油断ならない攻撃性があるというか。
メロディーの流れも、いわゆるポップとは違う響きをもった、独特の線を描いている。
この歌、冒頭は松村北斗のボーカルで始まっているが、冒頭のこの感じだけでも、そのことを強く感じさせる鋭さがある。
例えるなら、雪国で自然に生まれた氷柱のような鋭さがあるのだ。
上手く言語化するのが難しいけれど、このボーカルを安易に指で触れようとしたら、ケガをしてしまうような、そういう空気感がチラリとある。
そこから繋ぐ京本大我のボーカルも、クールかつホットな独特の塩梅でメロディーを紡いでいる。
というか、ほんとここだけで何度もリピートしたくなる、何とも言えない高揚感があるのだ。
SixTONESの中でも、松村北斗と京本大我のボーカルには独特なハイトーン感があると思っているのだけど、「CREAK」のAメロではそれが見事にマッチしている印象を受けるからだ。
クールな空気感があって、不思議とゾクゾクする感じ。
そこから先もぐっとくるポイントは多い。
マイクリレーの細かさも聴きどころだし、ドロップが炸裂するサビのブリッジで高揚感をマックスにしたところで、トドメを刺していく感じもたまらない。
猛々しさのある歌詞も、各々のボーカルの中でバッチリはまっているし、つくづくSixTONESが色んな意味で次のステージに向かったことを実感させる楽曲になっているのだった。
まとめに替えて
ということをトータルで見てみたとき、自分的に「CREAK」は触ると火傷するタイプの氷のような楽曲だなーと感じた。
この歌って、黒っぽい雰囲気があるし、全体的なボーカルもクール寄りの展開されている印象を受ける。
でも、冷ややかな歌かというとそんなこともなくて。
熱さ感じるというか、どことなくオラオラ感を滲ませた歌であるようにも感じるのだ。
なので、触ると逆に火傷しちゃうタイプの氷のような、そんな独特な空気感を持っているように感じたわけである。
あと、自分は冒頭でSixTONESの新曲は毎回新しく、それは、SixTONESが自分たちで作詞・作曲・アレンジを手掛けているわけではなく、毎回異なる人たちに楽曲を提供を受けているからこその部分もあるとは思うし、ジャンルに縛られない立ち位置にいるから、という部分もあるから、ということを書いたが、大事なことがもうひとつある。
どれだけ楽曲のカラーが変わろうとも、どれだけ違うジャンルの歌を歌おうとも、半端な表現力であれば、その歌は結局半端な色合いを生み出すことになる。
完全に楽曲の色が変わり、新しい楽曲世界を構築できているのは、SixTONESの並々ならぬ表現力があるからである、ということは最後に補足として追記しておきたい。
特に、今作はメンバーのボーカルの表情が絶妙だったので、この楽曲もミステリアスな色合いが際立つことになったのだと思う。
難しいメロディーラインを軽やかに歌いこなすそれぞれのボーカルには感服する次第だ。
兎にも角にも、今回も楽曲としてかっこよさが際立っていたので、早くリリースして音源として聴いてみたいなーと思う自分。
今は、その時が楽しみで仕方ない。
関連記事:SixTONESの「君がいない」、6人のボーカルが鮮やかすぎる件
関連記事:SixTONESのアルバム『声』に対する深読妄想記
スポンサーリンク