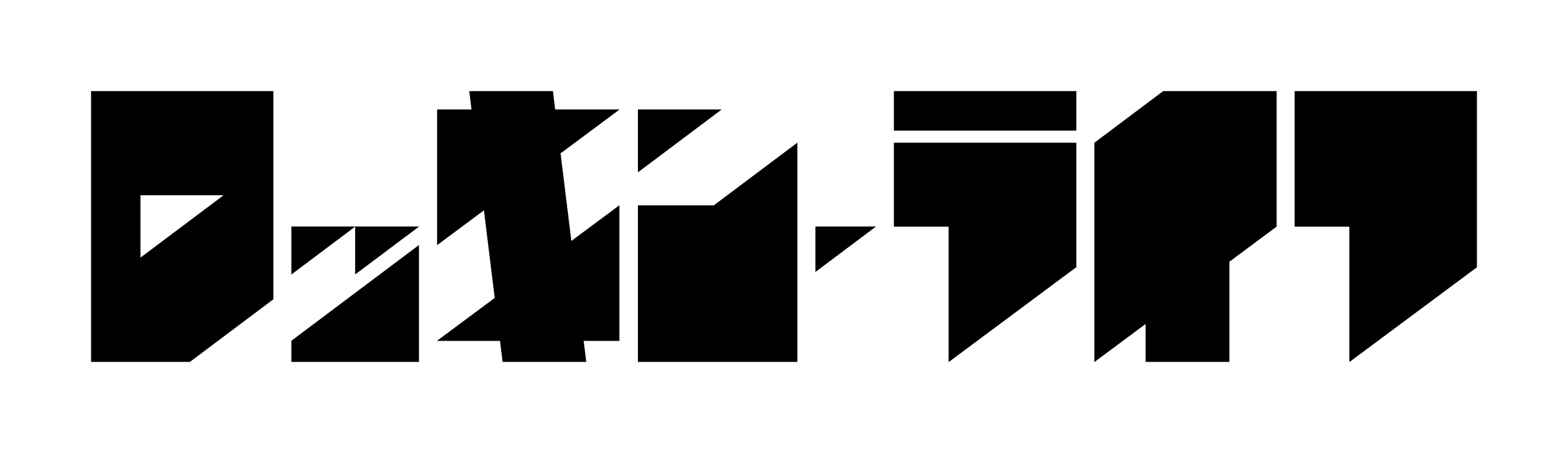King Gnuの『THE GREATEST UNKNOWN』の話をしようとしたら、どっか違うところに突き進んでしまった痕跡
スポンサーリンク
King Gnuは不思議なバンドである。
アルバム『THE GREATEST UNKNOWN』を聴いて、改めてそんなことを思う。
というのも、『THE GREATEST UNKNOWN』はマジで色んなバンドサウンドを展開するアルバムだからだ。
ジャンルレスなアーティストの場合は、ひとつのアルバムの中で色んなジャンルの音楽を入れるのはよくある話だ。
1曲目はこういうテイストの楽曲で、4曲目はしっとり目の楽曲を入れて、7曲目にはコミックっぽい楽曲でユーモラスに魅せて、ラストの楽曲では壮大な歌でがつーんと締めるみたいな・・・。
もちろん、アルバムによって構成は変わるし、アーティストによっても構成は変わるので、これがベタな構成・・・というものはないが、アルバムの中で色んなジャンルを横断しながらアルバムの核へと迫るというのは、魅せ方としてよくあるわけだ。
楽曲ごとにメンバーを変えたり、違う人に楽曲を提供してもらったりができるアーティストは、その自由度がウリになるのだから、そういう魅せ方で攻めるのも当然である。
が。
これがバンドになると、少し趣が変わる。
当然ながら演奏するメンバーも演奏する楽器も固定化される。
だから、アレンジを煮詰める布陣だって基本は一緒になる。
同じメンバーが作詞作曲を手がけることだって多いから、自ずと、パターンとして「被り」は出るだろうし、ジャンルの振り幅だって、ジャンルレスなアーティストよりは大人しめになるのが常田。
ただし、逆に作家性が際立つし、それが強みになるし、むしろその作家性にドキドキするからこそ、バンドに熱中している部分も大きい。
とはいえ、基本的に作家性が明確になると、その分、そのアーティスト(あるいはバンド)のパターンが想像しやすくなる、というのはあると思うのだ。
ただ、そう考えたとき、King Gnuって、ジャンルレス的だけど作家性が薄めでもなければ、作家性が濃いけれどジャンルが固定化されるかといえば、そんなこともない雰囲気がある。
いや、もちろん、バンドという形態である以上、どのメンバーの音も聴こえてこない、みたいな突破なアレンジに跳躍することはない。
んだけど、でも、想像できる範囲で想像できることを超えていく構成力・アレンジを展開させていき、色んなサウンドを横断しているにもかかわらず、作家性も克明にしていくのだ。
King Gnuって、そういう稀有なバンドであるように思う。
そもそも、常田大希はギターをゴリゴリにプレイする一面もあれば、ピアノをしっとり弾くこともできる。
チェロのような楽器もプレイできるし、電子音を巧みに扱うようなプレイを行うこともできる。
いわゆる、クラシック的なアプローチもできる一方で、ディープなロックサウンドに傾倒することができて、その辺りに常田大希の凄さが集約される。
音楽アプローチだけでいえば、一人で何役もこなしてしまう多彩さがある。
なので、『THE GREATEST UNKNOWN』で参照すれば、「SPECIALZ」のようなKing Gnu印のミスチャーなサウンドを展開する楽曲もある一方で、
「雨燦々」のような、ポップスとロックの中間地点のような楽曲も魅せる。
あるいは、「IKAROS」のような、クッソ繊細で井口の澄み切った歌声が堪能できる透明感のある楽曲を確認することもできる。
今作ではインストソングを巧みに配置させることで、多種多様に表情を変化させるサウンドの中を泳いでいるような心地も与えてくれる。
要は、作詞作曲を手がける人間がそもそもジャンルレスな存在であり、その人が作家性を発揮するとイコール的にジャンルがどんどん広がっていく、という時点で、King Gnuって稀有な立ち位置だよな、という話である。
そもそも、サブスクリプションの人気楽曲をみても、
「白日」
「一途」
「逆夢」
「カメレオン
と並んでいて、どれもジャンルが違いすぎるし、その振り幅が並のボーカルと並のボーカルではできないそれであることを実感するわけだ。
・・・ということを俯瞰で捉えてみると、King Gnuって不思議なバンドだなあと思わずにはいられない自分。
スポンサーリンク
バンドのアプローチの話
先ほどの項目で常田が生み出す楽曲の幅は広くて、凄いという話をした。
ただ、バンドの場合、いくら作詞作曲の頭の中で色んなパターンの絵がかけたとしても、チームとして、バンドとして、それが表現できなければ、話が始まらない。
そして、どんなメンバーだって得意なプレーがあれば苦手なプレーがあるだろし、プレイできる引き出しやアイデアだってパターンがあるように思うのだ。
だから、レコーディングの最中で一所懸命練習して、なんとか「理想」を音源の中で再現できるように、何度も同じ努力を繰り返す。やがて、その努力を積み上げた先に、感動的な作品が生まれる。
でも、King Gnuの作品って、アレンジの跳躍力に対して、あまりにもバンドメンバーの出立が傍目からみて、平然と見える。
「クラシカルなアレンジの音に、ゴリゴリのロックサウンドが展開される」
言葉で書くのは簡単だし、リスナーとして聴くだけだったらそれが当たり前のように受け止めてしまうけれど、よく考えてみると、それって全然当たり前じゃないよな、と思うわけだ。
どのパートも実力が半端ないからこそ、幅を超えたイメージが、きちんと形になる。
楽曲ごとのアレンジの詰め方がどういう進行なのかは正直よく知らない。
ただ、いちリスナーとして『THE GREATEST UNKNOWN』の楽曲を聴くと、幅に対して、バンドの雰囲気が、どこまでも平然としているよなーとは、思わずにいられない。
なんなら、これまでのライブのプレイを思い出してみると、なおのこと、その思いが強くなる。
King Gnuの楽曲ってカラオケでも難易度が高くて敬遠されがちだし、軽音部がゴリゴリにカバーするという話もあまり聞かない(音数的に、安易にカバーしても雰囲気が出ないというのもあるとは思うが)。
でも、当たり前の話だが、King Gnuがプレイすると、他の人ではなかなかできない「それ」を完全にライブで再現してみせてしまう。
生み出した本人だから当然なのかもしれないが、よく考えたら、その当然って他の人からしたら全然当然じゃないことを考えると、それをやってしまっていることの凄まじさを体感するわけだ。
まとめに代えて
なんて感じで話が脱線しまくったので、そろそろ『THE GREATEST UNKNOWN』の感想を書こうと思う。
んだけど、このアルバムで言いたいことってわりとシンプルで、構成力、おもしろい、に尽きる。
というのも、インストを巧みに挟んだアルバムの構成力が素晴らしい。
ただ、ここの部分を気の利いた言葉にできない気がしたので、この記事では、もう少し風呂敷を広げながら、King Gnuというバンドのことを改めて言葉にしてみた次第。
いやだってね、『THE GREATEST UNKNOWN』って既出曲が多いため、なかなかオリジナルアルバムとしてカラーを出すのが難しいと思うのだ。でも、きちんとそれをやっているのが凄い。
これは、インスト曲の配置が絶妙で、リアレンジした曲が良い味を出しているからこその尽きると思う。ほんと、初めて聴いたとき、このような形でアルバム全体の構成力を生み出すのか・・・凄っ!ってなったものだった。
きっと振り返ると、一曲一曲はタイアップとかに追われながら、そのときの最適解を生み出したため、そこまで「繋がり」は意識してなかったと思うのだ。
が、曲がひとつのピースとなり、集合体となったときに、こういう「編集力」を見せてアルバムというロマンを形にするのかというところで、改めて常田大希の作家性にぐっときたという話である。
そろそろ今年のベストアルバムを勝手に選んで記事にしようと思っているが、『THE GREATEST UNKNOWN』もまた、2023年を代表するアルバムだよなーと感じる、そんな師走の1日。
関連記事:King Gnuの「硝子窓」が1番ミステリ的な魅力を放っている件
関連記事:King Gnuの「SPECIALZ」が魅せる何とも言えないギラギラ感
関連記事:「[悲報]King Gnuのヒゲ、ステージ上でイキリ散らかす」
スポンサーリンク