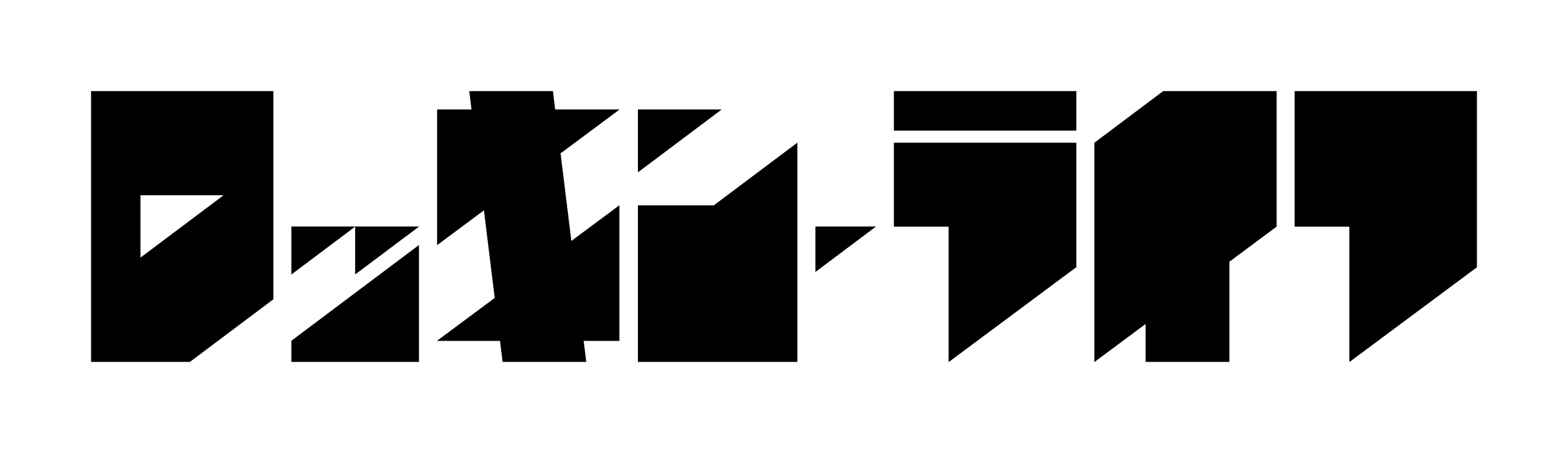聴けるタイプの毒または薬。米津玄師の「月を見ていた」の論考
スポンサーリンク
この曲は、『FINAL FANTASY XVI』のテーマソングとして米津玄師が書き下ろした楽曲である。
それが、リスナーである自分には、どう作用するかがちょっと不安だった。
というのも、ここ最近の米津玄師は「KICK BACK」といい、「M八七」といい、タイアップ先の楽曲とのシンクロ率がえぐくて、きっと「月を見ていた」も同じ性質を持っている作品だと考えたからだ。
なのに、自分は『FINAL FANTASY』は一部シリーズしかやったことがない人間なのだ。
そして、『FINAL FANTASY XVI』に至っては、どういうゲーム性になっており、どういう物語を描いているのかも正直把握していない。
そんな無知な人間が「月を見ていた」を聴いたところで、ちゃんとした形でその歌が刺さるの
かが不透明だったわけだ。
いや、もちろん、米津玄師の歌なので、歌としての完成度が高いことはわかっている。
でも、もしかしたらこれまでの米津玄師の歌よりは、ハマらないままになってしまうかもしれない。
そんな不安を勝手に抱いていたのだった。
でも、実際に「月を見ていた」を聴いて思った。
それは、宝くじを買って、もし一億円当たったらどうしよう・・・みたいな類の愚問だったのだな、と。
米津玄師の歌は当たり前のように、取り込んだ側から身体を駆け巡り、当たり前のように自分の感情をハックしていく。
アルコールを摂取していくと、シラフの自分とは違う感覚に変化していくかのように。
米津玄師の歌は、聴けるタイプの毒または薬となって、自分の身体に作用していく。
どういうことか。
もう少し、具体的に言葉にしてみたい。
なぜ、米津玄師の「月を見ていた」は毒もしくは薬になるのか?
ここからは実際に曲を聴きながら記事を読んでみてほしいのだが、毒もしくは薬の兆候は、楽曲ののっけから始まる。
この歌、秒速で米津玄師のボーカルが入るのだが、冒頭の、
つきぃ・・・
の段階で、米津玄師のイケボがすぎるのだ。
よく野球におけるピッチャーが最初から調子が良いと「肩が温まっている」と表現するが、米津玄師の「月を見ていた」は、つきぃ・・・の段階で喉が温まりまくっているのだ。
そのため、
つきぃ・・・
の低音が生み出す官能的な歌声のパンチ力も凄まじいのだが、その後の、
あかりぃ・・・・
の鼓膜の震わせ方に、うっとりとしてしまうのである。
もし歌声でフェザータッチを行うとしたら、こんな感覚なのかもしれない・・・というような絶妙なボリュームでメロディーを紡ぐことで、瞬時にして歌の世界観が確立していく。
で、Aメロの冒頭はこんな感じでイケボな米津玄師の低音が続くので、Aメロはこのまま包容力のある低音ボイスが続くのかな・・・と少しリスニングのチューニングを変えたタイミングで、
ぁ〜なぁたぁあのぉぉの姿
の部分でふいに少しメロディーが高くなり、良い意味で揺さぶりをかけてくるのだ。
このコントロールの仕方が絶妙で、緩急をつけるというのはこういうことなのかと意識させられる。
ひとつのパターンが慣れてきたなと思ったタイミングで、すぐにそのパターンを崩すことで、楽曲ののめり込み方を劇的なものに変えていく。
しかも。
この歌、わりと意図的にフレーズの終わりは”e”の音で終わるようになっている。
「礫」「ないで」「空へ」「込めて」「だって」「続けたって」・・・と、1番だけでも”e”を伸ばす形で終わるフレーズがいくつも存在している。
かつ、この”e”の音の表情が全部違う。
クールで低音な”e”の音をみせたかと思えば、ちょっと溌剌とした感じの”e”の音をみせたり、ウィスパーの部分を効果的に聴かせるように”e”の音を置きにいったり・・・。
繰り返しの感覚と、どんどん変化を加えているの感覚を、絶妙な混ぜ方をしながらメロディーとして差し出すことで、「月を見ていた」が持つ毒もしくは薬の濃度がどんどん濃くなるのだ。
そして、感情がぐちゃぐちゃになる頃、この歌のメロパートが終わるタイミングで、トドメを突き刺す。
メロのラストのフレーズは「あたなの姿」。
そこから無音・・・
一瞬の間の静寂。
その静寂は瞬間で終わり、サビに入る瞬間で、バーンと歌が炸裂するという流れ。
ここで、歌の盛り上がりが真骨頂になるのだが、関取が平らげるちゃんこ鍋でも、ここまでのぶち込み方はしないぞ・・・というレベルで米津玄師の巧みが「月を見ていた」の特定のパートに凝縮する。
濃縮還元の野菜ジュースですら引くレベルの濃縮具合と言ってもいいかもしれない。
そして、聴き手である自分は、米津玄師のこの巧みにあっという間に感情を揺さぶられ、中毒的に楽曲の魅力に引き摺り込まれていくのだ。
ちなみに、中毒性があるのは米津玄師のボーカルだけではない。
1番のサビ終わり、はじめてボーカルレスになってぐっとサウンドを聴かせるパートになっても、中毒性は継続していく。
というのも、楽器の音のチョイスと展開が素晴らしいのだ。
弦楽器の音が米津玄師のボーカルからメロディーパートを受け継ぐ流れなのも良いし、少し暗さと憂いのある鍵盤の音がコードを弾きつつ、たまに「ちゃららん」と音を鳴らすのも良いし、ベースと打楽器が一瞬姿を消して、なるべく余計な音を加えない流れにしつつ、音の空間の片隅には<存在が気になる音>を忍ばせるバランスも秀逸で・・・。
具体的にどれほどのトラックを使っているのかはわからないが、とにかくここの組み立て方も絶妙だから、確かにこの歌は米津玄師のボーカルがあってこそである一方、この米津玄師のボーカルレスもハイライトになっているという構図がある。
メインのキャラクターも魅力的だし、それだけでも十分成立しているはずなのに、サブだとおもていたキャラクターの方が実は魅力的であることに気づいて、気がついたらそのゲームがただただ沼だったときの感覚に似ているのかもしれない。
そして、これだけ楽曲でさまざまな揺さぶりを受けても、本当の最後の最後で違う角度でトドメを刺しにくる。
というのも、ラストの「きっと」がえぐいのだ。
ここが、今楽曲中最大のイケボとなっている。
瞬間イケボ指数が明確に基準値を超えた瞬間である。
そのため、この歌の魅力から抜け出せなくなった結果、無限ループへと誘われて、またリピートする自分がいる。
スポンサーリンク