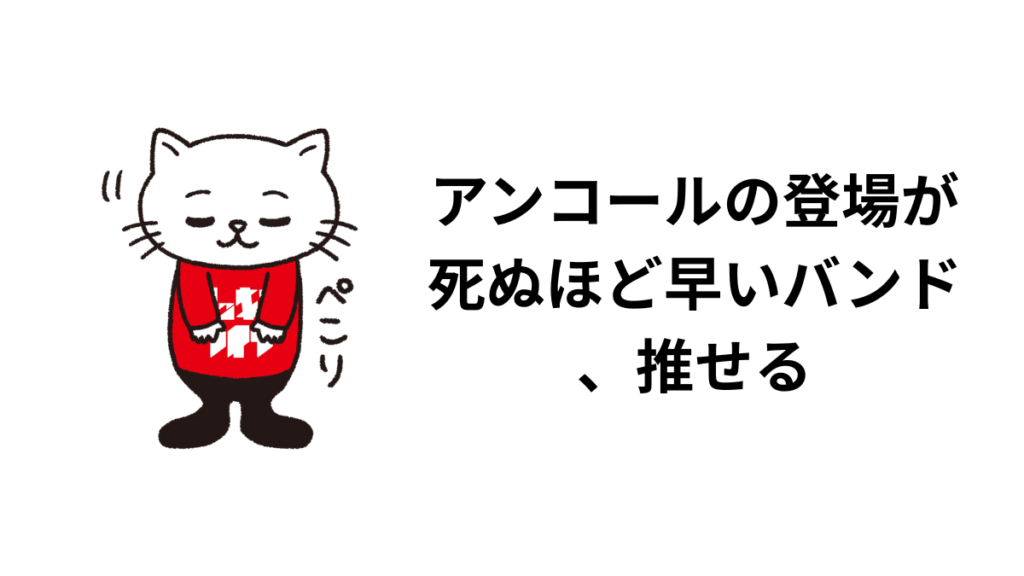インターネットが暴力的になる中で感じる音楽の話
極悪的なノルマに日々身体をズタボロにされる日々。「ギリギリchop」モードの稲葉浩志ですら、ちょっと引くくらいの崖の上行き。ネコバスになったら、もうちょい優雅に旅ができるのだろうか。数値化される業務態度、みるみる値段が上がるコンビニの炭水化物、ちょっと界隈の異なるインターネットを覗き込めば、右も左もウソか本当かもわからないトピックで、みんな殺伐としている。aikoすらも炎上してしまう、そんな身も蓋もない世界線。
世知辛い世の中である。なぜ、世界はこんなふうになったのだろう。仕事は忙しいとしても、それ以外の場所で殺伐の花が咲きすぎている。
思えば、昔はフィクション的であったインターネットも、いつしか現実と近づきすぎてきた。別々の世界で本来生きていたはずの人が、ふいに超至近距離になってしまうからこそ、訪れるコミュニケーションの不和。アスキーアートでワチャワチャしていた古のインターネット民は、子供時代の秘密の隠れ家よろしく、バレない形で好き放題していた。だからこそ、成立していたコミュニケーションもあった。しかし、気がつくと、インターネットは猛烈な距離感で歩幅を詰めるようになり、現実という名の鼻先に、ぐいっと顔を近づけるのだ。
アニメ版の五条先生みたいに。
いや、それにしても、五条、想像以上に顔近けぇな・・・。
まあ、それは置いとくとしても。インターネットの殺伐は厳しい局面を迎えているし、現実の色合いも日々変わっていく。だからこそ、という話ではないのかもしれないが、身の回りにおける音楽の役割も大きくなってくる。
少なくとも、自分にとっては。
現実逃避。聴ける緊急脱出ポッド。認識できるタイプの裏技コマンド。そこまで大げさなものではないにしても、確かに音楽は心のキズぐすりとなり、ささやかに己のHPを増やしてくれる。
でも、どんな音楽でもそういう役割を担えるかといえば、そんなことはない。自分の音楽史を振り返ってみると、そういう役割として、真っ先に頭に浮かぶのはいつも、BUMP OF CHICKENだった。
鼓膜に用意された、柔らかい毛布の類。内面の暗い部分を照らすタイプのサーチライト。暴力とは対局の世界にある、成熟したイノセントの住処。
自分にとって、BUMP OF CHICKENの音楽は、そういう存在だった。
いやね、マジで、BUMP OF CHICKENのフレーズって発明ばかりだと思う。
普通の歌だと透明化されている感情だったり現象だったり、すーっと視点というのカメラをクローズアップする。そして、フレーズの中で反復的・反語的にその視点の際に脚光を当てることで、対象となった何かを受け止めながらも、ムーディ勝山よろしく受け流すのとは違う形で、ポジティブなエネルギーに変換させてみせるのだ。
パワーがないなかやまきんに君的な何か。
ちなみに、そういう意味では、MVで羽生結弦が出演したことで話題になっている米津玄師もやっぱり凄い。
「BOW AND ARROW」で考えても、歌詞の凄さが際立つ。
けっこう難しいワードを平気で使うし、ポップスではあまり出てこないフレーズも盛り込む。けれど、コアとなる根本的な視点はブレない。
芸術的なんだけど普遍的で。
単純ではないんだけど実はシンプルで。
タイアップ元の原作の解像度も高いからこそ、然るべきフレーズを然るべき形で引用するからこその愛。
こういう音楽が、本当の意味で日本のポップシーンのど真ん中で炸裂するのは、希望であり単純にワクワクする。
閑話休題
音楽好き、と一口に言っても、ざっくり分けるとふたつのタイプに分かれるんだろうなーと思う。音楽がキズぐすり的に機能してしまっている人。音楽がコミュニケーションツール的に機能してしまっている人。このふたつ。
別に、どっちが良いとか悪いとかはない。
でも、音楽の価値があまりにも前者寄りな人によって、後者的な楽しみ方は特異なものとして映る。後者寄りの楽しみ方を重視する人にとって、前者的な価値を本質的な意味で理解するのは、けっこう難しいのだと思う。
音楽の現場においてちょっと難しいと思うのは、アーティストが明確に人気になっていく中で、前者と後者のタイプの母数に大きな変動が生まれる、ということだ。
だから、界隈で人気だったバンドがパブリックな人気を勝ち取ったとき、オーディエンスには独特の混乱が生まれる。よほど慎重な売れ方でもしない限りは。
それは、そのアーティストに求めることがあまりにも変容したり、多極化するから。
バンドなんだからアイドル的に見るな!という声もあれば、アイドル的に見ることができるからこそ生きがいを作れる人もいる。そういう事態が往々にして生まれるのも、上記のようなカオスが変容した結果のひとつだと思う。
何度も言う。
それは、別に善悪がつくような話ではない。
でも、どういう変化においても、確かに自分にとって望ましいか、望ましくないかの軸はあると思う。
売れたからそのバンドが嫌いになる、ということはない。でも売れたことで、そのバンドの社会的な役割が変わった結果、自分がそのバンドに求めていた予想そが小さくなる、だから別にそのバンドが自分の生活から離脱していく、というケースはある、と思う。
スターバックスやUSJですら、そういう変化の中でブランドの価値を右往左往させているのだ。そりゃあ”生きている”アーティストだったら、その変化なんて、もっとダイナミックで、劇的で、難しい話なのだと思う。
別に、答えのある話がしたいのでない。
だだ、日々、インターネットの色んなトピックが沸き起こり、それを素知らぬ顔で素通りしていく中で、色んな思うところが出ていて。かっといって強いワードで殴るのも違うなーとなっていく中で、なんとなく感じた思いをアレしてアレしたという、そういう話。
ぶりっ。