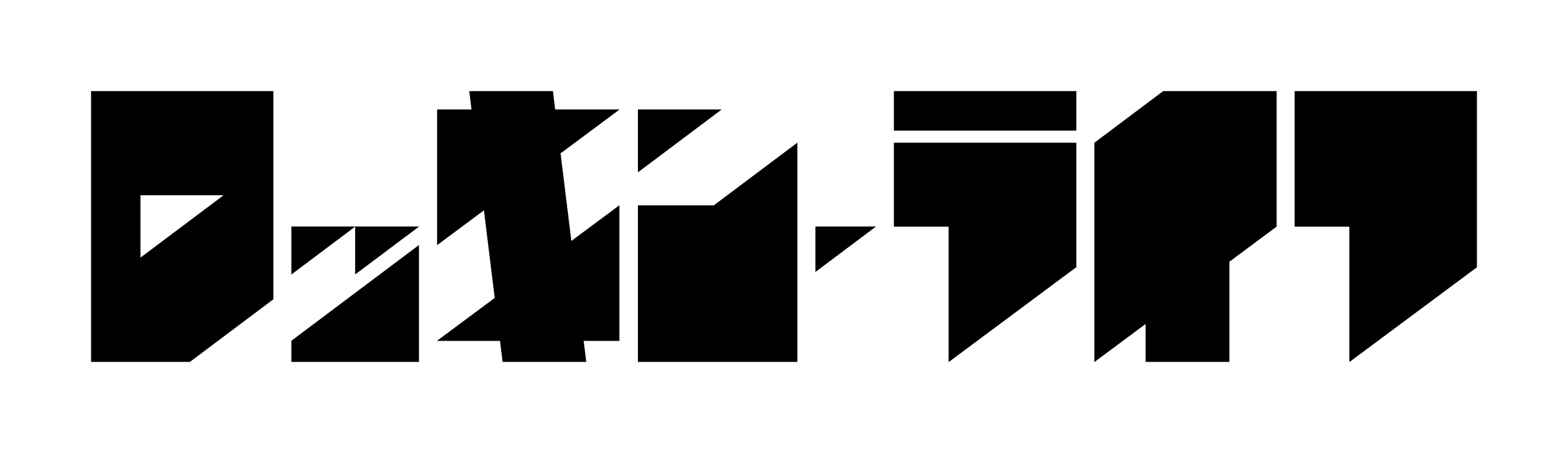前説
スポンサーリンク
ジャンルレスで予測不能なサウンドと表現力で唯一無二の存在感を放ち続けるロックバンド・RADWIMPS。
その自由奔放な音楽は今や国内に留まらずワールドワイドなポピュラリティーを獲得し、多くのリスナーを魅了してやまない。そしてこれ程までに彼等の音楽が支持を集める要因の1つとしてフロントマンである野田洋次郎が紡ぐ“歌詞世界”の存在は看過する事ができない。
2005年にメジャーデビューを果たしてからの15年間、ソングライターである野田洋次郎は一貫して「自分とは一体何者なのか」「一体何の為に生きているのか」という自らのレゾンデートルを音楽を通して探究し続けてきたように僕には思える。
“レゾンデートル”とはフランス語で“存在理由”や“存在価値”という意。しかしそれは周囲が認める存在価値ではなく、自分自身が求める存在価値の事を定義する。
自らのレゾンデートルの模索。これは野田洋次郎に限った事ではなく古今東西、この世界に生きる誰もが抱えている内的葛藤だったりもする訳だ。そんな我々人間にとって極めて根源的で本質的な問いと野田洋次郎はどのように向き合い、そして彼自身のレゾンデートルはどのように変化して来たのだろうか。本稿では野田洋次郎が描く〈僕〉のレゾンデートルという視座からRADWIMPSというロックバンドを論究していく。
本編
“地上で唯一出会える神様”の得喪(2005年〜2006年)
RADWIMPSの初期の作品において野田洋次郎の歌詞にフォーカスすると語り手である〈僕〉は〈君〉という存在をこの世界の絶対的な指標とし、そこに異常なまでの依存を見せている。
通算3枚目のアルバム『RADWIMPS 3〜無人島に持っていき忘れた一枚〜』に収録された彼等のメジャーデビュー曲である「25コ目の染色体」では《あなたが死ぬそのまさに一日前に僕の息を止めてください / これが一生のお願い》と〈君〉が存在しない世界からの逃避を示唆し、サビでは《I will die for you,and I will live for you》とまで歌ってみせる。
こうした野田の“恋人至上主義”とも言える独自の死生観と恋愛観はRADWIMPSがインディーズ時代に発表した2枚のアルバム『RADWIMPS』『RADWIMPS 2〜発展途上〜』から連綿と歌われ続けてきた。
《枯れ果てる世界なんて見たくない / 僕の心は君のもとへ》(自暴自棄自己中心的(思春期)自己依存症の少年)
《あなたがいるから僕は生きられる / あなたがいなけりゃ僕は…死んでるよ》(心臓)
《君と出会うまでの記憶など僕のモノじゃなくていい》(そりゃ君が好きだから)
野田洋次郎が音楽に発露してきた自らのレゾンデートルの所在は常に〈君〉という存在に帰結する程、野田にとって〈君〉とは絶対的であり、この世界で生きる理由の全てだったのだ。
3rdアルバムと同じ年にリリースされた通算4枚目のアルバム『RADWIMPS 4〜おかずのごはん〜』は野田洋次郎が標榜する“恋人至上主義”の最たる物と言えるが、これまでの作品と決定的に異なるのはそこに青天の霹靂と言うべき〈君〉の喪失が内在する点であろう。
野田洋次郎が高校時代から連れ添った恋人との破局(後に復縁)。“今世紀最大の突然変異”であり“地上で唯一出会える神様”であった〈君〉を失った〈僕〉は同時に自らのレゾンデートルの所在も失い、孤独の深淵で内観を極めていく。
失恋から間も無く歌録りがされた「有心論」では《この心臓に君がいるんだよ / 全身に向け脈を打つんだよ》と極めてメタフィジカルな自己暗示をし、「me me she」では《僕の好きな君 その君が好きな僕 / そうやっていつしか僕は僕を大切に思えたよ》と独り善がりな女々しさに悶える。
自らの肉体を以ってしてリアルに〈君〉の不在を味わってしまった〈僕〉だからこそ、そのレゾンデートルは混迷を極めていき「ギミギミック」では何億分の一という確率から生まれた自らの命を《当たりだったのかな 外れだったのかな》と天秤に掛け、「セツナレンサ」では《楽しくないのに僕たちは / 心に黙って笑えるから》と〈君〉以外の他の誰かとの共通性を“僕たち”という主語で提示して見せた。
こうしたある種の普遍性は「有心論」と同時期に作詞がされた「バグッバイ」にも発露し《近すぎて見えない誰か誤って「僕」と呼ぶ / この声の正体は誰なの?》という自己認識の問いへと繋がっていく。これも〈君〉を失った〈僕〉だからこそ成し得たレゾンデートルの模索だったように思える。
先述したように『RADWIMPS 4〜おかずのごはん〜』というアルバムはインディーズ時代の作品も含めた3枚のアルバムの底流にあった〈僕〉と〈君〉の濃密な愛だけで構築された世界という“恋人至上主義“が、時点的に〈君〉の喪失に直面した事でより揺るぎ無いものとして確立された作品であった。そして同時に〈僕〉にとってレゾンデートルそのものであった〈君〉の得喪は野田洋次郎により普遍的な自己認識を問うきっかけを齎し、アルバムの最後に置かれた「バグッバイ」の中でそれは1つの証明を終えたのだった。
“オーダーメイド”であるが故の揺蕩い(2007年〜2009年)
4thアルバム『RADWIMPS 4〜おかずのごはん〜』のリリースから2年3ヶ月という沈黙を経て、RADWIMPSは通算5枚目のアルバム『アルトコロニーの定理』をリリース。『アルトコロニーの定理』は「RADWIMPS+数字〜副題〜」というフォーマットから逸脱した事からも分かるように、これまでのアルバムと凡ゆる面で一線を画した金字塔的と呼ぶべき作品となった。
4thアルバムの中で〈君〉という絶対的な指標を失ってしまったが故に「バグッバイ」で初めて〈君〉を媒介しない自己認識を試みた〈僕〉は「オーダーメイド」という1曲で自分自身を俯瞰する視座を遥かに高め、生まれる前に出会った創造主である“誰か”との対話というプロットに辿り着いた。
生まれる前に“誰か”に欲しいものを尋ねられた〈僕〉はそれを享受しながら、時に謝絶しながら自分自身を着実に創造(オーダーメイド)していく。だが《きっと僕は尋ねられたんだろう 生まれる前 どこかの誰かに》と言うように、この物語が“きっと”で始まる以上「オーダーメイド」はフィクションの域を出ない壮大な自己覚知でしかない訳だ。
ではそんなレゾンデートルを自らの身体の成り立ちという超根源的な部分から精査し「オーダーメイド」という肯定的なレゾンデートルを獲得した意義は5thアルバム『アルトコロニーの定理』の中でどう作用していったのだろうか。
くどい様だが4thアルバム『RADWIMPS 4〜おかずのごはん〜』までに根差した“恋人至上主義”とは〈君〉を絶対的な存在である“神”とし、その存在を揺るぎのない定点とする事であった。肉眼で確認できるフィジカルな〈君〉を定点としたからこそ〈僕〉のレゾンデートルは〈君〉の得喪によって容易く揺蕩し、明滅し、混迷を極めていた。
だが5thアルバム『アルトコロニーの定理』の随所で見られるのは自身の立脚点をしっかりと定めて、その上で〈君〉と世界に向けて言葉を費やす〈僕〉の姿である。
《今に泣き出しそうなその声が 世界にかき消されてしまったら / 僕がマイクを持って向かうから 君はそこにいてくれていいんだよ》(One man live)
《外からずっと見てた僕の話を聞いてよ / 一番近くにいた僕が見てた 君は それは 君は》(謎謎)
《I’ll be you’re umbrella》(雨音子)
先述したような『アルトコロニーの定理』に於いての「オーダーメイド」の功績はこれに尽きるのではないだろうか。要するに自己覚知の末に〈僕〉自身の存在を“オーダーメイド”と歌えた自負が1つの確かな足掛かりとなり、アルバムの中で〈君〉の為に作用しているのだ。
そして看過してはならないのはこれまで〈僕〉と〈君〉以外のアウトサイダーの介入を決して許さなかった野田洋次郎の歌詞世界は『アルトコロニーの定理』を境にその射程距離を良くも悪くも拡張していき不特定多数が生きるこの〈世界〉を捉え始めた事である。
《そうさ僕ら人類が神様に気付いたらなってたの何様なのさ》(おしゃかしゃま)
1stアルバムから4thアルバムまでの〈君〉を“神様”とするフェーズを終えた〈僕〉は普遍性を持って世界を捉え始めたからこそ“神様”とは〈僕〉にとっての〈君〉ではなく〈世界〉が共通的概念とする“神様”に変化していった。「おしゃかしゃま」というタイトルが実にシンボリックだが、お釈迦様を幼児語で表記するという痛烈な皮肉が『RADWIMPS 4〜おかずのごはん〜』までの神様像との違いを如実に物語っている。
《枯れた言葉なら もう言わないでいいよ》(タユタ)
《このなんとでも言える世界がいやだ》(37458)
アルバム『アルトコロニーの定理』は「タユタ」で静かに幕を開けて「37458」で静かにその幕を閉じる。アルバム制作の序盤にクリエイトされたこの2曲では共通して言葉を紡いで生きる事に対する否定的な感情が吐露されているが、結果的にこのアルバムは〈僕〉が〈君〉や〈世界〉を定点観測して言葉を費やす作品になった。
それは決して「タユタ」や「37458」に対する否定ではなく、寧ろアンチノミーとして当たり前に共存する物のように思える。言葉を紡ぐことを否定する為に、言葉を紡いでしまうこと。自らの命をオーダーメイドとしながら、その命を誰にも裁かれずに殺められるということ。それを選択する気持ちを理解できてしまうからこそ、真っ向からそれを否定するということ。
そんな事を日常の中で何の気なしに繰り返す〈僕〉と目の前の〈世界〉の姿をそのまま野田は肯定も否定もすることなく『アルトコロニーの定理』というアルバムに刻印したかったのではないだろうか。
“絶体絶命”の中にある救済(2010年〜2011年)
5thアルバム『アルトコロニーの定理』から2年ぶりにリリースされたRADWIMPSにとって通算6枚目のアルバム『絶体絶命』はロックバンドがロックバンドである事を極限まで突き詰めた作品であったと同時に、野田洋次郎というたった1人の人間が描く死生観が余す事なくドラスティックに表現された作品であった。
4thアルバム『RADWIMPS 4〜おかずのごはん〜』で自らのレゾンデートルであった〈君〉の得喪を体得した〈僕〉は不特定多数が生きる〈世界〉にその射程を拡げ、5thアルバム『アルトコロニーの定理』というその〈世界〉を生きるための定理を築き上げた。そして『絶体絶命』は更にその先で〈世界〉と対峙する作品に仕上がっている。
前作『アルトコロニーの定理』との明確な違いを挙げるなら『絶体絶命』の〈僕〉は1人っきりだということ。当時のインタビューで野田が「自分と世界だけの会話でしかなかった」と語っている程にこのアルバムは〈僕〉が1人っきりの状態で〈世界〉と対峙し、そこで吐き出された膨大な言葉は〈君〉というフィルターを通すことなくダイレクトに〈世界〉を如実に捉えているのだ。こうして〈僕〉が1人っきりで〈世界〉と対峙して顕現したのは“絶対に命は絶える”というたった1つの厳然たる事実であった。
全人類に与えられた唯一にして最大の共通事項である“死”を果たしてどれだけの人間が日常的に自覚して能動的に生きているのだろうか。
それを自覚する、自覚させる為にも『絶体絶命』では日常的に生きる事を選択しながら常にそこに連関する筈の“死”に目を背ける世間の空気感を強制的にリセットする必要があった。
《生まれた時すなわちそれが入り口 あとは誰しもが死ぬ時が出口》(DADA)だと有限である“生”の終わりを提示し、それを誰もが拒絶するからこそ《どれだけ後ろ向きに歩いてみても未来に向かってってしまうんだ 希望を持たされてしまうんだ》(グラウンドゼロ)と希望をチラつかせるが《明日に希望を持ったものだけに絶望はあるんだ》(億万笑者)と瞬時に絶望にすり替え、挙げ句の果てには《僕が嬉しい時も 気持ちいい時も》(狭心症)同じ時間に顔も名前も知らない何処かの誰かは泣いて、慟哭して、発狂して、殺されているという圧倒的な鉄壁の論理で構築された間然する所もないこの“生”のプロセスこそが〈世界〉の様相なのだと野田洋次郎は歌っている。
野田にとって“生”とはそれだけ必死で、タイトルの通り絶体絶命な行為だったのだ。ただ〈僕〉はそんな〈世界〉の全てに絶望している訳ではない。何故なら〈世界〉の果てを感知する事が出来るからこそ〈僕〉のレゾンデートルはそこと直結していたからである。
自他共に認める寂しがり屋の〈僕〉は1人ぼっちにならないよう、常にこの〈世界〉に居場所を探し続けた。その最たる場所が愛する〈君〉という存在だったわけだが、その〈君〉を失ってから初めて1人ぼっちの状態で不特定多数が共存するこの〈世界〉と対峙した時に〈僕〉は「だいだらぼっち」で《一人ぼっちは寂しいけれど みんな一人ぼっちなら / 寂しくなんかない 一人ぼっちなんかじゃないから》という1つの理論に逢着した。
《「ところで君は じゃあどんな人?」と尋ねられて気付いたよ / 一人だけじゃ 誰かがいなきゃ 僕が誰かも分からない 僕は生きてさえいないじゃないか》(だいだらぼっち)
《そして君で 君の手で ねぇそうだよ僕は僕の形が分かったよ 僕は僕と はじめて出会えたの》(ものもらい)
《今日もどこかの誰かのポッケの中に僕の居場所が あるんだろう》(携帯電話)
《そのすべてが 今ここに僕が存在したことの証だから》(やどかり)
《君がいなくなったら きっと僕も消える / だって僕は君の中にしか生きれないから》(救世主)
これまで自らのレゾンデートルを何かに託けて徹底的に模索してきた〈僕〉は、実はその存在を証明するのが〈僕〉自身ではなく〈僕〉と相対する周りの人間、そして1人ぼっちの集合体である〈世界〉そのものであり、それこそが掛け替えのない救済だと気付いたのである。
かつて何とでも言えるこの世界で何とも言えない想いに支配されていた当事者だからこそ、野田洋次郎は『絶体絶命』というアルバムの中で《この何とも言えない想い》の正体を圧倒的な論理の形成と破綻で突き詰めた。
その正体とは全人類に共通する“生”を徹底的に肯定し、“死”を徹底的に否定する為に敢えて「生きること」こそが「絶体絶命」なのだと浮き彫りにすることであり、それこそが野田にとって平和ボケした幸せなこの国に対する痛烈なアンチテーゼだったのだ。
だがそんな野田の目論見はアルバム『絶体絶命』のリリースからわずか2日後……2011年の3月11日。人知を遥かに超える力でこの国と人々を覆い尽くしてしまったのである。
奇禍が齎した世界への諦観と再定義(2012年〜2013年)
野田洋次郎が5thアルバム『アルトコロニーの定理』と6thアルバム『絶体絶命』という2枚のアルバムを通して不特定多数が存在するこの〈世界〉の様相と“生”と“死”の絶望を犀利な切り口で露見させた真意は自分も含めた平和ボケしたこの国の人々を“生”に対して自覚的にさせる事にあった。
だが野田がそれを腰を下ろして希望的観測する間もなくリリースの2日後に発生した東日本大震災は誰もが“生”を自覚するという野田が理想としていた〈世界〉を数万という命の犠牲と引き換えにこの国に顕現させてしまった。
しかしそれ以上に絶望だったのはあれ程の天変地異を経ても世の中が不条理な仕組みを変える事なく震災前に戻ろうとしている引力そのものであった。RADWIMPSにとって通算7枚目のアルバム『×と○と罪と』はそんな〈世界〉に対する諦観とそれだけでは留まらない気概が同居した作品となったのだ。
6thアルバム『絶体絶命』で〈世界〉を形成するのが不特定多数の1人ぼっちで、そんな他者からの認識こそが自らのレゾンデートルに繋がるのだと気付いた〈僕〉は《君がいなくなったら きっと僕も消える / だって僕は君の中にしか生きれないから》(救世主)という絶体絶命の中の救済に辿り着いた。
だが『×と○と罪と』は《言えない 言えないよ / 今君が死んでしまっても構わないと思っていることを》(いえない)という衝撃的な言葉で幕を開ける。
〈僕〉を〈僕〉たらしめる存在の否定は〈僕〉自身のレゾンデートルの所在を自ら放棄する事であり、同時にそれは〈世界〉に対する否定とそこからの意識的な逃避であった。
こうした〈世界〉に対する否定は他の楽曲にも表れる。遥か遠い場所から神様と仏様が人類の生き様を実況する「実況中継」では《今回も失敗作ってことで一段落 だって仕方がない 致し方がない 直し方がない 話したくもない》と神々によって人類は断罪され、「最後の晩餐」では《この世の寿命がどうとかより とっくに終わってるってさ》と〈世界〉の寿命がとうの昔に尽きていると歌われる。
それ程までに震災によって浮き彫りになってしまった欺瞞と不条理に塗れた〈世界〉の様相は〈僕〉にとって否定的な存在だったのである。
そんな現実世界に対する〈僕〉の猛烈な否定感は自然とその活路を〈世界〉の再定義へとシフトさせた。
〈世界〉に対する諦念と絶望が飽和しても尚〈僕〉はこの〈世界〉で絶体絶命である“生”を選択することを諦めなかったのだ。
《飛ばされて 降り立った国に / 今なら過不足なく 愛を説けるでしょう》(ブレス)
7thアルバム『×と○と罪と』はこれまでのアルバムと比較してもトップクラスに絶望の数値が高いのにも関わらず、これ程までに開けた作風になったのは、野田洋次郎の意識が《僕だけが知る正解に丸をつけてる》(最後の晩餐)という自分だけの×と○を付けて新しい世界を創造する享楽と《明後日からの新しい世界に間に合うように この世のすべてを書き遺すよ》(アイアンバイブル)《Welcome to the new world》(Tummy)という次の世代の未来に向けられているからに違いない。
自己肯定の“光”(2014年〜2016年)
7thアルバム『×と○と罪と』から3年ぶりにリリースされたRADWIMPSにとって通算8枚目のアルバム『人間開花』はサウンドスケープにしても歌詞世界にしても過去最高に開けた作品となった。
特筆すべきは長らく遠ざかっていたナチュラルなラブソングがアルバムのド真ん中で肯定的に歌われてることである。
《僕たちは光った / 意味なんてなくたって》(光)
4thアルバム『RADWIMPS 4〜おかずのごはん〜』までに確立された〈僕〉と〈君〉だけの世界という構図は〈君〉を失った事で不特定多数の人間を有する普遍的な〈世界〉を捉え始め、それ故に5th『アルトコロニーの定理』と6thアルバム『絶体絶命』ではより視座を高めて〈世界〉を俯瞰するようになった。
あの時期もラブソングはあったが、それはたった1人の〈君〉に向けてのものではない。広義では生きとし生ける生命に向けたラブソングであった。
だが『人間開花』の中で歌われる〈君〉は奇跡だけが起きる街で出逢って恋をしたたった1人の〈君〉なのである。
野田洋次郎がこうした恋愛的な〈君〉の揺り戻しに成功した背景にRADWIMPSが2016年に公開された新海誠監督の長編アニメーション映画『君の名は。』の劇伴制作があった事は言うまでもない。
そして何よりも他者との交わりを意図的に遮断してきたRADWIMPSのようなバンドがアニメーション映画という異文化とのクロスオーバーを果たす事が出来たのは7thアルバム『×と○と罪と』で皮肉にも既存の〈世界〉に対するピリオドを打っていたからである。
アルバム『×と○と罪と』で世界の精査を突き詰めたが故の“無敵感”を提げて、バンドは新たなことに着手するマインドを築くことができたのだ。
このように野田洋次郎は映画『君の名は。』というフィクションの〈世界〉を通してナチュラルな〈君〉に対するラブソングを歌う感覚を取り戻したがそれは決して“恋人至上主義”への回帰ではない。
《これだったか僕がこの世に生まれた意味は / これだったか僕がこの世に生まれたわけは》(O&O)
3thアルバム『RADWIMPS 3〜無人島に持っていき忘れた一枚〜』から滔々と述べられてきた野田の死生観はその根幹を変えずに「生きること」への純然たる肯定というピースを手にした事で全く真新しいレゾンデートルを獲得した。
《そんな世界を二人で 一生 いや、何章でも 生き抜いていこう》(スパークル)
それは人間である自分を最大限に肯定し〈君〉と横一線でこの〈世界〉をどう生き抜いていくのかを一緒に模索しようとする〈僕〉の能動的な“生”である。
“大丈夫”というレゾンデートルの結実(2017年〜)
RADWIMPSは8thアルバム『人間開花』から2年ぶりに通算9枚目のアルバム『ANTI ANTI GENERATION』、そして翌年には新海誠監督との再タッグとなった2作目のサウンドトラックアルバム『天気の子』をリリースした。
アルバム『人間開花』のフェーズで獲得した〈僕〉と〈君〉が横一線になって一緒に〈世界〉での生き方を模索していこうとする能動的な姿勢は『ANTI ANTI GENERATION』というアルバムで更に頑強なものとなり、それはたった1人の〈君〉だけでなく大胆にも同じ時代に生きる全ての人々にも向けられた。
その根幹を成すのが大震災を経ても変わらなかった不条理な世界に対して野田が抱いた猛烈な不満や苛立ちである事は想像に難くない。
《世に溢れるは成功者達の言葉 いつだって敗北者にマイクは向けられない》(NEVER EVER ENDER)
《成功者の参考書 端から端まで読破して》(IKIJIBIKI)
支配する側の人間に圧倒的に打ち拉がれた〈僕〉はこのアルバムでも変わらず世の中の不条理を憂い、同時にそこに留まらず《僕だけの正解をいざ 探しにゆくんだ》(正解)という『×と○と罪と』にも共通する気概を持ち合わせている。
新しい世界の精査を〈僕〉だけで行っていた『×と○と罪と』から不特定多数を含む〈僕たち〉で行おうとする『ANTI ANTI GENERATION』ーーこの人間に対して開かれたマインドこそが『人間開花』が齎した最大の功績だったのだろう。
アルバム『ANTI ANTI GENERATION』が訴求する“自分だけの正解”を見つける姿勢というのは、RADWIMPSが劇伴を務めた新海誠監督の長編アニメーション映画『天気の子』のメッセージ性と共通する。何故なら映画『天気の子』は雨が降り止まない東京の街で期せずして世界の運命を背負った主人公の帆高とヒロインの陽菜の“選択”を描いた物語だからだ。
そんな映画のプロットと、野田洋次郎が執拗に描き続けた〈僕〉と〈君〉が隣り合わせで〈世界〉と対峙する構図がシンクロニシティを見せたが故に、映画の為に書き下ろされた「愛にできることはまだあるかい」や「大丈夫」で歌われる〈君〉への想いはフィクションの〈世界〉を奔走する帆高の代弁に留まる事はない。これまで野田洋次郎が描いてきた死生観、恋愛観の上で構築される真理であり希求なのである。
何故、人間は自らのレゾンデートルを世界の中で模索してしまうのか。
それは「生きる」という選択がそれだけ人間にとって絶体絶命な行為だからである。
この世界の誰もが“死”という共通事項を持って産み堕とされ、その中でそれぞれが生半可な希望を持たされては絶望し、大切な物が増えては失う恐怖に打ち震えている。いつか必ず来る終わりに向かって命を運び続けている。だからそれだけ絶望的である“生”に見合うだけの価値と理由をこの世界の中で探してしまうのだ。
《君を大丈夫にしたいんじゃない / 君にとっての「大丈夫」になりたい》(大丈夫)
野田洋次郎の描く〈僕〉にとって目の前にいる〈君〉の存在こそが自らのレゾンデートルそのものであった。そこを起点として〈僕〉と〈君〉の関係は15年という時間の中で大きく紆余曲折し、それに伴って〈僕〉のレゾンデートルも所在の混迷を極め続けた。
野田洋次郎は知っている。この絶体絶命な日々が自分の存在を認めてくれる人と居るだけで「大丈夫」と思えてしまう安心感とそこで得られる“生”への肯定を。
だからこそ〈君〉が世界の中で苦悩し、絶望し、慨嘆し、慟哭している時に今度は他の誰でもない自分自身の存在がこの人の中での「大丈夫」と同義であって欲しいと願うのだ。この混沌とした世界の中で〈君〉という存在が常に自分の中でそうであったように。
《僕は今日から君の「大丈夫」だから》
こうして野田洋次郎が追い続けた自分自身のレゾンデートルは大切な〈君〉の中で結実したのである。
筆者紹介
山田くん(@AOTOXXX_05410)
Twitterやブログ『夢番地日記』を中心に音楽についての感想を発信してます。
スポンサーリンク