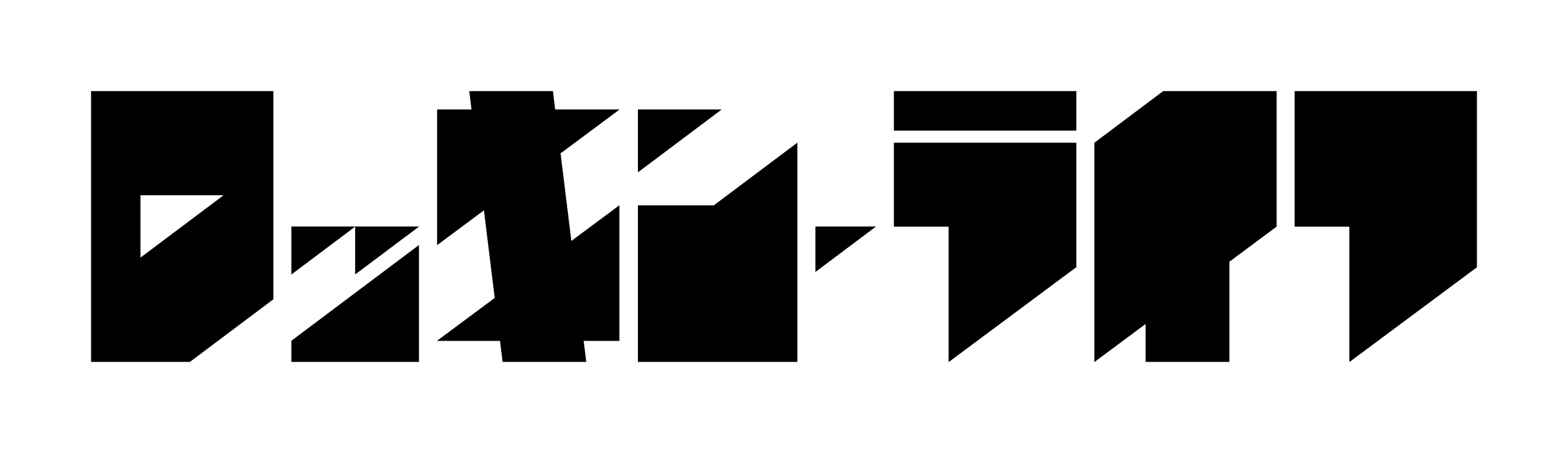クリープハイプのこれまでの楽曲について
スポンサーリンク
2010年代の前半くらいから大型のロックフェスに出演する頻度が増えてきたバンド、いくつかいたよなーと振り返る。
この時期あたりからどんどん大きくなっていたバンドでいえば、サカナクションだったり、KANA-BOONだったりの勢いが記憶が残っている。
あるいは、KEYTALKやthe telephonesがロックを軸にしながら「ダンス的な要素」を音楽に入れ込むことで、多数のお客さんを盛り上げていたことも記憶に残っている。
04 Limited Sazabys然り、BLUE ENCOUNT然り、THE ORAL CIGARETTES然り、それぞれのバンドの作風やルーツとなる音楽には大きな違いがある一方で、フェスといった場でパフォーマンスすると、お客さんが似たような反応をして盛り上がっていく空気があったなーということも記憶に残っている。
ボカロもアイドルソングも、あの頃はとにかく速い歌が多かったし、それがひとつの流行になっていたなーという記憶も起こっている。
ただ、シーンにおいて盛り上げるの「型」がどんどん決まってきたからこそ、その「型」から意図的に離れていくバンドも出てきた。
バンドによってはまったく違うジャンルの音楽をプレイして作品の幅を広げるようになり、バンドによってはより狭く深く自分たちのやりたい音楽を磨くようになった印象を受ける。
なので、前述したバンドの多くも、当時と今では異なるテイストの楽曲を生み出していたりする。
いずれにしても、2010年代のバンドシーンには確かに当時特有の「流行」や「型」や「空気感」というものが存在していた。
もちろん、その流行とはまったく異なる地点で音楽を生み出していたバンドもたくさんいるんだけど、そうなると、畑違いという扱いになるような空気があったのだった。
でも、畑違いという扱いにもならず、かといって当時の流行にも特にコミットしている空気感がなかったバンドというのも、いくつかいたことを記憶している。
自分の中で、それがクリープハイプだった。
というのも、クリープハイプって、ずっと染まらない立ち位置でいた印象を受ける。
ロックフェスが、ある種の運動会してきており、モッシュをしたくなるようなビートメイクやスピード感で楽曲を紡ぐバンドが意図的であれ無意識であれ増えてきた状態でも、クリープハイプは、そういうフェスに出演しつつも、そういう歌をリリースした記憶がないのだ。
00年代のクリープハイプの代表曲のひとつとして、「ラブホテル」という歌がある。
この歌、サビでこそドラムのビートが少しハネているが、ビートにのせて楽しませるというよりは、どちらかというと歌の世界にじっとり入り込みたくなるような空気を持っている。
「社会の窓」しかり「寝癖」しかり「百八円の恋」しかり、どの歌もサウンドのテイストやアレンジの方向性はそれぞれの違いがあるけれど、ダンス的なアプローチでリズムにのせて盛り上げる、という視点とは違う観点でビートを紡いでいるという意味で、当時の空気感とは違った輝きを持った楽曲である。
バンドの代表曲であり、ライブの定番曲でもある「HE IS MINE」でも、それは変わらない。
聴き手のリズム的な心地よさにコミットするのではなく、もっと違った部分でコミットする、そんな不思議な楽曲だ。
こうやってクリープハイプの歌を聞き直すと、良い意味でシーンからは独立していた歌の響きを持っている。
2010年代後半でも、尾崎世界観の楽曲が持つ独特の立ち位置の楽曲の”独特さ”は変わることはない。
ただし、めっちゃマニアックなところを走っているわけではなくて、かといって流行にはシンクロしてこない、不思議な距離感で居続けている印象を持つ。
特に「イト」はそんな尾崎世界観が持つ秀逸さが、色んな形で組み合わさった楽曲であるように思うし、今聞いても、この楽曲が生み出す展開は刺激に満ちているように思う。
スポンサーリンク
気がついたら、クリープハイプの今のルーツの源流にいる感
やがてロックフェスの空気も変わるし、”流行り”が生み出すバンドの楽曲のテイストも変わってきた印象を受ける。
近年は、TikTokをはじめとするショート動画ブームが影響することもあって、センセーショナルでインパクトのあるフレーズが話題になったり、弾き語り一本で披露できるような”歌”と”言葉”の強い歌が存在感を魅せる機会が増えてきた。
バンドにおいても、リズムのフックそのもので魅せるというよりも、もっと歌を軸にして、楽曲をしっかり聴かせる傾向が増えてきた印象。
そんな中で、若い世代がハマる歌の傾向として、特定の感情にくらわせる”エモい歌”が話題になる機会が増えてきた。
あえてここでは具体的な歌を挙げることはしないが、流行という括りでバンドの音楽を考え直してみたとき、その流行に入るタイプの音楽が変わったことは確かだと思うのだ。
で、ある特定の方向でその流行という枠組みを作ったとき、どうにもあの頃のクリープハイプの空気感とシンクロする楽曲を散見する機会が増えてきた。
実際にクリープハイプに影響を受けているのか、たまたまクリープハイプの楽曲と通ずる何かを生み出しているのかはわからないが、どうにも自分が聴く分にはクリープハイプと似た何かを持っている楽曲を散見する機会が増えたのだ。
あの頃は間違いなく”流行”とは異なっていたクリープハイプ的なエッセンスが、いつしかバンドシーンのある種の”流行”とシンクロしている印象を受けたわけだ。
10年代と20年代の今では、世の中のツールも変わっているし、音楽の聞き方も変わってしまったし、ライブの空気も大きく変わっているはず。
なのに、クリープハイプのあの頃の音楽がいつしかある種のルーツになるように、今のバンドシーンにも影響を与えているように、感じてならないのである。
きっとクリープハイプ側からしてみれば、つどつど感じていることが歌の土台になっているのだから、いちいちシーンとか流行とかと比べて語ることはナンセンスだとは思う。
のだが、自分的にはそう感じずにはいられない部分があるのだった。
しかも、今なお、クリープハイプの楽曲が、あの頃と変わらない刺さり方で、「当時の若い世代」だけでなく、「今の若い世代」にも刺さっている印象を受ける。
どんなバンドだって年をとるし、年をとれば自ずと若い人からすると、そのバンドの言葉って響かなくなるものである。
だからこそ、新しいバンドの似たような言葉こそが若い人たちに「刺さる」という状況も生まれるのだが、クリープハイプの場合、そういうことにもならなくて、そういう点からみても独特だなーと思う。
もちろん、これは、あくまでも自分の観測範囲ではあるのだが・・・。
ただ、クリープハイプの音楽が変わらずに色んな世代に届いているのは確かだと思うし、その届き方をみていても、クリープハイプの音楽の偉大さを感じる瞬間は多い。
でも、次のステップを進んでいる印象のクリープハイプの音楽
ただ、仮にクリープハイプが持っていたテイストの一部が、今のバンドシーンの流行とシンクロしているとしても、その頃にはクリープハイプは流行がどうのこうのとは関係なく進んでいる印象を受ける。
特に近年の楽曲は、バンドとしては違うフェーズに向かっている印象の作品が多い。
今年でいえば、「青梅」。
この歌は、バンドのサウンドの音づかいが面白いし、ベースとドラムのリズムの組み方も面白い。
ボーかレスな部分とボーカルの部分の接続の仕方にも面白みを覚えるし、尾崎世界観の音楽の引き出しがいかに豊かであるかを感じさせる一曲になっている。
また、「本当なんてぶっ飛ばしてよ」なんかでもそうなのだが、バンドがもっと自由に音を鳴らし、枠にはまらないリズムの中で音を紡いでいる印象を受ける楽曲が多い。
バンドメンバーがどういう着想を持っていたり、何を参照元にしながらそれぞれの音を鳴らしているのかはわからないが、聴いている分には、これまで生み出してきた歌とはまた違った枠組みの中で、アレンジの組み立てている楽曲が増えている印象なのである。
まとめに替えて
独特の立ち位置で楽曲を生み出したクリープハイプだからこそ、面白い形で今でもたくさんのリスナーに刺さっているのだろうなーと思うし、尾崎世界観のソングライティングの素晴らしさを改めて実感している自分もいる。
そんな結論の、そんなお話。
スポンサーリンク