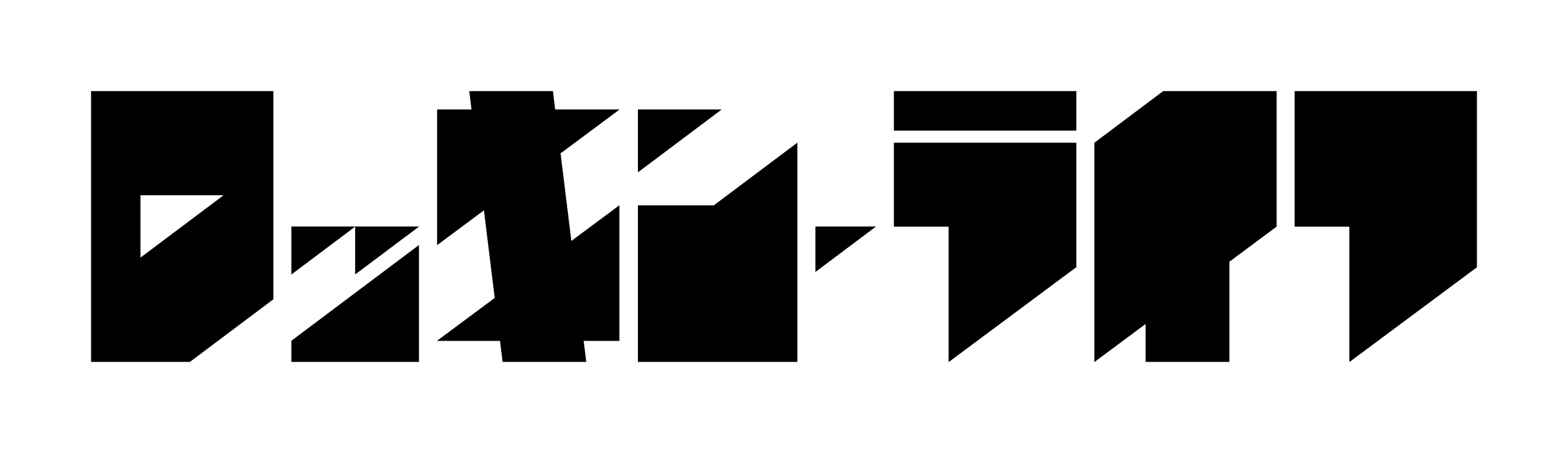藤井風の「花」に感じる、試行錯誤の果てに辿り着いた奥深い眼差しについて
スポンサーリンク
「花」をモチーフにした楽曲は世の中にたくさんある。
「花」って色んな人にとって身近なものだし、<花>は色んな比喩に当てはめてモノを描ける。なので、世の中にはたくさんの「花」の歌があるのだと思う。
こと、特定の<花>であれば、「桜(さくら)」は楽曲のタイトルとして、もっとも登場頻度が高い花である。
「桜(さくら)」といえば、どの歌を思いつくかと問えば、人の数だけ答えが出る気がしそうだ。
自分は森山直太朗の楽曲が頭に浮かんだので、ブログにリンクを記載してみるが、世の中にたくさんの<花>の歌があるという事実だけでも、いかに日本のポップスにおいて<花>は重要な要素として扱われてきたかが、よくわかると思う。
そんな中、J-POP史に新たな花の名曲が誕生した。
藤井風もまた「花」をモチーフにした楽曲をリリースしたからだ。
タイトルは、シンプルに「花」である。
これが良い歌だったので、早速その感想の記事を書いてみたいと思う。
藤井風の「花」の話
冒頭でも述べたが、「花」というタイトルの歌は世の中にたくさん存在している。
「花」というシンプルなタイトルの歌もあれば、「〜の花」という形式を取る楽曲ももある。
また、「花」というタイトルの歌は、文字通り、世の中にある”花”を丁寧に描いてみせる切り口で描かれることもあれば、ラブソングの中で重要なシーンとして”花”を登場させるケースもあるし、そもそもひとつのメタファーとして”花”を描ききってみせるケースもある。
藤井風の場合、木曜劇場『いちばんすきな花』(フジテレビ系)の主題歌として書き下ろしたため、それを踏まえたうえで”花”というモチーフを扱っているのだとは思うが、楽曲内では、どういう風に”花”を扱っているのか確認していくと、
しわしわに萎れた花束
小わきに抱えて
こういうフレーズがサビに登場していることが確認できる。このフレーズだけだと、実際に花を抱えている主人公を描写しているようにも受け取ることができるが、
咲かせにいくよ
内なる花を
サビのラストで上記のフレーズが登場することで、花というのはある種のメタファーとして機能していることが理解できる。
“花”という言葉を別の言葉に置き換えて捉えなおすこともできるような、そういうニュアンスで”花”という言葉を扱っている印象を受けるわけだ。
ところで、”花”を内面にあるものとして描く楽曲は、すでに世の中にいくつも存在している。
そのため、藤井風「花」の描き方やモチーフ自体は、特段特殊めいたものではない印象を受ける。かといって、よくある歌、として受け取ることができるのかと言えば、そんなこともないのがポイントで。これは色んな視点からお伝えできるのだが、”花”に対する眼差しにも、ひとつポイントがあるように思う。
例えば冒頭では、
<枯れていく>
と
<咲いている>
が並列されていることがわかる。そのあとには、
<儚い>
<尊い>
という歌詞が並列して出てきており、それぞれの単語と接続するような言葉選びがなされていることがわかる。
ここが、すでにひとつのポイントになっているように感じるのだ。
というのも、ポップスの場合、1番では<儚さ>にスポットを当たるように言葉を並べ、2番のサビ終わりあたりから、ぐっと<尊い>にスポットを当てることで、楽曲のコントラストだったり起承転結のメリハリをつけることで、楽曲のカタルシスを生み出す・・・というケースが多い印象なのだ。
が、
藤井風は最初から”花”にはふたつの要素があるよね、という話を出していき、そこからこの歌の主題に繋げるような構成になっている。
この感じに、藤井風らしさの一端を覚えたのだった。
言ってしまえば、わかりやすい形でドラマチックに楽曲を進行させるのではなく、掲げる主題を楽曲全編を通じて少しずつ浸透させていくような構成にしているところに「らしさ」を覚えたし、歌詞だけではなく、アレンジ自体のあり方としても、淡々とした流れで音を重ねており、優しさが際立つ構成になっている一方で、じっと聴き入りたくなるような味わい深さが際立っている印象を受けたのだ。
要は、歌詞もアレンジも、根ざしている地点が同じ感じがしたし、シンクロしていく心地を覚えたのである。
それが、「花」という楽曲自体の深みに繋がっているように感じた。
話は変わるが、「きらり」なんかだと、とにかくサビのインパクトが強くて、そのキャッチーさが大きな魅力になっている。
この歌は意図的にサビが際立つアレンジになっているからこそ、よりそういう印象を受けるのだと思う。
しかし、近年の藤井風はそういう構成を取らないケースも多い。
メロからサビへ移行するときのスリリングさ・・・みたいなものの比重を薄めて、もっと全体的に音楽と向き合えるようなアプローチをとっている印象を受けるのだ(海外の音楽的なアプローチに目配せしているのも、影響があるのかも、と勝手に思っている)
「花」は、イギリスのプロデューサーで、レーベル・PC Musicの主宰者であるA. G. Cookが楽曲のプロデュースを手掛けたということもあり、そこの化学反応も、「花」にこういう刺激を与えているのかな、とも思う。
何が言いたいかというと、
- 楽曲の眼差しと楽曲の構成やサウンドのトーンにシンクロ感がある
- そのシンクロ具合に藤井風らしさをどことなく覚える
- 「花」というよくあるテーマや描き方でありながらも、どこまでも藤井風らしい伊吹が入っている
- だから、「花」にぐっときてしまう
・・・みたいな感じの話になる。
スポンサーリンク
なんとなく感じる藤井風らしい哲学
歌詞の話に戻ると、今作、一人称の使い方が印象的である。
他の藤井風の歌でも同じような指摘をしたことがあるが、今作でも「僕ら」というワードが出てくる一方で、「わたし」という一人称が出ていて、楽曲の中で複数の視点を感じられる構成になっている。
かつ、楽曲内では「みんな」という一人称が登場する瞬間もある。
近年、日本の楽曲の多くは良くも悪くも内向的というか、”自分視点の自分の歌”が多い印象であった。そんな中で、藤井風の視点ってひとつ上の視点からの歌になっていて、ここも藤井風らしさを示す要素であるように感じる。
小説でいえば、一人称視点ではなく、三人称視点で描いている心地がするのだ。
視点を「みんな」に敷衍しながら色んな立場の人に思いを巡らせながら言葉を綴るからこそ、
誰もが一人
全ては一つ
という何気ないフレーズが持つインパクトにぐっとくることになるのだ。そして、そういうフリをもってサビに入るからこそ、このフレーズのインパクトも大きいものになる。
色々な姿や形に
惑わされるけど
いつの日か
全てがかわいく思えるさ
わたしは何になろうか
どんな色がいいかな
さらに言えば、「花」という楽曲自体が、アレンジとしてはシンプルな装いではあるけれど、音へのこだわりは鋭く、展開ごとに細かくアレンジを変化させていることが聴いていて、わかる。
「全てがかわいい」は前提の上で、「どんな色がいいか」を細かく選択していることが、アレンジでもわかるからこそ、「花」で示した歌詞が、よりリアリティーを持って響いている印象。
上記フレーズでは藤井風のボーカルに、己のコーラスを当てていることで、メロディーに深みを与えている構成になっているのも印象的で、歌詞とボーカルとアレンジの結託が、「花」の持つ美しさを際立たせていることがよくわかる、という話である。
まとめに替えて
一聴するとシンプルなんだけど、何度も聴くと奥深さを感じる、不思議な楽曲である「花」。
ポップで優しい歌だけど、藤井風らしい鋭くも温かい眼差しを感じられる楽曲で、今の藤井風のモードも、なんとなく感じられる楽曲である。
そんな諸々を踏まえて聴くからこそ、より刺さる楽曲になっている印象である。
関連記事:藤井風という次世代を代表するシンガーソングライターの話
スポンサーリンク