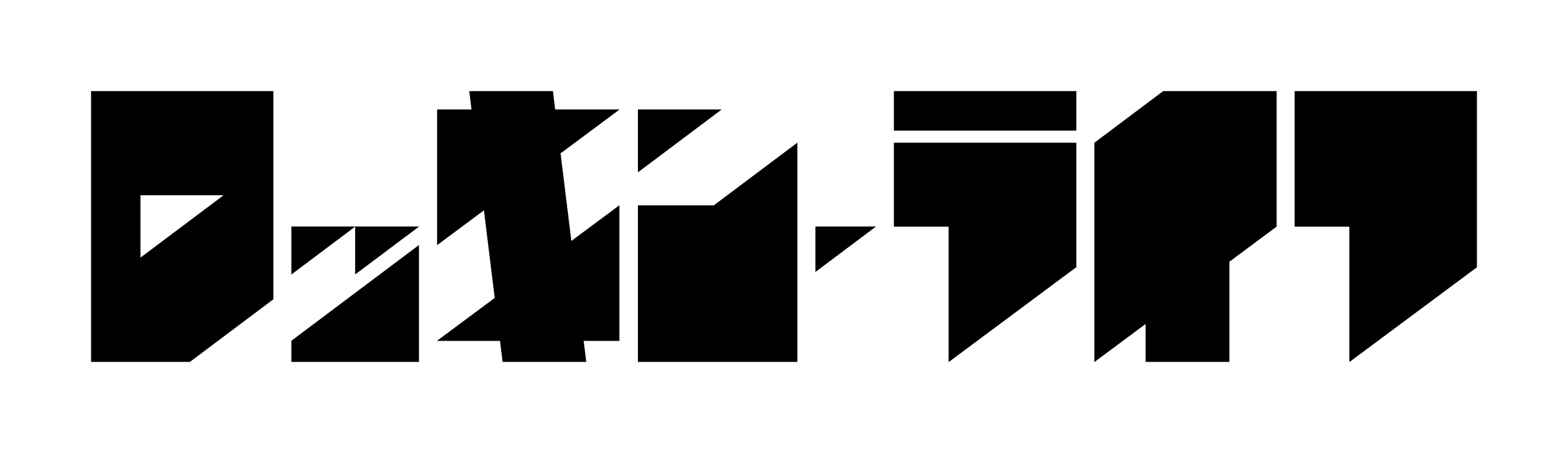前説
スポンサーリンク
コロナ期の今だからこそ、バンドの心境を聞いてみたい。
そんな使命感にかられた自分は、夏の終わりのある夜、2018年秋に日本コロムビア・TRIADでメジャーデビューを果たしたHalo at 四畳半の渡井翔汰さんと白井將人さんを招き、インタビューをしてみました。
今のタイミングだからこその切実な想いを言葉にしてもらっています。
では、どうぞ。
本編
最近の活動状況について
渡:一時期はもう配信ライブすらもできないという最悪な時期もあって、僕らのライブもツアーは中止が決まったりして、有人でのライブはまだちょっと厳しいんですけど、配信のライブの予定は少しずつ立って来てるっていう感じですね。
白:難しいですね、まだ。
──配信ライブをされたときの感触はどうでしたか?
渡:やっぱりめちゃくちゃ難しいなっていうのを感じて。普段お客さんが目の前にいる状態でのライブに慣れていて。(会場はまったく誰もいないわけじゃなくて)スタッフさんたちがたくさんいるわけですよ。ただ、スタッフさんはそれぞれお仕事をされていて、すごく真剣な表情で撮ってくださるわけで、その空気感の差にちょっと圧倒されたというのがあったりして。
白:みんなで音を出すのは楽しかったよね。
渡:そうね。あと、普段のライブよりSNSだったりで感想を呟いてくださる方が多くて、それがすごく良かった。久しぶりのライブっていう補正もあったのかもしれないですし、きっと生のライブに勝るっていうのはどうしても難しいと思うんですけど、それでも喜んでくださった方がたくさんいたので、やったこと自体は、良かったなという気持ちがありましたね。
──また配信ライブが控えてるかと思うんですけど、どういうモチベーションでやったらいいとか、掴んできた感じですか。
渡:そうですね。これは今画策中なんですけど、次の僕ら主催の配信ライブが10月13日に予定されていて。元々ツアーファイナルのZeppDiverCity公演の延期予定だった場所なんですけど。ツアーで開催できない地域があったりとか、Zepp DiverCity自体も新しいガイドラインで見られるお客さんの数よりもありがたいことに応募が来ていて、チケットを買ってくださった方が全員入れない状態になってしまって。それを考えた結果、平等にお客さんに楽しんでもらいたいという気持ちがあったので、(有人のライブは中止のうえで)中止になった日に配信ライブをするんです。
──そうなんですね。
渡:けど、ただの演奏のライブっていうのはちょっと限界を感じていて。僕自身も一音楽リスナーとして感じてる部分でもあって、配信という表現の中で何かできないかなっていうのがあって。Halo at 四畳半ならではの配信ということで、配信を完全にひとつの物語と捉えて、ライブ自体の進行を物語に沿って進んでいくようなHalo at 四畳半らしいベクトルでライブをしてみようかなと考えている最中です。
──その物語っていうのは、今年リリースされたアルバムに沿ってなのか、それともまた全然違ったもので考えているんですか?
白:完全にアルバムとは別軸というか、ツアーとは関係なく、ずっとやりたかったコンセプチュアルなことが配信だからこそできると思っていて。お客さんがいたら空気的にもちょっとやりずらいようなこともできるのかなって、逆にプラスに捉えています。
──もともと前からの構想だったということですか?
渡:そうですね。これはまだ実現するかは決まってないんですけど、物語のシーンという映像があって、(その後に)ライブがあってという、挟み込んで交互にやっていく構成を考えていて。それは急に思い立ったというよりかは、僕らの前身バンドの最初の企画でやっていたことなんですよ。
──最近はここまでコンセプチャルにやってなかった理由はあるんですか?
渡:ストレートに言うと、やりたいことと現実でできることの間を埋められなかったというか。現状のHalo at 四畳半という活動をしている中でできる範囲の中じゃなかった。だから、今回も実現するかまだわかんないんですよ。実際、打ち合わせ中っていうところもあって、まだ実現できないかもしれないんですけど・・・っていうのをちょっとずつ実現に向けて歩んで行ってるというところだったりして。
スポンサーリンク
アルバムの話
──今回リリースされたアルバムというのは、先程話にあったようなコンセプチャルなお題があって作られた感じなんですか。
渡:そもそもの話をすると、Halo at 四畳半というバンド名が空想上のものと生々しいものの共存を歌っていくというテーマを掲げているバンド名なんですけど、それでいうと、今までは空想的な要素の強い曲が多かったんです。けど、メジャーデビューして自分の中でどんどん心境の変化があったりして、「ANATOMIES」という作品はHalo at 四畳半の中でいうと一番現実味というか、自分自身が感じたことを赤裸々に描いた作品が多かったりして。今作に関してはHalo at 四畳半でいうと“四畳半”という生々しい要素が強くなった作品なのかなって思っていて。「月と獣」みたいに物語調の曲も入っていたりはするんですけど、制作期間中に自分たち自身が感じていた物をそのまま吐き出したという作品ですね。
──1か月くらいの製作期間を設けてバッと曲を作って、制作したアルバムというのを伺ったのですが・・・。
渡:そうですね。今までずっとそうなんですけど、(楽曲の)ストックっていうものが全くないバンドなんですよ。・・・っていうのもあって、そのひとつの課題じゃないですけど、事務所とレーベルから1か月間制作して、来月のいついつに10曲用意してみようってなって。Halo at 四畳半は僕と齊木がかいてるので、二人で20曲用意できたらいいねっていうことで始まった画策だったんですけど、その1か月間で僕は思いのほか進んで。
──ほう。
渡:今までだと1か月に2曲3曲かけたらほんとにいい方なレベルだったのに、その時は9曲持って行って。齊木が5,6曲もってきたのかな・・・だったと思うんですけど、「ANATOMIES」に入ってる曲もけっこうその期間に作った曲が多くて。中にはプロデュースに入っていただいている出羽良彰さんと一緒に作った曲もあったりしたので、それまた別途作ったりとか。「イノセント・プレイ」は別で生まれた曲で、逆に「蘇生」はその1か月間で生まれた曲だったりしたので、けっこう「ANATOMIES」の曲はその1か月間で生まれた感じです。
──普段と違った制作スタイルで、やってみてどうでしたか。
渡:すごく楽しかったんですよ。音楽的な興味というか趣味も広がった時期でもあって。数年前までは日本の、歌詞を自分自身で理解しながら聴ける曲にこだわって聴いていた節があって。そのタガを外して何でも聞いてみようと思って、昔から一緒にやっているプロデューサー的立ち位置の方からいろんな音楽を紹介してもらえていたタイミングでもあって。そのおかげもあって興味が広がって、こういう曲も作りたい、こういう曲も作りたいというのがたくさん溜まっていたタイミングでもあったので。
──そうなんですね。
渡:僕、迫られないと集中できないタイプなので、逆にそういう1か月間で作ってこいよというのを設けてもらったおかげで、思う存分制作できたというのもあって、楽しかったんです・・・けど、精神的にはだいぶまいってました(笑)。1か月間、人間の最低限のことと曲をかくしかほんとにやってなくて。そういう意味では地獄だった。んですけど、どっちかというと、楽しかったという気持ちの方が大きいですね。
──じゃあ、また同じようにかいてくれってなっても、やろうって感じですか?
渡:そうですね。またやりたいなっていう気持ちもありつつ、メンタルだけは強くしておかないとなっていう。
──このコロナの渦中で、曲を作るという部分においては影響はありましたか?
渡:めちゃくちゃありましたね。コロナ禍の中でも、頑張ってるミュージシャンはもちろんいるんですけど、逆に僕からすると、そういうのを見ることで更に追い込まれてしまって。こういう人たちはちゃんとこの中で曲を作ってコロナ禍の中であってもツアーが延期になっても中止になっても、その中でできることをやってるのに、俺はなんで、曲もかけず、何をやってるんだろうっていう負のループになってしまって。曲をかこうとしてもかけない、ほかの人のリリースを聴いてめっちゃいい曲だなって思って落ち込むみたいな繰り返しの中にいて、ほんとにまいってましたね。
──そうなんですね。
渡:曲をかくということに関してはまだ手探りというか、やっぱり僕らの歌詞ってファンタジックなものが多かったりするバンドではあるんですけど、それも実は自分自身のことを歌ってたりすることが多くて。100%のファンタジーってかいたことがないんですよ。だから、自分自身の整理がつかない状態で歌詞をかくというのが難しくて、いまだに制作に関しては悩んでいるところではあるんです。ただ配信ライブが10月13日に決まって、自分たち主催でやるワンマンライブとして決まったので、それが思ったよりも大きな光となっていて、やりたいことも構想としてあったので、それに向かって今、しぼんでいた気持ちが大きくなった気ではいますね。
──話は変わりますが、今回のアルバムを出されて一番思ったのは、今までとは違う音を使っている印象をすごく受けて、「蘇生」だったらピアノの音を入れてるとか。今までとは違う方向に向かっているのかなという印象を受けたんですね。それは、方向性を変えるという意図があってやったのか、たまたまいろんな音楽をインプットしたからそういうのが出た感じなんですか?
渡:この作品から大きく音楽性を変えてやろうと思って作っていたわけでは全然なくて。メジャーデビューするちょっと前くらいからストリングスの音を入れたりとかもし始めたんですけど、それって単純に曲を作ったときに、頭の中で鳴ってるからそれを入れたいという思いから始まっていて。今作の曲たちに関しても、ピアノに関してはピアノで曲を作ってみようという思いはあったんですけど、それもHaloの新しい意気込みを見せるというよりは、気分転換じゃないですけど、いつもギターでつくってるのでピアノで作ってみようかなって。まあ弾けないんですけど、弾けないなりにやってみようかなと思って、なんとなく弾いた何のコードかもわからないままで作ったのが「蘇生」だったりして。けっこう自然発生的に生まれたというか、アレンジに関しても僕らは、僕だけではなく、ほかのメンバーの意見も入れてアレンジをするので、その中でメンバーがそれぞれ思いついたことをとりあえず試してみるだとか、プロデューサーさんに入っていただいた曲とかは、そのプロデューサーとのディスカッションの中で、じゃあこういう音を使ってみようというので生まれたりとか。意図的というよりは自然に生まれたものが多い感じですね。
白:俺らもバランス感みたいのは気にしつつやっていて。昔はインディーデビューから3作くらいは4人だけの音にこだわってやっていて、でも4作目のメジャーデビュー前のアルバムくらいからはそういう制約をなくそう、好きにやってみようという時期に入って。お客さんに「すごく変わったね」って言われるのはすごく癪というか、変わっているんですけど、それが良くない見え方されちゃうのも嫌だなって思ってて。でも、やりたいことはいっぱいあるし、そのバランス感を調整していって。自分らのサウンドをずっと模索している最中だったんです。でも、今作くらいからはサウンドがどうこうじゃなくて、俺ら4人が演奏して、渡井さんが歌をのっければ、それでHalo at 四畳半になるよねっていう自信も出てきたので、外の音を入れる入れないみたいな変なジャッジはいらなくなってきたんですよね。どんなサウンドでも大丈夫だろうみたいな。お客さんとの信頼関係もあるし。
メンバー同士の話について
──コロナの間は、メンバー同士ではコミュニケーションとってましたか?
渡:コロナ期間中は配信をやってたんですよ、ハロスタジオというYouTubeでの配信を。それでzoom上ではありますけど、週一で顔を合わせてはいたんですけど、スタジオにはなかなか入れてなくて。でも、その後スタジオに入って終わった時のだべる時間がいつもの10倍で。コロナになる前は、毎日のように会ってたので、話すことがもうなかったんですよ。それが1か月くらい会わなかったので、みんなそれぞれ溜まってて。
──そういうときってどんな話をするんですか。
白:ほんとにくだらない話ですね、メンバーそれぞれが仲いい地元の後輩とかがいて、そことたまにご飯行ったりしてたという報告とか。
渡:何を話したかすら覚えてないという。
白:僕らは友達から組んだバンドだったんですよ。高校時代の友達、後輩、先輩というみんなだいたい友達っていう感じで組んで。ただ、ここ最近は友達で組んだけど仕事仲間みたいな感じでバンドをやってて。逆にコロナでしばらく会わなかったから、友達に戻ったというか。ちなみにメンバーチーム、仲はいいんですけど、みんな頑固になるところが違うというか、その頑固がぶつかるとめっちゃ喧嘩しますね。
コロナ期で変わったもの、変わらなかったものについて
──最後に、コロナの期間があって、ここは変わったなっていうところとここは全然変わらなかったなっていうところを教えてもらってもいいですか。
白:変わったっていうところでいうと、けっこう年がら年中ライブをしているようなバンドだったので、こんなにライブができなかったのってバンドを渡井さんと高校生のときに組んでから初めてだったんですよ。高校生のときの方がもっとライブをしてて、ライブがないと死ぬと思ってたんですけど、意外となくても生きていけるんだなって気付いたのが変わったことで。(そんな中で配信ライブをすると)もちろん不完全なライブだったりとか、お客さんがいないライブだったりとか、完全な形でのライブではないにしろ、4人で音を出すって楽しいんだなっていうことに気付けて。高校生のとき、スタジオが楽しかったとか、そういう感じを思い出したというか。もっと根源的なバンドの楽しさみたいなものに気付けた期間ではあったんですよ。だから、変わらないことで言えば、その音楽が好きなことは変わらずでした。
渡:変わらなかったことの方が少ないというか、ほとんど身の回りが変わったというかバンドやってること、音楽を作ること以外が全部一変しちゃったなという気がしているんですけど、自分自身がめちゃくちゃ変わったなと思っていて。作品とか作る度にけっこう思うんですけど、1年間だったり半年だったり振り返って、自分はこう変わったんだなって曲を書きながら気付いたりするんですけど、今年は更に曲を書けない中でも自分でも思ってしまうくらい、自分自身でも向き合う時間が良くも悪くも多くなってしまったので。今のこのご時世、お客さんの声だったりとかを見れたりするんですけど、それがあるのにライブがなくなってしまったというだけで、意外と自分が思ってた以上にお客さんと離れてしまったなという気持ちがあって。気持ちというか、ライブハウスで会って、というのがけっこう大きいことだったんだなって改めて気付いたというか。やっぱり生で味わえる感覚に、ネットを介して伝えられることってなかなか勝つのが難しいんだなって、すごくそれを思ったことで、コロナになる前から家で過ごすことが多くて、友達と外に出ることもそんなに多い方じゃなかったんですけど、他人と関わることで精神的に救われたりとかそういう風に生かされてたんだなっていうことに気付きました。
白:(変わらなかったことって)あんまないよね。
渡:けっこう自分の部屋が好きだったんですけど、ほんとにここにいたくなくなりましたね(笑)
白:(それも)変わってるじゃん。
渡:あー変わらなかったことで1個ちゃんとしたのがあったんですけど、曲を作るということにはけっこう思い悩んでしまっていたので、いろんな意識の変化はあったんですけど、歌うことが好きというのは変わらなかったなって思いました。どんな精神状況であっても、歌うのは楽しかったんですよ、ずっと。それは救いというか曲を作ること自体にも苦痛を感じていた時期もあったので、その中で歌うのは好きというのは変わらなかったんだなっていうのは、自分がそれに気付けたのも変わらなかったのも、嬉しかったですね。
関連記事:Halo at 四畳半の歌がぐっと刺さる理由について
スポンサーリンク