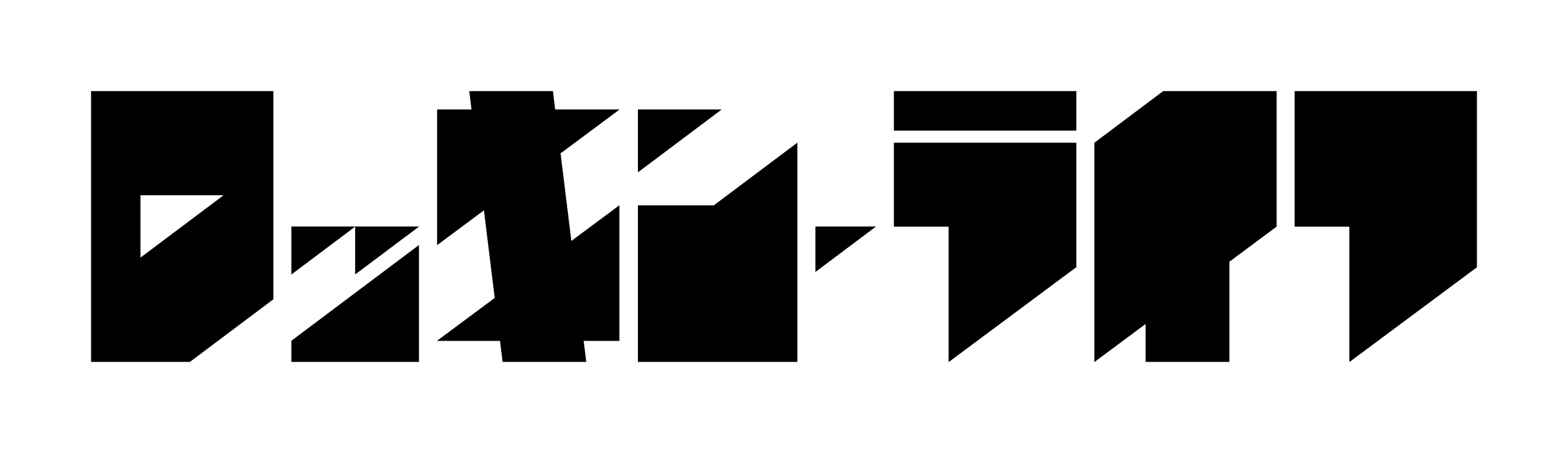前説
スポンサーリンク
バンドにはいくつかのタイプがいる。
けれど、ざっくり分類すると、ふたつの要素に分けることができる。
それは、バンドの外側の音に積極的か否か、だ。
打ち込みであったり、ストリングスであったり、管弦楽や鍵盤の音だったり。
そういう外部の音を積極的に取り入れるバンドかどうか、そこでまずは大別できるように思うのだ。
バンドのメンバーがどういう形で構成されるかによるけれど、「自分たち」だけで音を作るかどうかがひとつの大きな指標になるというわけだ。
そう考えたとき、Halo at 四畳半はシンプルなギターロックを志向していたように思うのだ。
バンドの内の音で完結させている。
内面にそのまま届くような歌詞が、この「閉じた」サウンドに似合っていたように思うのだ。
四畳半というバンド名が似合うような歌を歌い、音を鳴らしているバンドだったように思うのだ。
この記事では、そんなHalo at 四畳半について書いてみたい。
本編
ギターロックであるということ
シンプルなギターロックがHalo at 四畳半の持ち味。
これは間違った表現ではないと思うけれど、同じギターロックといっても色んなバンドがいるよなーとも思う。
例えば、cinema staffのように空間を塗りつぶすような音圧で魅了するバンドもいれば、初期の04 Limited Sazabysのように疾走感をウリにするギターロックもいる。
演奏技術そのもので魅せるバンドもいれば、リズムのフックの部分で魅了するバンドもいるというわけだ。
要は、同じギターロックでも、「どこ」をウリにしているのかはバンドによって違うということだ。
で。
自分にとっては、Halo at 四畳半は歌は歌詞もサウンドも、内面の機微をぐっと掴んでくるような鋭さがあった。
単純に歌詞が良い、っていうのとはちょっと違う。
単純にメロディーが良い、っていうのともまたちょっと違う。
歌詞とサウンドがある種の共謀関係になって、ぐっと内面に突き刺してくる鋭さがあったのだ。
彼らの代表曲である「リバース・デイ」にも、そういう要素をみることができる。
クリーンな音のギターのアルペジオでこの歌は始まる。
こういう導入から歌が始まることで、ボーカルが入ってきたときに、その言葉がすっと心の内に届くのだ。
ドラムにおいても、前半はいわゆる手拍子を喚起させるようなタイプのリズムではなく、タム回しを行うリズムパターンを選んでいる。
これが内面によりするっと入り込む要素になっている。
手拍子を起こさせるようにするとか、リズムのタメを作ってわかりやすい盛り上がりを作るのではない。
でも、きちんと聞けば、細かなこだわりをサウンドに忍ばせているからこそ、歌詞とサウンドが共謀し、圧倒的な鋭さを持つようになる。
Halo at 四畳半の音楽には、そういう魅力があるように思う。
内面に刺さる歌
ぶっちゃけ、こういう魅せ方って「派手」ではない。
テクニカルなギターリフとか、手数の多いドラムとかの方が、セールスポイントとしてはわかりやすい。
あるいはダイブを生み出すようなリズムパターンだったり、メタルのブレイクのようなリズムによるメリハリの方が、セールスポイントとしてわかりやすいことだろう。
でも、Halo at 四畳半の音楽ってそういうところでは勝負していない気がするのだ。
歌があって、言葉があって、メロディーがあって、サウンドがある。
それぞれが共謀して、圧倒的な感動を生み出してくる。
派手ではないけれど。
わかりやすい絵にはならないかもしれないけれど。
でも、聴く人の心には間違いなく爪痕を残していく、そういう魅力が詰まっているように思うのだ。
渡井のボーカルが澄み切っていて、的確に心に届くからこその、Halo at 四畳半ならではの魅力のように思うのだ。
スポンサーリンク
変化するギターロック
冒頭では、Halo at 四畳半はシンプルなギターロックだと述べた。
確かにインディーズ時代の楽曲は「外の音」は使わず、自分たちだけで音を構築していたように思う。
しかし、インディーズ時代は四畳半の中で「閉じていた」ものも、メジャーデビューをしていくと、意図的に広げていった印象を受ける。
外部のアレンジャーの招聘することも含め、外の音を積極的に取り入れるようになったように感じる。
「swanflight」、「from NOVEL LAND」、「ANATOMIES」というメジャー後の三作品を丁寧に聴いていくと、その歴史を明確に感じることができる。
というより、この三作品を通じて、少しずつ新しいことにチャレンジしていって、その殻をやぶっていった歴史を感じることができる、と言い換えた方がいいのかもしれない。
「リビングデッド・スイマー」が収録されている「from NOVEL LAND」では、ほとんどの楽曲でバンド以外の音が取り入れられている。
こういう変化って微妙なところがある。
なんせインディーズから好きな人からすれば、メジャーデビューによって変化してしまった要素には敏感に反応するだろうから。
ここで自分の意見を言えば、Halo at 四畳半にはこういうバンド以外の音が、とても似合っているように思うのだ。
元々突き刺すようなリリックとサウンドの共謀こそが、Halo at 四畳半の魅力だと自分は思っている。
だからこそ、サウンドの広がることで、楽曲の表情が豊かになることで、まさしくHalo at 四畳半が持つ魅了が拡張されていくように感じるのだ。
しかも、Halo at 四畳半が良いなーと思うのは、外部の音の扱い方。
毎回、外側の音をどういうふうに落とし込むかにはすごく腐心しているように感じるし、そこにすごい丁寧さを感じるのだ。
ちゃんと根本である自分たちのサウンドを大事にしたうえでの取り入れだからこそ、より楽曲は輝いているように思うのだ。
最新アルバムに収録されている「蘇生」では、大胆にも前半はバンドの音がまったく入らない状態で楽曲が進んでいく。
でも、このアレンジがすごくハマっていると思うし、外部の音を取り入れることでHalo at 四畳半の持つ繊細さとか鋭さがより輪郭を帯びているように感じる。
だからこそ、思うのだ。
これから先も、Halo at 四畳半はもっともっと化けていくはずだ、と。
外部の音を入れ方に関しては、迷っている部分もあるのかもしれない。
ギターロックだったりとか、バンドの音そのものに対するこだわりがあるバンドだから、きっとひとつひとつの変化に対しては慎重だと思うと思う。
そういう慎重さを持つHalo at 四畳半の持つ楽曲だからこそ、外部の音はどこまでも圧倒的な魅力に変化していくように思うのだ。
トータルで言い切ってしまうと、こういうHalo at 四畳半の変化は、間違いないよなーと思うわけだ。
少なくとも、僕は強くそう思うのだ。
まとめ
わかりやすい派手さを持ち合わせているわけではない。
なので、言葉にしてHalo at 四畳半の良さを語ると、少しまどろっこしい言い回しになってしまう。
でも、内面にぐっとくる曲の良さはきっと聴いてもらったらわかると思うのだ。
そして、内面にまでぐっとくる理由を改めておさらいすると、声が良くて、サウンドが良くて、すごく計算されたところで音のバランスを取っているからだと僕は思うわけだ。
他のバンドではわりとスルーするような部分に関しても、細かく気を使って楽曲を作るHalo at 四畳半の歌が良くないわけがないのだ。
今年リリースされた「ANATOMIES」というアルバムを聴いて、改めてそのことを実感した。
だからこそ。
まだ出会えてなかった人は、ぜひ一度彼らの音楽にそっと耳を傾けてほしいなーと、そんなことを思うのである。
スポンサーリンク