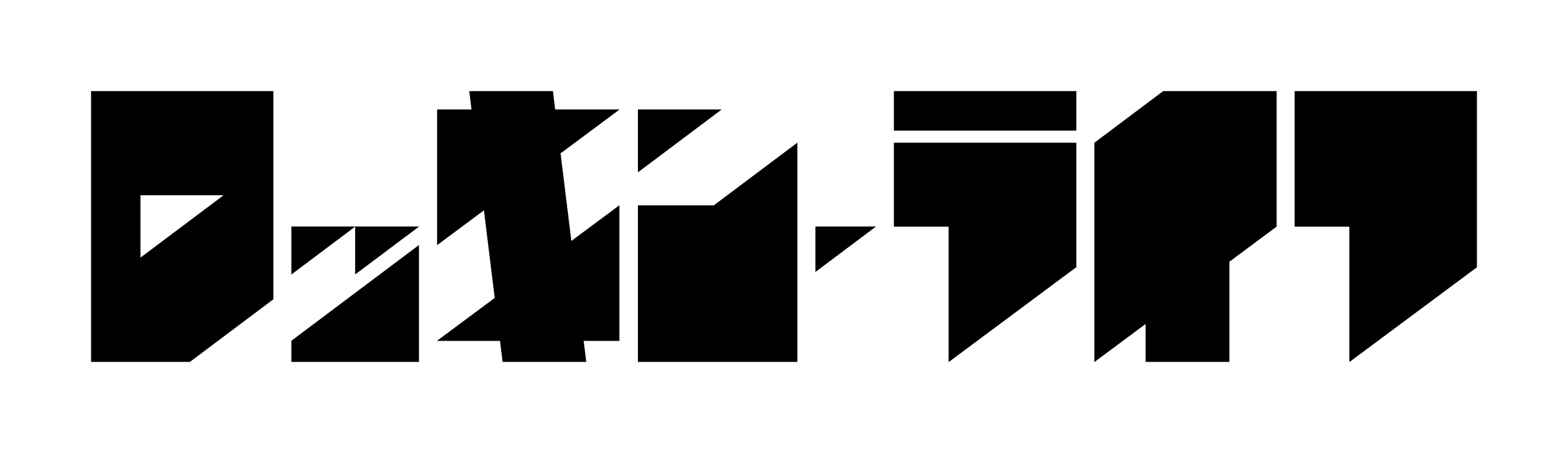前説
スポンサーリンク
UNISON SQUARE GARDENのニューアルバム「Patrick Vegee」がリリースされた。
今作も期待に違わず、自分の癖(へき)に突き刺さるアルバムだった。
というわけで、この記事では「Patrick Vegee」の感想を書いていきたい。
本篇
なんかグチャっとしてんだよな。
バンドのアルバムって一人の作家性が浮き彫りになるタイプのものと、バンドそのもののカラーが色濃く浮き上がるもののふたつがある。
UNISON SQUARE GARDENの場合、その辺がちょっと特殊だよなーと思う。
もちろん、アルバム全体の手触りでいえば、UNISON SQUARE GARDENというバンドのカラーが全面に出ているアルバムなんだけど、アルバムの中に宿っているロマンには全曲の作詞作曲を手掛けている田淵智也のそれが宿っている気がするのだ。
今作においても、曲順や曲間などで、そういう田淵ならではの作家性をひしひしと感じさせてくれるのだ。
このアルバムの特設サイトでは<なんかグチャっとしてんだよな。>という言葉がどーんと表示されているんだけど、そういう意味でいうと「グチャっとしている??????!!!!!!!いや、むしろ逆ですよ、逆!!!!!」みたいな気持ちになった。
なんせ、今作は過去のユニゾンのアルバムと比べても、曲順と曲間がキレイにハマっていると感じたから。
この曲順と曲間だからこそ、それぞれの楽曲たちが輝いているように感じられたから。
ひいては、アルバム全体がある種の魔法を放っているように感じられたから。
まずは、そういう話からこの記事を進めてみようと思う。
シングル曲とアルバム曲の繋がりについて
今回のアルバムは曲順と曲間が良い。
わかりやすいところでいえば、各シングル曲とその前に配置されたアルバム曲との言葉の繋がりにある。
「スロウカーヴは打てない(that made me crazy)」の最後のセンテンスは<つまりレイテンシーを埋めています>になっている。
これは、次に配置されたシングル曲の「Catch up, latency」のタイトルとシンクロするようになっている。
また、「夏影テールライト」と「Phantom Joke」でも、「ジョーク」というキーワードにより、ふたつの楽曲が繋がるように配置されている。
トドメは「弥生町ロンリープラネット」と「春が来てぼくら」の繋がり。
このアルバムにおける田淵のインタビューを読んでいる限りだと、「春が来てぼくら」だけは着想違いの作品だったため、あまりアルバムに入れたくなかったようだけど、入れざる得ない中で楽曲が浮かないようにするための方法として、前楽曲と連動するセンテンスの挿入を実践したと語っている。
当然、「弥生町ロンリープラネット」と「春が来てぼくら」でもその方法論を確認できる。
そして、こういう仕掛けを施されたことで(いや、施されていなくもだが)自分は「春が来てぼくら」は浮いているようには一切思わなかった。
確かに全体的にソリッドでシンプルなバンドサウンドが目立つ今作において、でかでかとストリングスが入っているこの歌は色がちょっと違うのかもしれないけれど、むしろこの色の違いがこの曲の名曲具合を鮮やかにしているように感じたのだ。
そのため、このアルバムをフルで聴くたびに、「弥生町ロンリープラネット」の最後のセンテンスがそのまま「春が来てぼくら」に繋がる流れに鳥肌がたってしまうのだ。
「春が来てぼくら」って曲としての求心力が高く、言葉がぐーっと入り込み、視界が広がるような風呂敷大きめの曲である。
アルバムが終盤に向かい、夏フェスでいうと夕日が見えてきそうなタイミングで、とたんにこういう大きな曲がどかーんと響く感じに、自分はゾクゾクさせられるのだ。
きっとシングル曲をシングル曲と知らずに聴いた人であれば、シングル曲が「アルバムの中の外側の曲」なんて一切思わないと思うのだ。
それくらいに、しかるべきタイミングに、しかるべき位置にそれぞれのシングル曲が収まっている。
そのように感じる。
「Hatch I need」〜「Catch up, latency」の話
これほどまでにアルバムを曲順通りに聴きたくなるアルバムもそうはないと思う。
捨て曲があるとかないとか、そういう話なのではなく、純粋にこのアルバムの流れでそのまま全曲聴きたくなる。
そういうアルバムなのだ。
そういう気持ちにさせてくれるのは、序盤の「Hatch I need」〜「Catch up, latency」までの流れが秀逸だからだ。
「スロウカーヴは打てない(that made me crazy)」と「Catch up, latency」がセンテンスに繋がりがあることは先ほど述べたとおりだが、センテンスがどうとか関係なしに曲と曲の繋ぎ方があまりにもかっこいいのである。
ロックバンドのライブのような迫力が、そこにあるのだ。
このパートでは、曲が終わるとすぐに次の楽曲が始まるように、なるべく余計な間を削っている。
センテンスの繋がりだって、斎藤のボーカルがオフられると、すぐに次の楽曲が始まる。
だからこそ、先程の楽曲のフレーズが余韻になって、次の楽曲と「繋がり」を強く感じさせてくれるのだ。
「Catch up, latency」までの突き抜けるような感じが、たまらない。
あと、歌詞やタイトル以外の部分でも、つながりを感じさせてくれる。
「Hatch I need」で言えば、ユニゾンのアルバム一曲恒例の数字遊びがあったり(今作は8枚目のアルバムのため、8=Hatchという音を効果的に使っている)、ジャケットやアルバム帯とリンクするように「白ヤギが食べる」というフレーズを入れてみたりしている。
さらに言えば、この歌の歌詞に出てくるAとBというワードは、昨年のユニゾンの活動とシンクロするようにもなっている(去年はB面の楽曲に光を当てるようなツアーを行っていたため)。
ユニゾンのアルバムって全体で捉えていくと、ユニゾンの物語に集約されるところがあって、冒頭のセクションでもそういう要素を予感させるものが散りばめられているわけだ。
それが、このアルバムのワクワクを増長させてくれるのだ。
「摂食ビジランテ」〜「Phantom Joke」の話
4曲目まではわりと疾走感が強かった今作。
だけど、この辺りから少し空気が変わる。
アルバム全体の流れでいえば、少し揺さぶりをかけているような印象を与える「摂食ビジランテ」。
テンポも大きく変えて、アルバムの流れに変化を加えていく。
ただ逆に言えば、アルバム全体に揺さぶりをかけてくる楽曲が、今作ではユニゾン三人の音で構成している曲であることがポイントのように思う。
前作のアルバム「MODE MOOD MODE」であれば、ここらへんで積極的に音の足し算をして、変化を加えていた。
しかし、今作はそういう変化の付け方はしない。
あくまでも三人のバンドサウンドで、揺さぶりをかけてくる。
このアルバムは、そういうモードのアルバムである、という印象をより色濃くしている。
あと、「摂食ビジランテ」に関しては、このアルバムのひとつのキーワードになりそうな「食」というワードが入っている。
「Hatch I need」と<食>の描き方がどう変わっているのかを見るのも、作品全体を捉えるうえで重要な要素になるかもしれない。(この記事ではわりとスルーしちゃいますが)
さて、「摂食ビジランテ」が終わったあとに展開されるのが「夏影テールライト」という、爽やかな楽曲である。
この曲も冒頭4曲とは違う雰囲気の楽曲であり、アルバム全体の流れに揺さぶりをかけている。
しかし、このアルバムではあくまでもユニゾンのバンドサウンドでそれを行うという意志を「夏影テールライト」のアレンジでも感じさせてくれる。
余計な音は入れず、ユニゾン三人のシンプルかつ緻密な音のアンサンブルを「夏影テールライト」で味わうことができる。
ユニゾンの三人でかかれば、こんな魔法を生み出すことができるんだぜ、ということを改めて宣告するような、そんな心地。
ここで少しゆったりしたバンドサウンドを展開するからこそ、再び疾走感のある「Phantom Joke」に戻ったときの、ユニゾンならではの爆発力がより鮮やかになっていく。
スポンサーリンク
「世界はファンシー」〜「春が来てぼくら」〜「101回目のプロローグ」の話
ユニゾンのユーモアがもっとも炸裂しているのが「世界はファンシー」だと思う。
そして、ユニゾンならではのエモさ・・・というか、ユニゾンならでは泣き歌ソングなのが「101回目のプロローグ」だと思う。
「101回目のプロローグ」の歌詞って、ユニゾン以外のバンドだとそこまで刺さらないというか、「は?何言ってるの?」みたいなひねくれ方をしていると思う。
でも、ユニゾンの今までの活動を追っている者からすれば、最後の楽曲のこのひねくれ方こそが「いつものやつ」であり、そういうある種のひねくれ方こそが逆にストレートに感じられると思う。
というか、今までのユニゾンのスタンスを理解している人ほど、この歌が語る「君」いう代名詞の中に、ストンと自分たちファンのことを代入できる歌になっているのかなーと思うのだ。
だからこそ、この歌が紡ぐ言葉がストレートに刺さる。
このバンドのファンだからこそ、歌われている言葉以上の意味が伝わってくるという意味では、同日発売されたヤバTのアルバムとも似ているところがあるんだけど、そのバンドのファンだからこその伝わるメッセージ・ソングってぐっとくるものがあるよなーと改めて思うし、15周年のときの大きなライブでは、あえて余計なMCはしなかった田淵が<本当の気持ちを話すのは 4年ぐらい後にするよ>という言葉をここでしたためるのは、ぐっとくるものがあるよなーと思う。
この時点で、すでに20周年に行われるであろう大きなライブの布石をしているのが、実にニクイというかなんというか。
このバンドのファンだからこそ、伝わってくる言葉を羅列していき、最後に<魔法が解けるその日まで>というファンだからこそ伝わる言葉で締めくくるところのが、良いなーと思うのだ。
このアルバムのメッセージとは?
まあ、アルバムのメッセージとは何なのか?というようなあまりにも野暮な問いだと思うけれど、あえて言葉にしたいと思う。
で。
このアルバムを聴いてひとつ言えるのは、このアルバムは「ファンの層を広げるためのアルバム」ではなく、「今までファンだった人だからこそ刺さるアルバム」であるんだろうなーということなのだ。
だからこそ、ユニゾンというスリーピースバンドが紡ぐバンドアンサンブルを重視したアレンジの曲を並べたのだと思うし、ユニゾンのファンだからこそわかるフレーズを随所にちりばめたんだろうなーと思うのだ。
そして、今作もトータルでみると、ロックバンドっていいでしょ?という、シンプルかつスマートなことを伝えるアルバムになっているのかなーと感じるのだ。
去年のB面ツアーを予感させるフレーズで固めた「Hatch I need」では<あらすじは終わっていない>と宣言して、このアルバムを始まった。
<運命は過去に置いてきた>という言葉が印象的な「マーメイドスキャンダラス」では、バンドはワクワクがなくなるまで、いつまでも駆け抜け続けるイメージを与える。
「スロウカーヴは打てない(that made me crazy)」では、<I must doubt “Pop music You may doubt “Rock festiva>という言葉を用いて、さり気なくバンドのスタンスを表明していき、「摂食ビジランテ」では、<万人が煽る ユートピアに期待なんかしてないから 今日は残します>という具体的な決意表明を行う。
「夏影テールライト」では、最後のフレーズの裏を読むと<(君が)幻に消え「ない間は」 ジョークってことに「しない」>でほしいという切実な願いがそこにあるように感じるし、だからこそ「世界はファンシー」では<My fantastic guitar!>というフレーズに代表するように、ユニゾンならではのロックを言葉とサウンドの両方でこれでもかと畳み掛けていく。
そして「Simple Simple Anecdote」では、今の君に対するメッセージをさりげなく述べて、「101回目のプロローグ」では、今の君(=ファン)に対して、これからの自分の決意をそこに示して、かっこいいロックバンドはまだまだ続いていくことを予感させて、終幕を迎えるのかなーと感じたのだ。
言ってしまえば。
物好きな君に対して、ロックバンドってかっこいいでしょってことを改めてお伝えするための、これからのユニゾンを自己紹介をし直すためのアルバムだったのではないか。
そんなことを考えるのである。
でも。
まあ。
本音の本音を言えば、メッセージなんてどうでもいいやって思ってしまう自分もいる。
だって、このアルバムがただただ好きだって思うから。
余計なことなんて抜きにして、何度も何度もこのアルバムを聴きたくなる自分がいるから。
それが、ぶっちゃけてしまえば、すべてなのだから。
スポンサーリンク