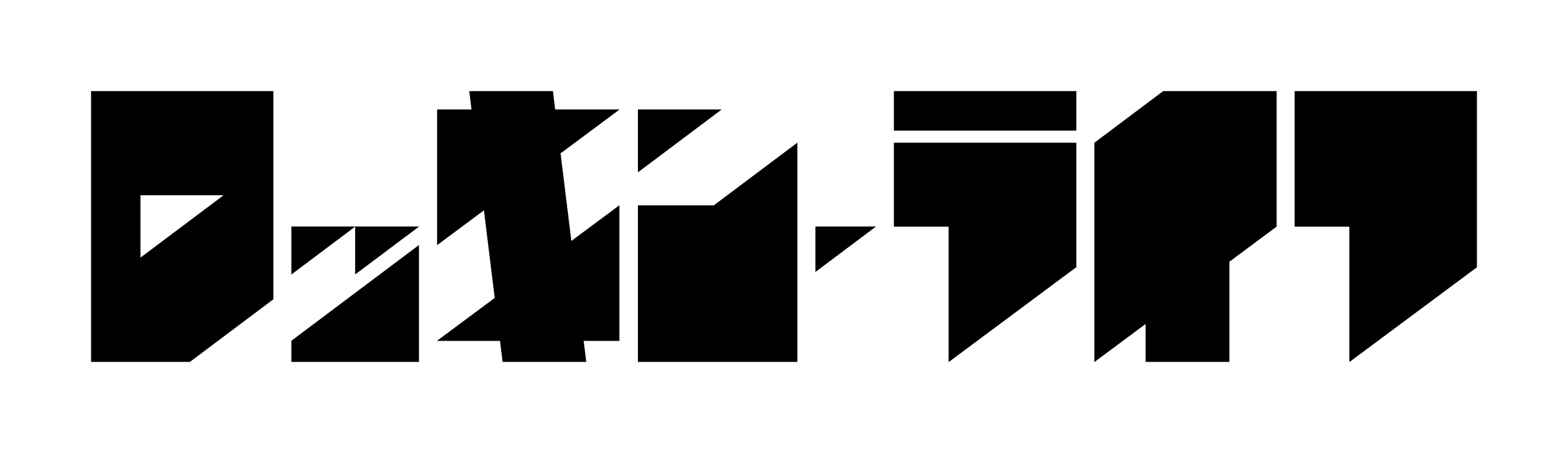SixTONESの「共鳴」から生まれる美しさについて
スポンサーリンク
今年の1月にリリースしたアルバム「CITY」も完成度が高かったSixTONES。
そんなSixTONESは、早くも3月にニューシングルをリリースした。
ところで、「CITY」を聴いて感じたのは、間違いなく年を重ねるごとに<次のフェーズ>に進んでいるという感触だった。
音楽性の幅広さや表現力の広がりを感じるんだけど、そこに集約するのは、よりたくさんのリスナーを巻き込んでいくような心意気だったのだ。
なので、ここから先も容赦ない作品を生み出すんだろうな・・・と勝手なことを思ったりしたのだった。
さて、そんな中でリリースされた2022年最初のシングルである「共鳴」。
今までのシングル曲とまた違う魅力を提示していた今作。
早速、この曲の感想を書いてみたいと思う。
本編
SixTONESの「共鳴」の話
きっと、リスナーの数だけ感想があると思う。
そういうタイプの楽曲だと思う。
というのも、「共鳴」って、いろんな切り口から楽しむことができる楽曲だと思うからだ。
ただ、その中でも自分が強く印象に残ったのは、ボーカルの素晴らしさ。
しかも、ここでいう素晴らしさというのは、SixTONESの6人だからこそ、が接頭についてくる。
どういうことか?
例えば、「うやむや」でもSixTONESの鮮やかなボーカル割と、ジャンルを飛び越える表現力が大きな話題となった。
「共鳴」でも、そういうSixTONESだからこその矢継ぎ早かつダイナミックなボーカルを堪能できるのだ。
細かくボーカルのチェンジが行われ、サビ以外の部分でも<魅せる>パートが多々ある構成。
しかも、個々のパートが際立っているからこそ、メンバーが揃って歌唱をする、
ギリギリに立たってんだって 分わかってるのに
それでも選えらんでしまった 夢ゆめと誇ほこり
というパートの存在感が際立つという流れ。
ここまで含めて、非常に秀逸だと思うし、SixTONESの楽曲がなぜ<沼>なのかがよくわかる流れとなっている。
スポンサーリンク
歌割りごとの具体的な話
・・・もう少し、具体的にパートごとの話をしてみよう。
例えば、冒頭のラップパートはジェシーが歌っている。
一方、1番のAメロの冒頭は田中樹が歌っている。
どちらかというと、ラップの歌唱で言えば、田中樹のイメージが強いのかなーと個人的に思っていた。
が、今回はその流れとは違うパートになっている。
でも、意表をつかれたという感じはなく、しっくりとくるような流れになっている。
広い役割の中で曲ごとに異なる歌割りができるのは、SixTONESだからこそだと思うし、SixTONESの魅せ方のひとつと言えよう。
なお、田中樹のパートに関して言えば、ここで歌メロパートを披露するからこそ、ラストのサビに繋がる後半のラップが冴え渡るという背景もある。
楽曲を全体として捉えていけば行くほど、一番と後半の対比が良い意味で際立っていくわけだ。
・・・話を、1番Aメロに戻そう。
このあと、松村北斗→髙地優吾→森本慎太郎と繋がるわけだが、ここであることに気づく。
今回の楽曲の開幕は京本大我で始まっているため、楽曲開始およそ30秒ほどですでに全員のソロパートが披露されるという超密度の構成になっているのだ。
これが、良い。
この短い時間の中で、6人の個性が冴え渡るという流れは、まさにSixTONESの真骨頂といえるのではないだろうか。
かつ、それぞれがスキのないボーカルを披露するからこそ、良い意味で緊張感をもったまま、次のパートへと流れる展開になっている。
加えて、もうひとつ言いたいことがある。
「共鳴」は全体的にソリッド感のある歌で、荒ぶるドラムが印象的な楽曲になっている。
ということもあってか、メンバー全員が良い意味でエッジのある歌い方をしている印象を受ける。
甘さの際立つボーカルが持ち味の松村北斗のボーカルでも、意図的にソリッド感が際立っており、それが「共鳴」の世界観を確固たるものにしている。
かと思えば、同じボーカルでもパートごとに表情が変わっていたりして。
例えば、先ほど名前をあげた松村北斗であれば、「暗転の〜」のパートと、「賽を奪う〜」のパートでボーカルの切れ味が変わっている印象を受ける。
前者はソリッド感があって少しエッジみが強い。
後者は美しいハイトーンが際立っていて、歌声の中にある種の彫刻刀感を覚えるのである。
あと、京本大我の「轟かす共鳴」と歌う際の、<きょうめい>の吐息感も絶妙だと思っている。
ここで絶妙な余韻を残すように息を解き放つからこそ、サビでぐっとモードが切り替わることを実感するのである。
まとめ
そう。
端的に言えば、個々もそうだし、楽曲全体を捉えた時のボーカルのコントラストが絶妙なのだ、という話。
この6人だからこその世界観が「共鳴」に刻み込まれている。
そんな風に思うのである。
ただ、やっぱりラストのサビに至るまでの、怒涛の流れが特に良いよなあと思っていて。
「共鳴」の歌詞の話じゃないけど、<役者は揃ってる>からこその息もつかせぬ流れに、魅了されっぱなしなのである。
まだ聴いていない人は、ぜひ聴いてほしい、そんな一曲だなーと改めて。
今年のSixTONESも、目が離せない。
関連記事:SixTONESの『CITY』の簡易なる妄想的レビュー
スポンサーリンク