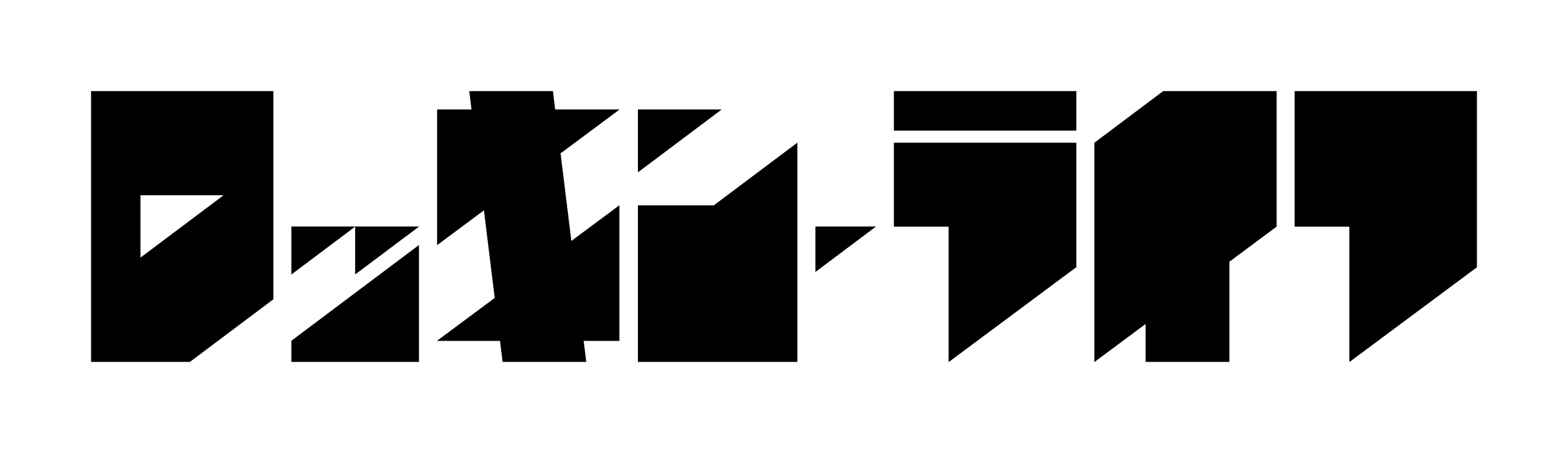Official髭男dismの楽曲に感じること
スポンサーリンク
大衆に向かって歌うことを意識している歌は、なるべく誰にでも当てはまるシチュエーションを歌うことが多い。
Official髭男dismもまた、そういう歌が増えているように思う。
某マツコ会議で、マツコ・デラックスが「Pretender」に対して指摘した内容とも通ずることだと思うのだが、Official髭男dismの歌って様々な人が歌のシチュエーションに当てはめて聴くことができる。
なぜなら、そういう余白のある言葉で物語を紡いでいるから。
「Pretender」は、その最たる歌だと思うわけだ。
ヒゲダンの歌を聴く人、と一口に言っても様々な立場の人がいる。
そして、様々な人がいるからこそ、その中にいる立場の弱い人に対して、配慮ある言葉を述べるべき、という価値が強く求めらがちとなる。
その中で自分たちならではの表現を落とし込むからこそ、恋愛が主題の場合、よりたくさんの人に当てはまるシチュエーションの歌を歌うことになるのかなあと思ったりするのだ。
少なくとも、表題曲ではそういう言葉選びに徹するのかなーと勝手ながらに思っていたわけだ。
だからこそ。
「アポトーシス」が発表されて、その音楽を聴くことになって驚くことになる。
なぜなら、この歌は代名詞しか使わない歌でありながらも、かなり厳密なシチュエーションと想像力を喚起させる歌になっているからだ。
Official髭男dismの「アポトーシス」について
まず、最初のセンテンスで「ダーリン」という言葉を提示をする。
その後、一人称を「私」、二人称を「あなた」と示すことで、登場人物の関係性を素早く的確に描いてみせる。
もちろん、歌全体がある種の比喩であるという見方をするのであれば別ではあるが、そうではないとすれば、この歌は明確な恋愛ソングであり、夫婦という立ち位置の二人組が登場人物であると想定できる。
そして、主人公は妻であり、二人称である旦那に対して言葉を紡ぐという構成を取っているように感じるわけだ。
これまで、恋愛ソングはたくさん歌ってきたヒゲダン。
結婚式で安心して使用することができるような、温かさに満ちた感動のラブソングの数も多い。
この歌でも<素敵になったね>というワードが出てくる通り、幸福と隣合わせの生活を過ごす二人が登場人物になっていることがわかる。
しかし、この歌が今までのヒゲダンの恋愛ソングと大きく違うのは<過去>ではなく、<未来>について言葉を多く費やしているところ。
しかも、その未来とは夫婦がきっと待ちかえるはずのもっとも悲しい別れ・・・つまりは、どちらかが「死」を迎えて、二人がいつか別れてしまう未来について、言葉を紡いでいるように感じてならないわけだ。
アポトーシスという言葉を調べると、あらかじめ予定されている細胞の死のことであり、細胞が構成している組織をより良い状態に保つため、細胞自体に組み込まれたプログラムのこと、であると出てくる。
アポトーシスという言葉は比喩としてのワードだと思われるが、ここでいう比喩とはきっと二人の関係性だったり、二人の未来を指差しての言葉のように感じてならないし、そう考えたとき、ある種の<死>を意味するアポトーシスという言葉が、印象的に響くわけだ。
仮に結婚する二人が末永く人生を一緒に歩むのだとすれば、どちからが先に死ぬという未来を避けて通ることはできない。
その二人が幸せであればあるほど、きっとその辛さは先鋭化していく。
どうしても、そのことを歌の中で提示すると重たいものになるし、しんどいものになるから、普通はそういう部分の語りは周到に避けるように思う。
しかし、「アポトーシス」はそういうこととしっかり向き合っているように感じるわけだ。
スポンサーリンク
「アポトーシス」に込められた意味
これは、勝手な想像だけども。
コロナ禍においては、音楽と現実との距離が近くなった。
音楽は辛い現実を忘れるためのものだ。
ライブやコンサートは非日常の空間なのだ。
そういう主張が空虚に響くようになってしまった。
現実の状況次第でライブは簡単になくなるようになったし、「音楽」はどこまでも現実と通じた場所に存在しているものであることを実感しないといけない事態が連続することになった。
綺麗なところだけを魅せることは意味をなさなくなって、辛いこととも対峙する必要性が生まれたわけだ。
「アポトーシス」そのことを受け止めて、表現に落とし込んでいるのではないか。
そんなことを感じるのだ。
なので、結婚を想定した恋愛ソングである「アポトーシス」では、いつか訪れるパートナーの死という辛い現実との対峙を歌の中で表現することにしたのではないか、そんなことを思うのだ。
だからこそ、軽やかで心地よいで終わるのではなく、そこから一歩二歩踏み込んだ深さと重さを歌の中に込めたのではないか。
そんなことを思うのだ。
ヒゲダンの楽曲として
ついつい歌詞の話をダラダラと書いてしまったけれど、音楽作品としての深みも凄まじい。
自由自在の転調のアプローチや、ここぞの時の美しくて伸びやかなハイトーンボイスも健在で、ヒゲダンにしかできない展開がされている。
なにより、今作は<時間の流れ>が歌の中で重要な意味を示すからこそ、その時間の経過をサウンドで表現する上手さを感じるわけだ。
この歌は、6分という比較的長い尺であるが、その流れと経過がまるで人生のように壮大になっている。
冒頭では、比較的音が淡々と響き、ベースもドラムも<躍動>というよりも<静けさ>を意識したアプローチをしているように感じるのだ。
歌詞とリンクするように、鐘の音が鳴ることで始まるサビでも、藤原が紡ぐ鍵盤の音が存在感を示していて、それぞれの音がしっかり鳴り響くのにどこまでも静けさを感じるテイストになっているのだ。
しかし、そのサビが終わると間髪入れず2番が始まる。
その時には1番のAメロとは違う空気感がサウンドの中に宿る。
具体的に言えば、ベースとドラムのリズムアプローチが変わっていて、それぞれで動きをつけるようなアプローチをしていくのである。
バンドサウンド全体で、歌の中で経過する時間を表現していくからこそ、二人が紡ぐ実りある時間と、だからこそやがて向かうはずの死までの道筋を感じにはいられなくなるのだ。
楽曲ごとにサウンドメイクをこだわってきて、その音や言葉が相手にどう届くのか、どういう印象を与えるのかを考え抜いたヒゲダンだからこそのリアル感とドキュメンタリー感が際立つのである。
単純に歌詞が素晴らしいから、この歌の<死>の雰囲気にぐっとくらう、のではない。
ヒゲダンというバンド全体が、この楽曲が紡ぐ景色に対して持つべき技術を注ぎ込んでいるからこそ、言葉がどこまでもぐっと響く。
つまりは、Official髭男dismというバンドの凄まじさを感じる一曲になっている、というけだ。
まとめ
とはいえ。
歌詞に対する話については、あくまでも自分はそういうふうに感じた、という話である。
インタビュー記事を読めば、ヒゲダンメンバーから、この歌はこういう意味を込めてました、という答え合わせが出てくることあるだろう。
その内容によっては、この記事が紡いだ言葉はまったく的外れの可能性もある。
でも、自分はこの歌のある種のドキュメンタリー性を感じたことは確かで、そこで感じた感動は作り手の思惑とは別のところにあると思うから、こうして言葉にした次第である。
人によって、きっと歌から感じる景色は違うと思うからこそ、ぜひ各々でこの楽曲を聴きながら、そのことを堪能してほしい。
きっと期待を裏切らない6分30分の体験となるだろうから。
関連記事:Official髭男dismが放つ「Cry Baby」のおぞましい世界観
関連記事:Official髭男dism、2021年も容赦がないことが判明する
スポンサーリンク