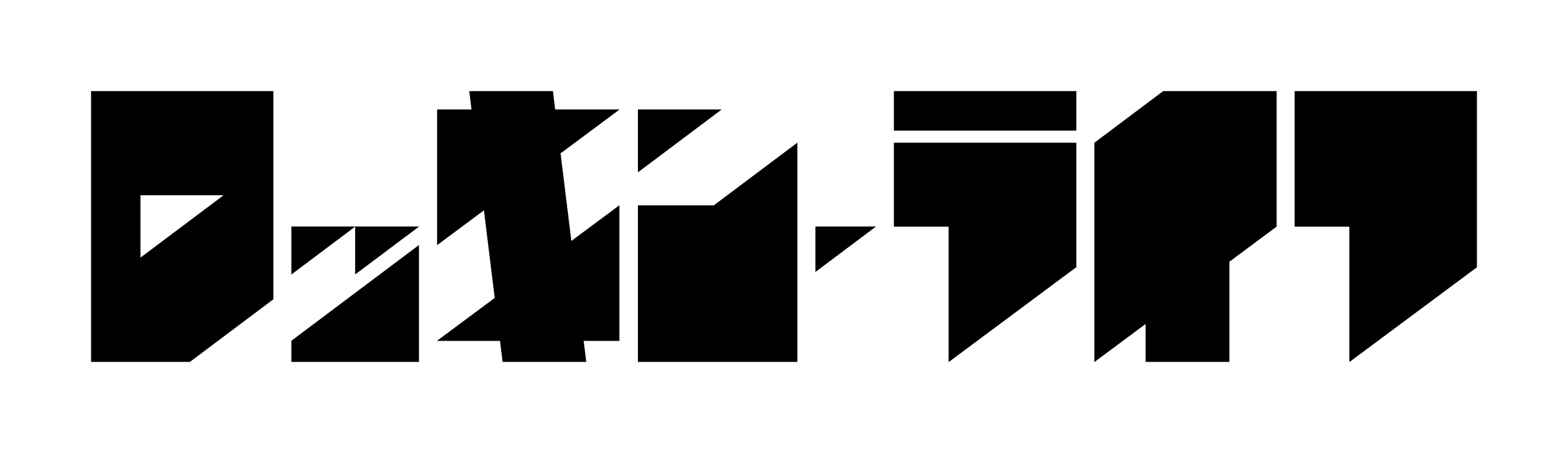前説
スポンサーリンク
2020年も色んなバンドが新譜を発表している。
気に入った歌もあれば、あまり気に入っていない歌もあるわけだけど、新曲を聴くといつも感じるものがある。
それは去年の作品との差異から生まれがちなもの。
というのも、新譜って、大きく分けると3つのパターンに分かれると思うのだ。
1つ目は、去年の焼き直しのような作品であり、そういう作品を作ってくるバンド。
いわゆる、新曲なのに既視感を感じるバンドって、この理屈にはめ込めやすいと思う。
もちろん、この「既視感」こそが人気の秘密なわけだからそういうものを作ることが正しいわけだけど、どうしてもいくつもある曲と比べると、そこにある魅了は薄まって感じてしまう。
2つ目は、去年とガラっと作風を変わった作品であり、そういう作品を作ってくるバンド。
こういうバンドも、わりといると思う。
去年だったらSuchmosはそういう代表だったのではないかと思うし、昔でいうところのレディオヘッドのように、新作の発表ごとに「なんじゃこりゃあ」なショッキングなものを与えるバンドもいたりする。
なんとなくだけど、King Gnuのこれからの新譜では、そういうレベルの変化が生じるのではないかなーと勝手に思っている。
そして。
新譜のパターンとして最後にあるのは、去年から露骨に感じさせていた変化をより先鋭的にさせる作品であり、そういう作品を作ってくるバンドである。
ん?
言いたいことが分かりづらい?(自分で書いていてもよくわかってない)
なんというか、曲を出すたびに変化を感じさせるバンドっているわけじゃん?
で、その変化が螺旋階段のように少しずつ変化していって、作品を出すたびにその変化がより深まってくるバンドっていると思うのだ。
そして、今年の新譜でもその流れが変わることなく、曲を聴いて「おっ!今回はこういうふうに変化を深化させたか」なーんて思うのである。
そう。
僕はパスピエの新譜を聴く度に、いつもそのことを感じるのである。
というわけで、この記事では、そんなパスピエのことを書いてみたい。
本編
下記が、新曲の「まだら」だ。
パスピエの持つミステリアスな感じをキーボードで演出していて、イントロだけでも不思議な世界に引き込まれてしまう。
アート的な要素とバンド的な要素、あるいはクラシック的な要素とロック的な要素を巧みに融合させているところがパスピエの持ち味のひとつだと思うんだけど、今作もひととつの切り口だけでは語ることが難しい、複合的な音楽の彩りを感じさせるのである。
キーボードは妙に不気味な音色を鳴らすのに、他の楽器隊は正確無二に不規則なリズムの中を生み出している。
これにより、不気味さはより混沌としたものになっていく。
なんなら、コード進行にもどこかしら逸脱したものを感じてしまう。
いわゆるポップスで見られるような安定感は、この歌にはほとんどない。
けれど、ただただ気持ち悪い曲なのかといえば、そんなこともなくて、絶妙なバランスでポップの部分に着地している。
そんな感じの曲なのだ。
言ってしまえば、パスピエだからこそ生み出すことができるバランスに着地している楽曲なのである。
思えば、「ONE」以降、パスピエの音楽は明らかに変わってきた。
他のバンドはたくさんの人に受け入れられそうなこっちの道に進んでいるけれど、自分たちは自分たちのやりたいようにこっちの道に進んでいくぜ、という意志を感じさせる名曲を立て続けに生み出している感じるのだ。
音楽に美学を感じるとでも言えばいいだろうか。
「まだら」のジャケットがアート的であるのと同様、パスピエの音楽の節々にもそういうアート性を宿しているのである。
でも、ちゃんとポップにもなっているし、なによりきちんとパスピエの音楽になっているのだ。
この感じが重要だと思う。
どんどんとマニアックな方向に走ってしまうバンドも確かにいるけれど、己の美学を追求しすぎたために、なんかよくわからん作品を作り上げてしまうバンドもいる。
でも、パスピエは変化を深化させつつも、きちんとそこにパスピエらしさを感じるのだ。
キーボードが奏でるミステリアスが、不思議とパスピエらしさを感じるのである。
大胡田なつきのボーカルも面白い。
今回の歌声には、すごく透明感が宿っているように感じる。
「まだら」って歌詞だけをみると、けっこうセンシティブなんだけど、不思議とそこに引っ張られていないのは、サウンドの抑揚の付け方と声のトーンにあると思っている。
そうなのだ。
ボーカルは、決してセンシティブな方向に寄ってはいかないのだ。
ここも先程でいうバランスの話とつながるんだろうけれど、ボーカルが良い意味で前面に出てくるような歌になっていないのだ。
あくまでも曲を構成する一部というか。
そういう感じでボーカルがサウンドに寄り添っているように感じるため、きっちりとバンドそのものの音に入り込むことができるのだ。
こういうバランスも絶妙なように思う。
単純に「言葉の物語」に収斂していくんじゃなくて、音楽そのもので魅了していく意志を感じさせる作りというか。
これもまたパスピエの美学のように思うんだけど、様々な要素を研ぎ澄ませて、自分たちが納得のいくバランスで着地させているところに、この歌の名曲たらんといしているところなのかなーと思うのだ。
まとめ
なーーんて言葉を紡いでみたけれど、この歌の良さを説明するには、あまりにも語彙力が足りない。
素の感想をテキスト化するなら「!!!!!!!!!??????????????」くらいの感じである。
だけど、この歌には、躊躇なく「名曲」という言葉が使える。
少なくとも、僕はそう思う。
それくらいに大好きな一曲であり、一発聴いた時点で感じた率直な思いなのである。
関連記事:キーボードやピアノがいるバンドを推していきたい選手権
スポンサーリンク