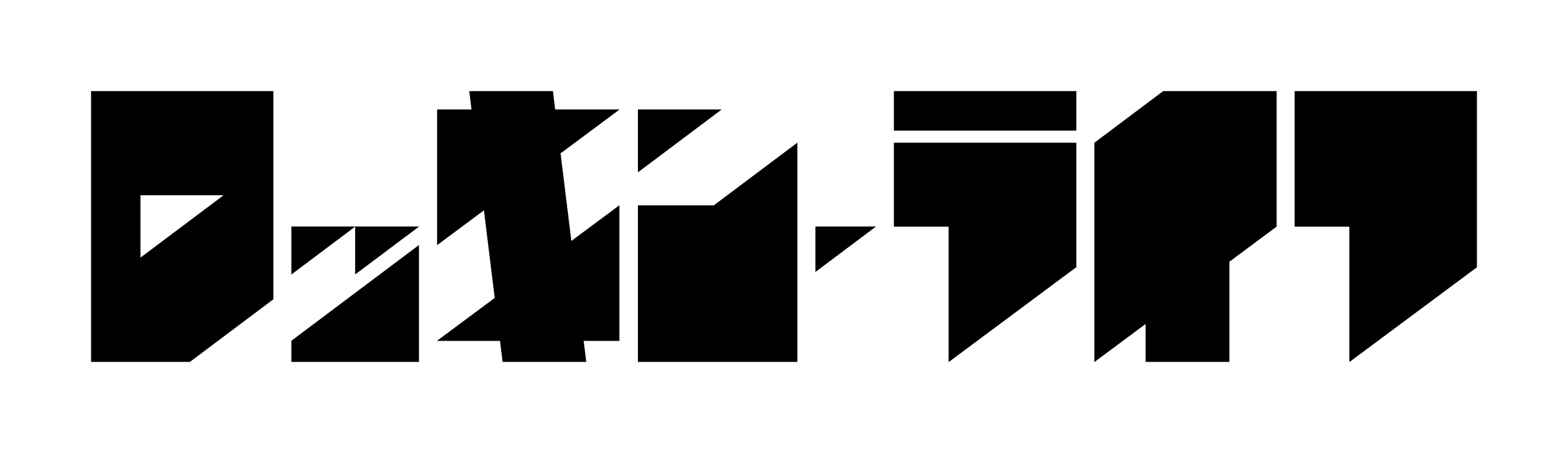ロッキン・ライフ in ライブハウス vol.3の話
スポンサーリンク
「ロッキン・ライフ」というイベントタイトルをつけて、定期的にライブイベントを開催している。
2021年12月30日、阿倍野ROCKTOWNでは、そんなライブイベントのvol.3が開催された。
今回出演頂いたバンドは、ココロオークション、The Songbards、カネヨリマサル、ザ・モアイズユー、Organic Call。
一応、自分主催のライブイベントなので、当ブログにてライブレポのようなものを書くつもりで筆を進めている。
ただ、自分はどうにもいわゆる<レポ>というものを書くのが苦手である。
そもそも、ここでセトリとMCを反芻するだけの記録のまとめを書いてもなあ〜という思いがある。
そこで、この記事では自分がライブを観て感じた、各バンドの所感みたいなものを綴ることにしてみる。

本編
Organic Callの話
タイムテーブル的に、最初に出演してもらったのは、Organic Call。
開口一番、Organic Callはぶちかましまくっていた。
ただただ、その格好良さに圧倒されるのだった。
コロナ禍において、バンドのライブって魅せ方を変えざるを得なかった部分がある。
なぜなら、自分のイベントもそうだけど、ライブを観ている人の動きにルールを設ける必要が出てくるからだ。
声出しはできないし、ライブ中にできるアクションも制限される。
なので、バンドによってはパフォーマンスの仕方を変えるというケースもあった。
だけど、Organic Callのライブを観ているとコロナ禍だからとか、ライブを観る環境が変わってしまったからとか、そういう言い訳を取っ払ってしまう凄みがあった。
いや、もちろん、コロナ禍前とまったく同じライブしている(できている)わけではないと思うんだけど、そんなことがどうでもよくなるほどにアガるライブをしていたのだ。
日常と非日常のスイッチをパチリと切り替えるかのように、ライブハウスの空気をがらりと変えたのが、何よりの証拠だ。
イケてないライブの場合、ここの切り替えができてない。
だから、『手を挙げる」とか「音楽に合わせて身体を動かす」ということがライブの中で<浮く>ことになってしまい、どこか白けたムードが出ていたり、恥ずかしさの空気が充満してしまうことになる。
でも、Organic Callのライブは、そういう空気を一瞬にして取っ払っていったのだった。
後ろからライブを観ていた自分は、「あ、ライブハウスの空気が変わった」と強く感じたのだった。
楽曲の強さがあって、歌の強さがあって、ライブバンドとしての圧倒的な説得力があるからこその破壊力。
一方で、躍動感に満ちているんだけどセンチメンタルな美しさもあって。
「朝焼けに染まった街へ」では確かに<赤色>がライブハウスに広がったし、「海が見える街」では不思議と眼前に<青色>が広がっていく心地を覚えたのだった。
ザ・モアイズユーの話
2番手として出演してもらったのは、ザ・モアイズユー。
ザ・モアイズユーのライブを観て感じたのは、良い意味での音源とライブとのギャップ。
楽曲を聴くと、メロディーの印象が強いバンドだから<聴かせること>に軸足を置いているバンドなのかなーと感じる。
もちろん、歌心があるのもザ・モアイズユーの魅力ではある。
だけど、ライブを観ると、それは魅力のひとつでしかないことを実感する。
ライブではライブバンドとしての迫力が際立ち、どの楽曲も音源よりかっこよく響いてくるのだ。
しかも、単純に<かっこいい>だけではなく、優しさだったり温かさも内包しているのが特徴で。
エモーショナルに舵切りめだったMCも相まって、ステージがハートフルな空気感に包まれていく。
あと、セトリの流れも秀逸だった。
最初は「花火」でいわゆる”エモい”空気にしたかと思えば、次の「光の先には」では躍動感溢れるパフォーマンスを披露し、「MUSIC!!」の頃にはステージを完全にザ・モアイズユーの色に染め上げていく。
後ろからライブを観ていると、オーディエンスの反応がとにかく良かったことを感じるし、そこにコールアンドレスポンスを行ったというわけではないんだけど、演者とお客さんの双方で素敵空間を作り上げている気がした。
そこもまた、個人的にぐっときたポイントだったりした次第。
カネヨリマサルの話
3番手で出演してもらったのは、カネヨリマサル。
「いつもの」や「ガールズユースとディサポイントメント」といった硬派かつ疾走感のあるナンバーが中心に構成されていた今回のセトリ。
バンドやっていて楽しいぜ感が際立つパフォーマンスで、不思議とワクワクする気分が充満してくる。
だけども、いや、だからこそ、中盤に披露されたミディアムナンバーの「ネオンサイン」が印象的に響いていた。
そんなカネヨリマサルもまた、ライブならではのギャップが炸裂しているバンドだった。
ギャップを強く感じたのは、ライブパフォーマンスとMC間でのこと。
というのも、楽器を演奏したり、歌を歌っているときは<音を鳴らしているのが楽しくて仕方がない>感が爆発している気がして、ロックバンドが持つ瑞々しさに心躍らされたのだった。
しかし、一度MCに入ると、パフォーマンス中とは違う感情がダイレクトに伝わってくる・・・そんな気がしたのだった。
<楽しさ>よりも<内に秘めた熱い闘志>が際立つMCだった・・・とでも言えばいいだろうか。
で。
丁寧に言葉を操って何かを雄弁に語る、というような内容のものというよりも、言葉を発するという行為を通じて内側に秘めた想いの大きさと熱さを表現するMCだったのだ。
いずれにしても、ライブだからこその見えてくる感情がそこにあって、ぐっとくるライブだったのだ。
とはいえ。
そこに感じたギャップの根底にある想いは、きっと同じだったようにも思う。
いかにこのバンドがロックだったり、ライブだったり、音楽だったりを大切に思っているのか。
その気持ちの強さが、パフォーマンスになっていることには変わりはないと思ったからだ。
このバンドもまた、ライブを観るとかっこよさが際立つことを実感させるライブだったし、きっとオーディエンスの多くがそのかっこよさに惹かれることになったように感じた。
The Songbardsの話
4番手で出演してもらったのは、The Songbards。
The Songbardsって、自分たちはこういうバンドに影響を受けました、というニオイをサウンドや楽曲構成でしっかり提示してくるところがとにかく良い。
時にはビートルズだったり、時にはレディオヘッドだったり。
音の質感やコードの外し方で、影響を受けたバンドの要素をのぞかせつつも、そういった要素を巧みに自分たちの表現に吸収していく。
しかも、その表現がどこまでも丁寧かつ正確で。
バンドの中にきっちりイメージがあって、そのイメージに対する妥協が一切ないプレイをするのだ。
今回のイベントにおいても、歌声やバンドアンサンブルが生み出す美しさは群を抜いていた。
ロックバンドによっては、演奏以外の部分のアクションを積極的に取り入れることで、音源とライブの<熱量の違い>を生み出すことも多い。
けれど、The Songbardsはバンドが持つパフォーマンスそのものだけで、明確に音源にはないライブの圧倒性を生み出していたのだった。
演奏に一切スキがないのはもちろんのこと、伸びやかなボーカルと鮮やかなコーラスワークも見事で、穏やかながらも強烈なインパクトを与えることになる。
「夏の重力」で始まった今回のThe Songbardsのライブ。
音源とは違い、コーラスワークから始まるアレンジが秀逸で、開始数秒で、他バンドにはない幻想的な感じを音と照明で形にしていったのが、とにかく印象的だった。
ライブの空気がまたひとつ大きく変わったし、完全にその場の空気をThe Songbardsが掌握していた。
あと、他バンドは比較的エモーショナルなMCをすることが多かった中で、The Songbardsはおばあちゃんとの心温まる穏やかエピソードを話している部分も、人柄のようなものが出ていてとても良かった。
ココロオークションの話
毎回、出演バンドが決まると、このバンドならこういう感じのイベントになるかな・・・とか、こういう並びだったらお客さんがより<ライブ>や<ライブハウスという空間>を楽しんでもらえるんじゃないか・・・みたいなことを考えて出演順番を考えさせてもらう。
で、今回のイベントはこの5バンドが出演することになる、と決まったとき、自分の考えから逆算して、今回のイベントのトリはぜひココロオークションにお願いしたいと思い、ココロオークションに締めくくってもらうようにお願いをした。
楽曲が持つ幻想的な感じと、ライブバンドとしての説得力。
ふたつの要素を持っているココロオークションが、絶対にこのライブイベントを良い形で締めくくってくれると思ったからである。
実際、当日のライブの流れは秀逸そのものだった。
冒頭は「星座線」や「スーパームーン」という、ココロオークションならでは景色が丁寧に描かれた幻想的なナンバーを披露。
端的な形で、ステージをココロオークション色に染め上げていく。
さらには、冬のライブということもあって、「スノーデイ」という季節感のあるナンバーもしっかりセトリに加え、年末だからこそのライブ感を鮮やかに演出してくれる。
そして、終盤に向かうにつれて、「ロックスターに憧れて」「フライサイト」という疾走感のあるキラーチューンを炸裂させることで、会場のボルテージをあげていく。
ライブ中で披露されたMCも過不足ない形で展開すると、最後は「魔法みたいな」で、しっかり本編を締めくくる。
この形で締めくくられたらもうアンコールするしかないじゃん・・・みたいな感じの空気にしたうえで、その後のアンコールの「ヘッドフォントリガー」。
この流れまで含めて、これしかないという形でライブを締めくくる構成力に脱帽したのだった。
キャリアのあるバンドだからこその構成力だったと思ったし、色んな楽曲・色んな展開をさせることができるバンドだからこその魅せ方に圧倒されたのだった。
色々あった2021年だったけれど、このライブ空間は間違いなく多幸感に満ちていて、その多幸感を絶対的なものとして印象づけたのは、ココロオークションのパフォーマンスであった。
後ろからすべてのバンドのライブを観た自分は、そんな風に思ったのだった。
まとめに替えて
やっぱりバンドのライブって良いなあ。
こうやってライブを観るたびに、そんなことを思うのである。
音源で聴くのも良い、短尺をSNSで触れるというのも良いとは思う。
でも、それらを軽く飛び越えてしまう魅力が、バンドのライブにはあるということを改めて感じさせる一日だった。
音源とは違った魅力がある、というのは当然なんだけど、この<音源とは違った魅力>がバンドによってまったく異なるのが良いのである。
ギャップという部分で魅せるバンドもいれば、演奏の迫力で魅せるバンドもいるし、MCで放った言葉が印象的なバンドもいれば、秀逸なセットリストが印象に残るバンドもいる(あの曲をやってくれた、みたいな嬉しさが残る場合もあるしね)。
なーんてことを今更ながらに思う、そんなライブのそんな総括。
スポンサーリンク