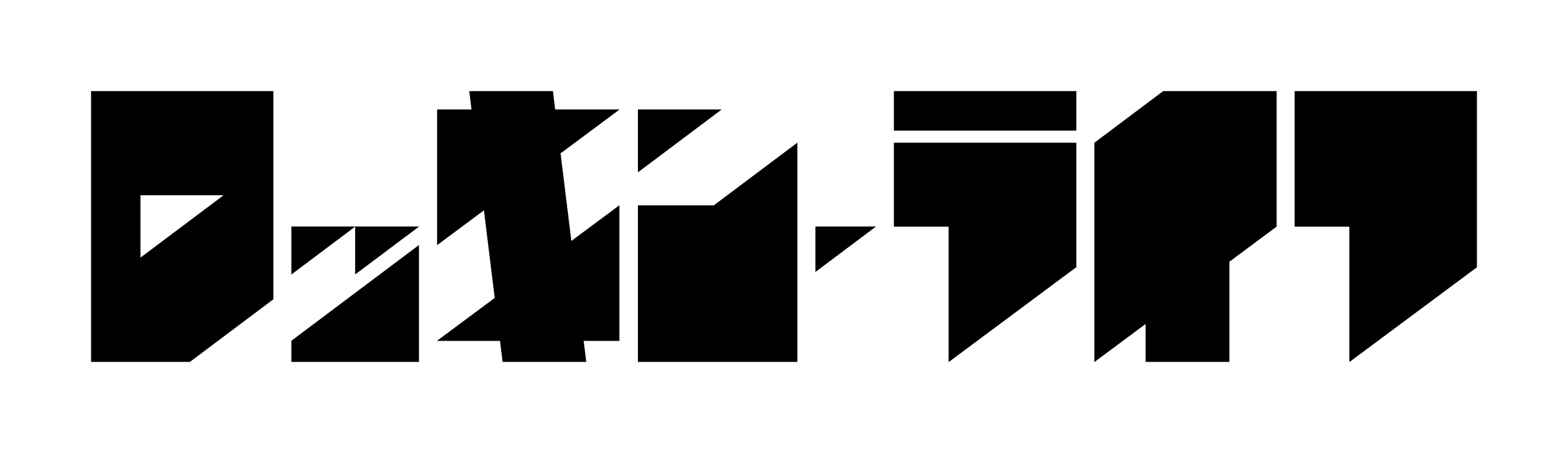なかなかにバンド名が覚えられないIvy to Fraudulent Gameの話
スポンサーリンク
自分は親しみのない英単語で構成されたバンドの名前はなかなかに覚えられない。
字面としては覚えているんだけど、音として口で発生しようとしたとき、「あれ? このバンドってなんて呼べばいいんだろう?」となってしまうのだ。
その中でも特に読めるまでに苦労したのがIvy to Fraudulent Gameである。
呼ぶときはいつも「Ivy」の部分だけで発していて乗り越えてきたけれど、フルネームで呼ぼうとしたときにいつも自信がなくなってしまう。
というのも、「Fraudulent」の部分の読み方をきちんと覚えていないからだ。
最近になって読み方はちゃんと覚えたが、声に発しようとすると噛んでしまう自分がいるんだけど、そんなIvy to Fraudulent Gameを、この記事では書いてみたいと思う。
本編
Ivy to Fraudulent Gameとの出会い
自分がIvy to Fraudulent Gameの作品をきちんと聴いたのは『行間にて』だった。
Ivy to Fraudulent Gameにとって初の全国流通盤の作品で、リリース直後、自分もタワーレコードでその作品を見つけたのだった。
ただ、実を言う、と自分が初めて『行間にて』を聴いた際は、「ん?」という感覚だった。
すっとその音楽が自分にはいるのではなく、その手前の違和感で止まってしまったのだった。
ポストロック的なアプローチを土台にありつつも、ポップで歌心があるラインの融合がIvy to Fraudulent Gameの音楽の良さだと思うんだけど、当時はその<絶妙なバランス感>がすっと自分の中に入らなかったのだ。
当時の自分にとって、Ivy to Fraudulent Gameだからこその<絶妙なバランス感>を上手く咀嚼できず、「これは、もしかすると自分には刺さらないタイプの音楽かもしれない」と思ってしまったのだった。
しばらくはその印象がずっと残っていて、Ivy to Fraudulent Gameの作品を丁寧に聴くことはなかった。
でも、今になって、当時自分がきちんと咀嚼できなかった部分に、Ivy to Fraudulent Gameだからこその美しさが詰まっていたことを実感する。
というのも、自分は最初に「ん?」と思う作品やアーティストほど、後々に惹かれてしまうことが多い。
例えば、自分はRadioheadがすごく好きなんだけど、Radioheadとの出会いである『OK コンピューター』は全然良いと思えなかった。「こんなよくわからん作品、聴けないや」と思っていたのに、色んな音楽に触れて聴き直すと、オセロがひっくり返えったかのように「良くない」が「いいやん!」に変わったのだった。
Sigur Rosの『Agaetis Byrjun』を聴いたときも、同様だった。むしろ、ん?の度合いが大きかった分、飽きたのフェーズがまったくやってこず、自分の中での名盤度合いが大きくなるのだ。
そう、自分においては初っ端に何かしらの違和感を覚えた作品こそが、自分にとって存在の大きな作品になることが多い。
ごちゃごちゃしたと感じたサウンドには、明確な美学と意味性が宿っていることを感じて。
その美学がIvy to Fraudulent Gameだからこそのものであることを実感して。
その構想力と表現力の高さにいつしか魅了されることになるのである。
Ivy to Fraudulent Gameの作品が持つ美しさ
それでは、Ivy to Fraudulent Gameの美しさって何だろうという話であるが。
そもそも、Ivy to Fraudulent Gameって楽曲ごとにサウンドアプローチががらっと変わるバンドである。
自分がIvy to Fraudulent Gameの音楽に触れたきっかけは『行間にて』だったが、この作品はIvy to Fraudulent Gameの<部分>だったことを、他の作品を聴いて実感することになる。
例えば、『回転する』というアルバムでみても、『行間にて』からの更新具合がすごく、アルバム内での楽曲のカラーも豊富なのである。
「青写真」や「アイドル」のようにエネルギッシュなロックサウンドを惹かせる楽曲がある一方で、「最低」や「+」のように静寂な空気感で丁寧かつ大胆に音を積み上げるナンバーもある。
細かいレベルでリズムを刻んだり、展開に合わせて音色を鮮やかに変えてみせたりと、サウンドそのものでの展開の作り方も鮮やかで。その展開の中でボーカルの表情が移ろいゆくのも良い。
・・・といった絶妙な流れの中でアルバムが進行した先、ラストの「革命」は言葉の力強さが印象的なナンバーで、少し内省的だった言葉の世界が、ぐっと開けていくのにぐっとしてしまう。
そう、このアルバムの流れも良いなあと思っていて。
『回転する』の場合、「最低」と「革命」のフレーズが対になっている部分があって、『回転する』というタイトル自体の意味性も立体的になっていく。
アルバムを通して聴くことで、アルバムの全体の美しさも実感することになるのだ。
バンドのメインソングライターであり、初期の作品はすべての楽曲を手掛けていた福島の美学が溢れている感じにぐっとくるのだ。
Ivy to Fraudulent Gameって、こうしたら人にウケるでしょ、よりも、まずはシンプルに自分たちが<良い>と思うものが前に出ている感じがしていて、そのこだわりが楽曲や作品全体に宿っているように感じていて、そこに惹かれることになるのだ。
・・・ということもあるのかわからないが、サウンドの展開の魅力もさることながら、言葉の良さもIvy to Fraudulent Gameの魅力だなあと思っていて。
Ivy to Fraudulent Gameの場合、歌全体のメッセージに刺さるというよりも、ふいに現れるフレーズが自分の内面に刺さる、ということがある。
おそらく、ネガティブ濃度高めの歌詞が多いんだけど、最終的に「ただネガティブのままでは終わらせない」着地になることが多く、その変化のきっかけとなるキモのフレーズに、自分は刺さるんじゃないかと思っている。
あと、寺口の甘くも鋭さのある歌声の表現力が、フレーズを意味性をクリアにしているからこそ、という部分もあるのだと思う。
ちなみに、自分は「革命」という歌のフレーズが好きで、<飼い慣らせ不安をこの歌で><掻き鳴らせ音楽をこの不安で>とい部分に惹かれる。
音楽で不安を吹きとばせとかじゃなくて、不安を<飼いならす>という表現が良いなあと思うのだ。
きっとこれって、どうあっても不安は自分に内在にしていることを認めたうえでの言葉だと思うのだ。
でも、その不安を認めつつも、そこから変化させようと意志感が好きなのである。
なお、このフレーズに出会ってから、アルバムの頭に戻り、「最低」を聴くと、フレーズの解像度が上がる、という構成も良い(「最低」はまさしく不安がベースにある世界観の楽曲だと思うから)。
言葉や歌そのものの求心力が強いからこそ、「夢想家」や「模様」のようにしっとりとしたバラードにも、ぐっとくる。
Ivy to Fraudulent Gameってメンバーそれぞれが影響の受けた音楽が違うというのが特徴のバンドで、ボーカルの寺口はロックではなく、歌謡曲に影響を受けている、というのも大きいんだろうなあと勝手に思っていて。
単純なるロック好きとは違って視点で歌を見ている人だからこその歌が、Ivy to Fraudulent Gameの楽曲にはあるんだなと思うのだ。
スポンサーリンク
進化するIvy to Fraudulent Game
コロナ禍を経て、Ivy to Fraudulent Gameの作品は変化をしているイメージである。
『再生する』『Singin’ in the NOW』と聴き進めていくと、バンドは次のフェーズに進んでいる印象だ。
特に2022年にリリースされた『Singin’ in the NOW』は、Ivy to Fraudulent Gameのアルバム史上、もっともシンプルな装いの作品であるように感じる。
というよりも、よりシンプルに歌そのものが際立った作品といってもいいのではないかと思っている。
コロナ禍になると、内に向き合う時間が増える分、ゴリゴリに内省的な作品を生み出すバンドもいると思うんだけど、『Singin’ in the NOW』はその逆をいっているイメージで。
音のひとつひとつがクリアになっていて、風通しが良いなあと思う歌が多くて。
「泪を唄えば」や「胸をこがして」は、そんなイメージが強い歌だ。
本来であれば、もっとテクニカルなアプローチもできるバンドだと思う。
難解なアプローチを突っ込んだり、シューゲイザーやポストロックを深堀りするようなアプローチをすることもできるのだと思う。
でも、Ivy to Fraudulent Gameの強みっていくつもあって、歌そのものも強いバンドだからこその美しさが『Singin’ in the NOW』にあった気がして。
初期作品で評価された部分とは違う展開で魅せる楽曲が多いんだけど、だからこそ、それだけのバンドじゃないことを実感させてくれる楽曲が揃っていて。
このタイミングで、楽曲の瑞々しさが炸裂している気がして、そこに惹かれていく自分がいたのだった。
まとめ
改めてIvy to Fraudulent Gameの作品を過去から聴き直すと、ひとつひとつのアルバムが良いことはもちろんのこと、その変化にも自分はぐっときてしまうのである。
初期作から独自の色合いが強いバンドだったからこそ、変化の鮮明さに惹かれる自分がいるのである。
スポンサーリンク