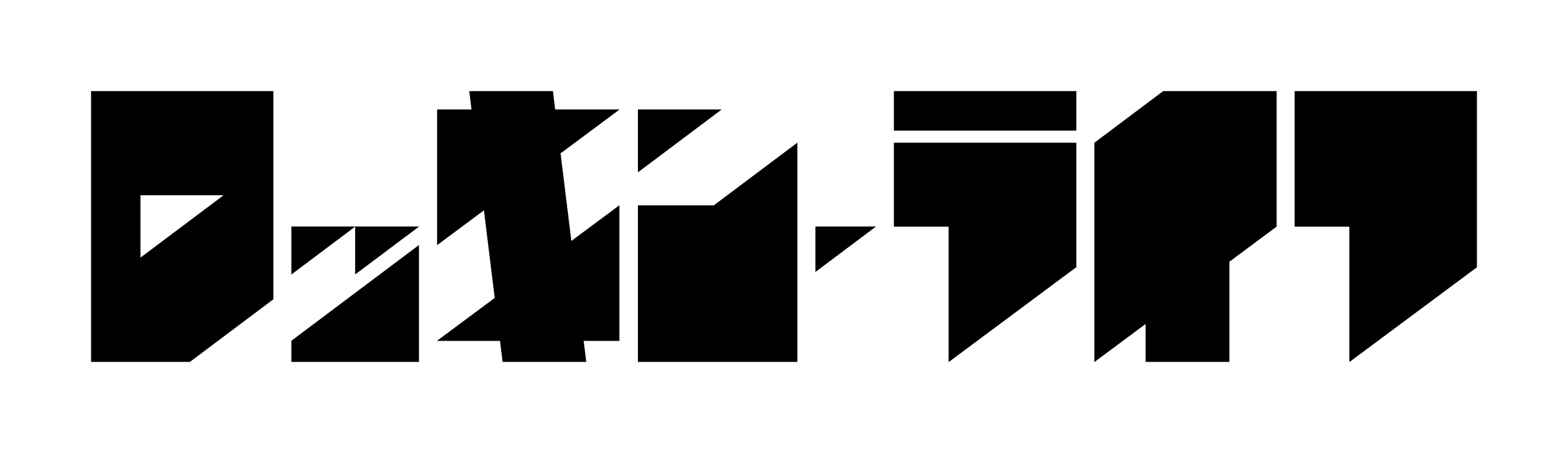米津玄師の「灰色と青」の歌詞について書いてみたい。
作詞・米津玄師
スポンサーリンク
考察その①灰色と青について
この歌のメッセージを端的に言えば、「幼少時代を共にした友人たちと、大人になってすれ違うようになってしまうが、離れてはいてもほんの束の間、重なり合う瞬間があり、その時に宿る刹那的な何か」を描いた楽曲ということになる。
大人になってしまった今を「灰色」と位置づけ、屈託なく笑えた幼少時代を「青色」と位置づけ、一瞬離れていても気持ちが重なり合うその瞬間、もうなくしてしまったのか、実は未だに持ち続けているのか、本当はわからないけれど、それでも確かに感じる自分の「青」を見つめ直す、そんな歌なのだと思う。
書いてみたものの、全然端的じゃないけれども。
まあ、もう少し細かく歌詞をみていこう。
この歌の登場人物は僕と君がいるわけだが、ふたりとも大人になり、それぞれ別の道を歩み、日々に忙殺されて「灰色」と呼ぶに相応しい日々を過ごしていることがわかる。
そして、少年時代の「青色」だった日々を回想しながら、今でも青色がちゃんと残っているのかなーと自問したりするわけだが、不思議なもので、米津玄師の声は「灰色」に、菅田将暉の声は「青色」に聞こえてくる。
だから、米津パートが灰色で、菅田パートは青色なんて考え方もできてしまう不思議。
まあ、とりあえず言えるのは、二人の声には違いがあって、だからこそ「すれ違い」を見事に表現しているということ。
ところで、この歌は色んなモチーフを散りばめながら「灰色と青」のことについて歌っているように見受けられる。
例えば、乗り物。
この歌には三つの乗り物が出てくる。
「電車」「自転車」「タクシー」。
歌詞を読めば、明け方に電車を乗るということは、夜勤をしているのか、残業がエグいかのどちらかであるし、タクシーを使うのだって終電までに帰れないことを指すわけだから、日々の忙殺ぶりを表現していると思うが、その一方で、一人の主人公は電車で、もう一人の主人公はタクシーで、子供時代の僕らは自転車に乗っているのは、それ以上の意味があるように感じるのだ。
例えば、電車。
電車というモチーフは、決められたレールを走って行くというイメージがある。
安定志向で着実的だが、冒険心がなく、保身に走った大人をイメージさせる。
一方、自転車は歩みは遅く、電車やタクシーなんかよりは遅いものの、自分でハンドルを握っているから、自分の意志でどこでも好きなところに行けるという、希望のモチーフなのではないか?と思うわけだ。
青色=幼少時代=色んな可能性に溢れていた、ということを表現するために、子供時代の僕らは自転車に乗っているのではないか?ということである。
また、忙しなく街を走るタクシーは、忙殺された日々の象徴であり、その気になればどの乗り物よりも自由に遠くに行くことだってできるのに、時間がそれを許さないという「大人であることの切実さ」を表現するものになっている気がする。
結局、遠くになんて行けず、いつもと同じ目的地を反復するかのようになぞるだけの日々を示す象徴になっているように感じるわけだ。
つまり、ここに登場する3つの乗り物は、全員の今の立場を表す象徴として機能している。
また、この歌でもうひとつポイントなのは、朝日が昇る前の欠けた月をみているとき、である。
最初のフレーズでは、末尾は「色が滲む」とある。
ここで滲む色は灰色のことなのか、青色のことなのか?
実はこれは判然としない。
ただ、ラストのフレーズでは、「始まりはいつも青い色」という言葉で締めくくっている。
もし、月を眺める夜を終わらせて、次の朝日を拝むことができれば、それは始まり=青色になるわけだ。
だから、その時に滲むのは灰色となる。
逆に朝日を登らせることができず、俯いたまま時間を過ごせば、滲んでいくのは青色となる。
実は、主人公がどちらに転ぶかは描かれない。
灰色になる未来、青色を見つける未来も提示して、あとは聴き手の想像に託すようになっているのだ。
言い切らないところが、米津が巧みだなーと思う部分。
スポンサーリンク
音に対する考察
この歌は冒頭は、米津の声を多重にしたコーラスで始まる。
このコーラス、ただ単に米津の声を重ねているのではなく、ボイスエフェクターをかけた声を幾層も重ねて、まるでオルガンのような楽器にして自分の声を響かせている。
これは、本来は楽器であるはずのボーカロイドを使って「キャラクターに歌わせる」という幻想を描き、音楽を作ってきたボカロ出身の米津だからこその芸当なのではないかと思う。
要は、ボカロと真逆のことを試みているのだ、この冒頭のコーラスは。
思えば、米津はボカロ出身のアーティストなわけだが、おそらく米津にとってボカロは「アーティストの始まり」であり、この歌になぞって「始まりは青い色」なのだとしたら、米津にとってのボカロは、青色の象徴ということになる。
やがて米津は、自分の肉声で歌うようになり、仕事として音楽と向き合うようになる。
この歌は社会人を灰色として描いているわけで、音楽を完全に仕事にしてしまった今の米津にとって、音楽はある種、青色のものから灰色のものへと移行してしまったものとも言えるのではないだろうか?
つまり、冒頭のコーラスは米津にとっての音楽が青色から灰色に変わってしまったこと、そして、その方式を転覆させるようなアプローチをすることで、再び音楽から青色を見出す作業をしているのではないか?と思うのだ。
ところで、冒頭でもうひとつ象徴的なのは、ギターの音色である。
米津の声は多重になっているのに、それに対するかのように、ギターの音色はアルペジオを採用して、音をバラバラに鳴らしている。
これは、僕と君が離ればなれになっていることを象徴する音なのではないかと思うわけだ。
そうなのだ。
この歌は音が主人公の心そのものを映している。そんなふうに感じるのだ。
だからこそ、Bメロは心臓の鼓動のように、打ち込みのドラム音を入れる。
BUMPの「モーターサイクル」宜しく的な、死んだ魚の目でも心臓は脈を打ってる、みたいな感じなのではないかと思う。
そして、灰色な日々のなかでも青色を見つけるかのように、サビではボーカルが声を張り上げ、それまでアルペジオ=バラバラだったギターの音がコード弾きになり、音がついに「重なる」のだ。
僕と君が一瞬重なるかのように、ギターの音も重なるのだ。
さらに、ドラムは打ち込みから、生音(に近い音)に変わり、ベース音も導入することで、より「生命」を宿している感をサビに作るわけである。
言葉だけでなく、音でもそれを物語るようにして。
関連記事:米津玄師の「Pale Blue」のメンタルのえぐり方が痛烈な件
関連記事:どこにも行けない米津玄師と、すぐに迷ってしまう藤原基央。
スポンサーリンク