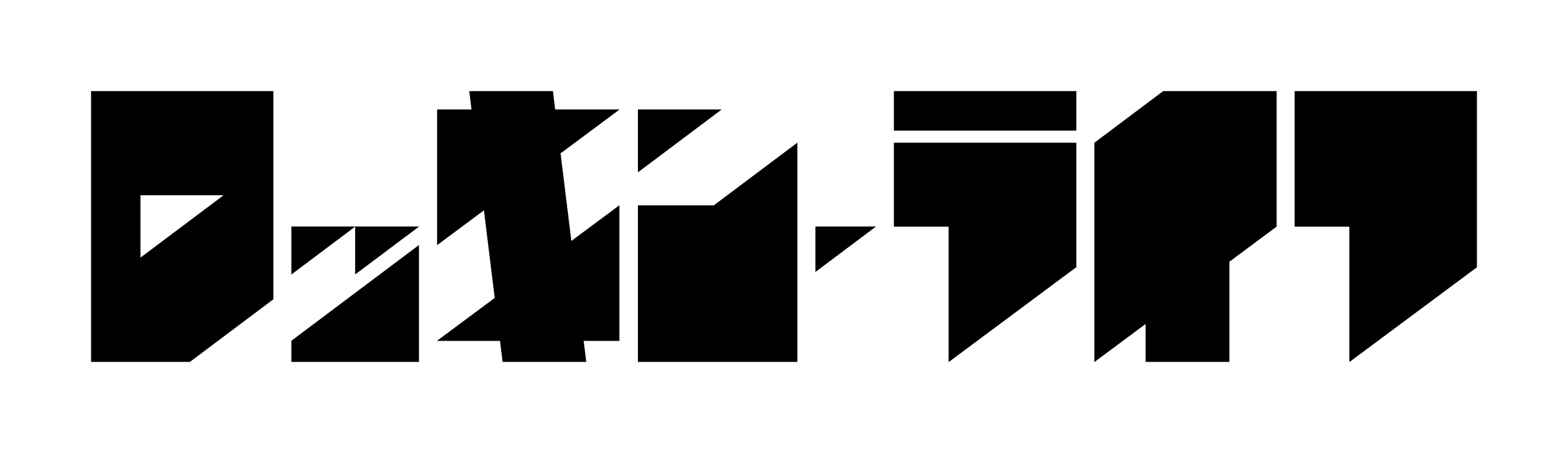岡崎体育の「式」の歌詞について書いてみたい。
スポンサーリンク
前置き
インディーズの頃から弾き語りで披露していた曲ではあるんだけど、それからもずっと手直しをし続け、2年くらいの歳月をかけて今の形になった楽曲なのだそう。
ひっそりとノートに書いたポエムのような歌だと岡崎は語り、今でもこの歌で自分が何が言いたいのかははっきりとわからないと語る。
ただ、人生をテーマにした歌であることには間違いなく、1番は子供、2番は老人をテーマに書いたとのことで、タイトルの「式」を含め、聴き手に解釈は委ねたいと語っている。
そんなことを踏まえながら、この歌詞について考えてみたい。
式から考える<四季>
空の色を丁寧に描くことで、時間を表現している。
歌詞の冒頭は空を通じて「朝」であることを知らせ、歌詞のラストでは空を通じて「夜」であることを伝える。
間に夕焼けを挟むことで、この歌詞で1日の時間を表現していることがわかる。
が、この歌は同日の1日を描いているのではなく、もっと長いスパンの「1日」を描いていることがわかる。
前置きにもあるように、子供と老人の話をこの歌詞を書いてるわけだが、もしこの歌の登場人物がずっと同じだとすると、60年以上の歳月を「1日」という時間に凝縮させていることがわかる。
ふつう、年単位の歌を描きつつ、時間を表現する場合、絶対に季節感を出す。
夏は幸せだったけど、冬は寂しい、みたいな。
が、この歌は「雪色」という単語を除き、季節感のある言葉はあえて一切使わない。
<四季>には言及されないようにしながら、時間というものを描こうとしているわけだ。
それはこの歌が「四季」ではなく、「式」というテーマで歌詞を構成したかったからなのではないかと思ったりする。
時間は明確に描いているのに、四季を感じさせない描き方をするところに、この歌の「思いの強さ」が現れているような気がする。
式から考える<死期>
2番が老人をテーマにしているからなのかもしれないが、<死期>の匂いを感じるような歌になっている。
サビでは主人公の「相槌がでたらめ」であることを幾度となく伝えるわけだが、おそらく子供パートの「相槌のでたらめさ」というのは反抗期的な意味で、いい加減に相槌をうっている感じがする。
母が「今日はごはんいるの?」みたいに尋ねると「ああ」ってテキトーに返事をする感覚である。
その「でたらめさ」を浮き彫りにさせるため、約束を破ることとか、ひとり洟水垂れる(泣いてるわけだが、なぜ泣いてるのか想像しさせるような作りとなっている)様子を描くわけである。
一方、老人パートの「相槌がでたらめ」というのは、ボケるという言葉からもある通り、老いぼれていくために生じている現象のように描かれている。
この老いの先にあるのはまさしく「死」であり、この歌詞では明らかにそこまでの想像力をはためかせるような描き方をしている。
「言葉に血の通った話がしたい」とか「先に呆けてしまえば寂しくないかな」というフレーズから漂う、どことなく<死期>を感じさせるフレーズは、人生という名の卒業<式>さえも想像させる作りとなっており、多重な意味で「しき」という言葉を反芻させるような作りとなっている。
スポンサーリンク
まるで<史記>のような歌
子供から老人という60年以上のスパンを歌詞にしたためたような構成。
まるで誰かの<史記>を描いたような感じがしないだろうか。
言い換えれば、それは人生の入学<式>から人生の卒業<式>までを描いた物語のようにも見て取れる作りとなっているわけだ。
まるで<私記>のような歌
この歌には二つの一人称が出てくる。
「僕」と「私」である。
子供パートと老人パートの違いを明確にさせるために一人称を使い分けていると思われる。
僕=子供
私=老人
なわけだ、
さて、一人称が出てくるということは、この歌は主人公の思っていることや考えていることをしっかり歌詞にしていることがわかる。
特に、主人公の感情が顕になるフレーズが「飯を口から零して テイブルを汚して にたついてる私を赦さないで」である。
これって変な表現である。
メシを落としたのに私は笑っているのも変だが、それを相手に赦さないでとお願いしているところがもっと変である。
私はメシを落としたくもないし、にたつきたくもないのにそうしてしまっている感じがする。
だから、それを叱ってほしいと懇願しているわけだ。
嫌ならやめればいいのに、それができないのだ、私は。
なぜだろうか?
それはおそらく、私はもう呆けてしまったからではないだろうか?
指輪が弛むのは衰弱して痩せてきているからだろうし、瞳の黴が生えているのは、意識が上の空になりがち=ボケているからだと思われる。
血の通った話がしたいとわざわざ公言するのだって、それがもうできないから、そんなことをいちいち望むわけだ。
メシを落としてもにたついてしまい、瞳に黴が生えてしまったように意識が上の空となり、指輪が弛むくらい衰弱して呆けた老人になってしまったのだ、私は。
だから、せめてそんな私を「赦さないでほしい」と相手に願うわけだ。
けれど、相手は相槌がでたらめになった私をみて、笑うのである。
先に呆けたから寂しくないかなと思ったけど、実は寂しさしか感じない私は、そんな相手のことをみて、どうして笑うの?と投げかける。
私に迫る<死期>をみてなお、あなたが微笑んでいることに疑問を投げかけるのだ。
あなたが何を考えているのかの答えはない。
なぜなら、これは私のことを綴った<私記>だからだ。
私からの視点を提示されても、あなたの視点が描かれることはないのだ。
だからこそ、この歌は「式」という名の<私記>なのだと断言できるわけである。
それは最終的にひとつの等式となる
「式」という言葉を「SHIKI」という音に変換して、色んな「しき」に変えて、この歌詞を考察してみた。
具体的な結論やメッセージが浮き彫りになることはなかったが、どんな「しき」に変換しても、それはひとつの等<式>となり、=となって繋がることだけはわかった。
だからこそ、「式」という歌は奥深く感じるのかもしれない。
あなたはこの「式」に、どんなメッセージを読みとっただろうか?
スポンサーリンク